| 12/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■冬コミおつかれさまでした! 夏コミよりも持ち込み部数を減らしたのもあり、無事完売! いつも確実に余るくらい持ち込んで案の定余り、送り返したりしてたわけだが。 今回は自分の分を確保せずに完売寸前までいき、慌てて献本分を確保した! 危うくメロンブックスから買う羽目になるところだった!(笑) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■過去に掲載誌た内容か段々わからなくなってきた ●星渡りの民 星渡りの民とは、遙か星界の彼方にある「地球」なる故郷を離れ、このフローラント大陸へと降り立った異邦の人々を指す呼称である。彼らは本来、この大陸に生きる人類とは全く異なる文化・言語・外見・技術体系を持ち込んだ旅人であったが、渡来からすでに700年以上が過ぎた現在、その血統は混血化を極めており、純粋な星渡りの民の末裔を見出すことはほぼ不可能とされている。人々の記憶に残るのは、もはや「かつて存在した民族」という歴史的概念でしかない。 星渡りの民とこの地の人類の血統がどう混ざり、どこで絶え、どこで繋がったかは、いまとなっては判別のしようがない。しかし、家名の由来――それが大陸古語の系譜に属するか、あるいは星渡りの民が持ち込んだ地球由来の言語を元としているか――によって、おおまかに「星渡りの民を祖に持つ可能性」の判断は行われている。とはいえ、それすらも数多の血統断絶や分岐によって曖昧で、確証にはほど遠いとされる。 彼らは一枚岩の民族ではなく、本来の故郷である地球でも多数の国家や人種に分かれ、その文化差は決して小さくなかったらしい。ヒノワ人が大陸の住民と大きく異なる外見・風俗・気質を示す背景には、この星渡りの民の「内部的な多様性」が深く影響していると語られる。 星渡りの民が持ち込んだ技術体系は、フローラントの魔導とは全く異なる、星の海をも越えることを可能とした“科学技術”であった。しかし、歴史はその栄光と衰退を語る。この科学技術は竜との戦いにおいて致命的な相性の悪さを抱えていた。精霊力の干渉や魔導の乱流の前では、電力や機械仕掛けは度々暴走・停止し、致命的な破綻を起こす。竜はその存在自体が強大な自然律であり、科学技術の機構を狂わせる要因の塊でもあった。星渡りの民は、持ち込んだ技術がこの世界の“根本法則”と噛み合わないという厳しい現実を前にし、次第にその技術体系を維持する術を失っていくことになる。 とはいえ、その遺産が完全に失われたわけではない。星渡りの民が残した機械、素材、論理体系、そして「世界を物理現象として理解する姿勢」は、物理魔導という新たな魔導に形を変えて、後の世の魔導師たちに多大な影響を残した。偉大なる魔導王国ファクセリオンの技術体系にも、星渡りの民の思考法が溶け込んでいると言われ、現代の呪甲装兵や魔導具にも、かの遙かなる星の文明の残滓がひっそりと息づいていると信じられている。 かくして星渡りの民は、今では血筋としても文化としてもほぼ溶けきり、伝説と史実の境界に揺れる存在となった。しかし、その影響は世界の至るところに残り、フローラントの文明そのものを形作る基盤のひとつとなっているのである。 ■マスターズ・コメント 地球人が大規模な恒星間移民船団で大挙としてやって来ましたよ、と。 とにもかくにも「言葉の壁」を突き破るために編み出された理屈。 いわゆる「異世界なのに地球の故事成語を使う問題」と言うやつだ。三國志が無い世界で「破竹の進撃」や、ローマ神話が無い世界で「バルカン砲」が存在するのはおかしいのではっていうね。これは気にし出したらキリがない為、多くの場合は「翻訳の結果そうなっている」と解釈するのが無難なのだが。そこでそういった好意的解釈に頼らず、どうにか理屈付けようとなればもう「その世界には地球が存在し、キャラクターたちは地球の言語を喋っている」ことにすればいいという力技。 そんなわけで地球由来の言語や度量衡がこの世界の文明として受け継がれた結果、作中のキャラがメートル法を用いた会話をしたり、「覆水盆に返らずだぜ」なんて言ったりしてもなんら問題無いのだ。 ついでにいうと、神霊界はあらゆる世界の上方次元世界なので、地球の神話に出てくるモンスターなんかも「実はそもそもが神霊界で生み出された存在だから、惑星エーヴィヒカイトにもいるんだよ」っていう理屈付けが行われている。 ●アーミア  猫耳&尻尾種族。 天性の狩猟者にして隠密であり、もの凄い量の追加技能ポイントを得ているに等しい種族ボーナスを誇る。同系統のマオナムとは長所が棲み分けされているので、お好み次第。 猫同様に自由気ままで気分は上々な気紛れ屋さんで、身体能力が凄まじく高い。 ティスリのように、基本的に外見に恵まれがちなのだが、あっちが理屈っぽくて閉鎖的な性格が相殺してるのに対し、こっちは人見知りで警戒心が強く、マイペースな性格が相殺している。空気が読めないのではなく、空気を読んだ上で「それにわざわざ合わせたくない」となりがち。  最初のハードルを乗り越えさえすればとても親密になれるのだが、「合わない相手と一切合わせる気が無い」ので、フィジカル的には忍者などの潜入工作員に向いているが、性格的にまったく向いていない。 法に縛られるのを毛嫌いする傾向も強いゆえに、単なるこそ泥もいれば、その才能を遺憾なく発揮して犯罪組織で活躍したりと、闇に染まるアーミアはとても多いので、泥棒猫的に社会的イメージがあまり良くない側面もある。  一方で「美人のワガママに振り回されたい」という需要を絶大な威力で満たすため、夜の町でのスターは彼女たちである。 アーミアの中でも協調性を備えた(つまり【魅力】が高い)個体は、ワガママというよりは寂しがり屋で甘えん坊、明るく元気で社交的、穏やかで面倒見が良いタイプもいる。  冒険者やクーゲルでは、腕利きの盗賊枠として重宝される一方で、トラブルメーカー的な性格からピーキーな逸材扱いとされることもある。が、わざわざこの道に進むアーミアは種の平均に対して優秀な場合も多く、その際はその潜在能力をフルに発揮して大いに名を上げるという。  奔放神の信者の大半はアーミアであるとはもっぱらの評判であるが、それを否定する要素は今のところ見つかっていない。 肉体的な成熟はフロウより早く、15歳前後で完成する。 青年期が長く、急速に老化する。寿命はフロウより若干短い。
一般的な身長・体重の範囲
■フローラント版ゲームデータ サイズ:中型 能力値修正:【筋力】-2、【敏捷力】+2。 移動速度:30フィート。 属性:アーミアは原則的に混沌属性である。 視覚:夜目。 セーヴボーナス:反応セーヴに+1。* 技能ボーナス:〈軽業〉〈聞き耳〉〈忍び足〉〈真意看破〉〈生存〉〈脱出術〉〈跳躍〉〈登攀〉〈平衡感覚〉に+2種族ボーナス。* 身軽:アーミアは〈跳躍〉に助走を必要とせず、助走を行った場合は+2技量ボーナスを得る。* 受け身:アーミアは落下時、被害を軽減する際の高さを半分として計算し、[転倒]判定などのバランスを求められる技能及びセーヴ判定に+2技量ボーナスを得る。* 猫族との意思疎通:アーミアは言語を持たないネコ科動物と、ある程度の意思が疎通できる。相手の知能に合わせた大まかな意向を伝え読み取ることが可能。 気まぐれ:アーミアは愛嬌に富んでいるが、その気まぐれな性格は相手を選ぶ。〈交渉〉及びなんらかの印象や対話を伴う判定時、混沌属性の相手に対し+4、中立属性の相手に対し+1、秩序属性の相手に対し-4を受ける。 言語:出生地に依るが、基本的には大陸語かアーミア語。 都市部のアーミアは、アーミア語を喋らずとも暮らしていけるし、全員がバイリンガルとなるほど教養があるわけではない。 種族代替特徴:気まぐれを得ない代わりに、属性を秩序に変更する。 *のついた特典は鎧や武器を着用していない状態または、非金属の軽装鎧を着用して、非金属の盾、軽い近接武器、いずれかの射撃武器を装備している状態で、装備品の総重量が軽荷重の場合にのみ適用される。 ■マスターズ・コメント 何気に一番最初のクラシックD&Dキャンペーンの時点で存在したオリジナル種族。D&D3.5版にも「キャットフォーク」という猫人間種族が存在するけど、あっちは「顔が完全に猫で、全身毛むくじゃら」であり、アーミアとは見た目もデータも全然違う。 なんにせよ、初のキャンペーンなのにいきなりハウスルールで新種族ぶっ込むとはなかなかにやんちゃなDMだな、昔の俺。 種族絵は実際に存在するキャラシートに描かれていたイラストを、AIに読み込ませてリメイクさせたもの。 性格に問題があるにも関わらず、キゲインと違って【魅力】が-2されていないのは、キゲインが特別容姿に優れた種族ではなく、アーミアは特別容姿に優れた種族だから。つまり普通なら【魅力】+2貰うような外見をしてるが性格と相殺しているだけなんで、【魅力】10のキャラはワガママお姫様ロールプレイしないといけない。で、その性格の割にはそれを完全に赦せるほど美人でもないので、世間の反応は「モブ顔の凡人」と同じ程度に落ち着くわけだな(笑) 協調性のなさが強調された設定は猫への熱い風評被害と思いきや、ヒトの世界が滅んだ未来における動物世界ワールドを描いたD&DベースのTRPG「パグマイア」では、イヌ族は「我々はかつてヒト様に仕えた忠実な一族である」ことを誇りにしているのに対し、ネコ族の歴史では「ヒトはかつて我々に仕えていた忠実な一族である」となっているので、俺は悪くない。D&D5版のキャットフォークなんてモロに「良識に欠ける」と書いてあるくらいだ。 ●エイク  エイクは草原に生きる民であり、その祖を鳥の血に求めると伝えられる遊牧の種族である。彼らの社会は風とともに移り変わり、定住を良しとしない。果てしなく広がる草原を渡り、群れを成して移動しながら生きる生活は、自然の摂理そのものと一体化したものである。優れた視覚と聴覚を持ち、遠くの風の音すら聞き分ける彼らにとって、戦場で弓を引くことは呼吸と同義である。エイクほど弓を自在に扱える種族はなく、斥候や狙撃手として匹敵する者はいない。 その身体はフロウよりもやや小柄で、骨格も細くしなやかだが、筋肉は緊張した鞭のように鋭く、筋骨隆々ではなく競技者的な洗練を備えている。風を切るような俊敏さと、持久力を要する長距離行動に適した身体は、まさに草原の生存に特化した造りであり、肉体的な成熟はフロウより早く15歳ほどで完成する。精神的な成長はフロウとほぼ同様だが、青年期が非常に長く、やがて老衰が始まると急速に命の炎が燃え尽きる。特に男性は老いによる死を恥と考え、「戦って死ぬことこそが誇り」と信じて疑わない。ゆえに老爺の姿は極めて稀であり、その死に様は戦士としての理想とされている。 男たちは勇敢で、時に粗野であり、理屈よりも直感を尊び、学問よりも体を動かすことを好む。言葉より拳、理屈より行動――それがエイクの男の気質である。一方で、女性は家を守り、血縁と群れを支える存在として極めて保守的であり、臆病で人見知りが激しい。だが、その臆病さは単なる弱さではなく、危険を察知して家族を守るための慎重さに他ならない。彼女らは温厚で理性的であり、家庭を守る役割を誇りとしている。 男女を問わず、エイクの心には「絆」を何より重んじる気質がある。最初の垣根を越えて心を通わせた相手に対しては、理屈を超えた深い信頼を抱く。友情は厚く、仲間を裏切ることは死よりも恥であり、これが彼らの誇りである。男の理屈嫌いは打算の無い信頼に、女の臆病さは優しさに転じ、彼らの社会は感情の絆によって成り立っている。 都市部での生活に適応できる男性は少ないが、女性のほうは都会暮らしに驚くほど馴染む。彼女たちは「家に留まり、家事をこなす」ことを安定と幸福の象徴と捉え、外へ出て働くよりも、家の中で役割を果たすことに深い満足を覚える。むしろ一歩も外に出なくても不満を抱くことがなく、それを退屈や束縛と感じないことこそが、彼女たちの特異な美徳とされている。その内向きな幸福感は、外の世界での自由を知らぬ怯懦ではなく、「家庭を守ることこそ己の務め」という確固たる信念に裏打ちされているのだ。 その勤勉さと穏やかさ、慎み深さは、侍女や給仕としての適性を極めて高く評価され、王侯貴族の屋敷で仕える姿も珍しくない。彼女たちは命じられずとも己の責務を果たし、与えられた場所で最善を尽くすことを誇りとしている。だが同時に、この“家の中で満ち足りる”という気質は、他種族から見れば閉鎖的に映ることも多く、良し悪しの両面を併せ持つ。内に向かう幸福は堅実さと忠実さを生むが、変化や挑戦を拒む傾向を強め、時に新しい環境への適応を妨げることもある。 また、娼婦として売られた女性エイクも少なくないが、そのほとんどが臆病で人見知りな気質ゆえに精神と肉体を病み、すぐに使い物にならなくなったという。こうして、これもまた同様に「エイクの女は商品にならない」とされ、次第に彼女たちを売る者はいなくなった。 男性エイクの多くは、その好戦的な本能を活かして傭兵として生きる道を選ぶ。中には一族そのものが傭兵団として活動する例もあり、草原の名を冠した戦団の旗印は、戦場において恐れられる象徴である。彼らの弓兵部隊はケンタウロス騎兵やキゲインの戦士と並び称されるほどの精兵であり、その正確無比な射撃と迅速な撤退戦術で知られている。風を読む力と俊敏な機動性を兼ね備えた彼らは、まさしく“草原の風そのもの”と称される戦士たちである。 財貨を必要としない遊牧的な生活を送る彼らだが、人類が作り出す魔導武具には強い憧れを抱く。より強い矢、より速い弓――それを手に入れるために、戦場で報酬を得ることは決して珍しくない。エイクにとって金銭とは目的ではなく、戦うための手段であり、戦そのものが生きる証である。単純にして誠実、義理堅く、裏切りを何よりも嫌うため、利害が一致する相手にとって彼らはこの上なく頼もしい味方となる。彼らに契約を結べば、最後の一矢を放つまで約束を守り抜き、撤退の際も潔い。 また、彼らが狩猟によって得る魔物の素材――強靭な革、魔力を帯びた骨、風竜の羽――は、かつては用途がなく廃棄されていたが、人類との交易が進んだことで高値で取引されるようになった。これらは武具や工芸品の素材として重宝され、彼らの収入源となるだけでなく、戦う者としての誇りを形に変える手段でもある。こうして「自然の恵みを分け合う」という形で、エイクと人類の関係は利害と信義の両面から結びつき、互いに風のようにしなやかな信頼を築いていった。 自然とともに生きる民として、竜を崇める者も少なくない。竜王の配下に加わり、竜の支配領域で暮らす者の方が多数派ですらあるが、それは必ずしも人類への敵意を意味しない。彼らにとっては「誰の味方か」ではなく「誰を信じるか」が重要なのだ。良くも悪くも個人主義的であり、信義に従って動く。ゆえにフロウ側でも「敵にも味方にもなる気まぐれな民」として認識されているが、長年の接触を通じて、「お互い適度な距離感で付き合うのが一番」という共通認識が築かれている。 魔導の扱いにおいては、精霊魔導や神霊魔導の才を持つ者は一定数存在するが、物理魔導に関しては著しく遅れている。彼らの社会には術式体系そのものが存在せず、魔導支援を得られない戦闘力は近代戦では脅威度が低下するため、しばしば人類側から侮られることもあるのも、この距離感の形成の一因であろう。 風を友とし、大地を渡り、戦って死ぬことを誇りとする民。 それが、鳥の血を継ぐ草原の民――エイクである。
■フローラント版ゲームデータ サイズ:中型。 能力値調整:【敏捷力】+2、【知力】-2。 移動速度:30フィート。 視覚:通常視覚。 武器習熟:ボーナス特技として、ロングボウ(コンポジット・ロングボウを含む)、もしくはショートボウ(コンポジット・ショートボウを含む)についての《軍用武器習熟》を得る。 技能ボーナス:〈知識:自然〉〈捜索〉〈生存〉に+2種族ボーナス。 技能ボーナス:〈聞き耳〉〈視認〉判定に+4種族ボーナス。* 戦闘特性:飛行する目標に対する攻撃ロールに+1の種族ボーナス。* 特技:《近距離射撃》を得る。* 種族代替レベル:エイクの聖衛士は《追跡》の代替として《武器熟練:選択した弓》を修得できる。 種族代替特徴:武器習熟、戦闘特性、特技、【知力】-2を失う。 言語:出生地に依るが、基本的には大陸語かエイク語。 都市部のエイクは、エイク語を喋らずとも暮らしていけるし、全員がバイリンガルとなるほど教養があるわけではない。 *のついた特典は鎧や武器を着用していない状態または、非金属の軽装鎧を着用して、非金属の盾、軽い近接武器、いずれかの射撃武器を装備している状態で、装備品の総重量が軽荷重の場合にのみ適用される。 ●  上流階級者4/魔導師9 筋力8/敏捷力10/耐久力8/知力14/判断力14/魅力19/PB27 バーン帝国第2代皇帝皇妃、エイレンファナ。ティスリであり、皇妃である。だが市井では、彼女のことを「史上初の平民出の王妃」と呼ぶ者が多かった。そのほうが分かりやすく、語りやすく、そして物語として映えるからだ。正確には皇妃であり、バーンは帝国であるが、その違いを気にする者はほとんどいなかった。平民の娘が玉座の隣に立っている――人々にとって重要だったのは、その一点だけである。 確かに、小国であれば前例は存在した。平民出身の女性が君主の配偶者となること自体は、歴史上まったくの皆無ではない。だがそれらは、列強という尺度で見れば、せいぜい侯爵領や伯爵領に相当する規模の共同体での出来事に過ぎない。国家間の均衡や大陸規模の力関係に直接触れるものではなく、限られた圏内で完結する婚姻だった。 それに対し、エイレンファナが立っているのは帝国という巨大な構造の中枢である。玉座の傍らに立つ彼女の姿は、淡い光を含んだ金の髪を癖ひとつなく背に流し、誰もが思い描く「ティスリのお姫様」をそのまま現実に落とし込んだかのようだった。その光景は、前例の有無や制度の細かな差異を意識するよりも先に、人の記憶に強く焼き付く力を持っていた。  エイレンファナは、北海の女王港ゼナを治める市長アルサッタの第5子として、皇太子チェスター・ファーランド公爵(当時)に嫁いだ。この婚姻が政略結婚であることは疑いようがない。ただし、それは即物的な懐柔や強要として受け取られる類のものではなかった。ゼナの併合から婚姻に至るまでには10年以上の時間が経過しており、両者の関係は十分に醸成された後の選択であったためである。 侵略者と侵略された側の婚姻自体は、歴史上さほど珍しいものではない。だがこの場合、「権力によって娘を差し出させた」という印象はほとんど広まらなかった。むしろ、「帝国がゼナという都市を軽んじていない」「形式的な属州ではなく、対等な取引相手として扱った」という評価の方が、内外に強く残った。この点において、この婚姻は政治的にも成功した一手であったと言える。 征服された西方諸国の諸侯の多くも、この婚姻を羨望をもって受け止めたと考えられる。できることなら自らの娘を差し出したい、そう思った者は少なくなかっただろう。相手が凡庸な人物であれば事情は異なったが、チェスターは竜殺しの英雄であり、皇帝の嫡子であり、容姿・人格ともに高い評価を受ける存在だった。「政略」という条件を外し、一人の娘の縁談として考えた場合ですら、これ以上の相手は想定し難い。 エイレンファナは、もともと交易商人の娘として生まれた。だが商家は破産し、その後アルサッタが後見人となって生活を保証している。市井では、この破産すらも「誰かが彼女を手に入れるために仕組んだものではないか」と噂されたが、少なくともアルサッタは破産を利用した側ではあっても、引き起こした当人ではない。  アルサッタは、莫大な負債を肩代わりしたうえでエイレンファナを養子とし、その将来に明確な道筋を与えた。その動機について、彼女自身は「美しいから養女にした」と公言している。一方で、私的な場では露骨なまでの愛情表現を見せており、「世界一可愛い」「愛している」と口にする様子は、姉たちが苦笑するほどであったという。この露骨な愛情と、冷静な政治的判断が同時に成立している点こそが、アルサッタという人物の特徴である。 なお、アルサッタは早くからエイレンファナに対し、「貴女を皇妃にする」と語っていたとされる。それは予言でも空想でもなく、時間をかけて価値を高め、適切な位置へ配置するという、彼女なりの現実的な展望の一部であった。  エイレンファナは、商人としての教育を受けていない。交易商人の家に生まれながら幼少期にゼナ市長アルサッタの養女となったことで、進路は早い段階から商家の後継ではなく、富裕層の令嬢としての教育へと切り替えられた。以後は教養教育と並行して、魔導学院に通う道が選ばれている。 この進路は偶発的なものではない。将来、バーン貴族に嫁ぐ可能性を見据えた場合、「一芸に秀でること」が明確な武器になるという判断が、当初から存在していた。魔導という分野はその条件を満たしており、潤沢な資金力を背景に、長期間にわたって学院で学ぶ体制が整えられた。 その結果、エイレンファナは形式的な教養に留まらず、実力を伴う魔導師として成長する。最終的には高位魔導師と認められる水準に到達しており、「一芸に秀でる」という当初の目論見は、もはや補足説明に過ぎない成果を挙げている。 性格面では、海千山千な養母アルサッタとは対照的に、たおやかで温厚な振る舞いを身につけている。ただしそれは生来の天然さというよりも、幼少期からの一貫した教育の成果である。状況を理解し、自身の立ち位置を弁えたうえで行動できる点において、彼女は決して操り人形ではない。 エイレンファナは、「自分が養女として迎えられたのは利用価値があったからだ」という認識と、「養母が裏表なく愛情を注いでくれている」という実感を、矛盾なく両立させている。そこに疑念を差し挟むことはなかった。幼少期には「期待を裏切れば捨てられるのではないか」という不安を抱いた時期もあったが、20年以上を同じ時間の中で過ごすうちに、その思いは現実味を失い、いつしか意識の外へと退いていった。 天賦の可憐さに加え、天才と呼ぶほどではないが、十分に優秀と評価される魔導の実力を備えている点において、エイレンファナという存在は極めて扱いやすい象徴だった。彼女は生まれながらの特権階級ではなく、才能と努力によって現在の位置に到達したと理解されやすい条件を備えており、その姿は「平民であっても、能力と研鑽次第で皇妃に至り得る」という物語を、内外に示す材料として機能した。結果として、それは帝国内の向上心を刺激する象徴として、きわめて有効であったと言える。 もっとも、その実態を支えているのは、ゼナという都市の戦略的価値と、アルサッタの政治的手腕である。その比重が極めて大きいことは、内情を知る者であれば否定しようがない。しかし市井の人々の目に映るのは、そうした構造ではない。「あの若さで高位魔導師の資格を得ている」という分かりやすい成果のほうが、遥かに理解しやすく、語りやすい。エイレンファナは、その一点においても、象徴として非常に優れた存在だった。  エイレンファナ自身は、この婚姻が政略結婚であることを十分に理解している。そのうえで、チェスターに対して抱いている感情は、政治的判断とは切り離されたものだと認識している。娘としての敬慕と、妻としての愛情は確かに存在する。ただし、それが養母アルサッタによる長年の教育や価値付けの結果なのか、あるいはそれとは無関係に自然に生じたものなのかについては、もはや検証のしようがない。 魔導師として心理学も学んでいる彼女は、その点について疑問を抱いたことがないわけではない。しかし、その問いを掘り下げたところで、現在の自分や選択が変わるわけではないと理解している。「解き明かしても意味がないこと」として、その問題を思考の中心から退ける判断を、過去に一度下している。 そもそもチェスターは、「皇帝の嫡子」「竜殺しの英雄」「容姿端麗」「人格面も評判が高い」という条件をすべて満たした、極めて突出した存在である。その事実を前提にすれば、「誰であっても惹かれるだろう」という認識は、自己弁護というよりも冷静な現実把握に近い。エイレンファナ自身も、「家の事情とは無関係に、この人物を好きになっていたのではないか」と考えており、同時にそうであってほしいとも思っている。 ただし、この認識は彼女の聡明さゆえに、別の問題を生む。あまりにも表面的な魅力が強すぎるがゆえに、「自分はその要素だけに反応しているのではないか」という疑念が生じるのである。感情を客観視できる能力は、そのまま感情を疑う回路にもなり、結果として彼女の内面には、答えの出ない思考の迷路が形成されている。 エイレンファナは、自身の感情が政略結婚の成否に影響しないことも理解している。そのため、現状に対する不満は存在しない。しかし、チェスターへの愛情が深まるほどに、その迷路の奥へと踏み込んでいく感覚が強まっていくことも、また自覚している。  エイレンファナは感情をあけすけに言葉にする性格ではないが、チェスターに向けた思慕や葛藤を、完全に内に秘めていたわけでもない。そうした感情は、あくまで私的なものとして、趣味で書き溜めていた詩の端々に自然と滲み出ていた。本人にとってそれらは、公に読まれることを想定した作品ではなく、整理しきれない感情を言葉として置いておくためのものに過ぎなかった。 その詩が、本人の意図しない形で外に出ることになる。チェスターがそれらをまとめ、詩集として出版したのである。エイレンファナにとって、この出来事は強い羞恥を伴うものであり、積極的に望んだものではなかった。ただし彼女は、自身の立場を踏まえればこれを拒むという選択肢は現実的ではないと理解しており、その前提のもとで同意している。 結果として、この詩集はまず富裕層の令嬢たちのあいだで強い反響を呼んだ。読書という行為自体が資産と教養を前提とする以上、主な読者層は必然的にそこに集中する。彼女たちの多くは、恋愛結婚を自由に選べない立場にあり、将来そうなると理解しながらも、感情を抱えたまま生きている。エイレンファナの詩は、「いずれそうなると知っている心」と「すでにそうなっている心」の双方に同時に触れる言葉として受け止められた。 やがて、その評価や解釈は噂として外へ漏れ出していく。「皇妃が人に見せるつもりで書いたわけではない、恋に悩む心情を綴ったものらしい」「政略結婚の中で、ああいう気持ちを抱くのは自然なのだ」といった語られ方は、富裕層の口から市井へと広がっていった。詩そのものに触れることができない庶民にとっても、それは難解な政治的逸話ではなく、極めて分かりやすい形で受け取られる。すなわち、「恋に悩む姫の物語」としてである。 この過程を経て、詩集は階級を越えた象徴性を帯びることになる。富裕層にとっては自分たちの将来や現在を映す鏡として、庶民にとっては手の届かない立場にある女性の、率直で人間的な物語として機能した。その結果、エイレンファナの内面に存在していた思考の迷路は消え去ることはなかったものの、それが「解き明かすべき異常」ではなく、「誰にでも起こり得る感情の形」であると社会的に位置づけられることになる。 もしチェスターが、この反応の連鎖までを見越したうえで詩集の出版を選択していたのだとすれば、それは横暴というよりも、皇妃という立場にある妻の感情を、社会の中に安全に接続するための配慮だったと評価するほうが適切だろう。少なくとも、この一件が示しているのは、夫婦関係の冷えではない。実際のところ、2人の関係は形式的なものではなく、親密なものとして成立している。 エイレンファナという存在は、しばしば象徴として語られる。平民出身の皇妃、高位魔導師、帝国とゼナを結ぶ結節点。そのいずれもが事実であり、同時に彼女の一側面に過ぎない。彼女自身は、その象徴性を自覚しつつも、それに呑み込まれることなく、自分の立場と感情を分けて理解しようとしてきた。 政略結婚であることを否定せず、愛情の存在も否定しない。そのどちらかを偽りと断じることなく、「そうであるもの」として受け入れて生きる姿勢は、彼女の聡明さであり、また強さでもある。迷いが消えたわけではないが、迷いを抱えたまま立ち続けることを選んだ点において、エイレンファナはすでに1人の完成した人物だと言える。 皇妃として、魔導師として、そして1人の女性として。いずれの役割においても、彼女は過剰に振る舞うことがない。だが、その慎ましさこそが、結果として多くの人々の視線と感情を引き寄せてきた。エイレンファナは、自ら前に出て時代を導く存在ではない。だが、時代が彼女を映し込み、人々がそこに自分自身を見出してしまう――そうした位置に立つ人物なのである。  だからこそ彼女は、物語の主人公でありながら、同時に現実の中に留まり続ける。皇妃エイレンファナは、英雄でも悲劇の象徴でもない。ただ、理解した上で選び続ける者として、今日も帝国の玉座の傍らに在り続けている。 ■名をつけないまま 窓辺に置いた冠は重く それでも私の名で呼ばれる 選ばれたのか 選ばされたのか 問いはいつも 夜だけのもの あなたの背に差す光は強く 私の影を長く伸ばす それでもその影の先に あなたが立っているのなら 恋と呼べば 軽すぎて 義務と呼べば 冷たすぎる だから私は 名前をつけず ただ 想っている 明日が決まっていることと 今日を偽らないことは 同じではないと 誰かに言ってほしかった それでも今は あなたの隣で息をする それだけで 間違いではないと信じたい ■マスターズ・コメント  ソード・ワールドRPGの、2つ目のキャンペーンに登場したキャラなのだが、生い立ちが全然違うので政略結婚でもなんでもない。普通にチェスターが冒険中に連れて帰ってきた嫁。 ……が、フローラント化の際に「てめぇの立場でそんな恋愛結婚出来るわけねーだろ!!」と言わんばかりに大改変された。だが結婚自体が無かったことになってないだけ幸運である。ねぇウィスティーさん。 個人の性格とかそーいうのは変わってないので、些細なことである。……いや、中学生の頃に考えたキャラがこんな複雑な心境を抱えているわけもないので、この辺も全部フローラント第2版で付け加えられた要素だわな。ちなみに現在のフローラントは第4版です。 なお、人生で初めて恋の詩を書きました。 ●  魔導師13/大魔導師5/擬似巫妖5/ 筋力10/敏捷力14/耐久力14/知力22/判断力17/魅力15/PB48 華やかな笑顔と底抜けの明るさで変成術と死霊術をぶん回す、最も陽気な「暗澹姫」。 その二つ名はもちろん自称であり、かっこいいからという一点に尽きる。そもそも暗澹という言葉の意味と彼女の性格の乖離がひどいが、本人は満面の笑みで「でも語感がよくない?」と返してくるので誰も何も言えない。 本来リッチとは、死霊術師が魂と引き換えに不死となる存在であるが、リティーシアはその定義から大きく外れている。なにせ彼女は霊冥神や他の邪神の信者ではなく、単純に物理魔導で新陳代謝を止めただけ。つまり「ちゃんと勉強してがんばったらリッチになれました」という、前向きすぎる死者である。専門用語でいうと擬似巫妖、ひらたく言うと「死んでないのに死んでる扱いを受ける女の子」である。 新陳代謝を魔導で制御しているため老化もせず、損傷部位は魔力でセルフ再構築。首が刎ねられようが、腕が吹き飛ばされようが、気付いたら元通りになっている。ちなみに本人曰く「イメージ的にはプラモデルのパーツ付け直す感じ! パテも盛るよ!!」とのこと。割とショッキング。なおこれは星渡の民に関する深い知識を有する者にしか通じない超高度なインテリジョークである。  とはいえ、こうした再生能力は魔力をガリガリ消費するため、日々の燃料補給は欠かせない。幸い、仲間に奈落の胃袋ことティアムがいるため、「ごはんたくさん食べる子って可愛いよね!」という風潮が天秤の守護者内部で完全に定着している。明るく食べて明るく戦う、死霊術師界の革命児である。 外見年齢は16歳前後。死んでるのに肌がきれい。リッチなのにチークを塗ってる。しかもピンク。だがそれも彼女のスタイルである。「死んでも可愛くいたい」という気概は、ある意味すべての乙女の味方と言えるだろう。いや、自認としては死んでないけど。  「キャラフロ2のセンターを飾ったのは伊達じゃないってワケ」 彼女の存在は陰翳神の信者としても特異なものである。影を知り、闇を受け入れながら、それでもなお明るく生きる。陰鬱と背中合わせの世界で、あえて笑顔を貫くその姿こそ、陰翳神の教えに最も忠実な実践者かもしれない。ある意味「ダークネスを着こなす系女子」の最終形態である。 なお、「暗澹姫」の称号について本人はこう語る。 「え? かっこよくない? あんたんきだよ? ダークでキュートで完璧じゃん!」 「うん……まぁ……君が幸せならそれでいい」 天秤の守護者には特殊な経歴を持つ者が多いが、リティーシアの過去はその中でも際立った異彩を放っている。彼女はかつて南方諸国の一つであるアステュパライアの姫として生まれた人物であり、若い頃から天才的な魔導の才を示し、特に変成術の分野では誰もが認める逸材となった。才能は早くから開花し、やがて30歳を過ぎた頃には、変成術を専門とする一門「メタモアクシア」を率いる立場に昇りつめ、その名声はアステュパライアの内外に広く知られるものとなった。とはいえアステュパライアという国そのものは、紀元前の都市国家の継承者ではなく、解放戦争の最中に遺棄された古代都市の廃墟に、戦乱で流離した流民たちが住み着いたことに始まる歴史を持ち、200年ほどの間に独自の共同体として再形成された国である。そのため伝統的な王統があったわけでもなく、指導者の権威は純粋に実績と力量によって裏付けされていた。 父王の死後、リティーシアはそのまま女王として即位した。小国とはいえ、彼女自身が既に大魔導師として広く知られるほどの権威を持っており、その求心力は圧倒的で、異議を唱える者はほとんどいなかった。事実、彼女の率いるメタモアクシアの魔導師たちは、外敵が迫るたびに国を守り抜き、幾度もの危機を退けてきた実績を持つ。その信頼は絶対的であり、リティーシアが「王」であり「魔導師」であることは国の安定を象徴するものでもあった。こうして彼女は自然と、魔導国家の支配者に与えられる尊称――「魔導王」と呼ばれる立場に至った。ただし、魔導王は本来、都市国家レベルの自治体を統べる魔導師に対する称号であり、アステュパライアのように一般的な国家として広い地域を治める者が名乗るのは極めて例外的なことである。それほどまでに、彼女の存在は国政と魔導の両面において圧倒的だった。 しかし即位から20年ほどが経過したある日、リティーシアは変成術の秘奥の1つに当たる擬似巫妖化へと踏み切ることを決断した。これは冥徒とならず不死に近い存在へ変質する危険な術であり、多くの魔導師が畏れを抱くものであったが、彼女は迷う様子もなく覚悟を固め、周囲に向けて「あたしは人間をやめるぞー!」と宣言し、王位を返上した。国民や弟子たちにとっては衝撃的な出来事であったが、リティーシア本人は「自由だーっ!!」と晴れやかな笑顔で旅支度を整えると、そのまま爵位すら放棄して国を出奔してしまった。こうして彼女は20年近く大陸各地で善を掲げて悪を討つ勧善懲悪の旅を続けることとなる。  彼女は変成術を用いて敵を強制的に“変異”させる呪文を好んで用いる。その行使を目撃した者は皆「単に殺されるより遥かに恐ろしい」と口をそろえた。リティーシアほどの魔導師が本気で術を行使すれば、一時的な変質に留まらず、対象を完全に別の存在へと作り替えてしまうことすらあり、こうなると解呪を試みても根本的な回復が望めない。旅路で彼女に裁かれた悪人たちは多く、動物に変えられて終わった者はまだ幸運な方で、中には無機物へと形質を書き換えられ、そのまま別物として扱われることになった例すらあったという。リティーシア自身はこれを「おしおき」と称し、明朗な笑顔で語るのだが、その明るさと術の苛烈さの落差こそが、彼女を知る者に深い印象を残す理由である。 そうして西方へと旅を続けた末、彼女はファクセリオン王国に辿り着き、自ら天秤の守護者への加入を志願した。魔導王として国を治め、擬似巫妖として不死を得て、諸国を巡って勧善懲悪を続けた末に、最後に選んだ居場所が天秤の守護者であったという事実は、彼女の気質と志向をよく表している。リティーシアは陽気で明るく、しかし同時に闇と変化を司る魔導を極め、そしてそれを正義のために揮うことを信条とした――その歩みは、彼女自身が掲げた「暗澹姫」という異名の裏側に、確かな覚悟と信念が息づいていることを物語っている。 ■マスターズ・コメント  変成術が専門だけど、死霊術も「クールでイケてる」ので得意です。 そのイメージとは裏腹に統治者としての経験もしっかりあるので、クラストの次は彼女が総帥になるのかもなーとか周りから思われていることもある。 が、本人は「えー、そんなキャラじゃないよ。弱っちぃし」とのこと。 ● 極めて高位の魔導師の一部が到達することを選んだ、秘奥の領域。 高位の術者が霊冥神に認められることで至る姿はリッチと呼ばれ、死霊術師の最高峰とされているのだが、当然ながらそれは霊冥神を信仰しなければならない。しかし不死を望む者すべてが霊冥神の信者ではなかった。当然である。 そして様々な不死へのアプローチが模索された結果、一つの回答として見出されたのが魔導による身体制御を極限まで突き詰めることにより、全ての代謝を魔力制御する方式だった。 これによりデミリッチは魔力で修復可能な損傷ならば即座に再構築を開始する為、肉体的に不滅、不老不死と言える存在となっている。その代償として生者の自然な生理機能も失うことになるので(この時点で死んでいると考える者も多い)、全ての魔導師が目指す到達点とは言い難い、極めて特殊な存在である。そもそもこの領域に達しているような魔導師に、「たかが肉体を破壊されたくらい」で滅ぶような者はおらず、各々がなんらかの手段で生存能力を獲得しているものなのだから。 なおオリジナルのリッチは様々な特殊能力を得るのだが、デミリッチはあくまで不死性を擬似的に再現したに過ぎない為、リッチが備える生命力吸収やアンデッド支配などは行えない。 最も著名なデミリッチは〈暗澹姫〉リティーシアであり、かつては魔導王の一人として変成術の一門を統べていたが、現在は天秤の守護者入りしている。 ■ゲームデータ解説 プレイヤーがなることを全く想定してない世界設定情報クラス。なってもいいけど。 死者蘇生呪文がある世界ゆえ、結局本気で殺される時は魂の方をどうにかされるんで、肉体的な頑丈さがどこまであっても死の恐怖からは逃れられないという説もある。 あとD&Dのデミリッチとは全然違う。あっちはもっとヤベー。人間性なんて欠片も残ってねー最上級の厄者だが、こっちは単なる魔導キチガイってだけなので見た目が骸骨なわけでもなく、普通。別に理性を失ってもいない。元々頭のおかしい人だったら引き続きおかしいだろうけど。 見た目若々しいのにメチャクチャ強い魔導師がいたら、デミリッチであることを疑っていいかも知れない。 自然な生理機能を喪失しているだけで、それをエミュレートして「普通の人のように暮らす」ことは可能なので、あまり見分けがつかない。食事しなくても餓死しないが、魔力補給としての食事は行える。魔封石をそのままエネルギー源として吸収も可能なんで、食事に興味がなければ機械的に摂取するだけでいい。 ■必要条件 技能:〈呪文学〉18ランク、〈知識:神秘学〉18ランク、〈治療〉15ランク 特技:《秘術的応急処置》《呪文24時間持続》《技能熟練:呪文学》《呪文熟練:変成術》《上級呪文熟練:変成術》 呪文:大魔導師クラスレベル3及び秘術呪文として9レベルの変成術呪文を発動できること。 ■クラス基本データ ヒットダイス:D12 基本攻撃ボーナス:劣悪 セーヴ:頑健、意志 クラス技能 :〈呪文学〉〈製作〉〈精神集中〉〈職能〉〈知識:すべて〉〈治療〉 技能ポイント:4+
デミリッチの種族特徴:クラスレベルを遡って全てのヒットダイスをD12とする。生理機能の喪失。睡眠、生命力吸収、毒、能力値吸収及びダメージ、病気、麻痺、変成術への抵抗判定に+12強化ボーナス。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■冬コミお品書き コミケ会場で僕と握手!!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■昨日は2025ボドゲおさめ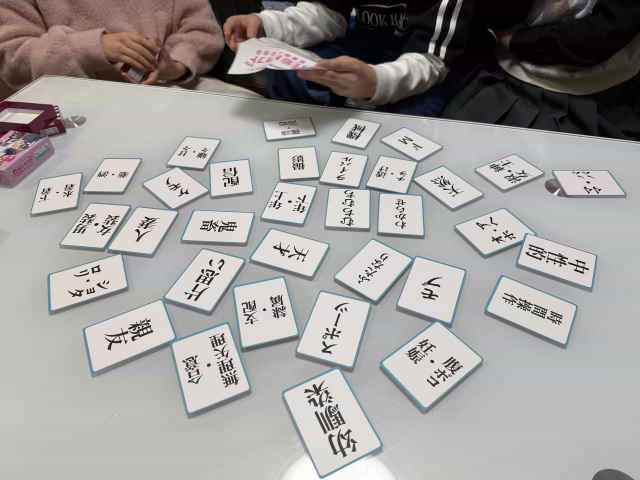 JK2人とボードゲームなんてリア充だなぁ!! ……いやまぁ親友と親友の弟の子供たちと遊んでただけですが!!! 親友長女のたっての希望により性癖ドラフトがファイナルゲームにチョイスされた模様。 子供たちの属性が赤裸々になるわけだが、むしろ逆に子供たちに対して属性を開示せねばならない父(親友)がなんの躊躇もしないことに敬意を評したい。 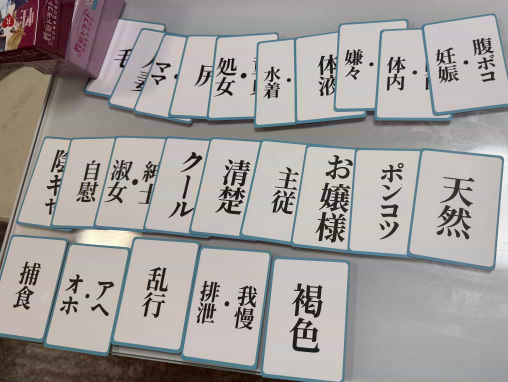 堂々と父はこれが好きだぞ、と宣言できるんだぜ! 仲が良い家族だな!!! なお、本来のゲームのルールは完全に無視しており、完全に単なる「好きな属性発表大会」になっていた。 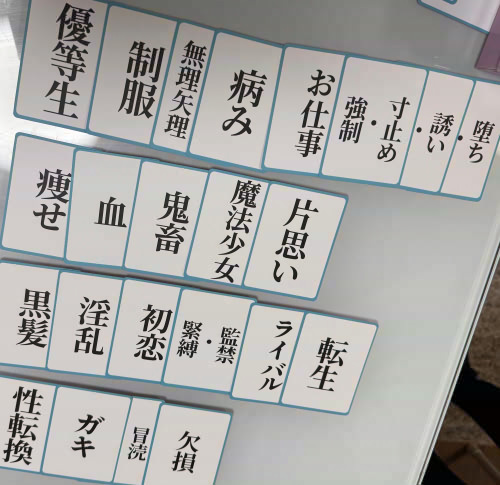 親友長女。 まぁ闇深い系大好きなんで、納得である。 ちなみに上に行くほど好き度合いが高い属性になっている(ゲームにそんなルールはない)。 先日初めてyoutubeに動画アップしたみたいだから見てあげてね!(笑顔 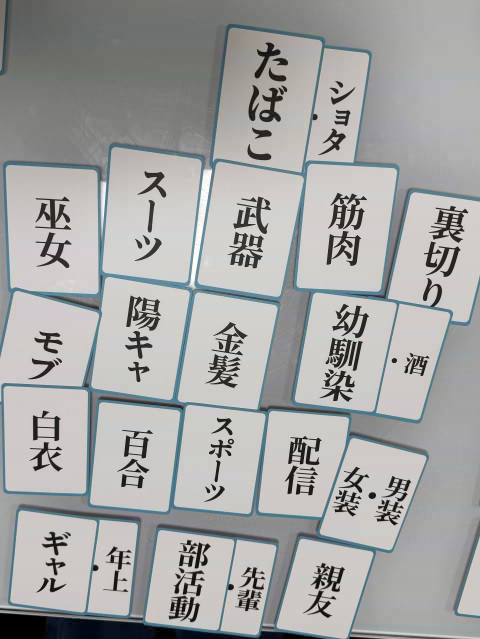 親友長男。 お前……ショタ好きだったのか……(笑) Tier1に堂々と君臨してて吹いた。 なお、俺とは眼鏡のカードでかち合った勇士でもある。 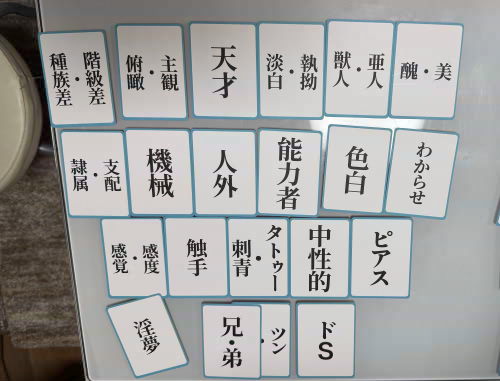 親友弟長女。 とにかく人外系が色々好きなことがよくわかる構図である。 まぁ伊藤潤二作品好きだしな! 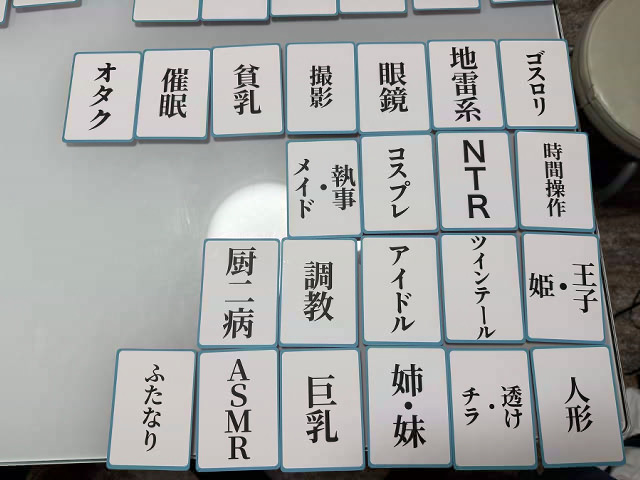 俺。 黒髪を取られてしまったのが痛い。 長年メイド好きとして過ごしてきたけど、現時点での熱量は地雷系なんだなぁというか、ゴスロリとかもあるんで結局好きな方向性のごった煮大好きなだけな気がしてならない。メイド好きじゃなきゃそもそも地雷系も好きにならなそうな気がするし。クロスオーバー作品は面白いけど、その面白さを下支えしてるのは、それまでの歴史の積み重ねであることを忘れてはならない理論。  そりゃ眼鏡で地雷系でオタクで姫なおっきー大好きだわ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■種族編はまだまだ続く ●クキナン  クキナンは、人類社会における代表的な小人族であり、キゲインが「身長は低いが質量ではフロウと変わらない」のに対し、彼らは「体積と質量そのものが1/4に縮んだフロウ」と形容される。その外見は子供じみたものではなく、比例の取れた成人体型を持つ。身体のスケールこそ小さいが、顔立ちや雰囲気は成熟しており、幼さよりも知性と落ち着きを感じさせる。そのため、初めて彼らを目にした者は「まるで小さな大人だ」と驚嘆することが多い。 彼らはもともと原始的な錬金術や精霊魔導に長じていたが、解放戦争を契機として誕生した物理魔導に対しては、特別な傾倒を見せている。フロウが「物理魔導は人類の叡智」と自負する一方で、クキナンの技術もそれに勝るとも劣らず、むしろ体格による不利を補うため、その依存度と発展の方向性はフロウ以上に明確であるとさえ言われる。製造面で優れた職人気質を発揮したキゲインが“技術者”であるなら、クキナンは“理論家”であり、“研究者”である。彼らにとって魔導とは生き方であり、誇りであり、自身の身体を超越する知の象徴なのだ。 魔導を戦闘術ではなく学術と捉える傾向が非常に強く、「戦いは戦いの得意な種族に任せておけばよい」と考える者も少なくない。彼らにとって呪文は殺すためのものではなく、理解するためのもの――自衛のために戦闘用呪文を習得することはあっても、それを本道とすることはない。実戦においては幻術を用いた撹乱を得意とし、敵を欺き翻弄することを好む。直接殺傷を目的とした呪文を使うことを「野蛮な他種族のやり方」と皮肉る者すらいる。 彼らは学問的には冷静で合理的だが、決して臆病ではない。危険を避ける本能と同じくらい、未知への好奇心に突き動かされる性質を持っており、「安全を求めながら危険に身を投じる」という矛盾を平然と抱える。そのため、無鉄砲な探求によって命を落とす者も少なくなく、「好奇心はクキナンを殺す」という格言はその実情をよく表している。 また、クキナンは知識と技術の延長としての「料理」を好み、その緻密な計量と加減を芸術と同義に扱う。理論的思考をもって味を組み立てる彼らの料理は極めて完成度が高いが、体格差ゆえに分量や器具の規模が合わず、キゲインの菓子店ほど一般的で広くもてはやされることはない。それでも高級料理店では、呪文によって一時的に体格を拡大したクキナンが厨房に立つこともあり、裕福な者たちにとっては名料理人として知られる存在である。 また彼らの料理に対する探求心は「学術研究」としての体系化にも及び、味覚や素材の化学反応を精緻に記したレシピ本は大陸各地で人気を博している。調理という行為すら“再現可能な魔導”と見なすその姿勢は、クキナンという種族の知性と職人気質の象徴でもある。 フロウと同じ速度で成長し、18歳で成人するが、その後の老化はおおよそフロウの半分の速度で進行し、寿命は2.5倍ほどに達する。小柄であるがゆえに体力的には脆弱だが、知的探究の深さと根気強さでは他のどの種族にも劣らない。彼らは研究者としても教育者としても優秀であり、魔導学院の教導師、家庭教師など、知の世界において欠かせぬ存在となっている。 また、体格差が明確に大きいため、長命種婚にありがちな性的嗜好や混血を巡るトラブルは少ない。もちろん例外は存在し、フロウとクキナンが惹かれ合うこともあるが、"現実的な問題"を乗り越えるには難儀することが多い。それを題材とした文学や寓話も多く、成人向けの物語では体格差による苦労をユーモラスに描き、子供向けの本では「種族の違いよりも心の絆こそ大切」という教訓に昇華されている。 長命種に共通するように繁殖力は高くなく、そのため竜から危険視されることはない。有史以来、彼らは「それなりに」繁栄を続けてきた。もっとも、フロウの異常な繁殖力と発展力が際立って高すぎるだけであり、他種族がわざわざ目の敵にされること自体がほぼないのだが。 他の種族もまた「竜に敵視されていない」という意味では同条件にあったが、それでもなおフロウに与した者たちの多くは、実利に基づく判断でその選択を下していた。「外敵が頻繁に襲うこの土地では、協力した方が安全だ」「解放戦争の折、頼まれて加勢した」といった理由がそのほとんどであり、言い換えれば、それ以外の多くは敵か、あるいは中立の立場を保っていたのである。 しかし、クキナンだけは違った。彼らは安全や利得ではなく、純粋な知識欲に突き動かされ、しばしば竜との対立すら辞さぬ選択を取ってきた。実際、解放戦争の時代には、特に差し迫った事情がないにも関わらず自ら進んでフロウ側に与し、物理魔導の習得に身を投じた氏族が数多く存在した。これは単なる安全保障上の判断ではなく、「新たな魔導体系の誕生」という知的刺激に惹かれた結果である。フロウ側にとっても、慢性的な人材不足の中で物理魔導に優れたクキナンの参加は極めて心強く、両者の利害は完全に一致した。こうして築かれた学術的・文化的同盟関係は、今日に至るまで強固な結びつきを保ち続けている。 個人レベルでの打算を越えた友情が芽生えることは、同種同士のそれと遜色ない程度に起こり得ることだが、種全体の傾向としては、クキナンは「護衛」として、フロウは「研究者」として、明確な役割の線引きをもって互いを理解している。彼らの関係は冷淡ではなく、むしろ互いの特性を尊重した上での成熟した距離感に支えられており、それが両種族の長き協調を保つ要因ともなっている。 種族全体としての傾向は極めて真面目で勤勉、研究熱心であり、知識に対して誠実である。だが、好奇心が理性を凌駕することもしばしばで、それが彼らの進歩の源であると同時に、最大のリスクでもある。彼らは「知の探求」に命を懸けることを恐れない。クキナンという名は、フローラントにおける知恵と危険、そして探求の象徴として語られる。
一般的な身長・体重の範囲
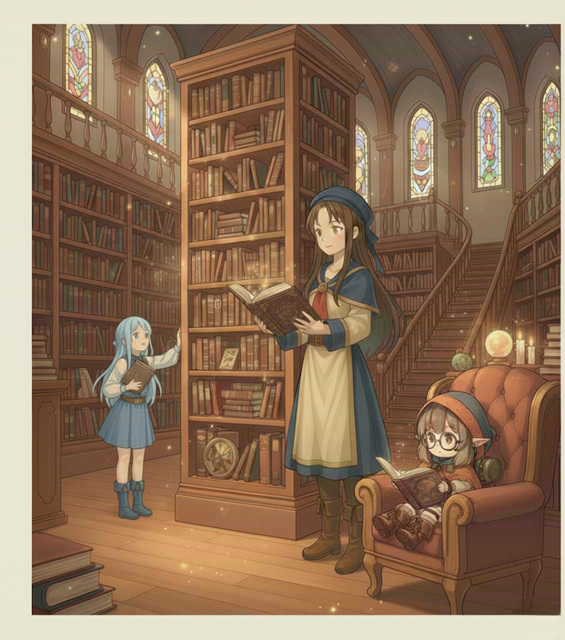 小人の描写はAIくんまだ苦手ですっげえええええええ大変。ここに至るまでにえらい苦労した。 てかこの本棚、なにげに異次元構造してて吹いた。俺も欲しい。 ■フローラント版ゲームデータ サイズ:小型。 アーマー・クラスに+1サイズ・ボーナス、攻撃ロールに+1サイズ・ボーナス、〈隠れ身〉判定に+4サイズ・ボーナスを得るが、中型のフロウ達が使うより小さな武器を使わなければならず、運搬能力の上限は3/4になる。データ上に明記されないが「小型だけど専有面積は中型と同じ」ことによる様々なメリットやデメリットを受ける場合がある。半マス先に届かないとか 能力値修正:【筋力】-2、【耐久力】-2、【知力】+1。 移動速度:20フィート。 視覚:夜目。 照明の「薄暗い範囲」が2倍となる。「明るい範囲」までは2倍にならない。 セーヴボーナス:幻術系呪文・効果に対するセーヴに+2種族ボーナス。 防御特性:巨人からの攻撃に対するACに+4。 【敏捷力】ボーナスを失うような状況の場合、同様に失われる。 技能ボーナス:〈聞き耳〉〈職能:錬金術〉に+2種族ボーナス。 呪文特性:幻術呪文使用時のセーヴ難易度に+1。 武器習熟:フックト・ハンマーを軍用武器として《習熟》《熟練》できる。 戦闘特性:コボルドやコブリン種への攻撃ロールに+1種族ボーナス。 言語:出生地に依るが、基本的には大陸語かクキナン語。 都市部のクキナンは、クキナン語を喋らずとも暮らしていけるし、全員がバイリンガルとなるほど教養があるわけではない。 種族代替特徴:戦闘特性、防御特性、武器習熟を得ない代わりに、〈技能〉ポイント+3。 ■マスターズ・コメント D&Dのノームはタフな種族なのだが、フローラントのクキナンは全然そんなことはない、華奢な小人である。 そして魔導に長じている設定なのだが、これをそのまま反映して【知力】+2出来る種族にすると、TRPG部の超絶優遇されたキャラメイク・ルール下において「容易く【知力】18+2=20のキャラが作れ過ぎる」という、割と無視できない問題が発生してしまうため、トータルで能力値が-4されるのに、増える能力値は+1だけというシビアな設定に。 これはどうしても魔導師が「他の能力値が低くても、【知力】さえ18ならOK」という基準でダイスロール成果の選択ができてしまうから。仮に「幾つか高めの能力値が欲しい」タイプなら「18が1個あっても、外が低過ぎる」と諦めらざるを得ない。そして魔導師以外のキャラなんて大抵はそうなのだね。武人や闘士も【筋力】【耐久力】さえ確保できればよしでその傾向はあるが、そもそも【筋力】ボーナスが+1増える程度のことと、【知力】が容易に20に達してしまうのでは、強さに与える影響が段違い。 そんなわけで、世界設定とゲーム性能をすり合わせた結果、こうならざるを得ないのであった。 ●ダーク・クキナン  ダーク・クキナンとは、地上に暮らすクキナンと同じ祖を持ちながら、古代より地下世界を主たる生活圏としてきた近親種であり、闇に満ちた土中環境の中で独自の文化と知性を発展させてきた民族である。彼らは体格こそ小柄で非力だが、聡明さと機敏さはクキナン以上に際立っており、地下世界という苛酷な生存環境で生き残るために、その長所を極限まで磨き上げてきた。力に頼れないという前提を受け入れた彼らは、知略・洞察・機敏な判断・戦略的思考こそが生存の鍵であると心得、長い時間をかけて種族全体の傾向としてそれを内面化していったのである。 彼らは優れた精霊魔導の使い手として知られ、ティスリと並ぶ精霊親和性を持ち、その魔導こそが武力に乏しい彼らの主兵装であった。地上のクキナンが知的好奇心や学術的探求心を中心として魔導に向き合うのに対し、ダーク・クキナンはその才を軍略や権謀術数へと向ける。すなわち、魔導とは研究対象であると同時に、戦場で生き残るための武器であり、敵を欺き、優位を築き、情勢を動かすための手段でもある。彼らの魔導戦は計算され尽くした罠のようであり、真正面から呪文を撃ち合うのではなく、戦いが始まる前に相手の戦意を削ぎ、布陣を崩し、勝利を確定させてしまうことを理想とする。非力な体格を不運と捉えることなく、それを補うために知略と魔導を極限まで磨き上げた結果、彼らは地下世界における“影の軍師”として確固たる地位を築いてきた。 地下の諸勢力において、ダーク・クキナンが共同体の参謀役として暗躍することは珍しくなく、時に氏族全体がひとつの参謀本部のように機能することすらある。彼らは他種族との関わりを積極的に求め、同盟という形で強者と繋がることで自身の弱点を補完し、また相手の欠点を補って繁栄を続けてきた。武勇に優れながら知性に劣る種族がダーク・クキナンを「利用しているつもり」で協力関係を結んだ際、気づけば主導権を握っているのがダーク・クキナンだったということは少なくない。これが彼らを「小賢しい小人族」「強者に寄生する腰巾着種」と揶揄する声の理由であり、その評判は地下世界の長い歴史の中で、良くも悪くも焼きついてしまっている。 もっとも、その印象のすべてが誇張というわけではないが、彼らが皆生まれつき狡猾で陰険というわけでもない。むしろ生物学的には“学習能力が高く理性的な者が多いだけ”であり、環境的に“策謀に長けた者が成功者となり易い”という偏りが発生しているに過ぎない。しかしその「生物としての事実」は人が知り得ることでなく、結果として悪評だけが広く浸透した。だがその偏見に抗う術は、彼ら自身も“評判を得ねば同盟者を得られない”という危機感ゆえに十分理解しており、信頼されるために努力する者も多い。彼らは狡知だけでなく、冷静な計算に基づいて“信頼を勝ち取る必要性”を自覚しているのである。 その知性は感情理解の面でも異彩を放つ。ダーク・クキナンは理路整然とした会話を好み、感情を“知識として理解すべき対象”と捉える傾向がある。激情や衝動を“理解不能なもの”として切り捨てるのではなく、あくまで研究対象として冷静に扱い、“衝動で生きる者たちとも表面上の付き合いをこなす”器用さを身につけている。そのため、理性と教養によって会話が成立する相手を深く尊重し、対等な敬意を払うことを躊躇しない。一方で、衝動に任せて行動する者は、知性の欠如した危険因子として下に見てしまい、“利用対象”として扱うことさえある。これは侮蔑というより、生存戦略の延長にある実利的判断だと言える。 こうした性質から、ダーク・クキナンは人類社会の物理魔導文明に強い興味と敬意を持っている。圧倒的な上位者――竜に抗い、知と連帯によって文明を築き上げたフロウの在り方は、彼らにとって魅力的な研究対象であり、模範でもあった。解放戦争期には、多くのダーク・クキナン氏族が積極的にフロウ側と共闘し、物理魔導の学習と発展に寄与した。安全保障の観点からではなく、“新たな魔導体系が誕生しつつある知的刺激”に惹かれて参戦する者も多かったことは、彼らの特性をよく示している。その結果、人類との間に築かれた学術的・文化的な同盟関係は、地下世界戦略における重要な結びつきとして現在まで続いている。 とはいえ、地上で大規模な共存を行うには、生息圏の差があまりに大きい。光を嫌い、暗闇でこそ本領を発揮する彼らは、主に地下領域の防衛幕僚として招聘されることが多く、地上社会で日常的に姿を見ることは少ない。フロウに対して友好的な傾向が強いとはいえ、彼らにとって地上種族はあくまで“数多ある同盟候補のひとつ”でしかなく、状況によっては寝返りもあり得るし、事実としてあった。これは彼らの打算的な本質に基づく判断であり、フロウ側が“地下防衛の中枢情報を握る参謀として彼らを迎えることに抵抗感を抱く”理由でもある。もちろん寝返りは人類同士でも珍しくはないが、異種族であるがゆえに、信頼の構築には常に繊細な努力が求められる。 さらに、ダーク・クキナンという種族を語るうえで欠かせないのが、生来備わった強力な抗魔力である。これは同じく力を有するダーク・ティスリと共通する資質だが、その運用思想は大きく異なる。ダーク・ティスリが抗魔力を盾に白兵戦へと踏み込み、近距離で敵を叩き伏せるのに対し、ダーク・クキナンは非力ゆえに肉弾戦を選ばず、抗魔力を“魔導戦を制圧するための基盤”として扱う。敵の呪文を正面からはね返し、魔導戦の主導権を握り、その瞬間に精霊魔導を叩き込む――この連続こそが彼らの戦術の核心であり、同格の術者相手なら魔導戦を圧倒することさえ珍しくない。 しかし、彼ら自身は“魔導戦で勝っても戦いが終わるとは限らない”ことを誰よりよく理解している。白兵戦へ移行すれば致命的に不利なのはもちろん、根本的に継戦能力が低く、追撃戦や掃討作戦のような長期の戦闘行動に耐えられない。敵の主力を魔導戦で崩せても、壊走兵を追って殲滅することはできず、結果として“戦争の決定打”にはなりにくい。この現実を痛いほど理解しているからこそ、彼らは同盟者の存在を絶対条件とし、自らの戦力を“戦局を揺り動かす一撃”として限定的に用いる。抗魔力は彼らにとって最大の矛であり盾だが、それだけでは戦争という長い営みを制することはできない――この冷徹な自覚こそが、彼らが極端な合理主義と周到な軍略を磨いてきた理由である。 種族全体の気質としては、共同体内部で特別に濃密な絆が結ばれるわけではないが、必要とあらば“種族のために個人を犠牲とする”判断を冷静に下せる者が多い。これは冷酷なのではなく、“弱者ゆえの危機感”に基づく合理的な判断である。典型的な封建貴族が「民は数字である」と考えるような冷徹さとは異なり、「同胞ではあるが、状況がそれを必要としている以上、やむを得ない」という理性による自己説得が働く。階級制度も存在するが、世襲制は主流ではなく、効率的な人材配置という範囲での秩序に過ぎない。 こうした徹底した合理主義と危機感は、地下世界では常に“弱者として生き残るための知略”として働いてきた。しかし地上社会に身を置き、強大な同盟者に守られた環境を得たとき、ダーク・クキナンの策謀は初めて純粋な“戦略”として発揮されるようになる。もはや生存のための苦肉の策ではなく、世界と渡り合うための知恵として才能を振るえるのだ。そうした自由な立場で軍略を任されたダーク・クキナンが歴史に名を刻むことは決して稀ではなく、優れた名将として崇められた者もいれば、同じだけ恐るべき奸雄として語られた者もいる。弱者ゆえの制約から解き放たれたときこそ、彼らの知性はもっとも鋭く、もっとも破壊的な力を持つのである。
一般的な身長・体重の範囲
■フローラント版ゲームデータ サイズ:小型。 アーマー・クラスに+1サイズ・ボーナス、攻撃ロールに+1サイズ・ボーナス、〈隠れ身〉判定に+4サイズ・ボーナスを得るが、中型のフロウ達が使うより小さな武器を使わなければならず、運搬能力の上限は3/4になる。データ上に明記されないが「小型だけど専有面積は中型と同じ」ことによる様々なメリットやデメリットを受ける場合がある。半マス先に届かないとか。 能力値修正:【筋力】-4、【耐久力】-2、【知力】+1、【判断力】+2 移動速度:20フィート。 属性:多くのダーク・クキナンは秩序である。 視覚:暗視120フィート。 暗闇の中でも白黒で見通せる。つまり色の識別は不可能。 セーヴボーナス:占術系呪文・効果に対するセーヴに+2種族ボーナス。 防御特性:呪文抵抗11+キャラクター・レベル。 標準アクションでオンオフ可能。 技能ボーナス:〈真意看破〉〈はったり〉に+2種族ボーナス。 呪文特性:占術呪文使用時のセーヴ難易度に+1。 光による盲目化:明るい光(太陽光とかデイライトの呪文とか)に突然晒されたダーク・クキナンは、1ラウンドの間[盲目]状態になる。これに加えて、明るい光にさらされている最中、ダーク・クキナンは、すべての攻撃ロール、セーヴ、判定に-1の状況ペナルティを受ける。 言語:出生地に依るが、基本的にはクキナン語。 ■マスターズ・コメント D&Dで言うところのディープ・ノーム。あっちは猜疑心が超絶強いスーパー閉鎖的種族で、得意なクラスはローグという設定だから大違いだが。でもダークエルフ物語に出てきたディープ・ノーム、気の良いやつだったんだよなぁ。 ●マオナム  マオナムは、全方向に好奇心旺盛な天性の旅人である。彼らは「寸詰まりに縮んだ小人」と形容されるように、小柄でありながら豊かな体積を持つ特異な体型をしており、クキナンが「完璧な縮尺で縮んだ小人」だとすれば、その対照的存在と言える。だがその見た目から想像されるような鈍重さは皆無で、実際には軽やかで俊敏、跳ね回る球のような機動力を誇る。短い歩幅を補う強靭な体幹により、不整地でも驚くほどの速度を発揮し、しばしば「最速の小人」と称されることもある。 好奇心の赴くままにあらゆる場所へ入り込み、遠慮という概念を知らぬままに行動するため、どの土地のどの集落にもマオナムの姿を見かけることができる。彼らは物怖じせず、初対面の相手にもずけずけと話しかけ、商業区では早口でまくしたてるマオナムの姿がもはや風景の一部と化している。しかし、饒舌さと社交性が必ずしも調和しているわけではなく、理路整然と相手を説得する力には乏しい。そのため、善意で動いたつもりが誤解を招き、トラブルメーカーとして扱われることもしばしばである。 とはいえ、全員が無分別というわけではない。話術に長け、機転の利くマオナムは、物怖じしない性格と相まって人脈を広げ、都市の人気者となることも多い。誰とでも分け隔てなく接するその気質は、他種族との潤滑油としても機能しており、フロウ社会の中でも比較的受け入れられやすい存在である。 マオナムは食べることが大好きで、食事は単なる生存のための行為ではなく、人生の喜びそのものと捉えられており、食卓を囲む時間は彼らにとって最も幸福なひとときだ。酒も好むが、キゲインほどの酒豪ではない。彼らが愛しているのは酔うことではなく、仲間たちと語り笑いながら杯を交わす「宴会という行為」そのものなのである。 危機に直面したマオナムは、まず真っ先に逃げる余地を考え、迷うことなく実行する。 だが、これは臆病ゆえの行動ではない。体格の不利を弱点とは認識しておらず、身軽で動き易いとしか思っていないので、立ち向かうより相手にしない方が「楽に勝てる」と知っているからだ。 彼らはむしろ勇敢でさえあり、「逃げるべき時には逃げ、戦うべき時には戦う」という本能的な判断力を備えている。意味のない戦いを避ける冷静さを持ちながらも、助けられる仲間がいるとわかれば躊躇なく身を挺する。その勇気は衝動ではなく理性の上に成り立っている。 幼い頃から石礫や投げナイフを使いこなす訓練を受け、体力の少なさを補うため、距離を取って戦う戦術を磨く。中でも弩は、非力な体格でも扱いやすく、彼らの代表的な武器である。巧みな狙撃術、狭い地形での迎撃戦など、マオナムの弩兵は小柄ながらも侮れぬ戦力として知られている。 15歳で成人し、寿命はフロウよりやや長い程度である。非長命種であるため、混血による長命問題とは無縁であり、種としての繁栄は安定している。彼らは古代より自由気ままな生活を送ってきたが、戦闘力の低さを自覚しており、積極的に外界へ進出することは少なかった。安全な土地にマオナム庄を築き、脅威が迫れば迷わず逃れ、新たな土地に再建する――その柔軟な生き方が、彼らの種の長い歴史を支えてきた。 しかし解放戦争以降、フロウが築いた文明社会との交流に魅了された若者たちが次々と旅立ち、都市で暮らすマオナムが急増した。彼らはキゲインやクキナンのように職人や学者として名を馳せることは少ないが、その代わり、どの土地にも溶け込み、人と人の間に新たな関係を生み出す。彼らが「何もないところに何かを起こす種族」と呼ばれるのは、その旺盛な行動力ゆえである。 一方で、その奔放さが悪事に転じることもある。身軽さと無遠慮さを悪用すれば、盗賊や隠密としては極めて優秀だ。日頃のやんちゃ程度であれば、愛嬌のある見た目と悪意のなさが彼らを赦せてしまうが、善良でないマオナムほど厄介な存在はいないとも言われ、「絶対にアーミアと組ませてはいけない」と冗談まじりに語られることもある。残念ながら、マオナムに「倫理観がしっかりしている」「誘惑に強い」といった評判は存在しないのだ。 もちろん、彼らが迷惑ばかりかけるわけではない。善意で行動する時も遠慮を知らず、助けたい者を助け、言いたいことを言う。気恥ずかしさや「迷惑になるかも」という抑制が存在しないため、その真っ直ぐさに救われる者も少なくない。こうした奔放さから、アーミアについで奔放神の信徒が多いとも言われており、実際、信仰的な親和性は高い。 マオナムの最も誇るべき善性は、差別意識や迫害意識の欠如である。彼らは他人や他種族を外見や出自で判断せず、常に「個人としてどうか」を基準に評価する。貴族と平民のような階級意識の存在は理解しても、そこに憎悪や偏見を持ち込むことはない。どの種族が優れているかなどという発想そのものを、彼らは理解しないのだ。自由奔放で、衝動的で、そして根っから平等主義者。この天真爛漫な公平さこそが、彼らが多くの種族に愛され、時に厄介に、そして確実に人類史を賑やかにしてきた理由である。
■フローラント版ゲームデータ サイズ:小型。 アーマー・クラスに+1サイズ・ボーナス、攻撃ロールに+1サイズ・ボーナス、〈隠れ身〉判定に+4サイズ・ボーナスを得るが、中型のフロウ達が使うより小さな武器を使わなければならず、運搬能力の上限は3/4になる。データ上に明記されないが「小型だけど専有面積は中型と同じ」ことによる様々なメリットやデメリットを受ける場合がある。半マス先に届かないとか 能力値修正:【筋力】-2、【敏捷力】+2。 移動速度:20フィート。 軽足:移動アクション以上を消費しての移動に際し、移動困難地形によるペナルティを一段階軽いものと扱う。 5フィートステップの条件を軽減しない。グリース等を無視しない。移動していない状態でのあらゆる不利益は通常通り被る。 視覚:通常視覚。 セーヴボーナス:すべてのセーヴに+1。[恐怖]効果に対してさらに+2種族ボーナス。 攻撃ボーナス:投擲武器および投射武器による攻撃ロールに+1種族ボーナス。 技能ボーナス:〈聞き耳〉〈忍び足〉〈跳躍〉〈登攀〉に+2種族ボーナス。 言語:出生地に依るが、基本的には大陸語かマオナム語。 都市部のマオナムは、マオナム語を喋らずとも暮らしていけるし、全員がバイリンガルとなるほど教養があるわけではない。 ■マスターズ・コメント 中つ国のホビットは閉鎖的な引きこもり種族なんで、大違いである。 ●  潜在魔力量とは、あらゆる生命体が生来、そして現在進行形で体内に内包している魔力量を指す概念である。これは単なる魔導師の資質や才能を示す抽象的な指標ではなく、現時点でその生命が保持している、実在するエネルギー量そのものを意味する。生命力や魔導脈と密接に結び付いた存在であり、三者は不可分の関係にある。より正確に言えば、生命力と魔力が合わさった総体こそが、その存在が「生きている」という事実を支える根源的な力であり、人間に限らず、生物が活動し続けるための基盤となっている。 潜在と呼ばれてはいるが、これは一般に想起される「潜在能力」や「将来性」といった意味合いとは異なる。才能の有無や、将来的に開花するかどうかを示すものではなく、あくまで現在の身体の内側にどれだけの魔力が蓄えられているかという、即物的な量的概念である。感覚的には、一般的な魔導理論において語られる最大魔力量や資質値ではなく、日常的に消費と回復を繰り返す「現在の魔力量」に近い。ゆえに、潜在魔力量は固定値ではなく、鍛錬や生活環境、戦闘や魔導行使の積み重ねによって増減し得るものとされている。  魔導の心得を持たない者であっても、潜在魔力量が完全に0である例はほとんど存在しない。呼吸し、歩き、物を持ち上げ、外界からの刺激に耐えるだけでも、生命は常に魔力を消費しているからである。魔導師でなくとも、人は無意識のうちに魔導脈を通して魔力を循環させ、身体機能を維持している。戦士が音速に迫る勢いで剣を振るい、巨人の一撃を正面から受け止めるほどの強靭な体力を発揮できるのも、筋力や骨格だけではなく、自身の魔力を燃料として肉体を駆動させているからに他ならない。 生来の潜在魔力量が多い者は、一般に魔導師としての適性が高いと見做される。初期値が高い個体が、その後まったく成長せずに終わる例は稀であり、伸び悩みや想定ほどの発展を見せなかったケースはあっても、結果として平均的な人間よりも多くの魔力量を保持することになる場合が大半である。一方で、生来の潜在魔力量が少ない者が、不断の努力や長年の研鑽、大器晩成によって大成する例も確かに存在する。ただし統計的に見れば、生まれつき多くの魔力量を有する者の方が、最終的に高い到達点へ至る割合が高いのも事実である。 この関係は、肉体能力に置き換えれば、生まれつき心肺機能が高いかどうかを見る感覚に近い。鍛えれば誰でもある程度は向上するが、初期状態の差は完全には埋まらず、長期的には明確な差となって現れる。潜在魔力量も同様であり、才能と努力の双方が結果を左右するが、初期値の影響が消えることはない。 そのため、魔導学院では入学時にまず潜在魔力量の測定が行われる。これは選別のためだけではなく、個々人に適した教育方針を定めるための基礎資料でもある。魔導は本質的に学問であり、高度な理論研究や魔導工学、補助魔導の分野では、必ずしも高い魔力量を必要としない領域も多い。そのため、潜在魔力量が低いことを特段問題視せず、研究者としての道を選び、大きな業績を残した者も決して少なくない。 一方で、特別魔力量が重視されるのは戦闘を前提とする者たちである。呪文の行使は魔導脈を通じて莫大な魔力を一気に消費するため、戦いに魔導を扱う者にとって、潜在魔力量の多少は生死に直結する要素となる。魔導師に限らず、前線に立つ軍人や冒険者、傭兵であっても、自身の力量や適性を把握する必要がある場合には潜在魔力量を測定されることは珍しくない。傭兵組織ファヴにおけるランク審査でも、当然のようにこの項目は確認される。 総じて、潜在魔力量が高いということは、原則として「強い」ことを意味する。ただしそれは絶対的な指標ではなく、技術差、経験差、戦術理解によって結果は大きく振れる。にもかかわらず、この数値が軽視されないのは、あらゆる行動の基盤となるエネルギー総量を示す指標であり、最終的な成長や限界値に強く影響を及ぼすからである。ゆえに潜在魔力量は、才能でも称号でもなく、生命そのものが内包する「現在の力」として、社会のあらゆる場面で静かに、しかし確実に重視され続けている。 ■マスターズ・コメント  身体測定なのにガッツリ着てるのはおかしいし、左上にMPメーターなんて余計なものがあるからボツになったけど、可愛いから載せる。 なお高レベル呪文な上に追加の触媒代もかかるんで「片っ端から調べて回る」は非現実的である。 試しに「50回使える魔法のレンズ」としてマジックアイテム価格を計算したら、銀貨20万枚を軽く突破した模様。 ●  塩商人10/交易商7/政治家12 筋力8/敏捷力10/耐久力9/知力20/判断力20/魅力18/PB42 アルサッタ・ラザード侯爵は、バーン帝国に連なるラザード侯爵家の当主であり、港湾都市ゼナの市長である。種族はティスリ。 ティスリの例に漏れず、その容姿は人目を引く美しさを備えているが、印象を決定づけるのは美貌そのものではない。金髪をきっちりと結い上げ、知的な眼鏡の奥から向けられる鋭い眼差しは、感情よりも理性、温情よりも判断を優先する人物であることを雄弁に物語っている。 彼女は就任以来、100年以上という長きにわたってゼナ市長の座に在り続けてきた。都市の表情が幾度も塗り替えられる歳月の中で、その頂点に立つ顔だけが変わらなかったという事実は、ゼナという都市そのものの性質を象徴しているとも言える。 人々が彼女を《久遠の長》と呼ぶのは、その長命ゆえである。しかしこの二つ名は、単なる寿命の長さを示す称号ではない。変わらず在り続ける存在への畏敬と、あまりにも長く権座にあることへの揶揄、その双方を含んだ呼称として定着している。 アルサッタはゼナの老舗にして屈指の大塩商人、ギャスガイサ商会当主レインディランの養女である。血縁ではなく、交易の世界が生んだ必然によって結ばれた関係だった。かつて商会の商船がホウルティーアの海賊に襲撃され、優秀な船長であった実父は命を落とし、母はその後を追うように自ら命を絶った。その結果として、アルサッタはレインディランに引き取られることとなる。 もっとも、その養育は配下への配慮や同情だけに基づくものではなかった。実父は商会でも腕利きと評されており、アルサッタ自身も幼い頃から経理を学び、その才覚は早くから周囲に知られていた。そうした資質と将来性が、レインディランの眼鏡にかなったのである。彼は後年、「部下への気遣いもあったが、優秀さと美しさがなければ引き取ることはなかっただろう」と公言しており、その言葉は商人としての冷徹さと率直さを何よりも雄弁に物語っている。 アルサッタ自身は、この現実主義を当然のものとして受け止めている。交易の世界では日常的に死者が出る。だからといって、その都度遺された者を引き取ることなどできない。それは理解すべき現実であり、恨むべき理不尽ではない。親に頼れなくなった時、自らの力で生きるために学び続けてきただけであり、その努力と能力を評価されたことを、彼女は誇りにこそ思え、不快に感じたことは一度もないという。むしろ、レインディランに対しては深い感謝と恩義を抱いている。  こうしてアルサッタは、ゼナ屈指の名うてであるレインディランの下で徹底的に鍛え上げられた。幼い頃から身につけていた経理の知識は、単なる学びの成果に過ぎず、実際の取引と責任の重さの前では常に試され続けることになる。数字そのものではなく、その裏にある意図、帳簿に現れない危うさ、取引相手の呼吸や迷い――そうした実務の感覚を、彼女は現場で叩き込まれていった。 基礎があったからこそ吸収は早く、レインディランの教えはみるみるうちに血肉となった。帳面の上ではなく、港と倉庫と交渉の場で積み重ねられた経験こそが、後にアルサッタを単なる優秀な商人ではなく、都市を動かす存在へと押し上げる礎となっていく。 結果として、アルサッタが天才的と評される商才を備えていたことが誰の目にも明らかとなるのに、然程の時間は要さなかった。金勘定の正確さに留まらず、勝機を嗅ぎ取る目敏さと嗅覚、人の欲と恐怖を見抜く洞察、そして場を支配する人心掌握と交渉術において、いずれも群を抜いている。その一方で、彼女は露骨な欺瞞や背信といった後ろ暗いやり口を本能的に忌避する矜持を持ち合わせており、利益のためなら何でも許されるとする商人像とは一線を画している。 彼女は慈愛に満ちた笑顔や温もりで人を包み込むタイプではない。取引の場に立つアルサッタは、感情を排した計算によってすべてを動かしているかのような印象を与えることが多く、その姿は「理屈の種族」と称されるティスリの一般的なイメージを裏切らない。冷静で、鋭利で、隙を見せない。そのため、近寄りがたい人物だと評されることも少なくない。  しかし、その表層的な印象の奥から、ふとした瞬間に垣間見える可愛げは、周囲に与える影響があまりにも大きいと囁かれている。常に理で固められた人物であるがゆえに、わずかな人間味が覗いた時、その落差は強烈な引力となる。その効果を彼女自身がどこまで自覚しているのかは定かではないが、結果として多くの人心を惹きつけてきたのは確かである。 こうした手腕によって、アルサッタは元来「ゼナ屈指」と評されていたギャスガイサ商会を、疑いようもなく「ゼナ随一」の地位へと押し上げた。その成功は偶然でも幸運でもなく、彼女自身の能力と判断の積み重ねによってもたらされた必然であった。 ゼナは本来、複数の大商人たちによる評議会制を採る自由商業都市であった。しかし627年、《マッセルの黄薔薇》事件を境にその体制は見直され、都市の代表として市長を立てる制度へと移行することになる。評議による合議ではなく、都市の意思を一身に担う存在が必要だと判断された結果であり、その最初の市長に投票によって選ばれたのがアルサッタであった。 彼女の選出は高い得票率によるもので、その最大の理由が卓越した実力にあったことは疑いようがない。ただし、それだけで説明できるほど単純な話でもない。アルサッタは若い頃から、ゼナの一部の豪商の若旦那たちを集め、交易や都市運営を学ぶための勉強会を連綿と築き上げてきた。この集まりはやがて《リューベック会》と呼ばれるようになり、名目上は学びの場でありながら、実質的にはアルサッタを中心とした人的ネットワークとして機能していく。  なお《リューベック会》という名称は、星渡りの民の歴史においてかつて隆盛を誇った商業同盟に由来するものである。遠隔地の都市同士が結束し、交易路と経済的利益を共有することで、王侯や国家すら無視できない影響力を持ったその同盟は、商人による自治と連帯の象徴として語り継がれてきた。ゼナの若き商人たちがこの名を選んだのは、単なる学びの場を超え、都市の未来を左右し得る結束体であろうとする意志の表れであり、同時に商人が力を合わせることで歴史を動かし得るという理想への明確な憧憬でもあった。 無論、商人としての格、実績、財力といった点だけを見れば、彼女を上回る大商人が存在していたのも事実である。しかし投票の結果において、そうした人物たちはアルサッタに及ばなかった。都市の未来を誰に託すのかという問いに対し、より多くの票を集めたのは、彼女が長年にわたって積み重ねてきた信頼と結束だった。 《リューベック会》は、率直に言えば「アルサッタに惚れ込んだ若旦那たちによる同盟」のような組織でもあった。半世紀にわたり、彼らは影に日向に彼女を支え、守り続けてきた。その結束は極めて強固であり、都市の内外における様々な局面で、彼女の背後に常に存在し続けたと言われている。 一説には、アルサッタが生涯にわたって特定の伴侶を持たず、独身を貫いているのは、このリューベック会の存在が影響しているとも囁かれている。ただし、それが事実であるかどうかは定かではない。 いずれにせよ、市長となることは偶然でも担ぎ上げでもなく、アルサッタ自身が明確に望んだ選択であった。都市を動かす立場に立つこと、それ自体が彼女の意志であり、ゼナという都市がその意志を受け入れた結果が、現在の体制なのである。 アルサッタは、聡明かつ鋭利な為政者である。彼女は、巧みな指導能力を持つ者による独裁が、衆愚に委ねられた政治よりも遥かに効率的であることを、理屈としてだけでなく実践によって理解している。ゼナの商人や民衆に対しては、自由都市としての気風と誇りを強く意識させ続けてきたが、それは自然発生的なものではない。民意は常に誘導され、方向付けられ、その結果として都市は極めて効率的に支配され、発展してきたのである。人々が「自分たちで選び、守っている」と信じている秩序こそが、彼女の手によって設計された統治の完成形であった。 バーン王国がゼナに併合を迫った際、アルサッタは抵抗の意志を示した。その姿勢は市民の目にも明らかであり、交渉と牽制を重ねる中で、都市としてできる限りの選択肢を探り続けた。しかしバーンが示した経済封鎖という手段を前に、彼女は最終的に、ほぼ無血での恭順を選び取る。一都市としては巨大な海軍と傭兵戦力を保有するゼナが、なぜ戦わなかったのかという声は、当時も今も小さくない。 だがその選択は、誇りを捨てた結果ではなかった。アルサッタにとってそれは、誇りを抱いて滅ぶよりも、実利を取って生き延びるという、あまりにも商人的な判断に過ぎなかった。彼女は、ゼナが誇ってきた「自由都市の商人としての気概」と誇り高さを美徳として認めている。しかし同時に、商人が実利よりも誇りを優先し、その結果として都市が滅びることを、徹頭徹尾ナンセンスだと考えていた。 アルサッタの選択は、市民の理想を裏切ったものではなく、その理想を存続させるために現実を選び取った決断であった。その冷徹さこそが、彼女を英雄ではなく、為政者たらしめている。 アルサッタは、傭兵組織ファヴの誕生にも多大な助力を与えた人物であり、実質的にはその創始者の1人と数えられている。組織としての体裁、雇用の保証、信用の構築――それらは剣や血だけでは成立しない。交易と契約、資金の流れと都市の利害を理解する者の存在が不可欠であり、その役割を担ったのが彼女であった。 後にファヴがバーン王国と対立関係に陥った際、その衝突が全面的な武力衝突へと発展せず、小競り合いの範囲に留まったことは、ゼナにおいてよく知られた事実である。最終的にファヴは本拠地をゼナから移転することになるが、その過程が比較的穏健に進んだ背景には、「唯一存命する創始者」としてのアルサッタの尽力があったとされている。 彼女は王国の側にも、傭兵の側にも過度に与することなく、双方が決定的な一線を越えぬよう調整を重ねた。結果としてゼナは大規模な流血を免れ、ファヴは組織としての存続を果たす。その静かな決着は、表立って語られることは少ないが、都市と裏社会の均衡を知る者ほど、その重みを理解している。 バーンへの恭順後、アルサッタは末娘エイレンファナを皇太子チェスター・ファーランド公爵に嫁がせる。その結果として、彼女自身はラザード侯爵位を授かり、皇帝の系譜に名を連ねる立場となった。この婚姻は明確な政略であり、ゼナという都市とバーン中枢を結びつけるための、最も確実な楔であった。都市の未来を守るために、彼女は自らの家族を交渉の卓上に置くことを選んだのである。 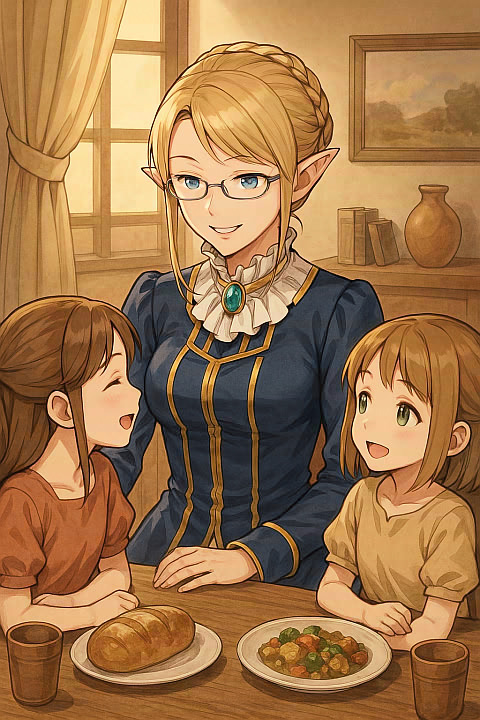 アルサッタは生涯にわたって特定の夫を持たなかった。彼女に子は5人いるが、そのすべてが養子であり、自身と同じく「優秀な部下の遺児」や「破産した商人の子」たちである。血を繋ぐことよりも、能力と縁、そして責任を重んじるその姿勢は、彼女の生き方そのものを体現している。もっとも、家族の前では為政者としての鋭さを脱ぎ捨て、穏やかな一面を見せるとも伝えられており、その表情を知る者は多くない。 白銀の聖騎士ラナーク・エルフォード伯爵とは、彼とその仲間が冒険者として名を馳せていた頃からの知己である。現在では、ゼナにおける文と武の両輪として、極めて親密な協調関係を築いている。都市の政治と防衛という二つの柱が衝突することなく機能している背景には、両者の信頼関係があると言ってよい。加えて、ラナークの細君が個人的にアルサッタの娘たちと親しい関係を結んでいることもあり、その結びつきは公私の両面にわたって安定していると評されている。 アルサッタ・ラザード侯爵という人物を、善政の体現者と呼ぶ者もいれば、冷徹な独裁者と評する者もいる。そのどちらもが間違いであり、同時に否定しきれない。彼女は理想を語ることを好まず、清廉を装うこともしない。ただ、都市が生き残るために必要な選択を積み重ねてきただけであり、その結果としてゼナは今も北海に君臨する港湾都市であり続けている。 彼女が築いた秩序は、温もりに満ちたものではない。しかし崩れにくく、現実に耐え、血と金と権力が渦巻く世界においてなお機能し続ける。人々が自由都市の誇りを語れるのは、その自由が守られてきたからであり、守られてきた理由を突き詰めれば、そこには常にアルサッタの判断があった。 《久遠の長》という呼び名に込められた揶揄と畏敬は、彼女自身が引き受けてきた時間と責任の重さそのものである。変わらぬ顔で変わり続ける都市を見下ろしながら、彼女は今日もまた、誰にも感謝されない決断を下す。その姿を、人は為政者と呼ぶのか、それとも都市そのものと呼ぶのか――答えは、ゼナが存続している限り、語られ続けるだろう。 ■マスターズ・コメント リューベック会、同世代の「若旦那」と言ってても、市長選挙のときには皆60越えた「重鎮」世代になってるから組織票の威力凄かったんだよ。 ●  貴族1/武人12/斥候4/竜猟兵10/竜哭擁空5 筋力15/敏捷力24/耐久力15/知力14/判断力16/魅力19/PB61 チェスター・ファーランドは、後に初代皇帝となるフレデリック・ファーランドの長男として生まれ、若くしてバーン帝国第2代皇帝の座に就いた人物である。 生まれながらに備えていた潜在魔力量は常軌を逸しており、「桁違い」という評価ですら生温いとされるほどであった。通常であれば、将来の大成が約束された大魔導師として育てられることに何の疑問も差し挟まれない水準であり、その魔力量は魔導師としての才能という尺度において、さらにもう1つ桁が多いとさえ言われた。 しかしチェスターの場合、その特異性は魔力量の多寡に留まらなかった。特定の系統に偏ることなく、あらゆる魔導脈において総じて高い資質を示していたため、将来の君主としては魔導師として一分野を極めるよりも、武をもって立つ存在であるべきだという判断が下される。こうして彼は、魔導師ではなく武人、すなわち騎士の道を歩むこととなったのである。 剣術においても十分に優秀ではあったが、その才が決定的に示されたのは、父フレデリックの狩猟に同行した際であった。その折に触れた弓において、チェスターは誰の目にも明らかな天才的素質を示す。一般的な騎士の修練から見れば異端とも言える選択であったが、フレデリックは迷うことなく「お前は弓をやれ」と言い切り、その一言によって、チェスターの武の主軸は弓術へと定められた。 彼の性格は明るく活動的で、常に率先して動くことを厭わず、人を自然と前へ引き出す力を持つ。冗談を交えることも多く、生まれ持った威厳に和らいだ空気を纏わせるその話術は、身分や立場を問わず人を惹きつけた。眉目秀麗で洗練された立ち居振る舞いは宮廷内に留まらず、国民からも絶大な支持、とりわけ女性からの人気を集める要因となっていた。 だがそれは単なる人気に留まらない。チェスター自身が女性の扱いに慣れており、多くの淑女から恋慕の情を向けられながらも、それが政治的・私的なトラブルへと発展する前に、巧みに芽を摘んで立ち回っていた。父フレデリックが「お前が色を好む性質ではなかったことを神に感謝するぞ」と語ったと伝えられるのは、その点に対する率直な安堵と評価を示すものに他ならない。 チェスターは17歳で、高貴な義務を果たすため遍歴の旅に出た。その旅は9年近くに及び、各地で積み重ねられた戦いと経験の果てに、彼は光の古竜アルスクルシェインを討ち果たすという、常識の外にある大功を成し遂げることになる。そもそも竜とは、成竜であれ若竜であれ、単なる強力な魔獣ではない。その存在は常に周辺の軍事・政治・交易・防衛体制に影響を及ぼし、個体としての強さ以上に、「生きていること自体」が戦略的価値を持つ存在である。 ゆえに、若竜を屠るだけでも「竜殺しの英雄」としてその土地の歴史に名が刻まれる。成竜を討てば地方の均衡は揺らぎ、老竜であれば列強クラスの国家であっても無視できぬ衝撃となり、国史に刻まれる伝説となる。これらはいずれも過大評価ではなく、竜という存在を討った場合に最低限付随する、妥当な実績評価に過ぎない。 それが古竜であったならば、その影響はもはや一地方や一国家の枠に収まらない。人類領域全体における戦略的前提が書き換えられ、その名は国史ではなく、人類史の中で語られることになる。この時点で、チェスターは一国の英雄ではなく、人類の英雄であった。実際、バーンを国家として認めていないヴィーリオン王国ですら、この偉業の持つ意味を否定することはできず、政治的立場を超えて、その偉大さを認める公式な賛辞を送ったと伝えられている。 チェスターは、神業としか言いようのない弓術をもって、この古竜を討ち果たした。その一矢が意味したのは、英雄譚の成立ではなく、戦略的現実そのものの破壊である。この瞬間、彼が皇帝の座に至る資格を疑う声は完全に意味を失い、皇位継承権は武と実績によって、もはや揺るがぬものとして確立された。  極限まで研ぎ澄まされた「技」と、莫大な潜在魔力量に裏打ちされた「力」が重なり合ったとき、チェスターの弓射はもはや1人の武人の所業として収まるものではなくなる。彼が矢を放つたび、空は裂かれ、制空という概念そのものが揺さぶられた。数多の竜を射落としてきたその戦いぶりは、やがて人々に「竜哭擁空」と呼ばれるようになる。それは、竜が恐怖と断末魔の中で哭き、空がその衝撃を抱え込むほかなかった光景を、そのまま言葉にした異名であった。  チェスターの矢は音速の数倍に達し、視認よりも先に命中する。瞬く間に無数の矢が放たれ、空間そのものが攻撃の媒介と化す。一矢は城壁すら貫く威力を備え、いずれも魔力によって極限まで増幅された武技の結晶であった。だがそれらは、いかに高度な技術を積み重ねようとも、技だけでは決して辿り着けない領域である。凄まじい魔力量を内に秘めているからこそ到達し得た、至高の境地としか呼びようのない戦闘力であった。 無論、英雄と称される存在は皆、人並外れた潜在魔力量を備えており、それゆえに超人的な力を発揮する。しかし、その前提を踏まえたうえでも、チェスターは明らかに飛び抜けていた。魔力の行使そのものに特化し、ひたすら魔力量の研鑽を積み上げてきた大魔導師と比較してなお、その保有する魔力量の総量と密度において凌駕していると語られるほどであり、武人でありながら魔力の器そのものが異質であった。 こうして定着した異名が《竜哭擁空》である。だが、皇帝に即位して以降、その呼称はさらに一段階、重さを増すことになる。チェスターは半神ではなく、神に召命された存在でもない。それにもかかわらず、人々は彼を《神弓皇帝》と呼ぶようになった。神でもない者が、神の名を二つ名に含むのは極めて異例であり、本来それは、複数の古竜を討伐し、剛毅神に召命された半神である天秤の守護者、《雷神》アノレスタンのような存在にこそ与えられる称号である。 それでもなお、チェスターはそう呼ばれた。個として神に至ったわけではない。だがその弓は、竜を哭かせ、空を抱え込ませるほどに、世界の側を歪ませた。ゆえに人々は、神ではないことを承知のうえで、彼を《神弓皇帝》と呼んだのである。 無論、古竜討伐は決して単独で成し遂げられたものではない。チェスターの傍らには、いずれも「伝説の英雄」と語られるに足る仲間たちが付き従っていた。だが、その多くは古竜との戦いの中で受けた精霊蝕により、戦後を生き延びることなく消滅している。古竜を討つという行為そのものが、勝利の代償として人の生を削り取る戦いであり、彼らはその最前線に立っていた。 弓兵という、敵と距離を取って戦う立場にあったとはいえ、チェスターが致命的な傷を負うことなく勝利できたのは、ひとえに仲間たちの献身によるものであった。彼らは前に立ち、道を切り開き、精霊蝕がチェスターに及ばぬよう、あらゆる手段を尽くした。そして口を揃えて、あるいは無言のままに、「この戦いの後に訪れる未来こそが、貴方の本当の戦場だろう」と示すかのように、自らの身を削って彼を守り抜いたのである。 チェスター自身は、その事実を痛烈なまでに理解している。自身が生き延び、皇帝として立つことができたのは、仲間たちが未来を彼に託し、自分たちの生をそこに置いていったからに他ならない。その想いを背負っているからこそ、彼の弓は軽くはならず、彼の在り方もまた軽くはならない。英雄として称えられるその背後に、決して忘れられることのない喪失と献身が積み重なっているのである。 チェスターは武人であり、その本質は今も変わらない。だが、攻めを是とした父フレデリックの路線とは異なり、彼は現在、膨れ上がった帝国領土の安定を最優先課題としている。それは彼自身の性格が穏健であるからではなく、帝国が置かれている状況が、そうせざるを得ない段階に至っているからに他ならない。度重なる戦争によって、帝国の外征能力はすでに限界に達していた。今なすべきは、新たな征服ではなく、外征によって得た広大な版図を整え、国力と人心の消耗から立ち直ることである。 遍歴の騎士として戦い続けてきた人生であり、政治の実務経験が乏しいことは、チェスター自身も重々承知している。だが同時に、ファーランド家が親子三代にわたって示してきた絶大なカリスマ性を、彼もまた疑いなく受け継いでいた。とりわけ、配下の扱いに関する勘と才覚は天賦のものであり、その力をもって有能な家臣団をまとめ上げ、彼らに支えられながら皇帝としての研鑽を積んでいこうとしている。 今、帝国に求められているのは、皇帝自らが細部にまで手を伸ばす政治手腕ではない。実力を至上とするバーンという土壌は、卓越した人材を次々と生み出す一方で、功名心と競争意識を過剰なまでに増幅させる。戦功や才覚によって引き上げられた者ほど己の正しさを疑わず、譲らず、衝突を生む――その構造は、初代皇帝フレデリックの代においても、その父の代においても、統治の中枢に立つ者たちが等しく腐心してきた問題であった。 チェスターに求められているのは、そうした有能でありながら危うさを孕む家臣や諸侯たちを排することでも、力で抑え込むことでもない。彼らを破綻させることなく束ね、帝国という巨大な枠組みの中で機能させ続ける力である。その点において、彼の武功は決定的な意味を持つ。少なくとも求心力に関して、これほど揺るぎない拠り所は存在しない。 極論すれば、「竜を殺せる存在が一番正しい」。それがフロウ社会の根底に横たわる、疑いようのない意識である。チェスターはその基準を、誰よりも明確な形で満たしてきた。だからこそ、功名心に突き動かされがちな者たちも、彼の前では己の主張を呑み込み、最終的には同じ旗の下に立たざるを得ない。彼の統治は、理念や理屈の積み重ねによってではなく、武と実績によって成立しているのである。 皇妃エイレンファナは、ゼナ市長アルサッタ・ラザードの娘である。両者の結婚は、明確な政治的意図に基づくものであり、私的な感情を前提としたものではなかった。チェスター自身もまた、自分が恋愛を自由に選べる立場ではないことを最初から理解しており、相手がどのような人物であれ、敬意と配慮をもって接するべき存在だと受け止めていた。 だが結果として、エイレンファナは彼にとって強く心を惹かれる相手であった。それは、与えられた役割としての立ち居振る舞いや完成された姿によるものではない。言葉の端々に滲む躊躇や、感情を抑え込む癖、その奥に隠された本来の在り方を含めて、彼女という個人そのものに惹かれたのである。政略によって結ばれた関係でありながら、チェスターは最初から、役割ではなく1人の人間として彼女を見ており、個人としても彼女を愛している。 エイレンファナは、「皇帝の妻」として在ることを前提に、言動や感情の示し方までも役割に合わせて整えられ、矯正される中で育ってきた人物であった。正しさとは常に「ふさわしいかどうか」で測られ、自然な反応は抑えるべきものとして扱われてきたのである。  そのため、チェスターが「気を許しても問題ない」と認識した相手に向ける態度は、彼女にとって完全に想定外であった。形式に寄り添うことなく距離を詰め、気づけば感情の奥に触れてくるその在り方は、意図が読めず、戸惑いと警戒を呼び起こした。エイレンファナは当初、それを好意として受け取ることができず、むしろ、庶民の娘を弄ぶ意地の悪さだと感じることすらあった。 だが時を重ねるうちに、彼女は次第に違和感を覚えるようになる。チェスターの言動には、駆け引きめいた匂いも、優位に立とうとする気配もなかった。引き出されているという感覚はなく、自然と応じてしまう。そのたびに尊厳が損なわれた感触は残らず、むしろ、役割の外にいる自分を前提として扱われているという事実だけが積み重なっていった。 それは技巧を誇示するものでも、狙いを悟らせるものでもない。ただ、彼女という個人に向き合っているからこそ生じる距離感であり、振る舞いであった。エイレンファナはやがて、それが嘲弄でも戯れでもなく、チェスターが自分を気に入り、好んで関わろうとしているからこそ生まれている態度なのだと理解するに至る。 現在、2人の関係は極めて良好である。政略によって結ばれた夫婦でありながら、互いを一個の人格として尊重し、信頼と親しみの上に成り立つ関係を築いている。  皇弟ミラード・ファーランドとの関係も良好であり、チェスターは彼を、高貴な義務を果たして凱旋した暁には、自らと並んで帝国の将来を担う存在になる大器だと信頼している。その評価は兄としての情に偏ったものではなく、周囲から見ても妥当なものであり、この認識に異論を挟む者がいるとすれば、それは人物評よりも穿った見方を優先する者であろう。 チェスター・ファーランドは、戦争を望む男ではない。剣や弓を手に取ることに躊躇はなくとも、それを振るう理由を、彼は常に選び続けてきた。竜を屠ったのも、帝国の頂に立ったのも、求めた末の栄達ではなく、そうせざるを得ない局面において、ただ最善を取り続けた結果に過ぎない。 だが彼に託された帝国は、すでに穏やかさとは程遠い場所にあった。度重なる外征の果てに膨れ上がり、傷を抱え、なお次の衝突を孕んだ、極めて厄介な状態の国である。チェスターはそれを理解したうえで、戦いたいとも、逃げたいとも思わず、そのすべてを当然のように引き受けた。 神ではない。半神でもない。 それでも《神弓皇帝》と呼ばれるのは、彼が力を誇示したからではない。戦わずに済む未来を望みながら、戦わなければならない現実から目を逸らさなかったからだ。 かつて空を裂いた矢は、いまも彼の手の中にある。 それは振るわれるためではなく、振るわずに済む時代を迎えるまで、置かれ続けるための弓である。 チェスター・ファーランド――望まずして、最も重い時代を任された皇帝の名である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■冬コミ新刊(火曜日 南a09ab) ●機動戦士Gundam GQuuuuuuX軍事読本02 いつものやつだ! 「そうはならんやろ!」「なっとるやろがい!!」なやつだ! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■捕虜英雄 #01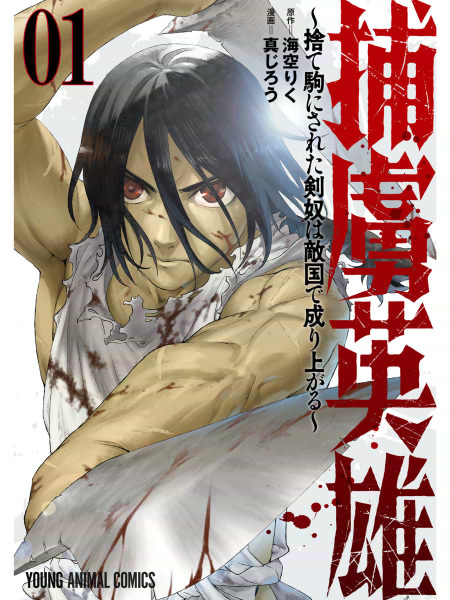 拍手で教えてもらったやつー。 内容がサブタイトルで説明されてて楽だな!!  つまり魔法王国カストゥール!!! 繁殖させずに絶滅を企図してるとしたら、その先細りするばかりの労働力に頼った政策はどうなるんだ(笑)  1日中肉体労働していると考えたらこれでも「徐々に痩せ衰えて最終的には死ぬ」ラインの食事ではあるんだが、それでも元の環境が酷過ぎるってのと、確かに「捕虜への待遇」としてはかなり立派である。 第2次世界大戦の「ネタ話」として、イタリア軍の捕虜になったイギリス軍の士官が、食事の豪華さに驚いたんだけど、「昨日は間違って兵士用の食事を出してしまってすまん。明日からはちゃんと士官用の出すから、捕虜虐待されたなんて後で言わないでくれない?」って言われたなんてのがあるな(笑)  立派なお姫様だなぁ。戦いの規模が大きくなって、物理的にそんなことするの不可能なことになったらどうなるのかなぁ。 ……なんて考えてますんよ! そんなそんな!!! いやマジで好感度高いと思ってますから!!!! そうなったらそうなったってだけの話で、そういった姿勢を持っていたことはとても素敵だと思ってますよ!!!  拙者、この手の高慢そうな高貴キャラが後々生涯の友となる展開大好き流の目録。いざ尋常に勝負!!!  そーゆーところだぞ!!! なお、別に一騎打ちで負けてズタボロになっているのではなく、後のシーンで起きた別のトラブルです。 てか血液型の認識がちゃんとある異世界ファンタジーなのな。こーゆーの、勝手に「理由」を深読みしがちで困る。 ネーミングが完全に地球由来なのもあって、異世転してきた奴らが知識や文化をある程度伝播せた世界なのか、とか考えちまう。 そーゆーの一切関係ない作品が大半なのは百も承知なんだけどね!!!!(笑) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ふつうの軽音部 完全にラブコメ路線に進入して行っちまってるよ! はい! 解散! もう読むの辞め!! チキショーメ!!! そりゃバンドやるようなやつらは色恋しますわな! ぼかぁ色恋よりイロコイの方が好きですよ! ヘリボーン開始!!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■列強超大国、最後の一角 ●北界連邦ホウルティーア  ホウルティーア連邦は、ヴィーリオン王国やバーン帝国と海を挟んで向き合う北方大陸の果てに築かれた、極寒の大地と過酷な環境を生き抜くために複数の氏族が寄り集まった連合国家である。開拓を主導したのはロシア系や北欧系の星渡りの民であり、彼らが選んだ土地は、地球の祖国と類似する環境を持つ、即ち大陸でも最も厳しく痩せた未開の地だった。 畢竟、この厳境を前にして力を合わせなければ生存できない状況にあったことは確かであり、その現実を受け止め、ばらばらの氏族が共存できる枠組みとして「緩やかな連合体=連邦」という形を具体化し、国として成立させたのが、真機ルパティ・クォーヴの操士として知られるフリストフォル・イズゥムルートである。彼はこの地を故郷としたばかりでなく、散在する氏族の利害を調停し、ひとつの連邦国家としてまとまりを与えた、その政治的・歴史的な功績によって現在も広く敬意を払われている。 だが、こうして成立した国家であっても、人口の大半を占めるのは現地人民族である。列強の中でも星渡り比率が最も低い理由は単純で、過酷な地ゆえ大規模な移住が継続しなかったからだ。膨大な氏族が寄り集まり、互いに協力を強いられる環境が、現在の連邦体制を自然と形づくったのである。 国土は広いが痩せており、生産力は全体的に低い。この弱点を補うように海軍力が異様に発達した。とはいえ彼らが持つのは大型の交易船ではなく、軽量なガレー船が中心で、用途は専ら上陸戦や略奪――つまり「遠征」である。ヒノワのように大資本が巨大商船団を持つ文化はなく、交易はほぼ個人レベルの商人によって行われる。その往来は常に危険と隣り合わせだが、彼らはそれを当然のものとして受け入れている。 統制力の低さゆえ、軍船の数に対して国家としての侵攻力は低く、烏合の衆と評されることも多い。しかし、個々の戦士の力は極めて高く、脅威の度合いは決して低くない。主要な輸出品は動物や魔物から得られる軽量で高価な素材類で、重く輸送効率の悪い鉱石は国内で使われることが多い。また、ホウルティーア産の強烈な酒はキゲインを中心に人気が高い。 彼らは大陸各国から「蛮族国家」と恐れられているが、一方で商取引は頻繁に行われ、敵対と交易が同じ日に成立することすら珍しくない。ただし商売の手腕はヒノワほど洗練されておらず、数字や合理を重視するよりも義理・メンツ・感情を優先する。その結果、しばしば大雑把な取引になるが、時に金銭よりも信頼を重んじ、疫病の村へ迷わず薬を届けた商人の逸話のように、深い人間的な絆を生むこともある。 宗教観はその生存戦略と密接に結びつく。主神は剛毅神であり、彼らの生活や価値観の核心である「生き残るために戦う」「困難に立ち向かう」思想が根付いている。強き者は雷光神に、沿岸の戦士階級は砕波神に、非戦士階級は選命神や氷雪神に、魔導師は極光神にそれぞれ信仰を寄せる。いずれもホウルティーアという土地柄と完全に噛み合った神々であり、この国の宗教体系はまさに“環境適応の産物”である。 社会全体を一言で表すならば「適者生存」であり、それは大陸側が抱く“命の軽視”という印象とは根本的に異なる。ホウルティーア人にとって命は極めて貴重な資源であり、その“使い所”を誤ることをこそ忌避する。無駄に捨てることを良しとせず、しかし必要とあれば躊躇なく差し出す。単純に、この地では“必要となる状況”が多すぎるだけなのだ。 また、ホウルティーアは列強で唯一奴隷制度を存続させており、捕虜や大陸に跋扈する闇商人を通じてホウルティーアに"入荷"した商品を購入することが一般化している。亜人を奴隷とすることすら散見され、これがまた大陸社会との価値観の断絶を深めている。 ホウルティーアの魔導文明は、列強諸国の中でも特異な発展を遂げている。最も顕著なのは、魔導艦や呪甲装兵に代表されるような大型魔導具の開発力が、大陸の文明圏に比べて著しく遅れている点である。これは、過酷な自然環境と絶え間ない竜勢力との戦いという現実が、そもそも巨大で精密な魔導機構を安定して稼働させる余裕を彼らに与えなかったことが大きい。常に移動し、常に戦い、常に奪い、常に死と隣り合わせである彼らの暮らしにおいて、大型魔導具は輸送・維持コストと整備環境の確保という点で著しく不向きだったのである。 しかし、魔導技術が未熟というわけではまったくない。むしろホウルティーアの魔導は、文明的な洗練とは別ベクトルの、異様なほどの実戦特化と現場適応性を誇る。魔導師たちは極光神の加護を頼みに、緻密な理論よりも直観と経験を重視し、実験と実戦の区別すら曖昧な環境で魔導を鍛え続けてきた。氷雪神や極光神を信仰する者が多いのも、厳しい自然と戦う中で磨かれた“野生の魔導感覚”を求めた結果である。 このため彼らの魔導は、体系化された魔法学から見ると未開で粗野にすら映るが、現場では驚異的な効果を発揮する。山中でのゲリラ戦、吹雪の中の遭遇戦、竜の影に潜む魔獣との突発的な乱戦――こうした予測不能な状況において、ホウルティーアの魔導師たちは、理論派の大陸魔導師では到底真似できない即応力を示す。 魔獣素材を用いた呪具や薬液など、野蛮とされる領域でも独自の発展が進んでいる。大陸では趣味や治療薬の領域に留まる魔獣素材の活用が、ホウルティーアでは生活必需品であり軍需であり、死活問題である。ゆえに魔獣を倒し、その臓腑を混ぜ、氷雪で冷やし、必要なら祈祷で封じるといった、まさに“戦の現場で生まれた魔導技術”が脈々と受け継がれている。 こうした背景から、ホウルティーア軍は「戦う人数が少なくなるほど強い」と称される。これは単なる武勇の評価ではなく、魔導戦の性質をも含んだ総合的な評である。統制された隊列戦よりも、個々の魔導師や戦士が瞬時に判断し、状況に応じて魔導と武技を融合させながら戦える環境こそが、彼らの真骨頂なのだ。小規模戦闘ほどその適応力が露骨に発揮され、統制重視の大陸軍では到底対応できない連携と突破力を生み出す。 ただし、この魔導運用の長所はそのまま弱点でもある。単独や少人数では無類の強さを誇るが、大軍団同士の会戦においては、個々の判断力に依存しすぎるがゆえに指揮が散逸しやすく、統制の取れた魔導戦には不向きである。数では圧倒しても、洗練された軍略に崩されるという逆転現象が起こりうるのは、そのためだ。ホウルティーア自身もそれを理解しており、だからこそ彼らは大規模な侵攻よりも局地的襲撃、ゲリラ戦、略奪といった機動戦に重きを置く。 つまりホウルティーアの魔導とは、文明の優劣ではなく環境が生み出した“生存のための魔導”であり、戦士の武技と溶け合い、雪風のように荒々しく、そしてしぶとい。魔導艦の代わりに、吹雪の中で一騎当千となる魔導師がいる。呪甲装兵の代わりに、竜の影で生き延びる術を知る戦士がいる。彼らにとって魔導とは豪奢な文明の象徴ではなく、極寒の死地で火を灯すための、最も原始的で最も実戦的な武器なのだ。 こうして形成されたホウルティーア連邦は、極寒の大地に根を張り、苛烈な生存戦争を戦い抜いてきた民たちの力と、それぞれの氏族が持ち寄った価値観と矜持によって支えられている。“文明を持つ蛮族”という評価は、彼らの生活様式と倫理観の生々しさをありのままに表しているが、それは同時に、彼らがこの世界で最も“適応し、生き延びることを知っている民族”であるという証でもある。 ●ホウルティーア連邦の貴族階級 ホウルティーア連邦の支配階級序列 1:始祖12族 宝石 王族級 2:征獣家 肉食動物 公爵級 3:威栄家 形容 侯爵級 4:界現家 自然現象 伯爵級 5:侍獣家 草食動物 子爵級 6:万生家 植物 男爵級 7:数忠家 数字 騎士級 ■始祖12族 過酷極まりない環境の中、殆どフロウの住まない地と化していた北方大陸に渡り、その最初の基盤を築き上げたロシア系星渡の民の有力者から7名、沿岸部に辛うじて存在したフロウの集落から1名、協力的だったキゲインとティスリの中でもフロウと交わる都市化を選んだ現地の氏族の長達がそれぞれ2名ずつの計12名の子孫を指す。 彼らはこの広大未踏の大地における結束を誓い、その象徴としてお互いが宝石の名を冠する称号を名乗ることとした。どの宝石を名乗るかはくじ引きによって決められた為、宝石の価値・希少性と序列は関係無く、同格である。無論、700年が経過した現在に於いては、12族間での国力差は厳然と存在しているものの。 ■征獣家 便宜上ヴィーリオン貴族の爵位と対応させると公爵級だが、その支配領域は「公領」というより「公国」である。 始祖12族を直接補佐した有力幹部達の子孫や、12族の分家。各地の大都市を支配する超有力者。12族を凌ぐ権勢を誇る者も存在し、中には政略結婚どころか武力を用いて12族を摂り込み、成り代わった者すらいる。それゆえに12族の名は残っているものの、血脈的には関係無い場合もある。 ■威栄家 侯爵に匹敵する家格。 広大な土地に広く薄い支配力を展開している為、このクラスの勢力範囲ですらヴィーリオンの天領よりも広いことがある。無論、生産力は雲泥の差ではあるが。 古竜を屠ったことで絶大な富と名声を手に入れ、その支配圏を自らの支配地域として引き継ぐことで、平民からこの地位に達した英雄伝説も存在する。 逆にこのクラスの場合、ヴィーリオンやバーンでは近年殆ど見られなくなった「魔物との勢力争いに破れて滅ぶ」ことも割とある。 小勢力が吸収合併を繰り返してこのクラスに到達することもあり、ともすればバーン帝国よりも実力主義かもしれないが、安定維持に求められる労力も半端ではない。 ■界現家 諸侯とされる下限となる家格。 広い領域を治める者もいれば、規模の大きい都市だけを所有し、実質都市国家の支配者な者もいる。前者は狩猟や農業を糧とし、後者は交通の要衝や鉱山等の資源を保有しているのが主たるケース。 このクラスは引っ切り無しに近隣勢力と小競り合いを繰り返しており、カジュアルに入れ替わったり滅んだりする。 なお、家名が唯一無二で、他家と被らないのはこの家格までである。基本的には、継承ではなく簒奪をもって家格に相応しい力を得た場合は勝手に名乗ることになるのだが、その地域で最も力を持つ12族にお伺いを立てるのが通例。マジで勝手に名乗って被ったら最大限の侮辱行為となり、様々な形で支配階級的懲罰を加えられることとなる。 でも後継者争いとかで敢えてお互い同じ家名を名乗って戦ったりすることもある。 なんにせよヴィーリオンのように厳密に家名を管理してて死ぬほど面倒なことになってるのと比べたらだいぶカジュアル。 ■侍獣家 中間管理ポジション。 ヴィーリオンやバーンの貴族と違い、魔物相手の戦闘が極端に多いこの土地では、戦場で武勲を挙げてこの地位を得て、戦場で死亡するケースはかなり多い。人間同士の戦いですら「戦ってトップを殺せば土地も総取り」というスタンスでぶつかることが珍しくない為、蛮族怖い。 家名は主が勝手に与えていいので、他と被りまくる。余計な火種になると困る場合は、近隣に被りがいないか配慮したりもする。被せて敢えて喧嘩売ることもある。 ■万生家 やはり最前線で入れ替わりの激しいポジション。 侍獣家もこっちも世襲は認められているので、子供はたくさん作っておきたい。 ぶっちゃけ武勇に優れてさえいればなれてしまうので、読み書きがおぼつかない者も珍しくない。ワイルドだろぅ? ■数忠家 家名とは名ばかりの、番号管理される切ない最下級の貴族。 大将首とは言わず、隊長首を挙げるだけでもOKで、ヴィーリオンやバーンと比べて遥かに簡単になることが出来るのだが、遥かに簡単に死ぬ。 とっととランクアップしないと毎回ノルマンディー上陸作戦で最初に上陸する人をやらされるので大変である。 大半が蛮族なので読み書きナニソレオイシイノ? ●剛毅神  諦めたらそこで人生終了を地で行く、不撓不屈と突破の象徴たる武神。あらゆる困難に立ち向かい、苦難を乗り越えることこそが己の存在意義と信じている。 ホウルティーアにおいては主神の座を占め、極寒の荒野や飢えと渇き、絶え間なき抗争といった過酷な環境下で生きる者たちの拠り所である。そこでは、剛毅神への信仰は生存の為の本能的な選択であり、老若男女を問わず広く根付いている。 彼の教義は「手強い敵にもひとまず当たれ、傍から見てみな漢だぜ」を旨とし、結果ではなく姿勢を問う。死地においてなお戦い、そこから生還してこそ栄光であるとされる。よって剛毅神の信徒たちは「生き残ること」への執念が尋常ではなく、瀕死の重傷を負ってなお立ち上がる者も少なくない。 ただしその信仰は冷たいとも評される。剛毅神は積極的な他者救済を推奨しない。他人を助けることがあっても、それは助けられた者が己の力で立ち上がれるように導くことが信条であり、安易な救済はむしろ鍛錬の機会を奪う行為として忌避される。 「力こそ正義」という解釈をする信者も少なくなく、大陸各地の傭兵、山賊、蛮族などにも剛毅神の名を信奉する者は多い。狂信的な勝利信仰ではないが、己の力を疑わず、ひたすらに前進するという姿勢が多くの戦士たちを魅了するのだ。まぁ深く考えてないバカが大半を占めるけれど。 彼の軍勢は恐れを知らぬ突撃部隊として知られ、敵将の名を叫んで真正面から挑みかかるその戦いぶりは、味方にとっては誇り、敵にとっては絶望である。被害率の高さも指摘されるが、敵の戦意を喪失させるには十分すぎるほどの破壊力とインパクトを持つ。 剛毅神の教義において、「逃げる」という選択肢は存在しない。退くときは味方を守る為であり、決して恐怖や挫折による撤退ではないとされる。逆に言えば、戦うべきでない相手に挑むことも選択肢に入るため、信徒が無謀に死ぬことも多々ある。しかし、それもまた信仰の純粋な在り方として尊重される。 属性:混沌にして中立 領域:勇気、苦難、持久力、力 信者:''ホウルティーアの民''、''傭兵''、''山賊''、''反骨精神を持つ者''、''己を鍛えたい者'' 神格武器:アックス 信者人口:★★★☆☆ / ホウルティーア:★★★★★ 信仰権威:★★☆☆☆ / ホウルティーア:★★★★★ ●  初撃必殺を旨とする保身無き零距離斬撃の使い手。 「渾身の力を込めて放たれる初撃で敵を屠る」というシンプルにして理想的な戦闘スタイルゆえに、世界各地で似て非なる戦闘術が存在するが、特にヒノワの剣術を祖として対人から対全へ発展させたのが魁滅刃の技とされる。 一の太刀で敵を仕留めることが最優先で、その技は防御の隙も大きい。しかしながら、魁滅刃の初撃を受けてなお致命となる反撃を放てるものなどそうおらず、畳み掛けるための連続斬撃の技も存在する為、最終的に立っているのがどちらかは明白なのだ。 その前のめりで命知らずな闘争理念はホウルティーア人の魂にも強く共鳴したのか、使い手の数は本場ヒノワの次に多く、剛毅神の教えと融合した「ホウルティーア・サムライ」と呼ばれる極めて危険な一派を生み出す結果となっている。 ■ゲームデータ解説 いわゆる幻想示現流。 足を止めての全力攻撃合戦に於いて最大の力を発揮するタフすぎてソンはない戦士。いきのこったヤツのかちだ。 でも抜刀突撃も好きなんで、移動攻撃の強化要素もある。戦線構築能力もある。つまり割と器用。 あと防御を考えてないと言いつつも、一刀無影と同じく重戦士運用が何の問題も無く可能。 ■必要条件 基本攻撃ボーナス:+7 技能:〈威圧〉6ランク、〈真意看破〉4ランク 特技:《強打》《武器熟練:打刀または太刀》《踏みこみ打撃》《威圧打撃》 クラス基本データ ヒットダイス: D10 基本攻撃ボーナス: 良好 セーヴ: 頑健 クラス技能:〈威圧〉〈視認〉〈真意看破〉〈跳躍〉 技能ポイント: 4+ クラスの特徴
一の太刀を疑わず(変則):[フリー][動作][音声]不動の構え状態での攻撃宣言時に使用可能。《武器熟練》を持つ武器による攻撃が命中した場合に、追加ダメージを得る。急所攻撃と違い、アンデッドや人造等の急所を持たないクリーチャーにも効果を発揮する。また、クリティカルヒットした場合にはダメージにも倍率が加わる(但しクリティカルヒットが発生しない対象にも発生するようになるわけではない)。この技を使用してから次の手番までの間、[立ちすくみ]状態になる。 猿叫(変則):[誘発][音声]君が敵に一の太刀を疑わずによるダメージを与えた場合、対象は意志セーヴ(難易度10+クラス・レベル + 【筋力】ボーナス)に成功しなければ、次のターンの攻撃ロールに-2のペナルティを受ける。 猛進撃(変則):[誘発][動作][音声]10フィート以上移動して攻撃した場合、ダメージロールに+2D6を得る。ただし、この攻撃は機会攻撃を誘発する。 気迫制圧(変則):[誘発] [音声]君が敵に一の太刀を疑わずによるダメージを与えた場合、次のターンの間5フィート以内の敵すべては意志セーヴ(難易度10+クラス・レベル+【筋力】ボーナス)に成功しない限り、移動速度が半減する。 血戦の構え(変則):[フリー][動作]ターン開始時に武器を構えた状態でいる場合に発動可能。即座に追加の5フィート・ステップを行う。全力攻撃を行わずに1回の攻撃を行う場合、この攻撃のダメージは1.5倍となる。 気迫撃(変則):[誘発][動作][音声]クリティカルヒットを成功させた場合、次のターンのダメージロールに+2D6を得る。また、命中した敵は意志セーヴ(難易度10+クラス・レベル + 【筋力】修正値)に成功しない限り、次のターンは防御専念しかできない。 雲耀(変則):[フリー][動作][音声] 不動の構え状態で《武器熟練》を持つ武器による攻撃宣言時に使用可能。その攻撃が命中した場合、自動的にクリティカルヒットとなる。この攻撃のダメージはいかなる武器を用いようとも倍率は2倍固定。 ●  闘士7/魁滅刃7 筋力17/敏捷力12/耐久力15/知力11/判断力11/魅力13/PB24 ホウルティーア南岸の港湾都市シルマーニエフに根を張る剣豪のサムライ・マーステル。 マーステルとは必ずしも武芸の最高位を意味するものではなく、道場主やそれに匹敵する達人を指す尊称。 ヴァーシリーはかつて侍獣家に列せられた家の出である。しかしその家は久しく没落しており、今や所領を持たぬ虚冠の身に過ぎない。もっとも、ホウルティーアにおいてはこのような“名だけ残る元貴族”は珍しくなく、彼もまた剣一本で生きる道を選び、幾度もの修羅場を乗り越えて後、道場を開いた。 彼の道場は単なる稽古場ではなく、私兵集団に等しい性格を持つ。門下生を率いて領主の遠征に従軍し、傭兵として戦場に立つ。さらに領主の子弟をはじめとする貴族の若者も通っており、剣術指南役としてシルマーニエフ領の武を支える存在だ。社会的には数忠家程度の扱いに留まるが、戦場での実力と道場の影響力はそれ以上と評される。 領主から所領を与えられる提案も幾度となくあったが、彼はことごとく断っている。土地を治めることより、戦いに身を置く日々のほうが性に合うからだ。ヴァーシリーは豪快で人当たりの良い兄貴分として門下生に慕われる一方、戦場に立てば戦闘狂と呼ばれるほどに剣を振るい、誰よりも前線に立つ。  ただし、彼の戦への姿勢には一線がある。剛毅神の教えにも沿い、戦いに勝つために必要な略奪は容認しても、無意味な虐殺は「武を貶める行為」として退けている。基本的には雇い主や領主の命に従うが、虐殺を命じられればと毅然と拒む。その際には「それは本当に必要なのですか」と凄みを利かせ、時に雇い主を黙らせることすらある。命令への反抗は決して軽い行為ではないが、彼にとって武の誇りを損なうことの方がはるかに重いのだ。 彼自身は聖人君子ではなく、門下生に品行方正を説くわけでもない。略奪や暴走を全面的に否定はしないが、それを道場の方針とすることもない。ヴァーシリーはあくまで「戦士としての誇り」を第一に据えており、それが彼を単なる豪傑ではなく、尊敬を集める剣客たらしめている。  その剛剣はかつて若竜の首を一刀のもとに斬り落とした逸話からМужик, разрубающий драконовの異名を得た。門下生にとっては豪快な兄であり、戦場では頼もしい将であり、敵にとっては竜をも斬り伏せる恐るべき剣鬼である。 ●  武人7/魁滅刃4 筋力16/敏捷力10/耐久力17/知力10/判断力13/魅力11/PB28 キゲインのホウルティーア・サムライにして、ヴァーシリー・ザイツェフの道場で師範代を務める人物。 彼女はキゲインらしくストイックな努力家であり、剣の道を極めようとする求道者でもある。実家は代々続く鍛冶屋で、研ぎに持ち込まれた一振りの刀に魅入られたことから戦士を志した。ホウルティーア文化では娘であっても「戦士になりたい」と言えば嫌がられることはなく、さらにキゲイン独自の価値観として「子供がなるなら戦士か鍛冶屋かお菓子屋か」とされている。彼女が剣士の道を歩むことになったのも、ごく自然な成り行きだった。 親の知己が所属する戦士団を紹介され、そこで彼女はヴァーシリーと出会う。以後、長く肩を並べて戦う戦友となり、彼の道場が旗揚げされる際にも最初期からのメンバーとして参加した。  熱く感情に身を任せることの多いヴァーシリーに対し、アーマニャンニャは冷静沈着で、常に的確に「仕留める」ことを重んじるタイプである。戦闘においては武器を無駄に痛めるような力任せの一撃を嫌い、洗練された技によって結果を導き出すことを旨とした。  特にキゲイン特有の小柄な体格を活かし、敵の足元を狙う低い位置からの足薙ぎは必殺の得意技とされる。小さな体躯ながらも鋭く確実に相手を切り裂く疾風のごとき戦いぶりはやがて「Храбрый крошечный серпик」の異名を呼ばれるに至った。  道場においては、三児の母としての生活経験から、若い門下生たちの世話役を自然と引き受けることも多く、その面倒見の良さから「道場のおかん」として慕われている。戦術家ではないものの、副将としての信頼は厚く、現場において指揮官を支える安定感ある立ち位置を占めている。 また、信仰に関しては剛毅神ではなく練磨神に帰依しており、反復と修練こそが真価を生み出すという思想を体現する存在である。鍛冶の家に生まれながらも、剣の道を選び、努力を惜しまず己を磨き続けるその姿は、まさに練磨神信者らしい生き方そのものである。  アグラフィーナとは仲良し。 社会的地位としては平民のアーマニャンニャの方が下なのだが、ガチで強い姉弟子として強くリスペクトしてくれている為、道場の外でも常に妹分として振る舞おうとする。お互い真面目な性格なので双方が敬語で会話し、お堅い雰囲気が拭いきれないが、当事者たちはそんなことない模様。休日を一緒に過ごしたりすることもある。 ●キゲイン  キゲインはフローラントにおける「ドワーフ」に相当する存在であり、山岳や地下に拠点を構える民である。彼らの国土は岩と鉄に満ち、鉱山の採掘や金属精錬を基盤とし、閉ざされた世界の中で独自の生活文化を築いてきた。屋内での食肉生産や菌糸類の栽培など、限られた空間を最大限に活かす一次産業にも長けており、かつては地下農業が盛んであったが、交易の発展とともに製造業で得た財貨によって食料を輸入する方が効率的となり、いまでは伝統技術として細々と続いているのみである。 鍛冶と工芸の分野におけるキゲインの技術力は、世界随一と称される。彼らの手による武具や装飾品は、単なる実用品ではなく芸術の域に達しており、王侯貴族から戦士まであらゆる階層に需要がある。物理魔導の体系そのものではフロウに及ばないが、魔導鍛冶の分野に限っては平均して上回るとされる。火と金属に魅せられた職人たちはしばしばフロウの都市に進出し、物理魔導師たちと共同研究を行う姿も珍しくない。彼らにとって技術の研鑽は信仰にも似た行為であり、「より良いものを作る」ことそのものが誇りである。 また、キゲインは酒と甘味をこよなく愛する。彼らの酒造技術は非常に高く、特に「石山蜜酒」と呼ばれる濃厚な蜂蜜酒は貴族たちの宴を飾る高級品として知られている。糖や穀物の原料はほとんど輸入に頼っているものの、発酵と蒸留の知識は地下社会に深く根を下ろし、嗜好品の文化として確立されている。閉ざされた環境ゆえの退屈を慰める楽しみとして、菓子や酒は彼らの心を豊かにするものであった。 彼らの成人は20歳前後であり、寿命はおよそ160年。成長の速度はフロウより遅く、老化も穏やかで、長い中年期を経てから急速に老いる。ただし、この肉体的な成熟過程は男女で大きく異なる。男性は堅牢で重厚な体格を誇り、筋肉と骨の密度が異常なほど高い。一方、女性は外見上、フロウの12歳前後に見える年齢で肉体的成長が止まる。この外見のまま数十年、あるいは100年を生きるため、他種族からの認識に大きな齟齬を生んだ。 星渡りの民が最初にこの事実を知った時、「ドワーフの女には髭がある」という伝承とのあまりの落差に衝撃を受けたことは有名である。だが、驚いたのは彼らだけではなかった。かつて都市国家という閉鎖社会の中で暮らし、異種族との交流をほとんど持たなかった原住のフロウたちもまた、初めて彼女らを目にした時、その外見と成熟の不一致に強い違和感を覚えた。中には「子供を戦場に立たせている」と非難する者すらいたほどである。 この認識の食い違いは、やがて深刻な誤解へと発展する。フロウの中にはキゲインの社会構造を理解せぬまま、「キゲインの男はみな小児性愛者だ」と嘲る者が現れ、それを侮辱と受け取ったキゲイン側が激昂したことで、短期間ながらも本格的な衝突――後に「侮辱戦争」と記録される騒乱――が勃発したのである。この事件は、単なる誤解が文化的侮辱に転じた末に流血に至った最初の例として知られ、のちに両種族の外交関係に深い影を落とした。 しかし、他の長命種たちにとっては「外見の若さ」と「成熟」は本来両立するものであり、むしろそれが自然な生理現象であった。ティスリをはじめとする長命の民では、200年を超えてなお若々しい母親が子を抱くことも珍しくなく、「若く見える親」という概念そのものに違和感がない。彼らから見れば、「外見の若さ=未熟」というフロウ的先入観こそ異様であり、理解に苦しむ偏見であった。フロウは他種族との接触が浅く、自らを基準に世界を測っていたため、その価値観がいかに狭いかを知らなかったのである。こうして、フロウ側の無意識の傲慢が他種族の怒りを買い、文化的衝突の火種となったのだ。 とはいえ、この痛ましい出来事こそが、両者にとって相互理解への第一歩でもあった。戦後、両種族の学者や聖職者たちの間で「外見年齢と精神的成熟の乖離は種の構造的特性である」と公的に認識され、やがて「肉体的にも精神的にも子供である者にしか欲情を覚えない者」と「外見が幼いが成熟した成人を愛する者」とを明確に区別する考え方が定着していく。共存の中で、フロウ社会もまた「見た目の若さ=未熟さではない」という新たな倫理観を受け入れていったのである。 キゲインは頑固な種族である。自らの価値観を曲げず、「うちではこうだからおかしくない」と言い張るのが常だ。だがそれは盲目的な頑迷さではなく、「自らの共同体の中で決めたことには従うが、他所の“正論”で強制されることは受け入れない」という誇りの裏返しである。彼らにとって誇りは生きる支柱であり、譲れぬ信念でもあるが、その誇り高さは時に他者との衝突を招く。外部の価値観を頑なに拒み、融通の利かなさを見せることも多いため、他種族からは「信用できるが扱いづらい」「真面目すぎて距離を置きたくなる」と評されることも少なくない。誇りが美徳である一方で、柔軟さを欠くゆえに関係を築くのが難しい――それが、キゲインという種族に対する一般的な印象である。 一方で、外部からの干渉を嫌うその気質は、共同体の内部においては極めて安定した秩序をもたらす。内部から出た意見には柔軟であり、新しい提案が仲間の口から出たなら、それを受け入れる度量を持つ。都市に住むキゲインの指導者層はとくに現実的で、「それはそれ、これはこれ」と割り切る思考を身につけ、他種族社会でも尊敬を集めている。 強靭な肉体と、宝飾を磨くような精密な指先――この両極の特質を併せ持つことが、キゲイン最大の神秘である。その姿は、岩と金属の民でありながら、芸術家としての魂を宿す存在そのものだ。彼らは今日も地下に火を灯し、鉄槌を振るい、己の誇りと信念のもとに新たな創造を生み出している。
■フローラント版ゲームデータ サイズ:中型。 ただし、身長・高さに関する判定では小型として扱われることがある。 能力値修正:【耐久力】+2、【魅力】−2。 移動速度:20フィート 鎧や重量による減速を受けない。 視覚:暗視60フィート。 暗闇の中でも白黒で見通せる。つまり色の識別は不可能。 セーヴボーナス:毒、呪文、疑似呪文効果に対するセーヴに+2種族ボーナス。 戦闘特性:オーク、ゴブリン、巨人に対する攻撃ロールに+1種族ボーナス。 踏ん張り:地面を踏みしめている限り、突き飛ばしや足払いに対する戦技防御値に+4種族ボーナス。 移動時も適用されるが、あくまで「地面や、地面の上で安定した構造物上」に限る。崩れかけた建築物や、船とかは適用外。 防御特性:巨人からの攻撃に対するACに+4。 【敏捷力】ボーナスを失うような状況の場合、同様に失われる。 技能ボーナス:石造物に対する〈捜索〉、〈鑑定:石または金属〉、〈製作:石または金属〉に+2種族ボーナス。 種族武器習熟:ウォーアックス、アーグロシュを軍用武器として《習熟》《熟練》できる。 言語:出身地に依るが、基本的には大陸語かキゲイン語。 都市部のキゲインは、キゲイン語を喋らずとも暮らしていけるし、全員がバイリンガルとなるほど教養があるわけではない。 種族代替特徴:戦闘特性、防御特性、種族武器習熟を得ない代わりに、《技能熟練:いずれかの鍛冶もしくは細工》を2つ得る。 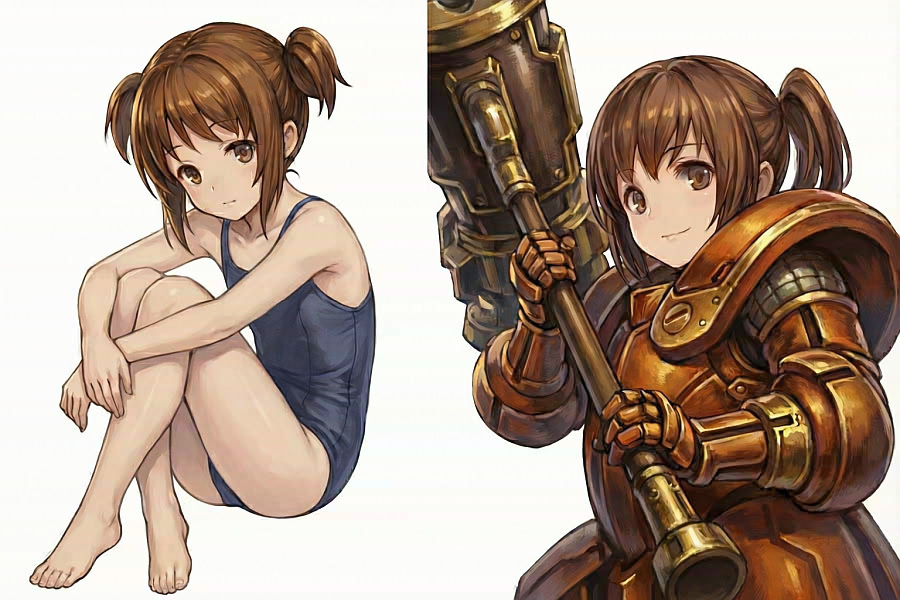 残念ながらこの世界にスク水の概念は存在しません。だって普通教育の学校とかほとんど存在しないから……。 ……が、どう見てもスク水にしか見えない超高級水着ならば存在するかも知れない。 ●ダーク・キゲイン  ダーク・キゲインとは、地上のキゲインと同じ祖を持ちながらも、別種として成立してきた地下世界の民である。彼らは闇を本拠とする生活様式を基盤とし、洞窟の湿った空気と黒い岩肌に囲まれた環境こそが、その精神と肉体を形づくる根源となった。キゲインが坑道と都市を行き来する広い生態圏を保ち続けたのに対し、ダーク・キゲインは長い歴史の中で、地下に生きる者としての性質を世代ごとに強め、生き方そのものを磨き上げていった。その適応は、単なる習慣の変化ではなく、生理的傾向と文化的価値観を巻き込んだ“種としての深化”であった。 地下の世界に適応していく過程で、彼らに受け継がれていったのは、何よりも強靭な肉体である。地底には、暗闇に潜み、形を保たぬ粘体や牙を光らせる異形、精神を侵食する怪物が数多く生息し、繊細な技ではなく“生き残るための強さ”が必要とされた。こうした環境に長く晒されるうち、ダーク・キゲインの血統では、戦闘向きの頑強さが自然と選ばれ、世代を重ねて種族的な特徴として定着していった。一方で、キゲインに顕著な繊細な指先や優れた鍛冶技術は、彼らの中では次第に影を薄めていった。これは劣化ではなく、“必要とされなかった能力が淘汰されていった”というべきで、今のダーク・キゲインには、磨かれた芸術的金工技法よりも、戦場を生き抜く武具の整備がよほど馴染んでいる。 暗闇に順応した視覚も、彼らの生態を象徴する要素である。彼らの暗視は鋭く、闇の中で敵の動きを捉えるには極めて優秀だが、色彩の識別には向かず、すべてが白と黒の階調に沈む。これは生存には最適であるが、文化の幅を狭める側面を持つ。絵画や染色といった色彩を前提とする芸術を、彼らは本質的に楽しむことが難しく、光の世界にある美術品はその価値こそ理解しても、その魅力を自らの感覚で味わうことはできない。地上民が色と光によって世界を理解しようとするなら、ダーク・キゲインは形と構造によって世界を読み解いていると言えよう。 彼らが光を苦手とするのは呪いや精神的弱点ではなく、生物としての傾向に過ぎない。強い光に触れると視覚が過敏に反応し、身体が一時的に混乱するのは、あたかも特定の民族が特定の病に罹りやすいとか、ある地域の民がアルコール分解能力を遺伝的に低く持つといった“生理的差異”と同じである。これは地下生活を主とした歴史が積み重ねた結果であり、彼ら自身にとっては自然な体質であって、羞恥や劣等とは結びつかない。 こうした生態と歴史が、彼らの社会性と気質を強く規定している。ダーク・キゲインは地上のキゲイン以上に極めて頑固で、己の種族の伝統と倫理観を何よりも重んじる。その価値観は共同体の中に深く根づき、掟は絶対であり、外部の規範を“自分たちも従うべき正しさ”とは認めない。これは傲慢ではなく、あくまで彼らの文化における秩序の軸である。だが、この頑固さは外部との協調を難しくし、少しの行き違いからでも衝突が生じやすい。ダーク・キゲイン自身もこの性質をよく自覚しており、そのため種族として外界との交流には慎重で、無闇に接触範囲を広げようとしない。 それでも外界との断絶を望んでいるわけではなく、必要な折衝は行われる。ただしそれを担うのは、共同体の中でもとりわけ人格と判断に優れ、対話に向いた“代表者”である。代表者は、外部社会と衝突しがちな同胞の代わりに交渉へ赴き、必要な協力関係を結ぶ役割を担う。彼ら自身、頑固さが外界との摩擦を生むことをわかっているが、だからといって根本的な気質を捨て去るつもりはなく、問題を解決する手段として“代表者制度”を採用しているのである。このため都市部でダーク・キゲインを見かけることは稀だが、それは外界を拒むからではなく、不要なトラブルを避けるための文化的選択なのである。 このようにして地上との繋がりは途絶えず、彼らは傭兵としてしばしば地上世界と契約関係を結ぶ。その働きぶりは実に誠実で、契約した内容を曖昧にせず、報酬に見合った働きをきっちりとこなすことで信頼を獲得している。ただし、契約に曖昧さがある場合は別だ。齟齬が生じたとき、彼らは絶対に譲らない。これは融通のなさではあるが、裏返せば抜群の誠実さであり、嘘をつかず約束を守るという彼らの鉄の倫理観の表れでもある。この性質ゆえ、「隣人としては厄介だが、戦場ではこれ以上なく頼りになる」と評されるのだ。 共同体内部では、彼らは極めて礼儀正しく、仲間に対して律儀である。友と認めた者には余所者であっても紳士的に接し、その信義は揺るがない。一方で、掟を破る者には厳しい制裁が下され、閉鎖的な社会構造の中で濃密な絆と厳格な規律が共存する。彼らの社会は階級制によって支えられ、実力だけで地位が決まる蛮族的な構造ではなく、秩序と役割を重視した封建社会に近い。強さは敬意の理由にはなるが、階級の全てを決めるわけではない。 そして戦場に立つとき、彼らは地底で鍛えた強靭さを余すところなく発揮する。荒々しく容赦のない戦士でありながら、無秩序な暴力ではなく、共同体と仲間のための戦いとして矜持を抱いて刃を振るう。その姿は、闇に育まれた鉄壁の民としての誇りそのものだ。
■フローラント版ゲームデータ サイズ:中型。 ただし、身長・高さに関する判定では小型として扱われることがある。 能力値修正:【筋力】+2、【耐久力】+2、【知力】-2、【魅力】−4。 移動速度:20フィート 鎧や重量による減速を受けない。 属性:ダーク・キゲインは原則的に秩序である。 視覚:暗視120フィート。 暗闇の中でも白黒で見通せる。つまり色の識別は不可能。 セーヴボーナス:毒、呪文、疑似呪文効果に対するセーヴに+2種族ボーナス。 戦闘特性:蟲、粘体、異形に対する攻撃ロールに+1種族ボーナス。 踏ん張り:地面を踏みしめている限り、突き飛ばしや足払いに対する戦技防御値に+4種族ボーナス。 移動時も適用されるが、あくまで「地面や、地面の上で安定した構造物上」に限る。崩れかけた建築物や、船とかは適用外。 防御特性:蟲からの攻撃に対するACに+4。 【敏捷力】ボーナスを失うような状況の場合、同様に失われる。 勇敢:[恐怖]効果に対するセーヴに+4士気ボーナス。 光による盲目化:明るい光(太陽光とかデイライトの呪文とか)に突然晒されたダーク・キゲインは、1ラウンドの間[盲目]状態になる。これに加えて、明るい光にさらされている最中、ダーク・キゲインは、すべての攻撃ロール、セーヴ、判定に-1の状況ペナルティを受ける。 種族武器習熟:ウォーアックス、アーグロシュを軍用武器として《習熟》《熟練》できる。 言語:出身地に依るが、基本的にはキゲイン語。 種族代替特徴:戦闘特性、防御特性、種族武器習熟を得ない代わりに、《技能熟練:いずれかの鍛冶》を2つ得る。 ■マスターズ・コメント D&Dではグレイ・ドワーフと呼ばれる種族のフローラント版。やはり別物レベルで能力も設定も変わっているけど。 グレイ・ドワーフはマインドフレイヤーに囚われたドワーフが生態改造を受けて奴隷として長きに渡り隷属されていたのが、独立して繁殖した存在なので、色々と改造人間ゆえの特殊能力を備えていたけど、こっちにそんなものはない。  魅力にとんでもないマイナス補正かかってるが、別にこーいうかわいい娘がいないわけではない。 確かに種族の抱える性質として頑固者なのだが、それでも最初からフロウ社会で育てばそこまで偏屈にならんで魔導師になれたりもするよ! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クリスマスプレゼントありがとうございます( ・`ω・´) クリスマス! すき焼き! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■青のミブロ 新選組編 #8 サムズアップっていつからするようになったんだろう(笑)  山南さん、ちるらんや薄桜鬼でも「どどどどどどんな流れで袂を分かつんだ!? こんなに絆が強い描写しといてここからどうやって!?」みたいにオロオロしてたわけですが、どっちも「新選組のことはガチで大事。絆には一切の曇りなし」であることを踏まえての「それぞれの展開」が描かれたわけで、やはり山南さんがズッ友な新選組は良い……! 実に良い……!!! ミブロは不穏な雰囲気を漂わせる陽動作戦も巧みな作品だったぜ……!!! 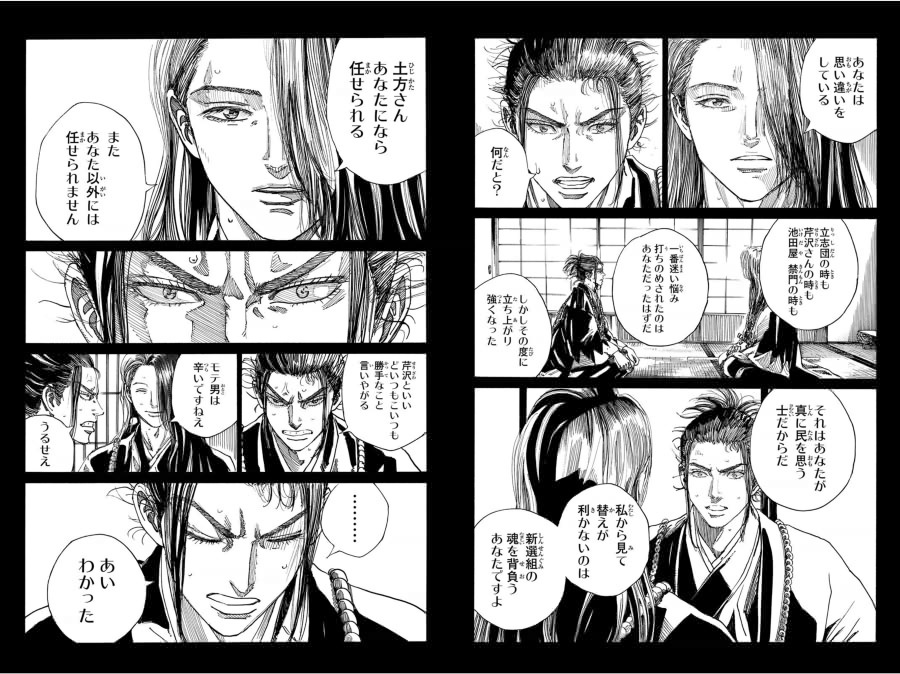 もうねーこの辺読んでる時点ですでにボロ泣きしてるわけなんすわ。 芹沢鴨をあれだけ徹底的に魅力的に描いたうえでそれを討った新選組なんで、そんじょそこらの描写じゃ「芹沢鴨が仕切った方が良かったんじゃ?」って読者に思われちまうわけで!! 作者に対して、自身の力量の高さが最大の敵になるというやつで!!! いいぞもっとかかってこい!! 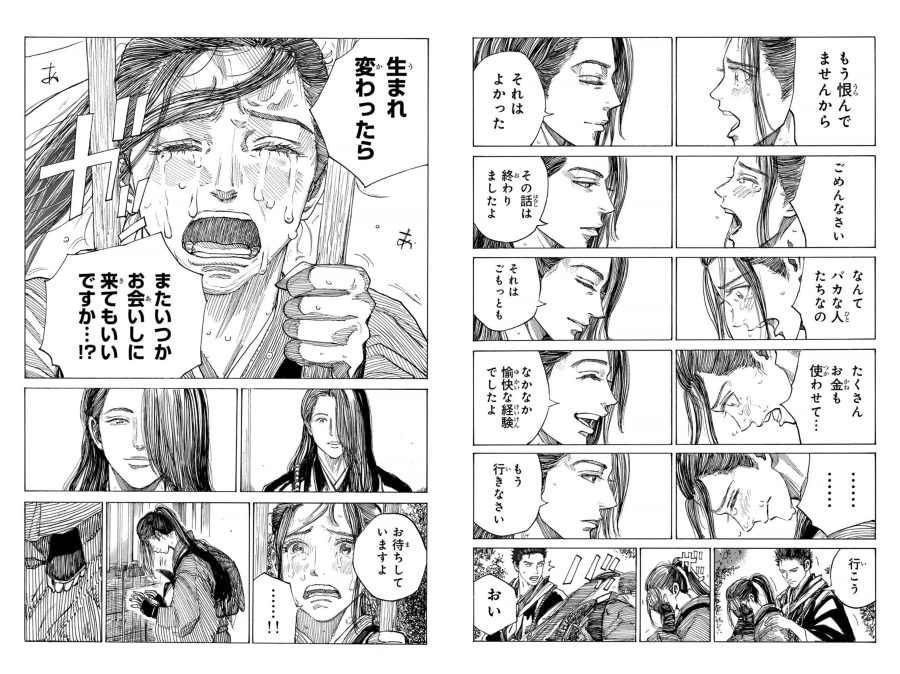 どうにか生まれ変わってお会いさせてくださいよ! 全然関係ない次回作で、なんか付き合ってる2人が似ている……みたいなやつでいいからさ!!!!  ワイトもそうは思いません。 このドシリアスなシーンでギャグを持ってくる……前々からそーいうところだぞ! 好きだ!! 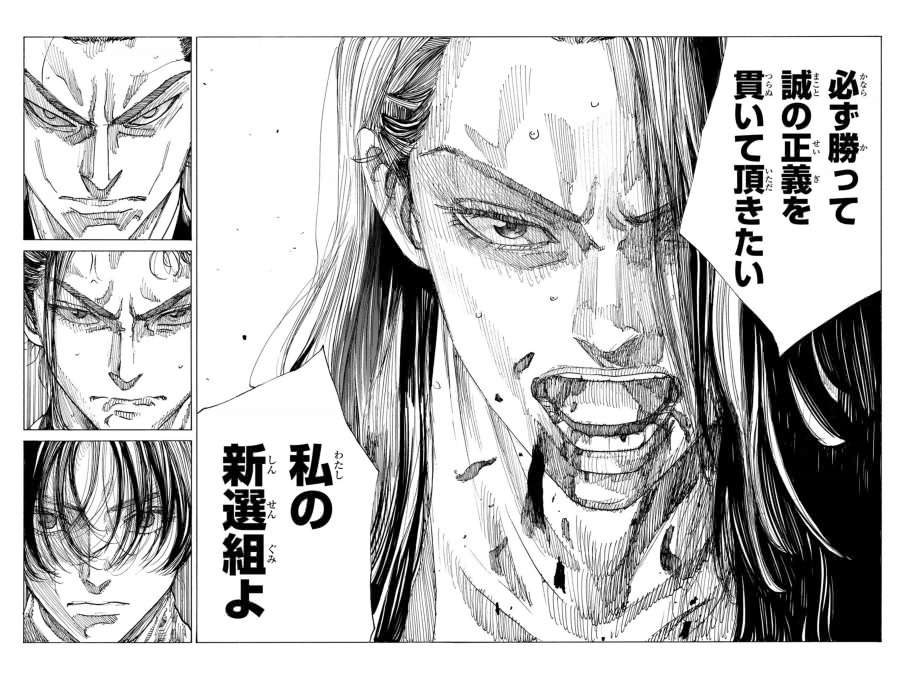 でさぁ。ほんとこの作者って見開きで最高に格好いいシーンぶっ込んでくるのが好きだよな! 俺も大好きだよ!!! こんなんポスターで欲しいくらい超痺れてボロボロ泣きまくりだったよ! ああもう!!! 左下にこれから袂を分かつやつがいるのがスゲー気になるよ!!!  谷三十郎をビックリするくらい魅力的に描く気がないなぁと思っていたら、まさか彼の死因をくだらない私闘で負けて死亡にするなんて大胆だな。 伊東甲子太郎が単純に「小物の嫌な奴」じゃないことは超大事だぞ! 彼は彼で新選組のことを評価してくれてる方が、後の衝突に悲劇性が増すから大事なんだ!!!  いつまでもちびっこのわきゃねーだろうと思っていたんで、遂に成長したな! 待っていたぜ、この時をよぉ!!! ここから始まる大修羅場! ひしめき合って諍うわ~とくらぁ!!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■地図は作中世界内で抱かれているイメージであり実際の地理を保証するものではありません(お約束 ●旭暉皇国日輪 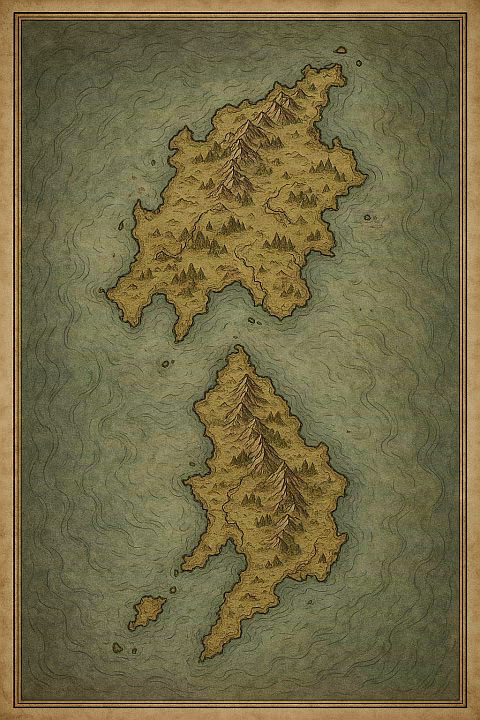 日輪皇国は、ヴィーリオン東方の海域に浮かぶ北島と南島の2つの本島、および多くの小島から成り立つ海洋国家であり、建国の起点は、解放戦争を戦い抜いた太陽神の神寵者・赤烏遊糸が戦後にこの地へ渡り、初代光皇として統治を開始したことに遡る。 星渡りの民の中でも日系人が中心となって建国し、かつて海竜王カミムマが海路を封鎖していた頃には外界から完全に隔絶された「絶対の孤島」であったが、解放戦争終結後は広く手付かずの開拓地として日系開拓民が次々と渡航し、入植が急速に進んだ。赤烏遊糸がこの地を新天地に定めた最大の理由は、彼らの故郷である日本と気候が酷似していたことであるが、さらに奇妙な一致として、この地に跋扈する原棲勢力――鬼や天狗に相当する存在たち――が、星渡りの民が知る「妖怪」に酷似していたことが挙げられる。これらの存在は神霊界から神魔の手によって物質界へもたらされたものであり、すでに当地では別の名で知られていたが、星渡りの民にとっては馴染みのある姿に見えたため、異世界の恐怖の中にほんのわずかな理解可能性を与え、心理的な安定材料となったと言われている。もっとも、安心など最初の一瞬だけで、原棲勢力はれっきとした敵であり、入植が本格化する頃にはそんな感慨に浸っている余裕など跡形もなく消え去っていた。 原棲勢力との生存戦争は激烈を極め、主要地域の制圧は決して平穏に進んだわけではない。太陽の機神《紅焔輪》と、それを操る赤烏遊糸の武威は現地人に神聖視され、人類と先住種族の間にある程度の融和を促したが、それでも入植は苦闘の連続であり、解放戦争の英雄たちの力が存分に発揮されて初めて、人類は平地における主導権を確立した。しかし山岳部の情勢はいまだに厳しく、解放戦争を生き延びた古竜を筆頭に、人類が手を伸ばせない領域が広く残り、現在も油断を許さぬ危険地帯として存在している。 国家としての日輪皇国は、列強諸国の中でも国土・人口ともに最小規模であるものの、海運力においては群を抜き、フローラント世界各地の港町ではほとんど必ずと言っていいほどヒノワ人商人の姿を見ることができる。海洋国家としての名声は高いが、実際には商才と交渉力こそが彼らの真の強みであり、海路はあくまで彼らが外界に進出する最初の手段であったに過ぎない。内陸都市にも積極的に進出し、その影響力は「すべての交路はヒノワに通ず」とまで言われるほどだ。 しかし、ここ半世紀の光皇家権威の衰退によって国内は戦国時代に突入し、士族同士の武力衝突が頻発している。日輪皇国の社会構造は大きく二分されており、誇り高い士族と実利重視の商人という二極が支配する形を取っている。農民の地位は大陸諸国よりもさらに低く、そもそも耕地が少なく食糧生産力の限界が明白であるため、農業は期待値の低い産業と見なされがちで、それが階層間の緊張や深刻な対立を引き起こす要因となっている。一方、鉱山労働者はその危険性と重要性ゆえに高い社会的評価を受けており、鉱物とその加工品は日輪皇国の主要輸出品であるため、国家としても彼らの地位を低く保つわけにはいかない事情がある。鉱山労働者は社会的尊敬を受け、鉱工業が国家経済の根幹を成している。 宗教面では、士族の多くが太陽神を主神として篤く信仰し、国家思想の根幹に太陽の威光が置かれている。一方で、商人たちは航海の安全を最重視するため海洋神への信仰が非常に深い。大陸に渡ったヒノワ人の中には、興隆神、構律神、栄華神へ宗旨替えする者も珍しくない。鉱山労働者の信仰は些か多様で、輝晶神、石巌神、瑞幸神など、何を重視するかに応じた神々への祈りが地域ごとに根付いている。 また、特殊な製法と用法で知られるヒノワ武具は一般流通しておらず、冒険中に失うと再取得が困難である。だが世界中の港町にヒノワ人がいるため、冒険者は彼らの私物を譲り受ける形でどうにか調達することができ、「本国まで買い付けに行く」必要はない。ただし定価で手に入ることを期待するのは無理であり、希少性と品質から高額になるのが常である。 このように日輪皇国は、解放戦争由来の文化的背景、海洋交易による莫大な影響力、原棲勢力との生存戦争、階層構造の歪みなどの要素が複雑に絡み合って成立している国家である。その有り様は世界の交易・文化に多大な影響を及ぼし続け、フローラント全域における独自の存在感を持ち続けている。 ●フローラントの種族
●フロウ  フロウはこの世界における人類の総称であり、同時にいわゆるヒューマンに相当する存在でもある。彼らの名は「フロウの地」すなわちフローラント大陸の名にもに由来し、星渡りの民がこの地を再発見した際に命名したものである。名の語源はドイツ語の「ラント(Land)」であり、彼らの文化的影響が言語の根幹に深く残されている。かつてはこの地に特別な呼称などなく、ただ「陸」や「大地」と呼ばれていたに過ぎなかったが、星渡りの民がもたらした言語と文明が、この世界に新たな言葉と秩序を与えた。 フロウの人々は、かつての原住民と星渡りの民の血を混ぜ合わせた混血の末裔であり、今や純粋な血統を語ることはほとんど無意味になっている。例外的に、島国ヒノワだけは独自の文化と言語体系を比較的強く保持しているが、それでも純粋な血統の保持者はごく少数である。現在では「フロウ」という言葉が単に人間という種を意味するだけでなく、広く「人類社会に属する存在」を指す語として用いられている。ティスリやキゲイン、マオナムなども共に生活し文明を築く限りにおいては「人類種」として扱われることが一般的であり、単に外見的な違いで線を引くことは蔑視と見なされる。文化的な境界こそあれど、生物学的には明確な区分は存在しないのだ。 一方で、「亜人」という言葉はきわめて慎重に扱われる。これは人類社会に属さず、共存関係を築かないオークやゴブリンなどを指す語であり、「人ではない者」を意味する蔑称としての色合いが強い。そのため「亜人種」と呼ぶよりも、「人類種」という包括的な呼称が社会的には正しい。フロウの文化では、共に暮らし言葉を交わし社会を支える存在であれば、種族が何であれ“人”として扱うことが礼儀とされている。言語的には、種族としての「フロウ」と人類全体を指す「フロゥ」は発音にわずかな差があるが、文字では区別されない。この曖昧さが、逆に「人類社会そのものが一つの種である」という意識を強めている。 フロウは肉体的には18歳ほどで成熟し、15歳前後で社会的な自立を果たすのが通例である。その成長と老化の速度は他種族と比べて標準的で、寿命も長くも短くもない。特徴を挙げるならば、「特長がないことこそが特徴」と言える。キゲインのような頑健さも、ティスリのような精霊親和性も、マオナムのような好奇心旺盛な気質も「種の傾向」としては持たない。だがその代わりに、フロウはあらゆる環境に適応し、数によって文明を築くという強みを持つ。彼らの生存戦略は個々の力ではなく、繁殖と拡張、社会的連帯にある。竜たちはこの“数による支配”を最も危険な力とみなし、人間こそが世界の均衡を揺るがす存在であると警戒している。 この種族は多様であり、個体ごとの差が非常に大きい。英雄も愚者も、聖人も悪人も、同じフロウという種の中に並び立つ。彼らの社会は信仰と理念によって方向性を変え、数の多さゆえに文明を発展させもすれば、同じ理由で愚行を繰り返すこともある。フロウの社会構造は、数の力に依存する傾向が強い。多数決や集団的正義を重んじる一方で、それが盲信的な同調を生みやすい。善にも悪にも偏りやすく、操りやすくもあるのだ。そのため、神々にとってもフロウは特異な存在であり、善神も邪神も彼らの信仰を巡って競い合う。フロウが信ずるものが世界を変え、その選択が善悪をも左右する。 彼らは、世界の中で最も不安定にして最も可能性に満ちた種族である。強さも弱さも、すべては人の心の中にある。竜の時代を終わらせたのも人であり、再び争いの種を生み出すのもまた人である。フロウとは、神々と竜とが見守るこの世界の縮図そのもの――数による発展と、理性と混沌の狭間で揺れ動く、永遠の人類の名である。
身長・体重の範囲
■フローラント版ゲームデータ サイズ:中型 能力値修正:なし。 移動速度:30フィート。 視覚:通常視覚。 特技:レベル1時に追加特技1つ。 技能ポイント:レベル1で+4、以後各レベルで+1。 繁栄力:1日に1回、アクションポイントの出目に+1出来る。 言語:出生地に依るが、基本的には大陸語。 ■マスターズ・コメント 他種族が持つ様々な特殊能力と比べても揺るぎない魅力を放つ、たった一つの追加特技枠。技能ポイント目的でフロウを選ぶ人を見たことないので、マジで特技一つで存在意義が成立している。それくらい、特技枠が一つ増えることは大きな効果を発揮する。 本来は「マルチクラスの自由度が高い」という、もう一つの大きな長所が存在したのだけれど、フローラントでは他種族からマルチクラス制限を撤廃したので、実質弱体化していた。それでは気の毒なので穴埋め強化を実施。AP能力が向上したのである。 ●ティスリ  ティスリはこの世界において、いわゆる“エルフ”と呼ばれる種族に相当する存在である。星渡りの民が初めて彼らを目にしたとき、「エルフが実在している」と驚愕と感動をもって迎えたという記録が残っている。その優美な姿と神秘的な雰囲気は、彼らにとってまさしく幻想種の象徴であり、ティスリという種の名は、かつての伝説を現実にした生ける証として刻まれた。もっとも、今では「エルフ」と呼ぶ者はほとんどおらず、たとえそう呼ばれても彼らは気を悪くすることはない。星渡りの民がその言葉に憧憬と敬意を込めたことを知っているからである。 ティスリの社会は、自然と都市の二つの世界にまたがって存在する。森や湖といった自然の中で精霊と共に生きる者たちは「森ティスリ」と呼ばれ、文明都市に溶け込みフロウと共に暮らす者たちは「街ティスリ」と呼ばれる。さらに地下世界に拠点を築き、光を避けて暮らす「闇ティスリ」も存在するが、彼らは闇を愛するがゆえにそう呼ばれるのであって、邪悪な種族では決してない。それぞれの生き方は異なるが、すべてのティスリに共通するのは、高い知性と精霊魔導への深い親和性である。彼らの多くは生まれながらにして精霊の声を感じ取り、その力を扱う術に長けている。 外見的にはきわめて美しい種族として知られるが、性格は理知的で保守的、閉鎖的で理屈っぽい傾向にあり、知的な冷静さが時に人間的な温かみを欠く印象を与えることもある。そのため、「美しいが魅力に欠ける」と評されることも少なくない。だが、その冷静さこそが長命を生き抜くための知恵でもあり、軽率な情熱を戒める精神的な強さでもある。 ティスリはフロウとほぼ同じ速度で成長し、20歳で成人に達する。しかし、そこから老化が始まるまでの期間が極めて長く、300年を過ぎても外見は壮年のままである。老化が始まると急速に衰え、まるで根を失った巨木が一気に枯れ落ちるように寿命を迎える。長命ゆえに戦場に立つ期間も長く、その多くが天寿ではなく戦死によって命を落とす。精霊魔導による治癒術の発達により、若年層の病死はほとんど見られないが、外敵の多い森で暮らすティスリにとって、戦場は常に身近な現実である。数百年にわたり戦い抜き生き残った森のティスリは、農村の長老にも匹敵するほどの希少な存在として敬われる。 一方で、街に暮らすティスリは比較的安全な生活を送り、敢えて外に出ることを選ばなければ天寿をまっとうする者も多い。だが、それが社会的な問題を引き起こすこともある。フロウ社会においては世代交代が進むことで権力や価値観が更新されるが、ティスリは数百年もの間、同じ地位に留まり続けることが可能である。その結果、200年前の王の后が今も若々しく生き、政治に影響力を持ち続けるような事態も珍しくない。彼女の子孫がハーフ・ティスリである場合、その寿命もさらに延びるため、権力構造の停滞や継承問題を引き起こす原因となることもある。これらの問題は長命種が社会の一部として共存するうえで避けられぬ課題であり、長命種たちはそれを自覚して慎ましく隠遁するという独自の倫理を確立してきた。伴侶を失った後は自主的に地位を返上し、穏やかに余生を過ごすのが最も賢明な生き方とされる。地位に固執する者もいるが、今ではそれは無用な災いを呼ぶ愚行とされている。……まぁ、それでもその愚行は珍しくないのだが。 繁殖力はフロウと比べて著しく低く、現実的な出産頻度はおよそ20年に1人程度である。もっとも、ティスリの出産可能期間は数百年に及ぶため、個体単位で見ればフロウよりも多くの子孫を残すことが可能である。だが、その長大な寿命に比例して世代交代のサイクルも緩慢であり、同様のペースで緩やかに「損耗」していく結果、共同体全体としての人口増加は依然として抑制的である。 ティスリの中でも、森に残る者たちは竜と深い関わりを持つ。精霊そのものの神格的存在が竜であることを考えれば、彼らが竜と協調関係を築くのは自然な帰結である。結果として、森ティスリの多くは竜側の勢力に属し、人類と敵対する立場に立つことも少なくない。それでも人類の側につく街ティスリたちは、同胞意識を強く保ちつつ、決して裏切りではなく「選択の違い」として互いを理解している。 人類との絆を深める契機となったのは、解放戦争時代に活躍した英雄たちの存在である。解放者エイファスの伴侶であり、英雄のひとりであったファーナがハーフ・ティスリであり、その父サファールが純血のティスリであったことは、ティスリと人類との絆を象徴する出来事として語り継がれている。彼らの存在が、人類とティスリが共に歩む未来を象徴し、両種族の信頼を決定的に結びつけた。 ティスリは知性と美、そして長命という三つの資質を兼ね備えた種族である。その生き方は時に冷徹に見えながらも、世界を俯瞰する深い洞察に裏打ちされている。彼らは精霊と語らい、自然と共に生き、人の世にあってもなお森の静謐を胸に宿す者たち――この星における叡智の守り手にして、永劫の観測者である。
一般的な身長・体重の範囲
■フローラント版ゲームデータ サイズ:中型。 能力値修正:【耐久力】−2、【判断力】+2。 移動速度:30フィート。 視覚:夜目。 照明の「薄暗い範囲」が2倍となる。「明るい範囲」までは2倍にならない。 技能ボーナス:〈聞き耳〉〈捜索〉〈視認〉+2種族ボーナス。 特性:(心術)系呪文・効果に対するセーヴに+2種族ボーナス。 武器習熟:ロングソード、レイピア、ロングボウ、ショートボウを単純武器として《習熟》《熟練》できる。 魔導適性:呪文の種類を識別する際の〈呪文学〉、呪文抵抗を突破する際の術者レベルに+1種族ボーナス。 言語:出身地に依るが、街ティスリは基本的には共通語(大陸語)、森ティスリはティスリ語。 種族代替特徴:上述した四つの武器への《習熟》優遇を得ない代わりに、技能ポイント+3。 ■マスターズ・コメント D&Dのエルフと言えばかつては魔法戦士の代名詞であり、バスタードでもロードス島戦記でも活躍していたわけだが。 3.5版のエルフは魔法戦士どころかウィザードに向いてない……というか、冒険者に向いていない。【耐久力】を削ってまで【敏捷力】が上がっても、まったく釣り合わないのだ。貰える武器習熟はそもそも魔法戦士やるなら前衛クラスとマルチするんで無意味だし、魔法が得意な種族的特徴も全然無い。どうしようもない。 TRPG部のレギュレーションは能力値がインフレしているんで、【耐久力】の低下は誤差みたいなもんだが、それにしたって「長所に魅力が乏しい」のは否めない。 そんなわけでフローラントのエルフことティスリは主に【判断力】で呪文を使う精霊使い系への適性を伸ばすべく強化。ティスリ社会は精霊信仰ばっかじゃないので、聖職者も普通にいる。軍用武器への習熟も精霊使いや神官・聖堂士では得られないので、これまた有り難い。更に呪文関係の能力も少し強化。 その代償として、ゲーム的過ぎて違和感のあった隠し扉の感知能力や、「D&Dのエルフは眠らない」ことに起因していた睡眠効果への完全耐性を失った。フローラントのティスリは普通に眠る。 ●  ダーク・ティスリとは、ティスリと同じ長命の血脈を持ちながら、地上ではなく地下世界を本来の居場所とする種族であり、遥かな時を経て地下の環境へ適応してきた種族である。彼らの暮らしは洞窟と陰影に満ちた世界に根ざし、地上で暮らすとしても深い森の奥や厚い屋根に守られた市街地の内部など、陽光が瞳にも触れない場所に限られる。突然の光は彼らの視覚を容赦なく奪い、闇に最適化された感覚は太陽のもとでは痛みに似た混乱を招くため、彼らにとって光は祝福ではなく脅威として扱われることが多い。故に地上での暮らしは、慎重に選ばれた日陰の街路や建物の中に限られ、光を遮るという行為そのものが、彼らの生活文化の中に深く組み込まれている。 その外見はティスリと同じく美麗でありながら、地下の静謐を宿したような独特の冷ややかさが漂っている。成長や寿命はティスリとほぼ同様であり、数世紀にわたって壮健な姿を保つ。だが肉体の傾向はティスリと同じではなく、ティスリがしばしば理知的な聡明さを象徴するとされるのに対し、ダーク・ティスリはそうした性向の偏りを持たない。むしろ地下の環境が求めるものは知識よりも生存術であり、狭く死角の多い洞窟では一瞬の判断と反射のほうが重要である。彼らの身体はフロウと同程度の強さしか持たないにもかかわらず、あらゆる魔力に対して驚くほど高い抵抗力を示す。この強靭な生来の抗魔障壁は、地下に生息する奇怪な魔物――錯覚、精神撹乱、擬態、幻惑を操るものたち――との長い共存が育んだ適応であり、肉体以上に魂そのものが鍛え上げられていった結果だと言われている。この魔力への耐性こそが、彼らを強力な戦士たらしめている。 また、闇に依存する彼らの生活は、視覚に頼らぬ感覚の発達を促した。洞窟は常に死角があり、物音は反響し、空気は複雑に流れ、光では判別できない危険が潜む。ゆえにダーク・ティスリの警戒心は強いが、それは猜疑心からではなく、生き延びるための本能的な姿勢である。目に見えるものよりも、匂い、気配、音、そして説明のつかぬ“感性”を重視する。彼らはしばしば「波長が合う相手」を瞬時に見抜き、それを深い信頼へと昇華させる。この感覚は理屈を超えた領域に属し、出会った瞬間に心が惹かれ合う“電撃的な確信”すら伴うため、ダーク・ティスリの恋愛には一目惚れが非常に多いと伝えられている。 とはいえ、彼らは閉鎖的な種族ではない。冒険心が強く、地下を離れて地上の世界へと踏み出す者も少なくない。都市において彼らは「珍しい」と見なされるが、「滅多に見ない」というほどではなく、ときおり旅人や傭兵、研究者として姿を見せる。性格は中庸であり、好戦的でも平和至上主義でもなく、生きるために必要とあれば戦いにも赴くし、必要がなければ静かに暮らすこともできる。彼らを単純な気質で語ることは不可能であり、その多様さは長命種としての深い歴史に裏打ちされている。  地下世界では、彼らはしばしば侵略的な外征を行う。これは領土欲というよりも、生存圏と食糧源の確保を目的とした、地上国家の戦略に似た合理的行動である。地上の人類とは、古くから地下防衛の同盟者として共闘してきた歴史があり、とりわけダーク・キゲインと並んで地下の要衝を守る重要な戦力として認識されている。人類側とつながりを持つ者たちは、その魔導文明に深い興味を抱き、魔力と技術の融合がもたらす恩恵を高く評価している。 しかし、彼らの大多数がどちらの陣営に属するかといえば、やはりティスリと同様に竜側につく者のほうが多い。竜の権威は地下世界に深く影を落とし、彼らの文化や歴史に影響を与えてきた。強き存在に従うことは、洞窟に根ざした生存の論理とも相性が良いのだ。それでも人類側を選ぶ者が多く存在するのは、彼らが実利を重んじる種族でもあるからだ。自らに益をもたらす相手であれば、種族の違いを理由に拒むことはない。人類の都市に暮らすダーク・ティスリは、街ティスリと同様に、人類社会の一角を担う住民として受け入れられ、主要種族とまでは言えないにせよ、確かな存在感をもって“人類種”の一員として数えられている。 光を嫌い、闇を住処としながらも、彼らは閉ざされた者ではない。洞窟の静寂に育てられた鋭い感性と、魔力すら弾き返す精神の堅牢さを備え、仲間との絆を深い情として昇華させる不思議な心を持つ。その生き方は、闇に生まれながらも闇そのものに囚われず、地上と地下の境界を越えて揺れ動く。ダーク・ティスリとは、闇の民でありながら世界の広がりを恐れぬ者たち――地上と地下の双方から信頼と警戒を注がれる、静かにして強靱な民族なのである。
一般的な身長・体重の範囲
■フローラント版ゲームデータ サイズ:中型。 移動速度:30フィート。 視覚:暗視120フィート。 技能ボーナス:〈隠れ身〉〈聞き耳〉〈忍び足〉+2種族ボーナス。 防御特性:呪文抵抗11+キャラクター・レベル。 標準アクションでオンオフ可能。 武器習熟:ロングソード、レイピア、ロングボウ、ハンド・クロスボウを単純武器として《習熟》《熟練》できる。 光による盲目化:明るい光(太陽光とかデイライトの呪文とか)に突然晒されたダーク・ティスリは、1ラウンドの間[盲目]状態になる。これに加えて、明るい光にさらされている最中、ダーク・ティスリは、すべての攻撃ロール、セーヴ、判定に-1の状況ペナルティを受ける。 言語:出身地によるが、基本的にはティスリ語。 種族代替特徴:上述した四つの武器への《習熟》優遇を得ない代わりに、技能ポイント+3。 ■マスターズ・コメント 地上で冒険するダーク・ティスリは適応特技や環境適応呪文が存在するよ。魔法のサングラスとかもあるしね。 ってわけで別にD&D公式のダークエルフのように種族レベルで超絶邪悪で好戦的で四六時中侵略することと内ゲバのことしか考えてないヤベー種族ではなく、「地下世界のフロウ」とでも言うべき存在です。 最大の特長はその生来備えた呪文抵抗能力。これはマジで強い。凄く強い。仲間の呪文まで弾き飛ばすので扱いに注意が必要だが、能動的にオンオフ可能だし、既にかかってるバフを引き剥がしたりとかはしない。 プレイの歴史としては敵味方どちら側でも登場しており、恐るべき敵だったり、気の良いナイスガイなウトラス君だったりと、人それぞれである。 ●蘇生と埋葬  フローラントにおける埋葬は、単なる形式ではなく、魂を神へ送る正式な儀式である。 この儀式によって魂は神霊界へと導かれ、神のもとに登録される。 一度神霊界へ帰還した魂は、本人の同意がない限り現世に呼び戻すことは困難であり、原則、強制的な蘇生は神の裁定によって拒まれる。 したがって、埋葬は死者の尊厳を守る宗教儀式であると同時に、敵対者による蘇生や魂の悪用を防ぐための霊的・戦術的封印行為でもある。
●死亡 レイズ・デッドは「死んだ状態のまま、死体に魂と生命力を呼び戻す呪文」なので、死んだ瞬間に即死するようなダメージを負ってない場合のみ、この状態と扱われる。 止血さえ完璧なら手足が吹っ飛んでようとも別に即死はしないわけで、蘇生自体は可能。欠損部位を再生するリジェネレイトの呪文をあとから別個にかけるように。 ●損壊 リザレクションは魂の呼び戻しと肉体再生を同時に行う呪文。 首が無いとか、首しか無いとか、髪の毛しか無いとか、なんにせよ「魂を呼び戻したところで即死する」のが明白な状態の死者にはこれじゃないと無意味。 ゲーム的には一括で扱われるが、世界設定的には損壊度合いで難易度変わる。 ●灰燼 トゥルー・リザレクションならば、正式な儀式で埋葬されてしまった死者すら蘇らせる。 儀式に則らず、単に火葬しただけなら損壊扱い。 アンデッド化された者でも、魂の破滅さえしていなければ浄化されて蘇る。 致命傷レベルの精霊蝕で死んだ人間は、魂の呼び戻し自体は可能だが、蘇生した瞬間即死するので、事実上蘇生不可能である。 これもゲーム的には一括で扱われるが、世界設定的には状態次第で難易度が変わる。死体の一部が残ってる方が楽。 ●石化 呪文や「メドゥーサに睨まれた」などの超常能力で瞬時に石化した状態。 この状態のクリーチャーは死亡していないため、蘇生呪文で回復することは出来ない。 最も手軽な「対象を半永久的に行動不能とする手段」であり、石化状態のまま何処かに隠蔽された場合、遺体が存在せずとも蘇生可能なトゥルー・リザレクションの呪文をもってしても無意味である。 ただし生存状態であるならば、魂しか存在しない場合よりも呪文による捜索が容易となるため、「どこかに埋められた」程度であれば対応可能。ここまでして蘇生妨害したい相手が、呪文対策をしないとは考えづらいが。 石化状態で異次元に放り込むことでかなり強固な妨害となるが、それでも単なる距離の問題かつ消息の把握に限れば、そこまで絶望的な障壁とはならない。高位の召還呪文で回収可能である。 ●封印  「トラップ・ザ・ソウル」「ソウル・バインド」の呪文に類する効果で「魂が封印」されていたり、「テンポラル・ステイシス」「インプリズンメント」の呪文に類する効果で「時間停止」されてしまっている状態。 結局埋葬しようが「超高レベル聖職者と金とさえ用意できれば蘇生出来てしまう」ので、それが可能な即ち高レベルだったり有力な存在であれば、嫌がらせにしかならない。つまり本当に蘇生を阻止するなら、魂の封印を行うしかない。 上記呪文がその代表例と言うだけで、様々な形で封印・固定は可能であるが、いずれも蘇生呪文に匹敵する高難易度・高コストなので、誰もがおいそれと行えるものではないものの、逆を言えば蘇生呪文を使えるほどの術者がいれば可能なことも意味するし、例えば「トラップ・ザ・ソウル」の呪文を1回だけ発動可能な魔導具ならばトゥルー・リザレクションの触媒代より安価だし、スクロールならばさらに一桁安い。 原則的に、封印された宝石や壺などを破壊したり、時間停止状態の対象に解呪を試みることで、解放可能。 封印状態のクリーチャーは、解呪を除くあらゆる外部からの干渉を受けなくなるため、一般的な呪文による捜索も不可能で、「ウィッシュ」「ミラクル」の呪文を複数回用いることで、少しずつ範囲を絞っていく必要がある。 ●消滅 なんらかの形で魂が霊的リソースとして消費されてしまったり、魂の破滅を迎えたなどで、神霊界にすら魂が存在しなくなった状態。 魂が封印されてしまい、神霊の呼びかけに応じない場合も、区別がつかないので消滅したと扱われることがある。それもあって、消滅した事実を「なにかに囚われているだけ」と思い込んで、諦めきれずに妄執に狂う者もいる。 一方で、魔王に囚われた恋人の魂を取り戻し、見事蘇らせた英雄譚も存在する。 ■蘇生と霊的影響 フローラントにおいて、埋葬とは単なる遺体処理ではなく、魂を神霊界へ正式に送達する宗教儀式である。 この儀式が完了した魂は神の管理下に置かれ、本人の同意がない限り、現世への呼び戻しは原則として不可能となる。 埋葬後の遺体には、記憶解析や下位の蘇生呪文は作用しない。 遺体の損壊そのものも蘇生難度を押し上げる要因ではあるが、正式な埋葬による封印効果はそれとは比較にならないほど強力である。 高位の蘇生術であれば、髪一本や骨片といったごく一部の肉体からでも蘇生は可能である。しかし、埋葬が完了している場合には、さらに高位の呪文、もしくは神自身の明確な許可が必要となる。 一方、簡易的な埋葬や形式的な祈祷では神霊界への送達が不完全なため、霊的封印としての効力は限定的に留まる。 ■戦場と軍事的意味 戦場において遺体を敵に奪われることは、アンデッド化や魂の悪用に直結する危険を孕む。 そのため、敵に持ち帰られるくらいであれば、その場で埋葬するという判断は決して珍しくない。 軍の運用としては、貴族や英雄の遺体は後送される一方、雑兵の遺体は原則として戦地で放置、もしくは簡易埋葬が行われる。 ただし戦場放置は自然発生的アンデッドの温床となるため、最低限の霊的対策として、簡易埋葬であっても神の印を刻み、魂の封印を施すことが推奨されている。 ■邪神による魂の奪取とアンデッド化 神霊界に登録された魂であっても、邪神や外界存在によって強制的に奪取される危険は存在する。 これは蘇生ではなく、魂の略奪と歪曲である。 すなわち、神の保護下にある魂を暴力的に引き剥がし、現世に縛り付け、アンデッドとして再構成する行為を指す。 この場合、魂は本来の神霊界への帰還経路を完全に失い、永続的に穢れた形で現世に留まる。 こうした存在は「神に見捨てられた者」ではなく、「神から奪われた者」として扱われ、その出現自体が神々への冒涜と見なされる。 ■儀式と実務 埋葬は聖職者による正式な宗教儀式であり、遺体の損壊度に応じて必要とされる位階が異なる。 ・五体満足の遺体:新米の聖職者でも埋葬可能 ・損壊が激しい遺体:高位聖職者による儀式を要する 儀式難度は蘇生ほど急激には上昇しないが、遺体の損壊が大きいほど、より高位の儀式が求められる。 正式に埋葬された遺体は神の加護を受け、屍問や魂拘束といった呪文に対する耐性を得る。 ■遺体散逸と象徴的埋葬 遺体が激しく損壊、あるいは散逸している場合であっても、共同体は区切りと祈りのために埋葬を行う。 遺髪、遺品、象徴物などを用い、実体が存在しなくとも神への託しを示すことがある。 このような象徴的埋葬は霊的効力が弱く、低位の聖職者では真の埋葬として成立しない場合も多いが、信仰的・心理的な区切りとしては重要な意味を持つ。 なお、埋葬の有無に関わらず、神が認めない限り同意なき蘇生は極めて困難である。 ■蘇生素材の制約 蘇生には、死亡時点で魂と結び付いていた肉体の一部が必要となる。 この結び付きは「魂の余熱」と呼ばれ、生体から完全に分離された状態で時間が経過すると失われていく。 生前に保存されていた髪、爪、血液などは、すでに魂との結び付きが希薄であり、蘇生素材としてはほぼ無意味である。 一方、死後すぐに切り取られた遺髪や骨片など、死亡時点の肉体であれば、蘇生媒体として機能する。 ■埋葬と蘇生の競争 遺体の一部(遺髪・骨片など)が確保されている場合、蘇生と埋葬の間で「競争」が発生する。 どちらの儀式が先に完了するかによって、魂の帰属先が決定されるためである。 このため戦場では、遺体回収部隊と埋葬隊が同時に行動し、一方は魂の救出を、他方は魂の保護を目的として動く。 ■社会的・倫理的側面 埋葬とは、蘇生の可能性を断つ行為であり、戦場の急場や庶民にとっては精神的にも重い決断となる。 高額な蘇生費用を支払えない者ほど踏ん切りがつかず、埋葬を引き延ばす例も少なくない。 その結果、蘇生の機会を得られる貴族や英雄と、埋葬によって完全な別れを迎える庶民との間には、明確な格差が生じている。 また、埋葬後に無理な蘇生を試みる行為は神への冒涜とされ、宗教的禁忌のひとつに数えられる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■死者蘇生といえば最近読んだ本田鹿子の本棚 過去一で可愛い女の子出てきたと思ったら秒殺で吹いた。 このあととんでもなく足が臭くなるなんて……!!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■プレゼントありがとうございます( ・`ω・´) 棚にはとりあえず怪獣を並べるのが我が流儀!!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■バンドリちゃん どうも。アフロで再推しはひまり、MyGO!!!!!は愛音のワダツミです。結婚したい。 てかリッキー、FXで有り金全部溶かす人の顔になっとる(笑) 実際、かなり「憧れの存在」に会う実績解除してきたけど、生涯で一番緊張したのって、人生初の「憧れの人と会う」経験だった、水野良先生サイン会だったかもなぁ。まぁ話した内容完全に覚えてるんで、ガチガチで頭真っ白とかでは全然無いけど。 あ、でも近年でもD4DJのライブの「お見送り」は可愛過ぎて凄まじいほどに舞い上がったわ。いやこれ緊張とかじゃないわ。単に可愛過ぎただけだわ。可愛いんだもん。 直近の「舞い上がり」は、去年のコミケで奈須きのこさんがスペース来てくれたときかもな!! あれはたしかに「もっと話すことあっただろう」と後から後悔したかもしれん。ほら、「葛木がセイバーボコれたのおかしくないすか?」とか(絶対やめておけ あ、でもこやまひろゆきさんに昔「イスカンダルの軍略Bはなんでですかね。人類史上で彼以上の軍略家、存在しないと思うんですが」は言ったことあるよ(真似しないように  いやだってこんな超速スピナーもといバトルするのがサーヴァントなのに、その数十分の1程度しかない「常人の限界速度」のパンチがどんだけ虚を突こうが遅い! スローリィでしょうよ!(ほんと一生言ってる 帝都聖杯奇譚、相変わらず画力が尋常じゃなくて迫力がぶっ壊れている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ワートリ こんにちは。太眉女子大好きなワダツミです。 町田ちまってロリ巨乳で超歌ウマな太眉妖精だなと思って歌以外の動画見たらとんでもねーモンスターで妖精じゃなくて妖怪でした(褒めてます  指揮系統を軽視して、誰も彼もが「融通を利かせて結果オーライしよう」と独断専行すると、日本軍みたいなことになるんで気を付けようね!! 日本軍に限ったことじゃないけどね! 直近で一番わかり易い身近の軍隊としてね!!! 融通が利く人って、融通が利かない人が育てた畑を効率良く収穫できる能力を持っている人ってだけだからね。トラブル起きた時には頼もしいけど、平時にそんなやつばっかいても困るっていう。  こんにちは。水上を応援し隊の隊員、ワダツミです。 彼の効率重視でありながらこーいうところでの差配まで、なにもかもが「素晴らしい指揮官」であり、最高です。絶対組織に欲しいタイプです。  こんだけ大量にキャラが居る作品の中で、おそらく唯一と言って良い「嫌いなキャラ」である香取に対して初めて好感度が上がった瞬間である。やはりワートリ、クソキャラをクソキャラのままにしない名作。作中での「兵士としての評価が著しく低い」扱いも含めて、ワートリは素晴らしい作品だ。ここからもっとバンバン香取を上げてくんだろ!? 来いよ! かかってこいよ! 受けて立つぜ!!! へい、カモンカモン! オッケー!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■大魔王が統治しているわけではありません ●建国戦争 706~714 リクター・ファーランドが周辺諸侯を糾合し、ヴィーリオン王国に対して挙兵した戦いである。 バーン側では「建国戦争」、ヴィーリオン側では「大叛乱」と呼ばれる。叛乱開始に際し、ファーランド公爵家およびそれに賛同した諸侯による「バーン王国の成立」が一方的に宣言され、これを鎮圧せんとするヴィーリオンとの大戦が始まった。緒戦においてヴィーリオンは惨敗を喫するも、戦線の再構築に成功し、やがてバーン軍も攻勢限界に達したことで膠着する。このおおよそ建国宣言から膠着までの期間を指して、建国戦争と呼称する。 ヴィーリオンの諸侯たちは自らの領地を守るべく、各々が独立した判断と戦力で応戦した。一方でバーン側は国家兵力を統合して中央集権的な体制を築き上げ、明確な指揮系統のもとに組織化された常備軍を形成した。この構造の差は決定的だった。なぜか。 ヴィーリオンの封建領主たちに「お前たちの領内の防備は最小限にして、国境周辺にだけ戦力を集中しろ」「自分の領地を手薄にして他人の領地を守れ」と命じたところで、応じるわけがなかったのだ。だが、中央集権化を果たしていれば、その戦力集中が可能だった。これによって総兵力では遥かに劣勢にあったにも関わらず、バーン軍は戦力の機動性と柔軟性によって常に局地的な数的優位を保ち、戦略的に終始ヴィーリオンを圧倒した。 加えてバーン軍の編制は従来の軍事的常識を覆すものであった。すなわち、騎兵・歩兵・魔導師を単一の指揮系統で一体的に運用する「完全なる剣と魔導の統合兵団」である。この構想自体は古くから多くの軍略家が構想していたが、封建制における複雑な指揮系統と常備軍の宿命である膨大なコストが障壁となり、実現は困難とされてきた。バーンはこれを成し遂げた最初の国家であり、その戦術思想は既存の封建的軍制を凌駕するものであった。 紀元前より人類社会における戦争は、竜の勢力に属する極めて強力な魔獣など、数の力では無駄な損害を増やすだけなことが多い、少数の強大な敵を討つためのものであり、大軍よりも少数精鋭の英雄による戦闘が主流であった。当然数が必要な局面もごく普通に起こり得ることだが、その場合は傭兵を用いればよい。そうした歴史的環境において、バーンが編み出したのは「人類同士の戦争に最適化された軍隊」である。これにより、バーンは封建的な戦闘構造の限界を超えた。 魔導戦力の比率もまた従来の数倍に達し、ヴィーリオン軍は圧倒的な魔導飽和攻撃の前に蹂躙された。これは「魔導師」という職位を根本から再定義した成果である。バーンは魔導師から学術的・研究者的側面を排除し、戦闘用呪文の行使にのみ特化した「魔導兵」および「法兵」を体系的に育成。育成コストを劇的に抑え、短期間で多数を揃えた。 ひとりひとりの実力はヴィーリオンの魔導師に及ばずとも、3倍の数を揃えれば圧倒できるという明快な理屈である。結果、戦場ではバーン軍の魔導戦力が常に制空・制圧を握り、ヴィーリオンの精鋭魔導師たちは数の暴力の前に沈んでいった。 同様に、騎兵戦力の構成も革新された。ヴィーリオンにおける「教養と品格を兼ね備えた貴族騎士」に代わり、バーンでは純粋な軍人教育のみを受けた「騎兵」を中核とし、指揮・戦術・運用のすべてを専門化。結果として「同数で戦えば個の質でヴィーリオンが上」であっても、バーンは常に数的優位と統制力をもって勝利を積み重ねた。 封建領主たちの曖昧な指揮系統と、動員力の限界に縛られたヴィーリオンは、しばしば戦術的勝利を収める英雄を輩出したものの、戦争全体では圧倒的に劣勢を強いられた。8年に及ぶ戦いの末、ヴィーリオンは虚無地帯を国境として北西部を完全に失陥し、バーン王国の成立を事実上認めざるを得なかった。 やがてヴィーリオン軍もバーンの戦術に適応しつつあり、迎撃体制の再構築が進んだ頃、バーンもまた攻勢限界を迎える。最終的な転機となったのは、諸侯連合ゲーゲンヴィントによる《金梃》作戦における戦略的大敗である。これをもってバーンは国家規模の攻勢を停止し、一方的に戦争終結を宣言した。この瞬間、バーンは実質的な独立国家としての地位を確立し、以後、帝国成立への道を歩むこととなる。 ●西覇戦争 717~728 ヴィーリオン王国からの独立を宣言し、建国を果たしたバーン王国が、西方に連なる小国群――いわゆる「西方諸国」を平定するために発した征服戦争である。ヴィーリオン王国側ではこの戦いを「西方戦争」と呼ぶ。 この戦役においては、バーン帝国第二代国王フレデリック・ファーランド自らが西方総軍の最高司令官として指揮を執っており、国家規模での総力戦として展開された。 もともと西方諸国とは、ヴィーリオン王国の西側にひしめく小国家群の総称である。だが、建国戦争によってヴィーリオン北西部がバーンの版図となった今、地理的には「バーンにとっての西方」を意味する呼称へと変化している。もっとも、ヴィーリオンの北東地域は依然健在であり、「バーンの版図をまたいだ上で存在する西方諸国」という呼び方も成立していた。 建国直後のバーン王国は、旧ヴィーリオン北西部のみに領地を持つ国家に過ぎず、その国力・版図のいずれにおいてもヴィーリオンを大きく下回っていた。建国戦争での圧勝によって一時的に優勢を得たものの、あくまでそれは“戦略的猶予”を生んだに過ぎず、いずれ封建国家特有の再編を終えたヴィーリオンが立ち上がれば、国力差によって押し潰されるのは明白であった。 ゆえにフレデリック王は、バーンの命運をかけて西方諸国のすべてを制圧し、上回らぬまでも拮抗し得る国力を獲得することを第一の目的に定めた。西方諸国を併呑すれば、国土面積の上ではヴィーリオンと肩を並べることができる。総合的な開発度や経済力では依然としてヴィーリオンが優位に立つものの、少なくとも「戦えば必敗」というほどの差ではなくなる。そうなれば、ヴィーリオンといえど軽々に手出しはできまい――これがバーンの目論見であった。 しかしそこには、バーン側にとって絶対的な制約が存在した。 すなわち、「ヴィーリオンが建国戦争で被った戦略的大損害から立ち直るまで」という、明確な終わりを伴う猶予の時間である。これを過ぎれば圧倒的な国力差の前に屈するしかない。ゆえにバーンの戦略はすべてが“速さ”に集約されていた。 その方針のもと、バーンは国力差で容易に制圧可能な小国を相手にしながらも、降伏勧告を極めて重視した。いかに最終的な勝利が揺るがぬものであっても、戦うという行為そのものが時間を浪費する。それが積み重なれば、やがて時間切れという形で敗北に等しい結果を招く。 完全征服によって得られる利得よりも、迅速な支配確立を優先する方が戦略的に合理的であった。 バーンは、公爵・侯爵などの地位を新たに授け、降伏した諸侯には自治を認めるという形式を採った。これにより、国家主権のみを奪い、即座に新国家秩序に組み込むことが可能となったのである。フレデリック王の掲げた理念は単純明快だった――「国家の命脈を握りさえすれば、あとはどうとでもなる」。 この「既得権益の温存」という餌は、多くの小国にとって甘美な誘惑であった。 国の矜持を重んじて戦う派閥と、降伏して実利を取ろうとする派閥が国内で衝突し、内紛の火種を抱える国が続出する。中には開戦前から密かにバーンに通じ、寝返りの機をうかがう者すら現れた。バーンはこの分断工作を主軸に据え、降伏を誘発し、王国諸侯を瓦解させていった。 封建国家の常として、支配者たちにとって「国」よりも「自らの封土」が優先される。国家の統一意識が希薄であるがゆえに、この策謀は極めて有効に機能した。結果として、戦火を交えぬまま降伏する国家、内紛で自滅する国家、あるいは単独で寝返る貴族が続出し、西方諸国の抵抗力は急速に瓦解していった。 こうして広大であった西方諸国の征服は異例の速さで完了した。 ヴィーリオン王国は反撃の機会を逸し、再編を終える前に戦線は完全に膠着。西覇戦争の終結をもって、バーン王国はその版図をもって帝国の成立を宣言した。以降、この地はバーン西部領と公式に呼称されることになる。 フレデリック・ファーランドはここにおいて初代バーン皇帝の玉座に就き、バーン帝国の時代が幕を開けたのである。 ●西覇帝国バーン 728~ バーン帝国は、フローラント大陸北岸中央部から西部一帯を版図とする大国であり、その成立はリクター・ファーランドが引き起こした建国戦争と、彼の子フレデリック・ファーランドが主導した西覇戦争という二つの巨大な戦乱を経て達成された。もとはヴィーリオン王国の公爵に過ぎなかったリクターが、封建秩序に縛られた体制を打ち破らんと挙兵して王国を宣言し、続いてフレデリックが西方に連なる小国家群を次々と平らげ、帝国の建国を高らかに宣言したのである。ヴィーリオンから見れば「地方貴族による大叛逆」に過ぎず、当初は“国内問題”とみなされていたが、西覇戦争の頃にはバーンは完全に「外部から侵略してくる巨大な敵」として認識され、西方諸国にとっては悪の象徴とまで評されていた。一方でバーン人自身にとってはまったく異なる歴史観が存在し、彼らは「偉大なる西覇王に率いられた無敵バーン軍が、西方諸国をまたたく間に解放し、古い封建領主の圧政から民衆を救った」と誇らしげに語る。実際には出迎える民衆の情緒は地域によって千差万別で、涙を流して迎える者もいれば、最後の一人になるまで抵抗したリュートリオンのように恨みを深く刻んだ国家もあるのだが、それすらも“帝国は多様性を抱えうる巨大な器である”と、バーン人は率直に信じている。 帝国は西部領の統治において細やかな心遣いを欠かさない。これは征服者として傲慢な態度を取れば、反乱の火種が絶えず、版図を維持できないことを理解したうえでの計算でもあり、同時に「バーンの支配下のほうが暮らし向きが良くなった」と思わせることが帝国の安定につながるという明確な戦略でもあった。西部領の旧王家は降伏の後も爵位を与えられ、王国・公国・侯国といった形で自治を認められることが多い。無条件降伏を拒み、「この象徴だけは手放せない」「この鉱山権だけは渡せない」「第1世代呪甲装兵だけは保持させてくれ」といった各国の譲れぬ願いが交渉の席で飛び交い、その結果として複雑怪奇な条件の連鎖が今も西部領の火種となっている。中には割に合わない条件を飲んだせいで内紛が続発し、逆に帝国が介入する隙を生んだ例も少なくない。だがそれすらも帝国からすれば「統治のための布石」であり、中央集権化が進む帝国本土とは対照的に、西部領では旧来の封建制度が濃厚に残存した地域が多く、皇帝はそこに手を入れる機会を虎視眈々と待ち構えている。 バーン帝国の本質は徹底した実力主義にある。無能が世襲によって利権を享受することは最大の悪徳とされ、バーン貴族は「高貴な義務」と呼ばれる特殊な継承儀式を通過しない限り、貴族の地位は法的に認められない。これは封建国家における世襲の否定であり、旧い貴族社会の完全否定であった。だが同時に、庶民にとっては「実力さえあれば意見を通せる」「功績次第で平民を脱し、貴族へ至ることすらできる」という明確な夢を掲げることでもあり、国家への忠誠心を育むうえで大きく機能している。軍で功績を挙げれば騎士へ、さらに高い功績を挙げれば男爵・伯爵へ──理屈の上では誰にでも開かれた道であり、現実には並外れた努力と幸運が必要だとしても、バーン人はこの理念を誇りとしている。もちろん「実力主義=弱者への冷遇」という構図は常に摩擦を生むが、そもそも封建国家も“強者が弱者を導く”という構造の上に立っていた以上、庶民の生活感覚としては決して大きく変わったわけではない。ただ、極端に競争圧力が強いため、合わない者にはとことん辛い国でもある。 帝都の貴族生活も華やかさとは程遠い。バーンは城塞都市であるがゆえに都市拡張が難しく、帝都に住まう貴族は身分に応じた規模の館が与えられるだけで、広大な庭園を持つヴィーリオン貴族とは雲泥の差だ。諸侯の取り潰しが相次いだ結果、皇帝領は異様な広さとなり、領地持ち貴族は限られる。新興貴族の大半は所領を持たず、国家から俸給と館を受け取り、職業軍人として仕える。平民上がりに大領地の運営を任せても破綻するだけなので、この仕組みはむしろ歓迎されている。一国一城の主になりたい者は、功績を背景に所領持ち貴族との婚姻を目指すという形が一般的で、これもまたバーンらしい“実力と縁の混合した昇華ルート”と言えるだろう。 宗教面でもバーンは特異だ。鉄血神を主神と定めたリクター・ファーランドは既得権益に溺れた教会の専横を許さず、信仰心を失い神霊魔導の腕も鈍った者たちを容赦なく粛正した。教会側は当然抵抗したが、民衆はリクターの掲げる「純化された信仰」を支持し、宗教戦争にはならなかった。結果としてバーン各地の教会は国家補助で運営される「公的宗教機関」の色が強く、聖騎士の多くもまた土地を持たない職業軍人となった。もちろんこれで教団組織が皇帝の傀儡となったわけではなく、神の権威に対する敬意は損なわれていないのだが、かつてのように教団が国家運営に対して強い発言権を持ち、戦略レベルでの「意見具申」が横行する頻度は激減した。軍事・政治中枢に身を置く聖職者は数多いが、彼らはあくまで「バーン帝国の公人が聖職者でもある」であり、「聖職者がバーンの公人をしている」わけではないのだ。 軍事面におけるバーンの特色は明白で、列強唯一の国家規模常備軍を組織している。総兵力では国力に勝るヴィーリオンに及ばず、総動員力では国民皆兵に近いホウルティーアに劣るものの、軍としての統制力においては両国を凌駕する。中央集権の強みはここでも活かされており、情勢に応じて戦力を柔軟に再配置できることは、漫然たる封建軍制では到底不可能な芸当である。西覇戦争終結後、帝国は動員を大幅に解除し、西部領の治安維持は従来通り傭兵に依存するという“逆戻り”を行ったが、これもまた中央集権化の恩恵であり、必要な場所に必要な力だけを効率よく投下できる。 国家としての外征力は、続く戦争の連鎖によって現在ほぼ枯渇している。国力は限界に近く、外へ出る余裕はない。だが西方を併呑したことで大量の地下資源を確保し、現在は魔封石をはじめとする戦略物資の生産に国家全力を注いでいる。“バーン式の戦争”に必要な兵站を整えるためであり、兵站が整えば、バーンは再びその牙を剥くことができると信じられている。 帝国は現在の国境の膠着をむしろ望んでいる。ヴィーリオンは依然として大陸最大最強の国家であり、バーンは完全には拮抗していない。しかしホウルティーアを含めたいずれか2国が全面戦争を起こせば、残る1国が莫大な利益を得てしまい、均衡が崩れる。もし三つ巴になれば、竜の勢力が一気に台頭する絶好の機会となる。ゆえに、いかなる理由があろうとも、この緊張した均衡状態こそが帝国の最も望むところであり、その維持こそが今の皇帝の最優先課題であった。 ファーランド家が英語圏の星渡りの民を祖にしているため、母国語は英語をベースにしたバーン語が用いられている。 これは独立前から一貫してそうであり、ファーランド公爵領はフローラント大陸における英語文化圏の中心地だった。 公用語としての大陸(ヴィーリオン)語は変わらず使用されており、話者の数でも圧倒的にバーン語よりも多いので、文法は大陸語だが単語はバーン語も交じる。はたまたその逆でバーン語を話しているのだが、固有名詞は大陸語だらけといった、混合的な言語文化が育ちつつある。 ●帝都ソル  バーン帝国の首都ソルは、星渡りの民の故郷とされる星界の名を継ぎ、かつてファーランド公爵家の領都アークフィールドであった街が建国に際して改名されたものである。現在、皇帝直轄領アークフィールドと呼ばれる地域はソルとその周辺一帯を指し、帝国の中心たるこの都市は、建国王リクターの時代以来、膨張し続ける帝国の心臓部としてその役割を果たし続けてきた。 内陸に位置するという地の利の悪さを補うため、北海に至る長大なゴト運河が整備されている。この運河は約400年前、膨大な資金を寄進した稀代の天才宮廷音楽家ゴトの名を冠し、完成以来、帝国の歴史と共に拡張と改良を重ねて成長してきた。帝都の商業と物流を支える大動脈として親しまれ、人々はしばしば「都の動脈」と呼ぶ。 ソルはアークフィールド時代からヴィーリオン王国屈指の大都市であったが、城塞都市という制約ゆえに慢性的な空間不足に悩まされてきた。建国後の急速な拡張を経てもなお、城壁の防備を維持しなければならないという事情は変わらず、都市の拡張のためにはまず城壁の拡張をせねばならない物理的な制限は大きい。他国のように防備負担の軽い地域へ自由に拡がることは叶わず、土地利用には厳格な制限が課される。 もっとも端的な例が貴族邸宅の面積制限であり、ヴィーリオンのような広壮華麗な邸宅を構えることは許されない。与えられる区画は徹底して機能性のみが追求され、「寝泊まりができ、執務ができ、必要十分な数の使用人が生活できる」ことだけを満たす必要最低限の広さに抑えられている。豪華な広間や舞踏室、巨大な倉や庭園、不必要に多い使用人を抱えるための部屋といった“貴族趣味”の空間は、帝都では贅沢とみなされ、原則として認められない。 もちろん、この「最低限」とはあくまで貴族基準であり、庶民と比べれば十分に広い。しかし帝都外の本邸に比べれば雲泥の差であり、当地の貴族は「自領こそ本宅であり、ソルの邸宅は仕事場である」と割り切ることを求められた。 こうしたソル独自の事情は、広大な土地を惜しげもなく使うヴィーリオンの貴族たちからはしばしば揶揄の対象となり、「ファーランドの貴族は、せせこましい犬小屋に押し込められて暮らしているらしい」と嘲笑われることもあった。だがバーンにおいては、華美よりも実務を優先する帝国文化の象徴としてむしろ誇りとされ、「帝都で贅沢を求める方が恥」とすら受け取られている。 一方で、建国戦争後に急増した“職業軍人としての平民上がり貴族”、すなわち領地を持たず俸給のみで生活する新興貴族層にとっては事情が少し異なる。彼らには元々広大な本邸など存在せず、帝都での邸宅こそが事実上の本拠であるため、俸給から住居費を捻出し、自らの裁量で必要最小限の自宅を確保することが当たり前となっていた。豪奢さより実務性と身軽さを重んじる帝国の価値観を体現した彼らは、むしろこの“機能だけを残した最小限邸宅”という形式に馴染みやすく、古参の領地持ち貴族が不満を覚える点でも平然としていた。 かくして帝都ソルの貴族邸宅は、「華やかさを捨て、機能に徹した帝国の縮図」としての側面と、「外部からは犬小屋と揶揄されるが、当人たちは誇りを持つ実務の奔流の場」としての側面を併せ持つ、非常にバーン帝国らしい空間となっている。 帝都ソルは、行政・軍事・宗教・物流など帝国のあらゆる中枢機能を一箇所に抱える都市であり、その結果として極端に密集・高層化し、街全体が「無駄のない機能性」を体現する構造になっている。だが、この無駄のなさは同時に息苦しさを伴い、経済の脈動が生み出す熱気と喧騒は裏側で様々な歪みを蓄積してきた。商業地区は比較的余裕を持って設計され、往来に支障を来さないよう配慮されているが、市民の居住区は猥雑で狭苦しい。乱雑さこそスラムと呼ぶほどではないにせよ、治安の目が行き届きにくい区域が点在し、城塞都市特有の圧迫感が否応なく人々の生活を覆う。 ソルは活気という意味では大陸随一であり、帝国最大級の経済圏を形成している。商人同士の競争は熾烈を極め、街の狭さゆえに店舗の確保がそのまま権威となる。バーン流の強烈な競争意識と、店舗用地の希少さが相乗して、商人の駆け引きは帝国港湾都市ゼナ以上に苛烈とされるほどだ。実際に大店による小店の買収・吸収が露骨に行われた時期には、商業の多様性が失われる事態にまで発展し、帝国は規制法を施行して市場の独占を排し、帝都の商業環境を建て直したという経緯がある。 人の出入りに関しては非常に開放的で、物流と経済の活発化を妨げないことが最優先される。その結果、帝都は人間・犯罪者・商人・旅人・野心家のすべてが渦巻く巨大な坩堝となり、治安は常に緊張状態に置かれている。帝国当局は交通規制よりも取締能力の強化によって混沌に立ち向かい、治安維持局テミスと帝国諜報機関アーガスを中心として、賞金稼ぎなど民間勢力も積極的に活用した濃密な監視網を築き上げている。そのため犯罪発生率こそ高いが、検挙率はさらに高く、都市全体が常に闇と光の両側面を濃く抱えたまま均衡を保っている。 この莫大な人口密度と熱量が帝都に魔力めいた吸引力を与え、善も悪も、成功者も野心家も、名声を求める者も逃亡者も、あらゆるものがソルに集まる。都市全体が巨大な渦であり、動けばその波紋が大陸全土に影響を及ぼすとすら言われる。大都市としての権威と混沌が同居し、整然とした行政機能の裏で、夜闇に潜む犯罪組織や野心家が暗躍し続ける――それが帝都ソルという特異点である。 帝都の常駐戦力は、主だったものだけでも各教団の最精鋭、剣聖ルーインズ・フォーマー率いる近衛騎士団、対竜特務部隊である第501巨竜猟兵大隊、そして真機クリムゾン・グローリーを含む3機の機神。それらの頂点にはフレデリックの急死により跡を継いだ長子、古竜殺しの神弓皇帝チェスター・ファーランドという、帝国の粋を集めた最強布陣が担っている。帝都に敵対することは、すなわち大陸最強戦力に挑むことになると自負し、その威容は帝国の威厳と権力を象徴している。 ●ファーランド家の政体3段変化 午前の陽光が高窓から柔らかく差しこむファクセリオン経世学院・政治史上層棟の大講義室では、半円状に並ぶ座席のあちこちで学生が羽根ペンを走らせていた。壁面の浮遊魔導板には大陸東岸から西岸までを一望する巨大な地図がゆっくりと回転し、ヴィーリオン王国の深い蒼、バーン帝国の紅、そしてその間を埋める複雑な諸侯領のモザイクが鮮やかに描かれている。 今日の講義テーマは―― 「現代大陸史の基軸――ヴィーリオンの覇権と、ファーランド家の政体三段変化」 であった。 歴史教導師アストロ・ラインヴァルトが講義壇へ立ち、杖の先を魔導板に軽く当てると、画面全体が東へ寄り、巨大な領域が青い光を帯びた。 「諸君、まず理解しておかねばならない。ファーランド家の変遷――公爵領から王国へ、そして帝国へ――この壮大な政治劇は、単独では決して成立しなかった。なぜなら、その背後に常に君臨していたのが……」 教授が杖をもう一度鳴らすと、大陸の東半分を覆う巨大な領域が強調表示される。 「人類史上最大の超国家――ヴィーリオン王国だからだ」 教室がざわついた。知識としては理解していても、“地図上の存在感”をこうして突き付けられると、圧力が違う。 「ヴィーリオンは文明の再出発点だ。解放戦争後、人類は竜王の脅威から解き放たれたとはいえ、再び世界を組み立て直す必要があった。その中心となった国家がヴィーリオンであり、700年以上、政治・宗教・文化・言語・軍事すべてにおいて基準となり続けた」 前列の女子学生が手を挙げる。 「では、ファーランド家の建国戦争は、ヴィーリオンの“内部抗争”という扱いなのですか?」 「その通り」 教授は頷く。 「720年代以前の史料では、建国戦争は“バーン王国との対外戦争”ではなく、“ヴィーリオン国内の地方公爵による叛乱”として扱われている。つまり、ファーランド家は巨大国家ヴィーリオンの一断片に過ぎなかった」 魔導板には“ファーランド公爵家の離反行為”という冷たい文字列が投影され、教室に小さなどよめきが広がる。 「しかしだ、諸君」 教授が杖を振ると、地図は西方へ拡大し、当時の“バーン王国”の紋章が点灯する。 「その“地方公爵の叛乱”が、わずか20年で“帝国”となる。ここに至る背景を理解するには、ヴィーリオンがどれほど巨大で、どれほど封建的で、どれほど動員力に欠けていたかを知らねばならない」 後列の男子学生が手を挙げた。 「ヴィーリオンほど強大な国家なら、地方叛乱など一瞬で鎮圧できたのでは?」 「いい質問だ。しかし現実は逆だ」 教授は微笑しながら続ける。 「ヴィーリオンは広大すぎて、“内部の異常”に即応する機動力が弱かった。領主は各地に散在し、常備軍と呼べる規模の統一軍は王家近衛と若干の大諸侯に限られていた」 魔導板が切り替わる。 「領土は世界最大だが、戦略的機動力は脆弱」 学生たちが笑い、教授も肩をすくめてみせる。 「対してファーランド家は――」 魔導板に3つの称号が浮かぶ。 「ファーランド公爵 → バーン王 → バーン皇帝」 「この3段変化を20年でやってのけた。一族は同じ、軍の中枢も同じ。しかし、政体の格だけが爆発的に上昇した」 すると、別の女子学生が手を挙げた。 「先生、これは臣民にとって混乱ではありませんでしたか? 仕えている相手が同じなのに、文書上は別の国の臣民になってしまうように見えます」 教授は満足げに笑い、魔導板に新たな記録を投影した。 「良い指摘だ。実際、当時の従士の記録を読むと困ることがある。同じ人物なのに、史料上の肩書きが3種類存在するのだ」 数年前 → 「ファーランド公爵家従士」 中期 → 「バーン王国軍従士」 現在 → 「バーン帝国皇帝直属従士」 「本人は転職していないのに、所属国家名だけ3回変わる。これは史料整理の悪夢だよ」 教室が爆笑に包まれる。 「じゃあ昔の家臣は、国名が変わるたび自己紹介を更新してたんですか?」 と前列の学生が冗談めかして尋ねる。 「――実はその通りだ」 教授も笑う。 「軍の制式名称、役職名、手当て、部隊番号……全部更新された。“王国→帝国”の時期は特にひどく、“バーン王国帝国軍”などという誤記すら残っている」 学生たちは肩を震わせながら記録しつつ、教授は続きを語る。 「しかし、この混乱そのものが――巨大国家ヴィーリオンの存在と不可分なのだ」 魔導板には再び3つの巨大国家の図が表示される。 ヴィーリオン ——最大の超国家、しかし緩慢で封建的。 バーン帝国 ——ファーランド家が作り上げた中央集権国家、動員力は大陸随一。 ホウルティーア ——国民皆兵型、軍事共同体的国家。 「この3国は、竜王亡き世界で“人類文明の屋台骨”を3方向から支えている。どれが欠けても文明は崩壊する。そしてこの3つの均衡こそが、いま我々の時代を形作っている」 女子学生が再び挙手する。 「では結局、バーン帝国とヴィーリオンはどちらが勝つのですか?」 教授は静かに笑い、講義室全体を見渡した。 「――決着がつくようなら、とっくに滅んでいる」 ざわめきが広がる。 「ヴィーリオンが本気で総力戦に踏み切れば、バーンは持たない。だがバーンの中央集権運用が本領を発揮すれば、ヴィーリオンの緩慢さでは防ぎ切れない。ゆえに両国は“勝つ”のではなく、“負けない状態”を維持する道を選んだ」 そして、杖が床を軽く叩く。 「ファーランド家の3段変化は、単独の英雄譚ではない。背後にはヴィーリオンという“人類最大の重力場”があり、周縁でのみ成し得た奇跡だ」 「大陸史とは、英雄の物語であると同時に――」 「巨大国家という化け物の呼吸音を聴き取る学問でもある」 学生たちは羽根ペンを置き、静かな余韻の中で地図を見つめ続けた。 ヴィーリオンの蒼、バーンの紅―― その境界線は今日も揺らぎ続けている。 ●魔導皇クラスト・フィフスター侯爵 637~  魔導師18/大魔導師5/宮廷魔導師5/賢者10 筋力9/敏捷力15/耐久力14/知力25/判断力20/魅力18/PB63 クラスト・フィフスターはかつてバーン王国の宮廷魔導師団において最高位である近衛魔導師の座を務め、国政・軍政の両面に深く関わった人物である。ファーランド家がまだ公爵家としてヴィーリオン王国の一部であった時代から彼は長く忠誠を誓い、当主としてアルヴァテイト侯爵家を率いていた。アルヴァテイト家は、ファーランド公爵家がその地を封土として授けられて以来の譜代中の譜代として知られ、クラスト自身もその伝統的忠勤の系譜を正しく体現する存在であった。  若き日にファクセリオン魔導学院で学んだ彼は、広大な学術体系と高度な技術を貪欲に吸収し、やがてファーランド公爵家の宮廷魔術師として仕えることになる。ここで彼は後の建国王リクター・ファーランドの学問の師となり、リクターが“全才の器”と称される所以を最も早く見抜き、その才能を導いた人物として知られる。クラストはリクターに心酔し、その叡智のすべてを惜しみなく伝授したと言われ、両者の関係は主従でありながら師弟としても深く結ばれていた。 建国戦争の折、クラストはバーン側魔導戦力の「設計者」として中心に立ち、戦略立案から実働部隊の調整に至るまで広範な役割を担った。魔導兵計画は彼の辣腕なくして成立し得なかったと後世の史家に断言されるほどで、戦争全体における魔導部門の中枢はまさに彼が握っていた。魔導師としての実力も当代随一とされ、直接戦闘能力も並の魔導師では到底比肩し得ない水準だったが、その本質は戦略家・政治家であり、知識と技術の総量が桁違いであるがゆえに、彼にとって“それなりにやる”という水準がすでに常人の限界を超えていた。 建国王リクターから寄せられた信頼は絶大で、クラストは名実ともに王の右腕として、軍政・内政の双方を動かす要石となった。後世のバーン帝国史には「クラストなくしてバーン建国は成立しなかった」と記されており、建国戴冠式の席でリクター自身が述べた「クラストがいなければ、私はそもそもこの計画を始めようとも思わなかった」という言葉は、史実として広く知られている。 しかし、両者の蜜月は唐突に終焉を迎える。後に“西覇戦争”と総称される西方諸国制圧計画において、クラストは「それではただの侵略者に堕するだけだ」として強く反発した。意見が退けられ、状況が改善しないと悟ると、彼は迷うことなく爵位を返上し、主君のもとを去ってファクセリオンへ向かった。この一件は当時のバーン内部に衝撃を与え、またクラストの名はそれ以前まで“叛逆の魔導侯”と糾弾されていたが、一転して正義と大義の義士へと変貌した。 同時に、右腕として国家の内外の戦略を共有していたであろうクラストと、建国王リクターの関係がここまで急激に破綻したという事実は、あまりに説明がつかないほど唐突であり、多くの史家・政治家が今なお憶測を続ける“歴史の謎”として扱われている。主従として、師弟として、深く結びついた2人が決裂した理由は、記録の上では完全には解明されていない。 ファクセリオンへと身を寄せたクラストは、到着して間もなく、まるでその存在を待ちわびていたかのように天秤の守護者へ迎え入れられた。外様としての経歴を抱えたままの彼が、この超国家級組織の中核に組み込まれるまでに要した時間は驚くほど短く、そして異例であった。さらにそのわずか2年後、クラストは天秤の守護者の総帥へと抜擢される。彼自身が当時すでに同組織随一の魔導師であり、知識・指導力・統率力すべてにおいて群を抜いていたことは誰の目にも明らかだったとはいえ、外様がわずか2年で最高位へ昇るというのは常識的には到底考えられない人事である。しかしこの決定は、天秤の守護者の内規や政治的力学では説明しきれない“決定的な要因”によって決定づけられていた。  それは――魔符《魔導師》による指名であった。 天秤の守護者における総帥任命は魔符《魔導師》の意思が絶対的な効力を持っており、それ即ち決定であった。当然、過去2代の総帥もまた魔符の直接の指名によって選ばれている。ゆえに、外様が短期間で総帥に就くという形であっても、天秤の守護者内部では「魔符の決定であるならば、それが最適解である」という理解が支配的となる。 魔符の声は、解放者エイファスの言葉そのものに等しい――そう信じられているからだ。解放戦争以来、人類社会における魔符の権威は絶対であり、その判断は人間の政治的判断を超越した“原初の意思の継承”と捉えられている。したがって、クラストの総帥任命に対して異を唱える者は皆無に近く、わずかに抱かれた不満や疑念も、魔符の名の前には黙殺されるよりほかなかった。何よりクラストには、実力面で誰ひとり言いがかりをつけられないほどの実績と才覚があった。必要なのは正当性だけであり、その大義名分として“魔符の勅命”ほど強力なものは存在しない。 “フィフスター”という称号は“守護”と“調和”を意味し、天秤の守護者における総帥のみが帯びる名誉である。単なる役職名ではなく、世界秩序の均衡を保つ存在であることを象徴する敬称であり、その権威は列強諸国の王家に比肩するとさえ評される。ゆえにこの称号を授かることは、一国家の実力者としてだけでなく、大陸に広がる勢力圏全体に対して発言力と統率力を示すものと解されてきた。特に歴代総帥たちは、それぞれが国家間の調停、竜勢力との折衝、人類圏の危機管理などに深く関与しており、その軌跡が“守護と調和”という言葉に相応しい重みを与えている。 このフィフスターは、各総帥がもつ本来の爵位とは明確に区別されており、世俗的な貴族制度とは別個に存在する“天秤の守護者独自の爵位体系”とも言うべき特殊な称号体系を構成している。たとえば過去には“フィフスター公爵”を名乗った総帥もおり、その爵位は出自や家格によって決まるものではなく、総帥としての任に応じた格式付けがなされてきた歴史がある。つまりフィフスターとは血統でも領地でもなく、“役割の重さ”そのものから派生する権威なのだ。 クラスト・フィフスターが現在なお侯爵位を帯びているのも、この爵位体系に沿う形で説明される。彼はもともとバーン王国においてアルヴァテイト侯爵家の当主であり、その爵位はファクセリオン側でも彼の身分として尊重され、引き継がれたものである。もっとも、ファクセリオンにおける侯爵位がクラストの最終的な格式を示すわけではない。在任期間の中で権威と責任が段階的に積み重なり、やがて“フィフスター公爵”へと昇格するのが歴代総帥たちの歩んできた典型的な軌跡なのだから。 クラストという男は、宮廷魔導師時代から老獪な人物として名を知られていた。目的の達成に際しては決して善人であることに拘泥せず、必要とあらば道義の境界すら踏み越える。それでもなお、天秤の守護者となった今の彼には、単なる策謀家とは明確に異なる評価が与えられている。それは――「人の世を守る」という一点において、誰よりも揺るぎない意志を持つ男であるという認識である。 彼は正義よりも秩序を、善悪よりも存続を優先し、冷酷と見える選択すら最終的には人類社会を勝利へと導くために行う。それは天秤の守護者という立場に就いて以降、彼の判断の一貫性として周囲によりはっきりと理解されるようになった。 守護者就任後のクラストは、これまで同様に前線で魔力を振るう戦闘者ではなく、徹頭徹尾、戦略と知識の提供者として組織に寄与している。天秤の守護者という組織はすでに長い歴史を持ち、その運営体系や戦力運用は確立していたが、クラストがもたらしたのはそこに“さらなる深度”を与える知識と経験だった。バーン宮廷魔導師として培った魔導理論、政治的判断力、戦略眼、さらには個々が直面しうる内面的な壁への対処法まで、彼が授ける教えは極めて広範かつ実践的であり、すでに成熟していた天秤の守護者の総合力を一段引き上げたと評されている。 圧倒的な戦闘能力を備えるがゆえに、人格面で常に危険視され続けてきた瑠璃の採用において、最終的な“許可”を下したのもクラストである。瑠璃の協調性の欠如や制御困難な気質は、従来であれば採用を即座に退けられてしかるべき重大な問題点だった。実際、先代総帥のような慎重な人物であったなら、瑠璃を迎え入れることは決してなかったと多くの者が語る。 しかしクラストは、その危険性を真正面から理解したうえで、なお「問題無し」と断じた。彼の眼には、瑠璃の扱いづらさすら制御可能であり、それを補って余りある戦力的価値があったのである。クラストの保証がなければ到底実現しえなかった決定であり、この一件は彼の老獪さと胆力、そして守護者としての覚悟を象徴する事例とされている。 クラストがこうした判断を下せる背景には、彼が単なる戦略家でも魔導の探究者でもなく、“後進を鍛え上げる達人”でもあるという事実がある。バーン王国の建国王となったリクター・ファーランドが、その若き日にすでに非凡を示していたとはいえ、公爵家の嫡男という立場ゆえに周囲が慎重に扱い、誰も本気で鍛えきれなかった才覚を、クラストだけは容赦なく磨き上げた。政治・戦略・魔導理論に至るまで、王の器が備えるべき要素を徹底的に叩き込み、その潜在を最大限に引き出したのは紛れもなくクラストであった。この前歴は、彼が人材の力量・危険性・将来性を長期的視野で見抜き、必要とあらば矯め、飛躍の段階を整えることのできる稀有な人物であることを証明している。ゆえに天秤の守護者内部でも、クラストが誰かを「扱える」と判断した場合、それは単なる楽観ではなく、歴史が裏付ける“本物の保証”として受け止められていた。 また、クラストが総帥となってから近年、彼の名に新たな異名が付随するようになったことも特筆される。バーン王国が帝国へと転じ、2代国王フレデリック・ファーランドが初代皇帝を名乗ったその時期と歩調を合わせるようにして、人々は彼を“魔導王”の格すら超える魔導師――《魔導皇》と呼ぶようになったのである。この呼称には、単に魔導実力への畏敬だけでなく、天秤の守護者総帥としての統率力、国家級の戦略に関わる判断力、そして魔符《魔導師》に選ばれた者としての特別な権威が複合的に織り込まれている。バーンが“皇帝”を戴くのであれば、ファクセリオンは“皇”を名乗るに値する魔導師を擁している――そんな半ば冗談めいた言い回しすら語られ、次第にそれが揶揄でも誇張でもないと信じられるほどに、クラストの存在は国内外で重みを持つようになっていった。 クラスト・フィフスターが天秤の守護者総帥となってから、まだ僅かな時しか経っていない。しかし彼が大陸規模の情勢に与えた影響は、すでに一個人の枠を明らかに逸脱している。バーン建国を陰で支え、後にはその王国さえ揺るがして去り、今はファクセリオンの要たる立場にある――その歩みは常に時代の転換点と重なり続けてきた。ゆえに人々は恐れと期待を込めて語る。クラストの物語は、まだ序章に過ぎないのではないか。彼がこの先に何を選び、どのような未来を引き寄せるのか――それこそが、これからの人類史を左右する最大の未知なのだ、と。 ● 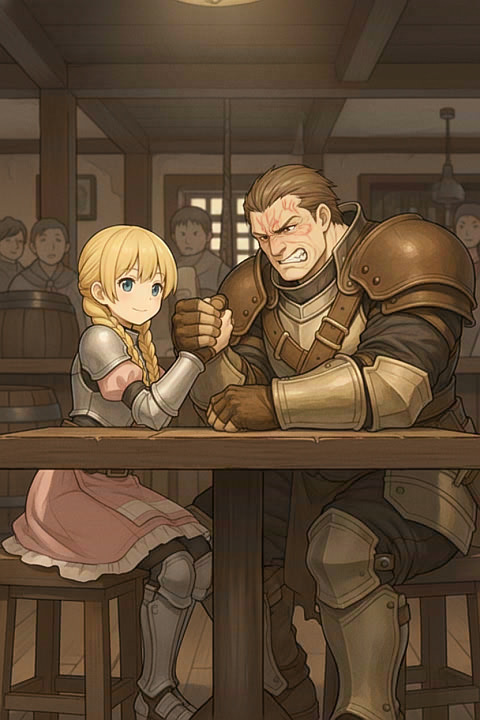 魔導脈とは、この世界に生きるすべての生命体に共通して存在する、魔力を伝導する内的脈系の総称である。動脈・静脈・神経・経絡の概念を併せ持つ独自の生体構造であり、生物が魔力を扱う際の“通路”として作用すると同時に、筋肉と魔力の連動、生命維持、呪文制御といった多様な機能を担っている。形態は肉眼では確認できない微細構造の網状組織で、魔導視や呪術的診断では淡い光をもって走行する脈として知覚される。 魔導脈は広義には一本の体系だが、機能別に三つの系統へと分化している。身体強化を担う霊筋脈、呪文構築や精密操作に関わる精霊脈、生命維持を支える生命脈である。これらは互いに独立した経路を持ち、用途によって発達箇所が異なる。腹筋を鍛えても指先の器用さが向上しないように、魔力もまた“使われた部位だけが成長する”ため、肉体的強さと呪文の巧緻さは必ずしも比例しない。 筋力とは筋肉量の物理的出力と霊筋脈を通じた魔力的出力の総和で決まる。このため、小柄な個体でも霊筋脈の効率が極端に高ければ怪力となり、逆に魔力比率の低い巨漢でも筋肉量そのものが並外れていれば同等の怪力となる。これは種族や体格を問わず観察される現象であり、フロウ族の姫騎士や細身の青年が大剣を軽々と振るい、巨人を一刀両断するような光景も決して誇張ではなく、魔導脈の働きによって説明される事例のひとつとされる。もっとも、総合出力が同じであっても体格と質量の差は容易には覆らず、組み合いや押し合い、体勢崩しといった“質量がものを言う”場面では巨漢が優位に立ち、跳躍・瞬発・器用さといった軽量型の得意分野では小柄な魔力型が有利となるなど、戦闘様式によって強みは大きく変わる。 魔導脈の種族差は大きく、とりわけキゲイン族はその典型である。男性キゲインは骨格と筋肉量が非常に発達しており、生得的に霊筋脈が太く、筋繊維と密接に結びついている。肉体鍛錬による筋肉増加が霊筋脈の増幅を直接促し、“筋肉と魔導脈の相互成長”が最も明瞭に現れる種族である。そのため絶対的質量と筋力を兼ね備え、取っ組み合い、押し相撲、重量武器の扱いなど“体格を活かす戦闘”では他の追随を許さない。 一方で女性キゲインは体格こそ男性より小柄であるが、霊筋脈の“効率”が著しく高く、筋肉量に対する魔力寄与が大きい。細身の体格のまま驚異的な怪力と体幹安定を示す個体が珍しくなく、鍛冶職や戦士階級では“ロリ体型の怪力”として知られる。ただし女性の霊筋脈は男性のような太く短い幹線型ではなく、細く密度の高い網状構造を取る傾向があり、この構造が瞬発力や体幹制御の精度を高める一方、重量を用いた押圧や組み合いでは絶対的質量差や接触面積の不利を埋めきれない。そのため、同等の霊筋脈を持つ者同士であっても、押し合い・体格戦では男性キゲインが優位となる場面が多い。 呪文制御に関してはキゲイン男女に大きな差はなく、女性キゲインが怪力でありながら呪文を扱えないわけでもなければ、男性キゲインが筋肉特化のため術に疎いという単純な図式にもならない。精霊脈は霊筋脈とはまったく別の経路を走るため、身体強化に魔力配分が偏りがちな戦士型が呪文を苦手とする場合、それは魔力量の不足ではなく“魔導脈の配分特性”に起因する現象と考えられている。 魔導脈は鍛錬・環境・精神状態によって強化される。肉体訓練は霊筋脈を、瞑想や呪文訓練は精霊脈を、健康的生活や生命魔導は生命脈をそれぞれ成長させる。ただし急激な強化や過負荷は魔導脈炎・魔導脈閉塞を招き、呪文暴発・筋力低下・生命力減退の原因となるため、多くの武人や魔術師は魔導医術による脈調整を習慣としている。 以上のように魔導脈は、怪力・呪文・耐久力・種族差・性差といったあらゆる身体能力の根幹を支える生体魔導構造であり、世界における“細身の剣士が巨人を両断する理由”から“少女体型の怪力鍛冶師”まで、幅広い現象の背後に存在する普遍的法則とされている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■プレゼントありがとうございます( ・`ω・´) すでにある棚と入れ替わった結果こうなった。  そしてモニター上の棚はこんな感じに。良い眺めだな!!!  近所のまいばすけっとで突然目に飛び込んできて、「え、こんな場所でこんなエッチな商品が!?」と狼狽するも吟味したところ、一番好みっぽいこのキャラのだけ無くて、歯ぎしりしながら帰宅するも、後日行ったら補充されてたので確保した。キャラの名前も知らんくせに! 相変わらずこのゲームは見た目が好みのキャラが多過ぎるぜ!!! でも「これで目が開いてたら最高なのにな」とか思ってるんで、原作ファンの人から「それは目を瞑ってるのがいいんだよ! 意味があるんだよ! 台無しだよ!」と怒られるんだろうな!! セブンセンシズ!!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■アルミホイルだなんだ言ってきた人への私信 界隈の知識がろくにない人間の「それゆえの俄な発言」に対して上から目線で思いっきり小馬鹿にした態度をとるの、なにがそこまで馬鹿にされなきゃいかんのだっていう「不愉快さだけ」が残るから、もしそれ以外の反応を引き出したかったんだとしたらマジでやめとけ。そうじゃなくて単に喧嘩売りたいだけだったんなら了解する。好きにしてよし。でも単なるノリでやっちゃっただけだと俺は信じている。 追記 あやまってくれたのですべてよし!! もう俺はなんも気にしてないんで、これからもよろしくな!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■バンドリちゃん ここをキャンプ地とする!!! ギャグストーリーなのは間違いないのだが、チュチュ様はマジでこの「人の期待は絶対に裏切らない」っていうプライドが本当に魅力的なんだよな。 理由はどうあれ受けて立たねばならないところが実に素敵な話だ(笑)  Vtuberで、カードゲームの配信中に舌打ちが多過ぎて、あまりに不快で耐えきれずに観るの辞めた記憶が蘇る(笑) 日本人と外国人では舌打ちのニュアンスが違う、とはなんか最近ツイッターで見た気がするけど、よく外国人勢と統率者戦してた経験としてはそんな舌打ちされまくるイメージ無いんだよな。ファックやシットかはカジュアルに出てくるが! それはさておき、無言の舌打ちはマジでショックでかいからそりゃ泣いちゃうわ!!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■FGO そりゃさぁ。最強の2騎でかかってこいやとか言われたらさ。これしかないわけよ。 キャストリアと村正とかもエモかろうとは思うが! 俺の最強は間違いなくこれだ!!! てか歴史的にもイスカンダルが外征して諸葛亮が内政するの強過ぎて熱いな。  俺のボックスガチャ、今回はこのへんにしといてやる!! 他にやることが多い!!! てか交換素材が在庫ダブついてるやつばっかだから、レベル120用の種火くらいしか喫緊の必要物がないんだよな。 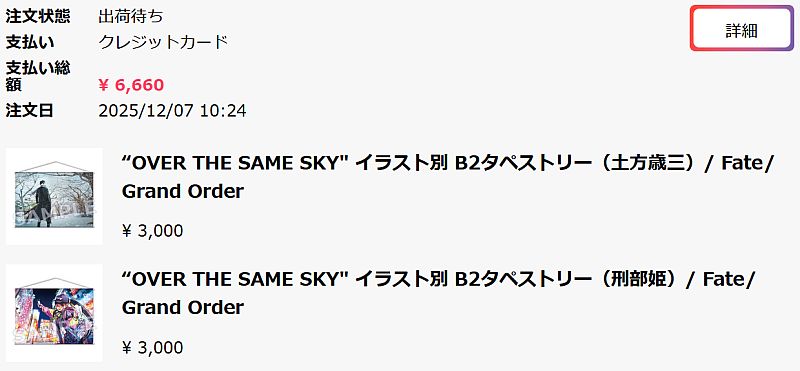 タペストリー出るのはわかってたから新聞は取り寄せなかったってわけよ!!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■前回の地図の全景はこうなってますよ いわゆる「世界の中で認識されている大雑把な地図」ので、実際の地形と完全に一致しているわけではない。 ●魔導王国ファクセリオン  ファクセリオン王国は、バーン西部領の西端に隣接する魔導都市国家であり、その姿は大陸に数ある諸国の中でも異質といえる。建国者は“解放の英雄達”の一柱にして、エイファスから最も深く魔導技術を受け継いだ大賢者ジェイシント。彼が物理魔導の研究と、それに付随する膨大な学術施設を収めるために築いた都市を母体とし、後に彼の没後、2人の高弟へ都市元首の地位と“天秤の守護者”総帥の地位が継承されたことで、王家すら誕生した国家である。 その国家構造は、かつて星渡りの民が現れる以前の紀元前都市国家に近く、封土を持たない支配階級による中央集権社会という点で、異様なほどに旧態依然としている。しかし同時に、ジェイシントが集めた魔導師と研究者の層の厚さが社会全体を支え続けており、バーン帝国誕生以前は「世界で最も繁栄している中央集権国家」と称されたのも決して誇張ではない。 この国家の存在意義を語る上で、“天秤の守護者”を欠かすことはできない。これはファクセリオンの軍事組織であり、同時に「エイファスの遺産たる危険魔導兵器を管理するために結成された最精鋭の英雄集団」という二重の意味を持つ固有名詞である。建国時点でファクセリオンには大量の魔導具が持ち込まれ、中には“竜を殺せればいい”という一点のために安全性が完全に無視された危険な魔導兵器も多く含まれていた。つまり「持ち込まれなかった大多数」はそのまま死蔵・遺棄され、世界各地に潜在的な脅威として散在していた。その管理と収集を担うのが天秤の守護者である。 ファクセリオンにはいわゆる「大規模な軍勢」というものは存在しない。しかし、彼ら1隊は他国の1軍に匹敵する戦闘力を持つ「一騎当千」の精鋭ゆえに、それで十分なのだ。 この国には徴兵制が存在するものの、多くの成人は適性試験でふるい落とされる。試験を通過した者も、殆どが天秤の守護者候補にすら届かない。だがその訓練から“落ちこぼれ”た者ですら列強他国の正規兵の平均練度を凌駕しており、治安維持要員とはいえ畏怖される存在である。むしろ天秤の守護者の偉大さを最大の誇りとする彼らにしてみれば、その異常なまでの狭き門ぶりこそが"かく在るべし"となり、その頂に挑戦した事実すら家族の誇りとなる。侮られることはほぼない。  ファクセリオンは領地をほとんど持たない。周囲に広範囲に及ぶ領土を持たず、王都そのものが国家機能の大半を占めているにもかかわらず、世界各地に飛び地とも呼ぶべき領域や採掘権を多数保持しており、それが国家としての富と影響力の中核を成している。飛び地の多くは、天秤の守護者が竜の支配する地域を制圧して得たものであり、資源的価値が無ければそのまま周辺諸侯へ譲渡するが、価値があれば領有し、代わりに近隣諸侯へ十分な利益供与を与えて関係の軋轢を防ぐ。この「利益供与による納得感」の演出は、ファクセリオンが諸国と安定的な関係を構築するための重要な技術であり、彼らは外交においても“技術国家”としての本領を発揮してきた。 鉱山の領有よりも採掘権を握ることが重要視されているのも特徴的である。ある日突然、領内に貴重な資源が眠っていることが判明したとしても、それを採掘・精製できる技術がなければ意味がない。そしてそれらは一朝一夕で手に入るものでもない。ファクセリオンはその圧倒的な魔導技術と資本力を背景に、各地で鉱山開発を推し進め、地方領主であれば20年かかる採掘量を僅か3年で叩き出す例すらある。それゆえに、多くの諸侯が「自領の開発促進」を期待してファクセリオン資本を誘致し、また採掘権を委託する方が安全かつ確実であると認識している。 とりわけ鉱山を巡る領土紛争において、諸侯がファクセリオンへ採掘権を委ねるのは、もはや常識と言ってよい手堅い選択肢となっている。というのも、前述した通りファクセリオンが保持する採掘・精製技術は他国を圧倒しており、その上、保守についても天秤の守護者の武威を背景に極めて厳格に運用されるため、「ファクセリオンが委任されている鉱山」であるという一点だけで、周辺諸侯が武力で奪いに来る危険性がほぼ消滅する。いわば“領有しているだけでは守れない資源”を、“委任さえすれば確実に守れる資源”へ変質させる防衛手段であり、武力を用いて利権を巡る消耗戦を繰り返すよりも、ファクセリオンに採掘を委託し、その収益の何割かを確実に得るほうが、長期的に見ても遥かに安定する。特に自前の鉱夫や設備を十分に確保できない領主にとっては益々合理的であり、ファクセリオンに任せること自体が“領地を戦乱から護る最も安価で確実な安全保障”と見なされているのである。 もちろんこういった戦略的な資源の取扱はその土地に住む者たちの様々な思惑が絡み合う。ましてや封建貴族という「土地に魂を縛られた階級」とまで呼ばれることすらある彼らにとって、それを安易に他者に委ねることは強い抵抗が生まれ、「楽に儲かる」からと飛びつけるかは別問題だ。「ファクセリオンのおこぼれで満足しろというのか」といった考えは強い勢力を持つし、純然たる事実として自前で採掘できればそれが一番「美味しい」ことも間違いないので、最終的にこの手段を選択するケースは全体の中で然程多いわけではない。 しかしながら、それでも世界各地の採掘施設から生産される物資は大陸全土で取引され、その加工技術の高さは贋作が生まれるほどに絶大な信用を持つ。 このような巨額の富によって支えられているのが、都市全体を福利厚生施設のように運営するという独特の国家観である。住民の生活は輸入品と魔導技術で支えられ、街には純粋な“民間の商店”という概念がほぼ存在しない。都市内の建物は都市全体の機能の歯車として計画的に配置され、景観は冷徹なまでに統一されている。通りは整然として美しく、衛生状態は世界一と称えられるが、その反面、商区ですら活気が薄く、雑然とした生活感や人間臭さは希薄である。 魔導都市としてのファクセリオンは、魔導具・呪甲装兵・高位魔導素材といった専門的な商品を扱う商人の往来こそ大陸最大規模と評されるほど活発であり、都市の出入り口では常に魔導関係の積荷を抱えた商隊が行き交っている。しかしその一方で、都市経済は通常の商業活動によって利益を追求する必要がまったくないという、他国とは根本から異なる性質を持つ。そのため「観光」を目的とした外来者の流入は制度的に制限されており、街を歩けば世界各地から来た高度な技術商人や魔導研究者こそ見かけるものの、珍しさを求めて押し寄せる旅人の姿はほとんどない。結果として、都市が過密になるような雑踏や混乱はまず起こらず、商業地区ですら冷静な空気を保ち、都市全体が常に“必要な数の人間だけが管理された状態で存在している”という、奇妙な静穏を維持しているのである。 さらに街の空気を特徴づけるのが、外部からの敵対行動に対する抑止力として住民全員が存在と行動を管理されている社会構造だ。違法行為や迷惑行為は徹底して取り締まられ、罰は迅速かつ明確であり、住民たちは日常的に「己が見られている」という感覚の中で暮らしている。 教育制度も例外ではなく、魔導学院以外にも「一般教養を身につけるためだけの学校」という非常に稀有な教育機関が魔導師や軍人を志さない者の受け皿となり、これが世界唯一の"義務教育"として機能、世界最高の識字率を実現する。このようにして、いわゆる“教養のない者”は制度的に育たず、招かざる来訪者が都市内部に居座る余地も少ないため、街中では喧噪や乱行が極めて起きにくい。飲食街ですら喧嘩ひとつ大きくならず、騒音ですら抑制された“奇妙な静けさ”がファクセリオンという都市の空気を象徴している。 もっとも、ファクセリオンの住民が皆、監視の網に怯えて生気の乏しい暮らしているわけではない。都市に商業的な猥雑さや喧噪こそ乏しいが、それは犯罪やトラブルが極端に少ない社会構造の副産物であり、善良な市民にとってこの上なく過ごしやすい環境を意味している。教育水準が高く、生活インフラは驚くほど整い、衛生環境も世界最高水準で、夜道をひとり歩こうがまず危険に遭わない。混雑も騒乱も少なく、過度な競争もないため、日々の暮らしは落ち着き払っており、静かで平和だ。 この“静謐な平穏”は、裁獄神を奉じる神聖王国アルスファリウナのような、恐怖による沈黙とは決して同質ではない。アルスファリウナが「神の裁きの恐怖ゆえに誰も動けない」ことで治安を維持しているのに対し、ファクセリオンでは「住民の大半が高い教養と遵法意識を持ち、社会構造そのものが犯罪を起こしにくい」ために安定が保たれている。市民の表情は険しくないし、息苦しい緊張感が張りつめているわけでもない。むしろ、魔導によって生活が過不足なく満たされ、煩わしい脅威も少ないがゆえに、穏やかな安堵と静かな自尊が漂う都市である。 もっとも、その静謐は健全さだけで成り立つものではない。「天秤の守護者にふるい落とされた者たち」は、周囲からの侮蔑こそ受けないものの、自尊心の破砕という形で精神的な負担を抱えやすく、内部には表に出ない軋みも存在する。ファクセリオンの住民は総じて理性的で優秀だとされるが、それは“もとから優秀であった”というよりも、優秀である者だけが最後まで居残り、他は制度の外側に振り落とされていく仕組みゆえの結果である。 人類の魔導文明は長らくファクセリオンからの技術伝播に依存してきたと評され。実際には各国も独自の進歩を行っているため、すべてがそうというわけではないのだが、そういった印象を持たれてしまうことを否定できない部分はあった。特に呪甲装兵の建造技術はファクセリオンの独占領域であった。大型魔導具の製造や管理において他の追随を許さず、特に呪甲装兵はその秘匿性と技術水準から“ファクセリオンの切り札”とされていた。しかし、この独占体制は各国の反発を強く招き、結果としておよそ100年前、技術開放が段階的に行われることとなった。これはファクセリオンにとって確かにアドバンテージの喪失ではあったが、人類全体の対竜戦力を底上げし、同時に外交摩擦の解消にもつながったため、負担と利益を天秤にかければ妥当な判断だったと評価されている。 一方で文化的な独自性は低く、多くをヴィーリオンからの伝播に頼っている。魔導以外の分野は徹底して「必要最小限」の思想のもとに整理されており、街は整然としているが、人の欲望の発露による活気は控えめである。しかしそれは、すべてが「竜と戦う都市」としての本質に基づく構造的必然であり、魔導技術に全てを偏らせた国家の宿命でもあった。 この街では、秩序は常に美徳であり、混沌は常に排除される。 そして、その秩序は魔導という力によって実現されている。 ファクセリオンとは、人類が竜と戦うために作り上げた、世界最大の“魔導の砦”に他ならない。 ●マスターズ・コメント なんかもう書くことが多過ぎて全然書ききれてない。 大変なんだよこーいった「作中の認識の雰囲気」で書くの!  もっと雑に「叡智神学会の本拠地もあって、眼鏡っ娘がたくさんいるよ」とか書くなら楽勝なのに!! それはさておき、一歩間違えれば「世界を管理する悪の帝国」みたいなことにもなりかねない技術独占をしている為、敬意と同時に敵意も集めがちな「世界の警察」ことファクセリオンさんです。 ヴィーリオンが人類の保護者として君臨しているなら、ファクセリオンは監督者なんで、そりゃ風当たりも強い。「危ないからそのアーティファクト僕が管理しとくね」で、その危ないアーティファクトをしこたま溜め込んでるわけで、一国が核兵器独占しているよなもん。 ……とかを、世界設定に即した文章で書くの面倒くさいんだよ!!! とにかく、彼らの「解放者エイファス様の腹心なジェイシント様の後裔たる我らがそれを私利私欲で使うわけないでしょ。信用してよ。逆らうならどうなっても知らないよ」という言い分に渋々従わざるを得なかった人類諸国の不満は相当なものであり、「国~の怒りは爆発寸前~」なところへのガス抜きで呪甲装兵技術開放したわけだな。 ●天秤の守護者 天秤の守護者は、“創造師”ジェイシントが人類社会の均衡を保つために創設した武の最高機関である。人の手に余る魔導遺産の管理と、竜との永続的な戦いという二つの大任を背負い、世界秩序の土台として長く機能してきた。特に戦略魔導具の確保はその本懐であり、発掘、占有、封印いずれの局面においても、天秤の守護者は常に前面に立つ。扱う物品の多くは、一国の軍略さえ変質させ得る規模の影響力を持つため、彼らの慎重な管理が不可欠とされる。 組織はファクセリオン王家と対等の権威を持ち、王家が政の全権を握る一方で、天秤の守護者は武の全てを担う。もっとも、この二つの権威は決して互いを侵食しない。天秤の守護者はジェイシントが残した規範に従い、政治への過剰な介入を自ら禁じており、王政と武政が衝突した前例はない。王家は対外的な交渉や調整を一手に引き受け、天秤の守護者はあくまで“武をもって世界秩序を守る者”として振る舞う。この自制によって、両者は独立性を保ちながらも一つの国家を支えている。 他方で、戦略魔導具の扱いに関する判断においては、天秤の守護者の意志が最優先される。魔導遺産の放置が均衡を壊すと見なされれば、各国の政治的事情に左右されることなく収集に動く。その際には十分な対価を提示することを原則とするが、それで事が収まらない場合は、組織本来の武威が最終的な担保となる。国家レベルではこの姿勢を警戒されることもあるが、同時に“彼らが存在するからこそ大陸が保たれている”という認識も揺らぐことはない。 人材の選抜は極めて厳格で、強い力量と“竜と戦う意思”が加入の絶対条件となる。出自は問われず、人外や他国の罪人であろうと、目的と規律に従えるのであれば候補となる。一方で、力を私欲に使う者や、破滅的な思想を抱く者は初期段階で排除される。加入後も規律は厳しく、背いた場合は即座に同格以上の戦力が投入されるため、無法が通る余地はない。結果として選ばれる者は、人格的にも高潔である場合が多い。 内部では青銅兵を最下位として、一つ分銅、二つ分銅、三つ分銅が続き、その上に天秤の守護者本人が位置する。青銅兵の時点で独立した任務に耐え得る力量を持ち、三つ分銅は実質的な士官として直属部隊を束ねる。多くの天秤の守護者は複数の三つ分銅を配下に持ち、予算と戦力規模は諸侯の軍勢に匹敵することも珍しくない。ただし配下の規模は個人の裁量に委ねられており、意図的に小規模で在り続ける者もいる。 天秤の守護者の戦力は、単独で成竜を討つ者が存在するほど突出しており、未熟な者だけで組んでも老竜を仕留めるのに十分とされる。ただし優れたのは武勇だけではない。参謀、研究者、鑑定を専門とする魔導師など、多様な技能を持つ者が所属し、戦略魔導具の管理や運用において不可欠な知的基盤を形作っている。国家からすれば、天秤の守護者という肩書自体が巨大な権威であり、宮廷魔導師や大司教などの要職が即座に用意されるほどだ。 また、天秤の守護者は世界全土で有能な人材を捜索し、必要とあらば司法取引すら用いて取り込む。英雄譚の多さから若者の憧れを集めるが、その実態は過酷な職務そのものであり、生半可な覚悟では到底務まらない。なお、直轄の特務部門として、諜報を担う者や遺産回収を専門とする者、あるいは直属戦力を編成する者などが存在するが、それらは天秤の守護者の本質から派生した機能にすぎない。 天秤の守護者とは、政治から距離を置きつつも、武の領域においては絶対的責務を負う存在である。危険遺産の管理と竜との戦いという二つの極致を担い、どちらにおいても決定的な役割を果たす。彼らは国家の力を超えた“秩序そのものの守り手”としてあり続け、人類世界の均衡を支える最後の柱となっている。 ●主な天秤の守護者(更新が追いついてないだけで設定上は他にもいます)
●煌愛神  愛と美を司る女神。愛染神と煌閃神は妹。 彼女の慈愛は、恋愛に限らず、隣人愛、家族愛、友情といった幅広い形での愛を包み込む。恋に悩む者には勇気を与え、夫婦の間に溝が生じたならば和解のきっかけをもたらし、親が子を愛し、子が親を敬うことを祝福する。そのため、煌愛神への信仰は、恋人たちだけでなく、家族や友人との関係を大切にする者たちの間でも広く根付いている。彼女の名は出産や子宝祈願の際にも唱えられ、また、仲直りや再会を願う者たちが頼る神としても知られる。 その母性に溢れた性質から大いなる慈愛の女神と讃えられるが、彼女のアヴァターは少女の姿を取る神アイドルである。幼さの中に気高さと純粋さを宿し、愛の輝きを広める存在として信仰を集める。彼女を象った彫像や絵画は、美と純潔の象徴として装飾され、多くの神殿では神像が恋人たちの誓いの場として祀られている。 伝説によれば、恋愛の機神には煌愛神から下賜されたものが組み込まれていると言われている。それがどう戦闘力に寄与しているのかは謎。 彼女の教えの根幹には「愛の輝きは世界を照らす」という信念がある。愛することは決して弱さではなく、むしろ人を強くし、絆を深める力となる。恋愛においても、友情においても、家族の絆においても、大切なのは互いを想い合い、支え合うことであると説く。そのため、煌愛神の聖職者たちは、恋愛相談だけでなく夫婦や家族間の仲裁を行うこともあり、社会において重要な役割を担っている。 彼女を怒らせるのは「愛を弄ぶこと」「約束を破ること」「誠実でない愛を貫こうとすること」である。誠実な愛を尊ぶ彼女にとって、偽りの愛や欺瞞は最も忌むべきものであり、信仰の深い者ほどそのような行為に手を染めることは許されないとされる。特に純粋な愛を踏みにじる者は、彼女の加護を失い、愛する者を失うという罰を受けると言われている。別に離婚禁止とかはしてないが、浮気とかDVみたいにストレートに離婚の原因作った側には天罰覿面である。 信者には恋人たちをはじめ、結婚を望む者、家族の絆を大切にする者、そして芸術や美を愛する者たちが多い。煌愛神の祝祭では、花々で飾られた広場で、愛を誓う儀式が執り行われ、恋人たちは神の名のもとに指輪や誓いの言葉を交わす。街角では音楽や舞踊が奏でられ、甘い香りのする菓子が振る舞われる。愛を讃えることは、彼女にとって最大の崇敬の形であり、その祝祭は一年で最も華やかなものの一つとなる。 信仰の広がりは大きく、煌愛神の神殿は都市部を中心に数多く存在する。恋人たちが訪れる場所であり、夫婦が絆を深める場所であり、孤独な者が心の支えを求める場所でもある。彼女の名が語られる限り、愛の輝きは世界のどこかで灯り続けるだろう。  世間一般的に「愛染神とは愛の女神姉妹」となっているが、権能としての愛を司るのは煌愛神だけである。 顔を合わせようものなら光と闇の果てしないバトルが勃発してウェイクアップ・ザ・ヒーローの号令が下されるかと思いきや、基本的には「無駄とわかっててもやらずにはいられないお小言」に留まっている。  煌閃神は「姉上、こんなビッチは今すぐたたっ斬りましょう」と鼻息荒いが。 属性:混沌にして善 領域:レイピア 信者:恋人たち、夫婦、芸術家、仲裁者、祝祭の主催者 神格武器:美、契約、愛、家族 信者人口:★★★★☆ 信仰権威:★★★☆☆ ●麗騎士 愛ある限り戦い、命が燃え尽きるまで美を体現する正義の剣士。 煌愛神に仕える愛の戦士たちの中でも特に高い美意識を持ち、愛情に満ち溢れ、それに負けない剣術を駆使する華麗な勇者だけが麗騎士の称号を得られるのだ。 勇壮にして華麗、凛々しくも優美。人々が思い描く輝ける勇者の姿がそこにある。 元来聖騎士やそれに類する者たちは武勇のみならず高いカリスマ性を備えているのが大前提ではあるのだが、麗騎士のそれは頭抜けてると言っても過言ではないだろう。 そして美しいバラには棘がある。煌愛神は実を伴わない者を認めない。戦いの中で常に美を意識する余裕を忘れないほどの手練れが麗騎士なのだ。見掛け倒しと侮った者には例外無くその代償を払うことになる。 ●ゲームデータ解説 英語で書いたらElegknight! 魅力度が高ければ高いほど強いのは聖職者系のお約束なのだが、ひときわ魅力度による補正が高まるクラス。必然的に魅力度の高いキャラとしての立ち居振る舞いを強く求められる為、ロールプレイの難易度がとても高そう。 が、その苦労に見合ってとても強い聖騎士系上級職であり、ノリノリでプレイできるもんならめちゃくちゃ楽しそう。てか俺がプレイしたいレベル。NPCで出すと超楽しいだろうなぁ。  ナルシスト気味なんだけど決して軸はブレなくて、美意識に沿った価値を認めた相手には敬意を払うことを惜しまない系キャラをやりたい人にオススメ。 価値基準が「魂(生き様)が美しいかどうか」なキャラならば、それはもう煌愛神的なのだ。  無論、ナルシー系とかそんな尖らなくてもこういった価値観を持つことだって煌愛神的である。 ●必要条件 基本攻撃ボーナス:+7 技能:〈交渉〉5ランク、〈知識:宗教〉5ランク、〈任意の芸術/芸能〉5ランク 特技:軍用武器と重装鎧への《習熟》、《騎乗戦闘》、《攻防一体》、《二刀流》 神格:煌愛神への信仰心レベル5。 ●クラス基本データ ヒットダイス:D10 基本攻撃ボーナス:良好 セーヴ:頑健、反応 クラス技能 :〈威圧〉〈軽業〉〈鑑定〉〈騎乗〉〈芸能〉〈交渉〉〈視認〉〈呪文学〉〈職能〉〈真意看破〉〈製作〉〈精神集中〉〈知識:王族・貴族〉〈知識:宗教〉〈知識:歴史〉〈治療〉〈動物使い〉〈はったり〉〈変装〉 技能ポイント:6+ ●クラスの特徴 レベル 特殊 1 煌愛神の祝福、細剣鴻毛が如し、ボーナス特技 2 優雅なる太刀筋 3 巧みな守り+1、ディフレクト 4 期待は誇り1回/日、ボーナス特技 5 俊足の鎧武者 6 巧みな守り+2 7 ディフレクト強化、ボーナス特技 8 期待は誇り2回/日、煌愛神の怒り 9 高位二刀流、巧みな守り+3 10 我が美技に酔え1回/日、上級ディフレクト、ボーナス特技 煌愛神の祝福(超常):聖騎士の癒しの手と同等。聖騎士のレベルと累積する。アンデッド・クリーチャーにダメージを与えるためにも使用できる。 ボーナス特技:《騎乗戦闘》《攻防一体》《二刀流》を前提条件とする特技を修得する。 細剣鴻毛が如し(変則):[常時]レイピアを軽い武器として扱うことが出来る。 優雅なる太刀筋(変則):[誘発]シミター、レイピア、ロングソードを使用時、追加ダメージに【魅力】修正値も加算する。 期待は誇り(変則):[誘発]守るべき第三者に見られている場合、AP使用時のダイスロールに【魅力】修正値を足すことが出来る。 高位二刀流(変則):[常時]利き手でない手に持った武器で-15のペナルティを受けて4回目の攻撃を行える。 我が美技に酔え(変則):[フリー]【魅力】修正値ラウンドの間、攻撃、ダメージ、戦技判定、技能判定、セーヴロールに【魅力】修正値に等しい清浄ボーナスを足すことが出来る。 ●  神寵者8/剣士6/麗騎士10 筋力14/敏捷力19/耐久力12/知力16/判断力13/魅力24/PB56 《風煌明美》の二つ名を持つミオは、ティスリの父とフロウの母の間に黄金の聖気をまとって生まれ落ちた、生来の神寵者である。煌愛神そのものの祝福が宿るかのような輝きをその身に抱き、赤子の時点で既に人々を息を呑ませるほど見目麗しい存在として世に現れた。 物心つく頃には「りゅうとたたかう」「たみをまもる」を口癖とし、幼心にして既にその在り方は定まっていたかのようで、まるで愛と美の女神が“この子の生き方はこうである”と告げているようであった。  ミオが生まれたブルーメンフェルト伯爵家は、紀元の始まりとともにヴィーリオンへ合流したティスリの族長を祖とし、その血脈は解放歴の最古級の街ティスリに連なる名家として知られている。つまりミオは、ティスリの歴史と誇りを体現する家柄の出であり、フロウ社会においても特別な象徴性を帯びる存在であった。そのような高い由緒を持つ家は、当然ながら後継者の教育に並々ならぬ情熱と投資を注ぐ。父であるブルーメンフェルト伯爵は、ミオの天賦を極限まで磨き上げるべく名の知れた剣豪たちを次々と招聘した。その中には、後に天秤の守護者として名を馳せるシェナン・アルザートの姿もあった。ミオはシェナンを最も尊敬すべき師として仰いでおり、その敬意はいまなお変わっていない。  しかし、天秤の守護者となるということは、ブルーメンフェルトの民を直接守ることを放棄するに等しい選択でもあった。長らくミオはその決断に悩み続けたが、伯爵領はヴィーリオンの中心部に近く、歴史的にも長い安泰を享受していたことから、「今、危機にある人々を見捨てることこそが罪ではないか」と考えるようになった。そして最終的には、広く人類全体を守るという決意に至り、天秤の守護者となる道を選んだのである。奇しくもミオのほうが20年以上早く守護者となったため、シェナンよりも先輩という立場ではあるのだが、その序列に慢心はなく、今でも変わらず「我が師!」と無邪気な敬意を捧げている。  剣士としてのミオはまさに天才であり、黄金の輝きを帯びた神寵者としての才能を、麗騎士としての美しき武技へと昇華させている。小柄で可憐な剣士が織りなす太刀筋の流麗さは天秤の守護者の中でも随一とされ、優雅に舞うような戦い方に魅了されながら討ち果たされた敵は数え切れない。ミオは「世界で一番可愛い」と自認しており、「あとは世界で一番強くなれば完璧ね」と臆面もなく言い切るが、それはただのナルシシズムではなく、揺るぎない自己肯定をそのまま力へと変換できる資質の表れである。そして「世界で一番可愛い自分を愛してくれるみんなを絶対に守る」という強固で温かな意志が、ミオの剣にさらなる輝きを与えていた。 期待を浴びるほど強くなる麗騎士という存在において、ミオはまさに純粋結晶のような適性を示す。人生においてプレッシャーを感じたことは一度もないと語り、敗北を経験しても決して挫けない。竜の討伐任務で窮地に陥ることもあるし、天秤の守護者という化け物揃いの訓練仲間たちには負けるほうがむしろ多いのだが、それで心が折れた様子を見た者は誰1人としていない。どれほどの逆境であろうと、ミオは必ず前を向き、胸を張り、笑顔を絶やさないのだ。  ライミリアとは天秤の守護者の2大アイドルとして名を馳せ、式典の司会を務めれば熱狂しすぎて話がまったく進まなくなるほどである。本来なら当人たちが観客をなだめればよいのだが、残念ながら2人ともファンサービスが大好きすぎて余計に混沌が広がることも多い。  だがその華やかさの裏には確かな実力があり、同じく戦いにおける技巧の中にある美意識を追求するサーフィスとは妙に息が合うことで知られている。2人が主軸となる任務は余計な被害を出さずに要所だけ正確に仕留めると評判であり、隠密行動にはまったく向かないものの、戦術的な精密さが重要な局面では重宝される組み合わせであった。  その愛らしい外見に反し、宴会好きで大食いかつ酒豪という豪胆さも併せ持つ。アノレスタンやティアムと連れ立って酒場に姿を見せれば、なだれ込んだ3人が食い尽くし飲み尽くすという光景が恒例となっている。ただしミオだけは妙に上品に食べるので、見た目と行動のギャップがさらに周囲を魅了した。もちろんティアムのように、明らかに自分の胃の体積を超える非常識な量を食べるというわけではないのだが、それでもその小柄な姿を考えれば明らかに「想定外」な健啖ぶりである。  ミオの手にある炎の魔剣ノーヴルスカーレットは、燃え盛る刀身による直接的な炎熱攻撃に加えて、魔力を注ぎ込むことで瞬間的に周囲へ超高熱領域を展開し、剣士が抱える対多数戦の弱点を補って、数を頼みに包囲圧をかけてきた敵を一掃する。また出力調整により周囲に小さな炎域を展開でき、敵の動きを牽制する用途にも優れている。一方、氷の魔剣フローズンレルムは、凍てつく刀身の直撃だけでなく、振るわれた軌道に沿って極寒の"線"を残し、それに触れた者にさらなる凍気を襲わせる特性を持つ。ミオが連続して攻撃を繰り出すことで戦場には無数の氷の領域が残存し続け、敵の回避の余地を奪い、さらに足場そのものを凍てつかせて機動力を削ぐ。この炎と氷の二振りを自在に扱うさまは、まさに麗騎士の名にふさわしい華麗さと致命性を兼ね備えている。 こうしてミオ・ブルーメンフェルトは、愛と美を体現する煌愛神の神寵者として、そして天秤の守護者の中でもひときわ眩しく輝く剣士として、常に人々の前に美しく、強く、朗らかに立ち続けている。彼の歩む道は、期待を浴びれば浴びるほど輝きを増し、誰かの願いがさらに高みへ押し上げる。世界で一番可愛いと自認するその守護者は、同時に世界で一番“愛されるに値する騎士”でもあるのだ。 ●  主に対竜や大型魔獣を想定した魔導兵器。ロボ。 星渡りの民が用いた機動兵器、機甲装兵を魔導の力で再定義した、人類の新たなる力。 機械的な構造を持ちつつも、あらゆるシステムが物理魔導に撚った技術で構成されており、精霊力干渉を受け付けない。電力ではなく魔力で動く、輝ける勇者の鎧。 その保有数は諸侯の戦力を測るバロメータであり、どれだけ多くの英雄と呪甲装兵を擁するかは外交の場においても無類のカードとなる。しかしながら本命を相手にする前の消耗を避ける為、フロウ同士の野戦に投入されることは稀。特に屠竜級は暗黙の了解で禁止されている。 一方で攻城戦となると、もう後がない守備側が最終兵器として投入されかねなくなるので、そうなる前の降伏勧告や和平交渉によって落とし所を探ることが多い。呪甲装兵はともすれば領土以上に貴重な場合もあるゆえに、城兵の一兵に至るまで徹底抗戦するケースは極力避けたいのがお互い望むところ。土地は人類内での所有権が移るだけだが、戦闘喪失した呪甲装兵の再就役にかかる金と時間は膨大であり、どちらも英雄に対する蘇生呪文の比ではない。その間に竜に襲われる悪夢を、皆恐れている。 五つのランクに大別される。 屠竜級(ドラゴンスレイヤー)、将軍級(ウォーロード)、騎士級(ナイト)、兵士級(ソルジャー)、魔符級(エンシェント)。 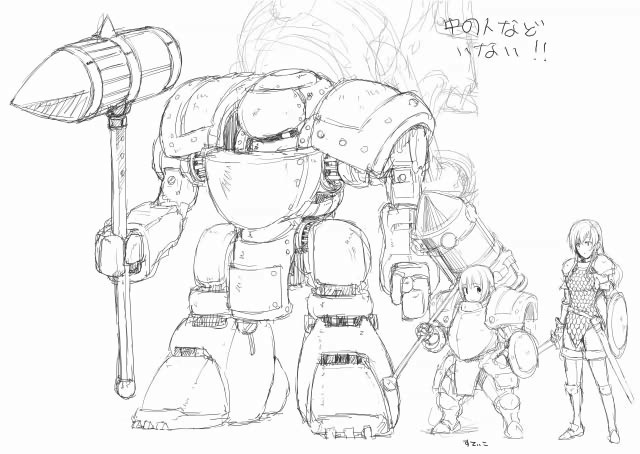 ●兵士級 銀貨1万枚~ 一番安価な呪甲装兵で、無人。ゴーレム程度の自律能力すら無いので、良いも悪いもリモコン次第で魔導師が外部からリモートコントロールするか、上位機である騎士級からコントロールされないとまともに動けない。 対大型生物用の格闘戦及び攻城兵器として運用されるが、単純なパワー頼りの戦闘しか行えない上に機動性に劣る為、「その気が無い相手」は手に余る。 僅かな例外を除いて、おおまかに格闘戦特化か射撃戦特化の2択しか存在しない。無論、土木工事にはたいてい使える。 低価格帯の機体でもヒグマ(脅威度4)は余裕でねじ伏せ、ヒル・ジャイアント(脅威度7)程度ならタイマンで互角の戦いを演じることが可能。高価格帯ならばフロスト・ジャイアント(脅威度9)もどーにかこーにか。  ●騎士級 銀貨3万枚~  有人としては一番安価。単座が基本。男爵クラスの貴族ならば最低でも騎士級1機と随伴の兵士級3機を保有していることが殆ど。 対竜戦闘は騎士級呪甲装兵小隊による対応が大前提。 近距離肉弾戦がメインの下竜相手ならばタイマンでの対応も可能。 普及数でこそ兵士級が多いが、バリエーションという意味では呪甲装兵のメインストリームであり(貴族が大枚はたいてのセミオーダーメイドが多い)、性能差がとても幅広いため、ピンとキリでジム・カスタムとグスタフ・カールくらい違う。 戦力の象徴としての美意識も求められる為、高級機ほど人間のフォルムに近付いたり、優美だったり威圧的なフォルムになる傾向が強い。ゆえに「やべぇ。かっけぇ。強いぞアレは」って判断できる。逆に安物だけど見た目だけ追求したハリボテは、魔力スキャンで看破された時に超恥ずかしいので皆やらない。  兵士級と違い汎用型も存在するが、多くは格闘戦特化や法戦特化。が、その他にも指揮型や索敵型など様々なタイプが開発されている。 これらを組み合わせることで初めて竜と戦う舞台に立つことが出来る。 飛行能力を持つ機体は殆ど存在しない。 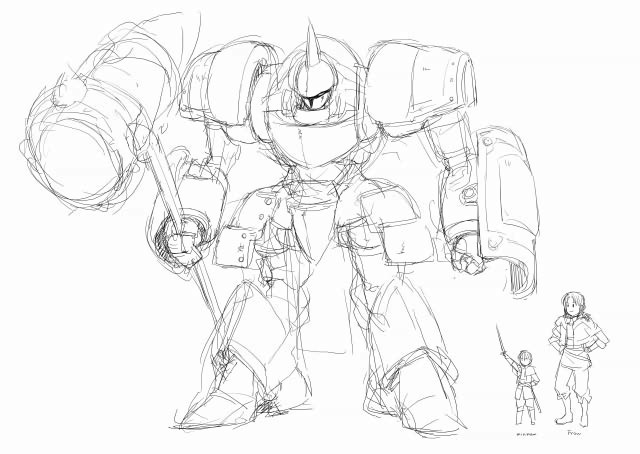 操士はそのまま搭乗するのではなく、魔導の力で小型化する。画像右が通常の等身大で、左が縮小したサイズ。 厳重にシールドされているので、小型化の魔力が解呪されるような状況はもう機体が大破してると思っていいので、中で詰まってグロいことにはなる前に死んでいる気がする。  ●将軍級 銀貨100万枚~ 複座。飛行能力を備える機体も珍しくなくなる。 高い戦闘力と、指揮型の騎士級すら凌駕する指揮能力を備えている英雄機。伯爵クラスの領内に3機配備されていたら多い方。 操士自身が化け物じみた強さを持ってることが多いため、ようやく擱座させたらコクピットから飛び出した超人兵器が更に大暴れし、機体を壊すので精一杯だった部隊を壊滅させたケースもある。 さらに上位の屠龍級に匹敵する性能を有し「違うのは人型かそうでないか」くらいのハイスペックマシンも存在する。 なお、「対人間の戦争では将軍級までしか使用しない」という不文律があり、「屠竜級じゃ使えないじゃん」と敢えて将軍級に抑えた条約逃れみたいなケースもある。しがらみ抜きにしても、屠竜級のスペックは「対竜」に特化し過ぎてて使い勝手が悪いのは否めない。「なんでもノイエ・ジールやディープストライカーを投入すればいいってもんじゃない」ってやつである。 ●破城級 バーン帝国が西覇戦争中盤から投入し出した呪甲装兵の新カテゴリー。 呪甲装兵は大前提として「対竜」の為の兵器であり、まともな対空戦闘能力を持たない兵士級ですら下竜対策が主目的で、攻城戦に用いられるのはあくまで「戦車にブルドーザーの代わりをさせる」が如し余技だった。しかし破城級はその名の通り攻城兵器で、対空戦闘能力、運動性、機動性を切り捨て、水平火力と装甲のみにステータスを極振りした戦争機械である。 明確に「対人」を目的としている呪甲装兵の開発はタブーとされていたが、近年「竜側の城塞への攻撃」に於いて、より大きな攻撃力への需要が高まり、現地改修する形で重装化する傾向が無視できないものとなっていたのが契機となったのもあり、空気を読まず急進的なことに定評のある西覇王が開発を断行した。彼としてはバーン独立戦争中に間に合わせたかったものの、開発は難航して実戦レベルの機体がロールアウトしたのは西覇王の没後であった。 西覇戦争では様々な先行試作機とも呼べる機体群が投入され、時に故障し、時に大爆発したという。 厳密には将軍級や騎士級といった、性能規格に与えられた等級のニュータイプというわけではなく、「巡洋艦」に対する「重雷装艦」といったカテゴリーなのだが、現状は十分な出力を得る為に将軍級をベースにした機体しか存在しない。将来的に低コストの小型機が実現した場合、新たなカテゴライズが行われるかも知れない。 城塞火力との殴り合い、即ち回避運動を取らない目標への火力投射に特化しているので、範囲攻撃で仕留めきれないだけの性能を持つ騎士級を相手にするだけで敗北の危機だが、基本的に護衛が付く。 当然ながら対軍勢の火力支援能力も高いことになるのだが、戦略的機動性が極めて低い故に、おいそれと戦場を選べない。フローラントの列車砲。まぁ線路を敷く必要が無いだけマシだけど。 ●屠竜級 モビルアーマー。複座以上。 老竜と渡り合うことに特化した採算度外視のモンスターマシンで、魔導戦艦を凌駕する火力・防御・機動力を併せ持つヤベーカテゴリー。 法撃したら超高位攻撃呪文に匹敵する火力が毎ランド降り注ぐとかになり、人間同士の戦争に投入するとオーバーキル過ぎて洒落にならないことから、「肝心の竜を相手にする時に疲弊してたら困るし」と核兵器的に空気読んだ運用制限が課せられている。 公爵クラスの大貴族が1機保有していたら良い方で、事実上の最終兵器。 ●魔符級 通称“機神”。解放戦争時代の発掘兵器。 桁違いの性能を持つが、量産技術は存在しない。22機存在したと言われている。 列強超大国が最低1機保有している外、現存する機体は非常に希少。 ●呪甲装兵の世代 呪甲装兵には大別される幾つかの世代が存在する。 画像はイメージであり、本当に同じくらいの強さを意味しているわけではない。 ・第零世代  解放戦争に於いて解放者エイファスが建造した機神群。原初の呪甲装兵。 当初は竜王との戦いにおける支援機として建造されたが、実際は太古竜との戦いをエイファスが不在の戦場でも可能にする為の運用が主たるものだったと歴史書は語る。 ・第1世代  解放戦争での戦域維持を主任務として多数建造された機神の廉価版。どの機体もある程度の同型機が存在しているらしい。 機神同様完全にロストテクノロジー化しており、最低でも現代の屠竜級に匹敵するスペックというのが一般的な認識。 解放戦争後も完全なメンテナンス技術が失われた状態で残敵掃討戦に逐次投入され、可動機は殆ど存在しないと言われている(それでも機神よりは多い)。 ・第2世代 エイファス死亡後、彼の知識を部分的に受け継いだ解放戦争経験世代の魔導師達による「呪甲装兵量産計画」が始動。中心となったのは魔導王国ファクセリオンの建国者にしてエイファス直属の配下であったケンタウロスの魔導師である“創造師”ジェイシント。 残存している超オーバーテクノロジー機体をリバース・エンジニアリングするところから始まり、「落とし所」を算定するまでに様々な試作機が開発され、結果として「極端過ぎて使い物にならない機体」「著しくコストに問題のある機体」など夢と希望に溢れたワンオフ機が百歌繚乱し、「解放戦争を生き抜いた世代」と「その直弟子」が存命中の内に懸命な技術蓄積が行われた。これが「第2世代呪甲装兵」で、ファクセリオン王国の呪甲装兵部隊の中には今もエース機としてこの世代の機体が現役なケースもあるが、その多くは「実戦テスト」によって喪われている。ピーキーな高性能機を死蔵する余裕など人類には無かった。 このリバース・エンジニアリングは今日に至るも絶え間なく行われており、「人類の呪甲装兵の歴史」そのものと言っても過言ではないとされる。 ・第3世代 リバース・エンジニアリングの成果によって確立した基礎技術を土台とし、実用的な兵器であることを大前提として開発された世代。 当初はまだ等級分けはされておらず、無人機も存在していない。今日の第一線機と比べると遥かに低性能であり、有人機でありながら(現在普及している)兵士級に及ばない機体も珍しくなかった。 その低性能故に第一線に存在する機体は絶無と言っても過言ではないが、この世代が積み上げた経験は人類の宝である。 第4世代 無人機の開発に成功し、兵士級、騎士級、将軍級が定義された。 機体毎にチグハグだったスペックにある程度の秩序が生まれ、「これは兵士級用のパーツだから精度はこの程度でいいだろう」等と区別されるようになり、加えて近い性能の機体同士の共食い整備のハードルも下がり、建造及び運用コストが低減された。 第4.5世代 実用レベルではファクセリオンの独占技術に等しかった呪甲装兵の建造技術だが、列強各国との間で様々な思惑が重なり合った結果、建造技術の供与を開始。これまではファクセリオンから購入するしかなかったものが、列強各国で(現実で言うところの)ライセンス建造が行われるようになり、基礎技術も供与されて将来的な独自建造も視野に入るようになった。 なお、それ以前は厳重な契約によって「リバース・エンジニアリング厳禁」とした上で売買されており、列強各国では整備技術のみで運用されていた。大規模損傷となるとパーツをファクセリオンから購入せざるを得ないという、厳しいものであった。そりゃ反感も買う。 門戸開放時により厳格な等級分けの仕様が固まり、運用コストが低下したことから4.5世代と言われることが多い。 ・第5世代 列強各国が建造するようになった、現行のメインストリーム。 当初は「ファクセリオン製よりも低性能ながら、国産品ということでコストが低い」のが強みであったが、今日ではそのギャップもかなり埋まっている。 少なくとも国(やそれに準ずる広範な共同体)単位で共通な規格の基礎パーツ(ネジとかね)が導入されているのが、この世代の特徴。 ・第6世代 現状、屠竜級のみを指す。 人類はその不断の努力により、第1世代呪甲装兵に迫る性能の機体を建造するに至った。 無論「人類が駆る呪甲装兵の全てが第1世代だった時代」と比ぶべくもないが、それでも大いなる一歩である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■プレゼントありがとうございます( ・`ω・´)  CO2センサーをTRPGしてるリビングに設置し、どこまで上がるのかをチェックしたのが左。 台所の換気扇を強でぶん回したらみるみる下がるのである。 いやー今まで暖房のせいだと思ってたボーッとする感じ、酸欠だったんだな(笑) 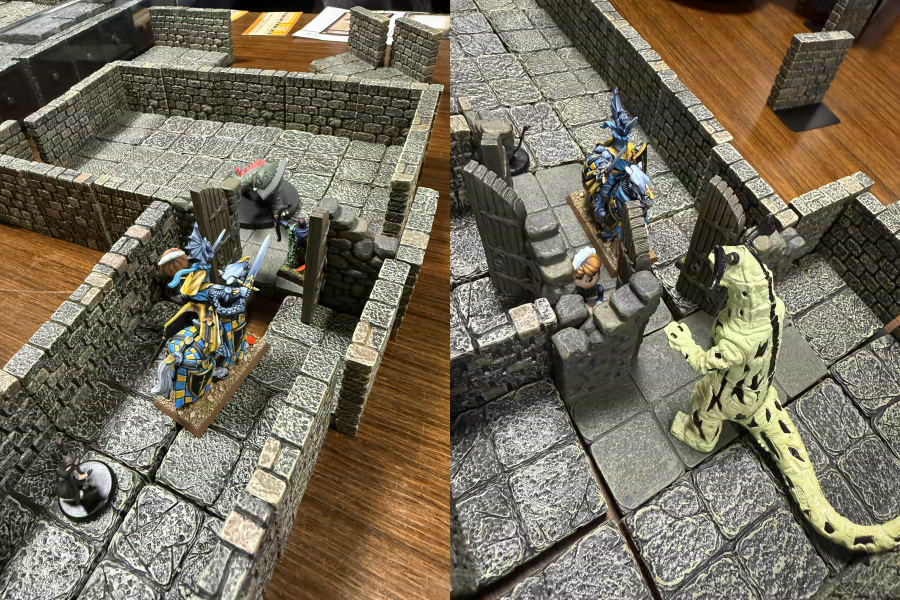 モンスターのミニチュアの代替品として怪獣を使っているのではなくて、本当に怪獣のデータを元にした(もちろんこのサイズなので超弱体化した)モンスターと戦っているので、ギロンにぶっ放したサウンドランスは反射され、エレキングの尻尾に絡みつかれて感電するのだ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■バンドリちゃん パスパレどうでしょうがはじまってしまった。 でも秩父橋から都内までは確定してたから温いんだぜ……と思ったら最後は長野(笑) これ地獄谷到着まで観客ずっと待たせてたのかよと思ったが、それは完全にただのご褒美だから問題ないわ!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■紙の本で出版することは諦めた ●人類王国ヴィーリオン  地図、王都ファイファイトは誤字だな……(笑) ヴィーリオン王国は、永久の森の東に連なる大陸東海岸一帯を領する、人類史上初にして最大規模の超国家である。王都ファイハイトを中心に広がるその版図は、解放戦争終結後の人類が、竜王なき世界を再び構築し直すために選び取った「文明の再出発点」であり、ここから700年以上にわたり、人類社会の秩序・政治・宗教・文化・言語の中心として絶え間なく影響力を放ち続けてきた。 その成り立ちは特異だ。解放戦争中、人類は都市国家の寄り合いでありながら、絶対的指導者エイファスに率いられることで奇跡的な統合を果たし、竜王すら討ち払う連帯を実現した。しかしエイファスの討ち死にと、敵首魁である竜王の事実上の全滅によって戦争が終息すると、人類は即座に“国家”という持続的な枠組みを構築せねばならなくなった。各地に点在する都市国家というバラバラの形では長期的生存が望めず、人の文明を再び滅ぼさぬための新たな基盤として、東方の沿岸地帯に王都を建設した。それが今日まで続く王都ファイハイトである。 封建制度が採用されたのも、この世界における“現実的な選択”である。竜という圧倒的外敵は常に存在し、これに対抗するためには領主と領地が一体となり、責任を伴う軍事的備えを整えるのが最も合理的だった。最初期の諸侯は解放戦争で武勲を立てた英雄たちであり、彼らが各地に根を張って秩序を築いた。紀元前の都市国家時代から続く「戦士階級と聖職者階級による統治」という構造は維持されつつ、かつてエイファスの命令一下で強制的に平等と統制が取られていた時代の“特異性”だけが終息し、世界は本来の姿へと戻っていく。 この王国の象徴的な特徴が“風”である。ヴィーリオンという国名は「風の在る場所」を意味し、実際に領内にはペガサスやグリフォンをはじめとする有翼魔獣の巨大な生息圏が広がっている。そこから供給される天空騎士団は大陸最大規模の航空戦力であり、空の覇権はヴィーリオンの軍事的威光の象徴でもある。同時に、主神たる戦勝神と、次いで強く信仰される蒼穹神が示す“騎士の誇り”と“風の機動力”は、この国の軍事思想と精神性を深く形作っている。 戦勝神の教義は単なる道徳ではなく、人類に初めて授けられた“神授の騎士道そのもの”である。降伏勧告を無視する虐殺、捕虜の虐待、民を盾に取る卑劣な戦術――それらはすべて戦勝神の教えに反し、信仰を持つ者ならずとも忌避される。「いかに勝つか」よりも「いかに気高く勝つか」が重要であり、この価値観が人類同士の殲滅戦を避け、人類文明全体の存続を支える倫理基盤となっている。感情論ではなく、竜という圧倒的脅威がいる世界では“人類同士のとどめ合いは自殺行為”であるという冷徹な現実認識からも導かれた必然である。 解放戦争の終結後、人類は竜王の脅威から解き放たれたものの、各地の都市国家は互いに疲弊し、再び争いを起こすことだけはなんとしても避けなければならなかった。そうした中でヴィーリオン王国をはじめとする諸勢力の指導者たちは、どれほど地理的な条件が許すにせよ、互いに近すぎる場所を避けて建国地を選んだ。これは明文化された条約ではなく、あくまで「人類同士で争ってはならない」という共通の反省と危機感から生まれた、自然発生的な配慮である。 ヴィーリオン自身も例外ではなく、広大な領域を得られるだけの力を持ちながら、他の新興国家群とかち合わぬよう、あえて距離を置いた地を選んだ。都市国家時代の混乱と、解放者エイファスが築いた奇跡的な共同体の崩壊後、秩序の再構築に失敗すれば待つのは種族の緩慢な滅びであると、誰もが理解していたからだ。 同じようにヴィーリオンから枝分かれした者たち、あるいは別の地域で独自にまとまった人類共同体も、互いに領域が重ならぬよう慎重に距離を置き、中途半端に隣接することを避けた。彼らもまた、竜に対抗するためには人類どうしで血を流すわけにはいかないと考えていた。 しかし永い年月の後、各国が発展し続けた結果、当初は遠く離れていたはずの国家同士の版図が、いつしか自然と接するようになっていく。だが、それは侵略の準備などではなく、繁栄の果てに訪れた必然だった。ヴィーリオンもまた、かつて遠方にあった国々と国境を共有するに至ったが、それでも建国当初の理念――「人類同士の無益な争いを避ける」という原則――を変えることは決してなかった。 こうして形成されたヴィーリオンの秩序は、国外にも影響を及ぼしている。小国が危機に陥れば救援に赴き、結果として臣従を申し出て飛び地化する例も多い。人類の盟主としてこの国は振る舞い、その自覚を持つだけの政治的安定と軍事的余裕を保ってきた。 魔導においてもヴィーリオンは高い力を誇る。魔導師は騎士と聖職者に並ぶ知識階級であり、平民が貴族階級へ到達し得る最も現実的な上昇ルートでもある。諸侯に使える宮廷魔導師の発言力は下級貴族を凌ぎ、領主の政治にも重大な影響を与える。この国はファクセリオンほど専門化してはいないものの、良質な魔導師を多く抱え、軍事・行政・宗教すべての領域で魔導が活用されている。 軍事面では、ヴィーリオンの戦力は質量いずれにおいても騎士が中心に据えられている。魔導支援、歩兵、呪甲装兵といった他要素は、最終的には「騎士の突撃で敵を粉砕する」ための補助と見なされることが多い。これは竜や強大な魔獣など“数で押しても損害がかさむ敵”に対し、「英雄的な強者による一点突破が最も効率が良い」という古来の人類ドクトリンに根ざしている。騎士団は決戦兵力として機能し、日常的な治安維持や小規模な問題には傭兵を用いるため、騎士国家でありながら傭兵需要がもっとも高いという特徴も持つ。 もちろん「少数精鋭部隊戦力」という思想は、騎士運用以外にも連綿と受け継がれている。英雄的な強者を中心に、魔導支援と密接に連携しながら敵に致命の一撃を与えるという戦い方は、竜という圧倒的強敵と向き合い続けてきた人類の経験則そのものであり、国家規模の戦争であってもなお、その思想は高い価値を保ったままだ。いざという時に即応できる戦力として、この精鋭小隊型の編成は今も重宝されている。 しかし国家の基幹となる主力戦力は、やはり騎士であった。ヴィーリオンにおいて騎士は「武門の精鋭」であると同時に「領土を預かる封建領主の戦力」であり、古くから続く領地防衛の在り方と密接に結び付いていた。ゆえに騎士たちは「常備兵力」ではあっても、その実態は諸侯ごとに整備された独自の私兵団であり、編成も装備も訓練体系も統一されていなかった。国家全体として戦いの準備を整えているにもかかわらず、「常備軍」と呼べるほど一枚岩ではなかったのだ。 広大な国土と複雑な封建制度の中で、多数の騎士や呪甲装兵を揃えた直轄戦力を維持できたのは、あくまで国力に余裕のある巨大領主だけであった。多くの伯侯は領地防衛で精一杯であり、家臣団の維持で十分と感じていたため、傭兵に成り代わるだけの戦力規模を持つ領主は少数派だった。 結果として、ヴィーリオン全土において明確に「常備軍」と呼べるものは、王家の近衛軍、そして公爵家の麾下にある大規模戦力くらいのものだったと言える。 言語面でもヴィーリオンは世界に深い影響を与えている。星渡りの民以前は大陸古語――竜語ベースの各都市国家方言の寄せ集め――が使われていたが、相互互換性に乏しいため共通語としては破綻していた。星渡りの民の中で最大勢力だったドイツ語圏の言語が暫定共通語として採用され、ヴィーリオン建国後には正式に標準化されてヴィーリオン語となり、最終的には「大陸語」として広く使われるようになった。 政治構造としては典型的な封建国家であるが、同時にその体制が700年以上続いている事実は、この国が“非効率の積み重ねですら巨大な安定を生む”という強みを持つことを示している。世襲ゆえに無能が権力を握ることは避けがたいものの、貴族たちは理想と現実を区別できるだけの歴史と経験を蓄積しており、不都合の多くが致命的に膿む前に調整されてきた。その一方で、この封建構造の欠陥を徹底的に排除して理想の国家を築こうとしたのがバーン帝国であり、両国の戦いは現在こそ小康状態にあるものの、未来においてどのように決着するかは未だ予断を許さない。 そして――ここでようやく語るべきが、バーンとの激闘である。ヴィーリオンは建国後長らく大陸最大の超国家として君臨していたが、バーン建国初期においては典型的封建国家の弱点、すなわち総力戦能力の欠如と動員力の低さが露呈し、立て続けに惨敗し、広大な領土を喪失した。だが当時、一部の先見性ある諸侯がバーン式の組織運営術を取り入れることで自領の維持に成功し、バーン側が攻勢限界に達したことも相まって、現在の国境線が成立した。これがヴィーリオンにとって痛烈な教訓となり、改革を進める契機となった。なおヴィーリオン側の認識では、バーンは「国家」ではなく「反乱を起こした地方貴族」にすぎず、この戦争は対外戦争ではなく“内乱”と位置付けられている。 総合的に見れば、ヴィーリオンは先進性ではバーンに、商才ではヒノワに、強靭さではホウルティーアに、魔導技術の最先端ではファクセリオンに及ばない。しかし、それらをすべて“各国の特化”として横に並べ、それ以外のすべて――軍事的信頼性、人口規模、経済基盤、宗教体系、政治的安定性、文化的影響力、外交的信用――を総合した時に、真に人類最大の超大国として君臨し続けているのがヴィーリオン王国である。この国は、竜の支配する世界において、人類文明の屋台骨として風を吹かせ続けてきたのだ。 ●王都ファイハイト  ファイハイトはヴィーリオン王国の王都にして、フローラント大陸最大の都市である。政治・経済・文化・軍事・宗教・学術の全領域において他都市を凌駕し、事実上の“人類文明圏の中枢”とみなされる。都市人口は約200万に達するとされ、これは一般的な王国の総人口を超えており、単一都市としては大陸史上最大級である。その発展は王国の国力を示す最たる証拠であり、大陸の文明の潮流は常にこの王都を起点として流れていく。 市街は途方もない広さと密度を持ち、多種多様な商業施設、文化機関、芸術院、学術施設、各種ギルドが林立し、王国中の諸侯が王都内に構える城館はそれぞれが壮大な規模を誇る。これらの城館は単なる邸宅ではなく、いずれも王都防衛計画の中で軍事的意義を持つよう綿密に配置されており、市街の各地点に対して即応的に戦力を展開できるよう工夫されている。王都の都市構造は、その広大さにもかかわらず、高度な統治と軍略に裏付けられた秩序ある機能配置によって維持されている。 経済面では、王都は大陸随一の交易と産業集中地である。海上物流の要衝たる港湾はヴィーリオン王国最大規模であり、バーン帝国最大の港湾都市ゼナをも上回る取引量を記録する。夜を徹して往来する交易船団によって外縁区の倉庫街は常に賑わい、市場は国際的な流通の焦点となる。単一都市の経済生産力としては比類なく、王都だけで形成される富のみで多くの国家を凌駕すると評される。 王都の学術の中心である魔導学院は、大陸で最も規模の大きい魔導教育機関として知られる。研究分野の先進性はファクセリオンに譲るものの、体系化された教育の質と学院の権威は他の追随を許さない。王国内外から優秀な門下生が集まり、彼らは後に王都の魔導行政、都市インフラの魔導補強、防火結界、水利管理、衛生魔導など都市の核機能を支える人的資源となる。王都の機能維持には魔導学院の人的蓄積が不可欠であり、これが大都市の土台を形成している。 ファイハイトの宗教的中心性は特筆に値する。多数の教団の総本山が王都に集中し、それぞれが固有の聖堂区と広大な敷地を持つ。この密度は他都市に類例がなく、王都そのものが複数の神々に仕える大聖域のような性格を帯びている。教団は救済・教化を担当する一方、治安維持の重要な構成要素として王権と緊密に連携している。王都には強力な魔導警備網が張り巡らされているが、その運用の根底にあるのは教団組織との共同統治体制である。救済活動の手に余る人物、あるいは秩序を著しく阻害すると判断された者は、教団と警備隊の判断により都市外へ排除されることもあり、これによって王都の治安は異例の良好さを保っている。 宗教権威が都市防衛にも直結するため、ファイハイトを攻める行為は“神に弓引く”ことと同義に受け取られ、大陸の国家や集団に強い抑止効果を持つ。もし王都が外敵に包囲され陥落の危機を迎えれば、各教団は文字通りの"全身全霊"となる大規模儀式を発動し、神霊界より神を降臨させるとされる。複数の総本山が集約する王都では複数神の同時降臨すら起こり得るとされ、この儀式は大地規模の魔力を呼び込み、戦場全体を神域へと変貌させるほどの威力を持つ。いかなる強国であろうと、この“宗教的抑止力”を無視して王都への侵攻を行うことは極めて危険と認識されている。 さらに、王都固有の象徴として建国王オスカー・ヴィーリオン1世の存在がある。彼は解放者エイファスに次ぐ大英雄であり、死後には半神として神霊界へ迎えられたとされる。王都陥落の危機に際しては、最終防衛手段としてオスカーが召喚される可能性が語られ、彼と対峙する覚悟なくして王都に攻め入ることはできないとされる。このように、ファイハイトの防衛は軍事・魔導・宗教・英雄伝承が融合した独自の体系として成立し、ただの城壁や兵力の問題を超えた重層的抑止構造を備えている。 ファイハイトは建国当初から城塞都市化をあえて行わず、開放的な市街拡大方針を採った。これは、竜側戦力が弱体化し、機神や英雄級戦士が王都周辺に集中していた時代背景に支えられていた。王国の版図拡大に伴い、王都の外周には多数の城塞都市が建設され、それらが縦深防御網を形成することで、王都自体の開放構造は長期的にも維持可能となった。今日では“国土そのものが防壁”であり、市街が攻撃されても王都陥落に至る可能性は極めて低いと認識されている。ただし、広大な市街区を完全に覆う防衛は現実的ではなく局地的被害は避け難いが、それでも王都を守護する戦力は絶対的と評価される。 王都の市街は地上だけでなく地下にも広がる。地下には同盟を結んだ地下種族が住む大規模都市網が存在し、人類が不得手とする“地下からの侵攻”に対する防衛基盤として機能している。地上種族が魔導によって地下対策を行う場合の膨大なコストを考えれば、地下種族との協力体制は都市機能の維持に不可欠である。他都市にも地下共生は見られるが、ファイハイトほど徹底した二層構造を形成している都市は存在しない。 都市の繁栄の裏には、人口の急増という深刻な課題がある。王都の人口はすでに許容量の限界に近づいており、構律神教団を中心として都市計画の抜本的改訂案が検討されている。外縁区は経済格差が顕著で、貧困が原因の軽犯罪が多発する。王都は雇用需要が大きいとはいえ、人口流入の速度がこれを大きく上回り、「王都に行けばどうにかなる」という夢を見て流入した人々の多くが帰る余裕もないまま困窮し、最終的に犯罪へと転落して強制労働に送られる例が絶えない。これは王家直轄領における採掘人員の補填として重要視されるが、同時に食い詰め者たちにとっては「食事と寝床を得られる最後の手段」としても有名である。また水夫の職は一般的な就業先であるにもかかわらず、傭兵や鉱山労働者を凌ぐ過酷さで知られ、食い詰め者が割り当てられる船は特に危険とされる。 社会的評価の仕組みにおいても、ファイハイトは一風変わった性質を持つ。王都は“一攫千金”の都市ではなく、むしろ“正しく積み重ねてきた成果が正しく評価される都市”である。実績そのものよりも、それを認める人物が周囲に保証し、信頼ネットワークの中で評価が確定する性質が強く、人間関係の積み重ねが成功の鍵となる。努力が報われる社会ではあるものの、その性質はバーン帝国のように“個の才能が爆発する社会”とは大きく異なり、より緻密で、秩序的で、相互承認的な社会構造を持つ。 超大都市としての問題を抱えながらも、ファイハイトは依然として大陸最大の都市であり、人類文明の象徴とされる。その威容は建国以来の長い歴史の中で培われたものであり、政治・経済・宗教・学術・文化が渾然一体となって都市の生命を形作っている。治安、軍事、魔導、宗教、地下共生、経済、人間社会の総体が互いに支え合うことで、王都は今日も大陸文明の中心として脈動し続けている。 ●炎覇将エスカナス・ザーム伯爵 673~  貴族5/君主2/武将10/将軍1 筋力14/敏捷力10/耐久力13/知力15/判断力17/魅力17/PB37 リュートリオン王国の伯爵にして、かつて王国が健在であった時代には王族を除けば国内第4位の実力者と目された人物である。王国滅亡後にはヴィーリオンに亡命し、亡命政府の元首を務める。  ザーム家はその先祖にテレシオ・ザームとアルティサイア・ザーム、2人の竜殺しの英雄を持つ武門の名家であり、彼も若き頃から将としての才覚を遺憾無く発揮し、永久の森やアーエイト山脈から襲来する竜の勢力に対して数々の武勲を積み重ねてきた、百戦錬磨の名将。 彼は前線指揮官として卓越した才能を発揮する一方、国家戦略の規模では致命的に無能とも解釈できる稀有な人物であった。すなわち、戦場における天才であり、政における破滅者である。しかしその矛盾は彼の信念の強さと表裏一体であった。 バーン王国が後に西覇戦争と呼ばれることになる西方諸国への侵攻を開始し、その矛先が南方へも向けられた際、ザームは慎重論をことごとく退け、自らが統括する国家総戦力の3割を率いて、北の隣国センクオン王国へ進軍中であったバーン軍の側面を急襲した。  実のところ、バーン軍はリュートリオン軍への誘い水を企図し、軍列に意図的な隙を作っていたことがこの奇襲を成立させた大きな要因ではあるのだが、問題はザームの将としての力量を過小評価していたことで、想定に数倍する大損害を発生し、多くの有能な人材を失うことになっている。これはバーンがザームを凡将と見くびっていたのではなく、竜の軍勢との戦いに生涯を費やしてきた歴戦の猛将と認識していたにも関わらず、なお「まったくもって足りていなかった」ことを意味する。 だがこの独断専行は戦術的大勝利をもたらしたが、戦略的には国家を滅亡へ至らせる導火線に火を付けるものであった。彼の勝利に奮い立った民衆は一斉に抗戦派へと傾き、こうしてリュートリオン王国は全面戦争の道へと突き進むことになる。 彼自身は名誉や権勢に執着する人物ではなく、純粋に国家と民族の誇りに殉じているつもりである。彼の独断を非難する声は少なく、むしろ敵味方を問わず「巨大な力に抗い、誇りを捨てなかった武人」として尊敬された。バーン軍の将たちですら、彼を「無駄な抵抗をした愚将」ではなく「不屈の気概を体現した男」と評する者は少なくない。 かつての永きに渡る「竜種による支配の時代」から、人類にとって「自由は命を賭して守るもの」という観念は正義とされていた。だがそれは本来、人ならざる外敵に対してのものであり、人間同士の戦争においては「過剰な虐殺に至る前の積極的な妥結」を是とする倫理が存在していた。そこから外れて「積極的な虐殺」に及ぶ者も当然いるが、絶対的な悪行と認識されるのだ。ザームはその境界を超え、人同士の戦争にも同じ理念を適用してしまった。尊厳への妥協無き誇りの戦士――それが彼の本質である。  「西方の諸国が団結すればバーンに抗し得る。時間を稼ぎ、ヴィーリオンの救援を待てば勝機はある」――彼はその信念を生涯疑わなかった。隣国の危機を看過できず、救援に向かったのもこの信条によるものであり、彼はその行為によって「英雄」と呼ばれるに至った。 リュートリオンの人々は太陽神を主神として崇め、誇りと潔白を尊ぶ国民性を持つ。その精神はザームの行動を後押ししたが、同時に「そこまでの覚悟を持たぬ者」も少なからず存在した。ザームはそうした者たちを惰弱と切り捨て、理想のためにすべてを賭した。彼にとって玉砕は目的ではなく、あくまで勝利の手段であった。しかしその勝利構想は非現実的であり、ヴィーリオンが援軍を送るには、永久の森やアーエイト山脈を越えねばならぬ地理的困難をまったく考慮していなかった。 実際、ヴィーリオンもリュートリオンを見捨てたわけではなく、救援を試みたものの、バーンが建設した国境要塞イモータルフレイムに阻まれ、すべて撃退されている。ザームもヴィーリオンが自らの描いた戦略に呼応してくれようとしたことは事実と認識しているので、亡命後もヴィーリオンに対して恨み言一つ漏らさなかった。彼にとって、力を尽くしてくれたという事実こそが誇りであり、感謝の対象であった。たとえそれが「形だけで明らかに最初から突破できるわけもない戦力」であったとしても、彼がそれを知ることはないし、疑うこともない。 そもそもがヴィーリオンの全力を尽くしてもなお成功は困難な構想であり、ザームの作戦は「精神論による希望」でしかなかったといえる。だが、それこそが人々が求める「英雄譚」でもあり、彼の誇り高き姿勢は人々に感動を与え、結果として「徹底抗戦したリュートリオン」と「力を尽くしたが届かなかったヴィーリオン」の物語は、美談として語り継がれている。  リュートリオン本土にバーンの侵攻が始まってからも、エスカナス・ザームは最後の瞬間までその才を失わなかった。彼の指揮は常に冷静でありながら激情を孕み、数において10倍を超える敵軍を相手にしてなお、幾度も局地戦で勝利を収めた。地形を読み切り、兵を巧みに動かし、敵の補給線を断ち切る戦術は神懸かり的と評された。彼の下で戦う兵士たちは、常に死と隣り合わせでありながらも不思議と恐れを感じなかったという。ザームが前線で掲げた軍旗は、絶望の只中において希望の象徴であり、王都カーフィオンを包囲するバーン軍の将らすらも、彼の統率と戦意に畏敬の念を抱いた。 王都陥落の際には幼き姫の脱出護衛を命じられるが、「王族が城を枕に討ち死にすることは、当然果たすべき責任である」として最後まで防衛線に踏みとどまり、脱出経路がバーンの広域結界に封殺されるまで抗戦を続けた。結果的にそれが姫の退避を不可能にしたが、ザームにとって戦場を離れるという選択肢は存在しなかった。  その後のザームは尚も剣を置かず、滅亡が確定した後でさえ彼は残存兵力を再編し、散り散りになった民の避難を援護し続けた。自らを盾とし、敗走する国民の背を守りながら、彼は次々と後退線を築き、追撃するバーン軍を巧みに遅滞させた。その戦いはもはや国家の防衛ではなく、「人々の生存のための戦い」であった。 やがて避難民がヴィーリオン領へと退避し終える頃、ザームの部隊はもはや壊滅寸前だった。それでも彼は最後の一兵まで指揮を執り、退路を断たれた状況で奇跡的に突破を果たす。短絡的な玉砕を選ばず、なおかつ決して保身に走ることもなく、自らを死地に置きながらも部下を生かし、生還するという離れ業――それは彼の戦術眼と統率力、そして冷静さがあってこそ成し得たものであった。彼は血に酔う猛将ではなく、誇りのために戦い、命を繋ぐことをも誇りとする真の指揮官であった。 ザームに政治的手腕はなく、軍略も戦場に限られた。しかし彼の純粋な理想主義は、人の心の美しさと可能性を信じ続けた結果でもあった。その純粋さが国を滅ぼす結果を招いたという事実は、歴史を俯瞰できるほどに賢明な者たちにのみ理解されている。しかし、圧倒的多数の人々にとってエスカナス・ザームとは、理想と誇りに殉じた偉大なる英雄そのものであり、バーン帝国と戦う勢力にとっては「抵抗の象徴」であり、その存在を貶めようとする動きは一度として主流になったことがない。 リュートリオン王国の滅亡とともに西覇戦争は終結し、バーンは帝国として再編成を果たした。 だが、燃え盛る炎の中でなお抗い続けた名将の姿は、「炎覇将ザーム」として語り継がれた。リュートリオンの光であり、バーンの炎を粉砕した男。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■プレゼントありがとうございます(`・ω・´) マルチモニターは長いこと使ってるけど、モニターアームは初使用なんですよ。……便利だな!! この位置にあるの見易いし、テレビ使う時だけ横に退かせるの素晴らしい!!  千葉の僻地で長距離バス待ってる時間の心細さが半端なかった。肉眼だともっと暗いからな!!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■バンドリちゃん 従来のガルパピコ同様に、イカれたギャラクシーエンジェル的な展開が目白押しになることを期待してたのだが、このアニメけっこー大人しいな!? ただのRoseriaが可愛いだけなアニメじゃないか!!!(まぁそれはそれで  モニカ……というかましろちゃんはライブパフォーマンスとかでも自分の無力感とか閉塞感をポエミーに展開するとか、とにかくネガティヴさが前面に押し立てられたキャラ性を最大の個性としてプロデュースされているのだが、富裕層のお嬢様が恵まれた環境の中で「自分にはなにもない」と鬱屈しているから……共感し難い……!!!(笑) AKBの恋するフォーチュンクッキーで「男はみんなどうせ可愛い子が好きなんでしょ」みたいな歌詞を唄われても「お前がそのモテモテ可愛い子層だろ!」って気持ちが先に来るくらいに!!!  美味しいよね、ミレメーレのアップルパイ。 軽井沢で食べてその後も取り寄せるくらいには好きだよ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ちなみにパラメータのPBはポイントバイ換算で能力値が幾つか、つまりどんだけ基礎スペックが高いか指数です。 ●柚乃香 708~  専門家3 筋力7/敏捷力8/耐久力8/知力12/判断力11/魅力15/PB15 元リュートリオン国民の女性で、ヒノワ系商人の娘。生まれて間もない710年、家族と共にヒノワからリュートリオンへ移り住み、穏やかな幼少期を送る。兄の陽和、姉の月奈とは4歳の年の差がある。  幼少のころから器量良く、要領も良い。世渡り上手な性格で、周囲から可愛がられ、蝶よ花よと育てられた。可愛らしい顔立ちと明るい気質で、同世代の男子からも早くから注目されており、その環境の中で培われた自己肯定感は極めて高い。人に愛されることが当たり前だったため、他人の悪意というものをほとんど知らずに成長した。誰かに冷たくされても「機嫌が悪かったのかな?」と考える程度で、人の悪意を悪意として受け取る発想自体に乏しい。 このため、他人の気持ちを深く読み取ることは不得手だが、その場の空気を察し、機嫌を取るのが自然にできる。時に「一番力を持つ存在」に無意識に愛想を振りまくことがあるが、それは打算ではなく、長年染みついた“身の処し方”に過ぎない。幼いころから両親の商談や社交の場に「珠のように美しい娘」として同席させられ、愛想を振りまいて褒められることが当然だったがゆえの成長結果である。  その振る舞いは天性のものというより、純粋な育ちの良さと、他者に悪意を向けない性質から生まれた自然体の人懐こさだった。美しい少女が、否定的なことも言わず笑顔で会話をしてくれる――それだけで多くの人は機嫌を良くし、柚乃香はそれを“人を喜ばせること”と信じていた。勉学にも秀でていたが、運動は不得手で、それすらも周囲から「か弱くて可愛い」と受け取られてしまう。彼女にとって世界は優しく、家族は温かかった。  両親と兄姉を深く愛するその生活の中で、やがて兄の親友であったジヴ・ヒューリックに淡い想いを抱くようになる。彼の誠実さ、武人としての気質、そして孤児院で育ちながらも優しさを失わぬ人柄に惹かれ、12歳の頃から積極的な好意を示すようになった。幼い恋のようでいて、柚乃香の中では本気であった。15歳のとき、半ば押し切るようにして交際が始まる。 ジヴは顔立ちの整った少年であり、人柄も良く、しかも平民の中では高い社会的地位を持つ騎兵となる身であった。柚乃香の本能的な“選択眼”は決して間違っていなかった。彼女にとってジヴは理想そのものだったのだ。年頃を迎えるころには裕福な商家の男子たちからも引く手あまただったが、柚乃香の心はすでにジヴ1人に定まっていた。 しかし、幸福は長く続かなかった。やがて勃発した西覇戦争、そしてバーンによるリュートリオン侵攻によって、彼女の世界は崩壊する。両親と兄を失い、姉の月奈と共に難民団の一員となる。護衛隊長を務めていたのはジヴ・ヒューリックであり、彼の指揮と騎士たちの犠牲によって2人は命を繋ぎ、ヴィーリオンへと辿り着いた。 この護衛戦での功績により、ジヴは戦後に正式な騎士に叙される。だが、それは同時に彼が亡命政府の中核に組み込まれ、限界を超えた仕事を背負わされることを意味していた。柚乃香と月奈はその間、王都に向かう彼の庇護を離れ、難民として過酷な生活を余儀なくされる。ヴィーリオン王国は難民を受け入れてはいたが、彼らの受け皿となった辺境の領主達に、全体を見れば万を優に超える難民の暮らしを用立てるほどの余裕はなかった。生活の面倒など望むべくもなく、難民の多くは自活できる者だけが生き延びる現実を知っていたが故に、その力に自信を持てない多くの国民たちが、亡国の時を共に過ごすことを選択していたのだ。 柚乃香と月奈は商人の娘として育ったが、実際には自ら働いて生きる術を持たなかった。両親と共に安全に亡命するはずだった計画が崩れ、頼るべき財も失われていた。国境の町で難民団が解散したのち、手元のわずかな路銀と、彼が渡してくれたなけなしの手持ちで細々と暮らしたが、それもすぐに尽きた。 過酷な現実の中で、2人は飢えに苦しみ、衛生も安全もない生活へと追い詰められていった。節約しているつもりでも、それは「貧しさを知らぬ者の節約」に過ぎず、財布は瞬く間に空になった。姉妹の困窮は誰の目にも明らかで、2人には周囲の人々の視線が"果実が熟して墜ちるのを待つ"ように映りもした。 生きるために、柚乃香は最悪の覚悟――自らの身体を売ること――を心のどこかで受け入れようとしていたそのとき、ようやくジヴが彼女たちを見つけ出す。 再会は涙に濡れたものだった。騎士となったジヴの生活は安定しており、2人を保護して共に暮らし始める。柚乃香は恋人との再会に歓喜しながらも、心の奥では「もう飢えなくて済む」という安堵を覚えていた。その感情を恥じながらも否定できず、彼女は静かにその幸せに身を委ねた。 彼女にとってジヴは、愛する人であると同時に“生きる術そのもの”だった。幼いころから他人の善意と庇護の中で育ってきた少女が、戦火の中でようやく再び手に入れた“誰かに守られる場所”。その穏やかな笑顔の裏に、彼女はかつて知らなかった「生の重さ」と「幸福の脆さ」を抱えている。 ●マスターズ・コメント トップ絵の柚乃香さんは、英雄であるジヴの恋人としてパーティーに出席しているときの姿なんだが、本文の中で特に入れられる場所がなかったんで(笑) 亡命政府がそんな裕福じゃなく、ジヴの俸給もたかが知れてるのだが。彼の名声は大きいので、ヴィーリオンで暮らす裕福なリュートリオン人商人とかから柚乃香へ個人的なプレゼントとしてドレスや化粧品、宝飾品の数々が贈られたりするらしいよ。柚乃香さんは無邪気に喜んでるよ。 ●月奈 704~  専門家3 筋力8/敏捷力5/耐久力13/知力14/判断力10/魅力10/PB12 リュートリオン出身の女性であり、柚乃香の姉、陽和の双子の妹。 彼女はヒノワ人の商家に生まれ、家族とともに幼い頃にリュートリオンへ移住した。生来、手足の自由が利きにくい障害を持ち、そのために幼少のころから極端に不器用で、日常の些細な動作にも苦労を伴っていた。身体的な制約から来る不自由さは、やがて彼女の性格に影を落とし、強い自己否定と遠慮深い気質を育てることとなる。努力家で地頭の良い彼女は勉学において優れた成果を上げ、宗教学、法律、経理といった理知的な分野では常に上位に位置していたが、同時に要領が悪く、社交や交渉の場面では致命的なほど不器用だった。人の機微を読むことも不得手で、勝負勘や勘所といった直感的な判断を必要とする場面では力を発揮できなかった。月奈という人間を一言で表現するなら、いわゆる「どんくさい」とならざるを得ない。 陽和と柚乃香という2人の兄妹はともに器量が良く、誰からも愛される性格で、幼い頃から社交の場で華を添える存在だった。柚乃香は明るく愛嬌があり、陽和は気配り上手で頭の回転も速い。対照的に月奈は、初対面の相手と話すことすら苦手で、空気に呑まれて言葉を詰まらせることも多かった。両親は、そうした彼女の性格をよく理解していた。兄や妹のまわりには自然と人が集まり、月奈にだけ輪ができにくいことを察しており、その光景が娘の心をどれほど痛めるかを想像していたのだ。だからこそ、家族で社交の場に出るときには、月奈を連れて行かないことが多かった。それは決して彼女を軽んじたためではなく、むしろ深く気遣った結果だった。娘が比較によって傷つくのを避けたい――それが親の本心だったのである。だが月奈自身はそうは受け取らず、「自分は使えない娘だから置いていかれるのだ」と感じてしまう。両親の配慮が、彼女の中では自己否定の証拠に変わっていった。 そもそも兄が太陽を意味する名前を貰い、自分は月である。親としては単に「力強い」「美しい」くらいのつもりで名付けていたものだったが、月奈としてはこれすらも「兄の添え物」という皮肉に受け止めていく。 それでも月奈は心の奥底に、折れることのない芯の強さを持っていた。絶望に沈んでも立ち直り、諦めることはあっても投げ出すことはない。最初から人生に大きな期待を抱いていないため、落胆も少なく、平穏を望む心が彼女を支えていた。家族に迷惑をかけずに生きること、それだけが彼女の願いだった。  興隆神の神学校に通い始めた月奈は、そこでジヴ・ヒューリックと出会う。孤児院の院長の実子として多くの孤児と共に育った少年であるゆえか、閉じた心を優しく開かせることに長けた、誠実で柔らかな気質を持つ青年であった。人見知りの激しい月奈にとって、ジヴは生まれて初めて「怖くない他人」で、自然体で接し、彼女の緊張を解くことができる稀有な存在だった。月奈はそんな彼に少しずつ心を許し、いつしかその優しさに惹かれていく。彼はやがて陽和の親友となり、家にも訪れるようになったが、ジヴにとっては常に「親友の妹」「同級生」であり続けた。  必然的にその想いは恋心として形を成したが、彼女は自分から伝えようとはしなかった。「恋人になりたい」とは思っても、「恋人になれる」とは思わなかったからである。ジヴは孤児たちを支える優しさと信念を持ち、月奈から見れば、まぶしいほどに遠い存在だった。  そんな中、妹の柚乃香が成長し、社交的な魅力をより鮮やかに開花させる。柚乃香は明るく要領が良く、ジヴに対しても積極的に想いを寄せ、やがて2人は交際を始めた。月奈はその現実を静かに受け入れた。酷く落胆したが、もともと自分が選ばれるとは思っていなかった。「私はジヴ君が幸せならそれでいい」と言い聞かせ、心を保ち続けた。柚乃香は姉の想いなど露ほども知らず、無邪気に惚気話をしては笑い、ジヴに甘える姿を見せた。ジヴもまた恋愛に関しては鈍感で、月奈の感情に気づくことはなかった。唯一、陽和だけが交際の始まる遥か前からこの三角関係に気づいていたが、それを言葉にしても誰も幸せになれないと理解し、沈黙を選んだ。柚乃香が好意を向け出したからといって「月奈が先に好きだったから柚乃香は諦めろ」と言うのは、あまりに不公平で無意味だと思ったのだ。誰も悪くなく、ただ運命がそう巡っただけだった。 その甘くて苦いママレードが如き日々も、西覇戦争の激化とバーン帝国の侵攻によって崩壊する。家族は離散し、両親と陽和は先行する難民団に加わったが、逃避行の途中で襲撃を受け命を落とす。月奈と柚乃香は幸運にも脱出に成功したが、裕福な暮らししか知らなかった柚乃香は難民生活の過酷さに心身をすり減らし、飢えと不衛生、暴力への恐怖に怯える中で急速に衰弱していった。月奈は妹を励まし、懸命に生き延びた。所持金は尽き、身寄りもなく、助けの手は到底足りるものではなかった。現実を理解するほどに、2人は追い詰められていく。商人の勉強を積んできたとて、土地勘も人脈も資金もない難民の立場で自活する術などなく、「身体を売って日銭を稼ぐ」「裕福な者の"庇護"を受ける」といった手段が最も確実な現実であることを、頭では理解していた。それでも受け入れがたい屈辱であり、どうしても踏み切れずにいた。飢え死にが視野に入りかけたその時、ジヴが彼女たちを見つけ出し、救い上げた。 ジヴは戦功を認められて騎士に叙され、亡命政府の中核に迎えられた。彼は柚乃香と月奈を保護し、ヴィーリオンの王都に小さな屋敷を構えて共に暮らすようになる。月奈は不自由な身体ながらも家事を担い、経験と工夫によって動きを最適化し、家の中を切り盛りしている。柚乃香もまた「騎士の恋人」であることのみにかまけず、姉を助けながら家庭を支えている。3人の暮らしは静かで、穏やかであった。月奈の心の奥底には、今もなお言葉にならない想いが残っているが、それを口にすることは決してない。ジヴはかつて恋い慕った存在であり、今は守るべき家族そのものだ。柚乃香はそんな姉の想いなど知らぬまま、今も「大好きなお姉ちゃん」として慕ってくる。  どうせ無理だからと化粧に興味のない月奈に、柚乃香が「お姉ちゃん、素材は良いんだから」と微笑みながら化粧を施すのは、昔から変わらぬ姉妹の遊びだった。その穏やかな光景は、失われた国の中でようやく手に入れた小さな平和であり、戦火を越えてなお生き残った彼女たちが守り続ける、ささやかな幸福の形である。 マスターズ・コメント 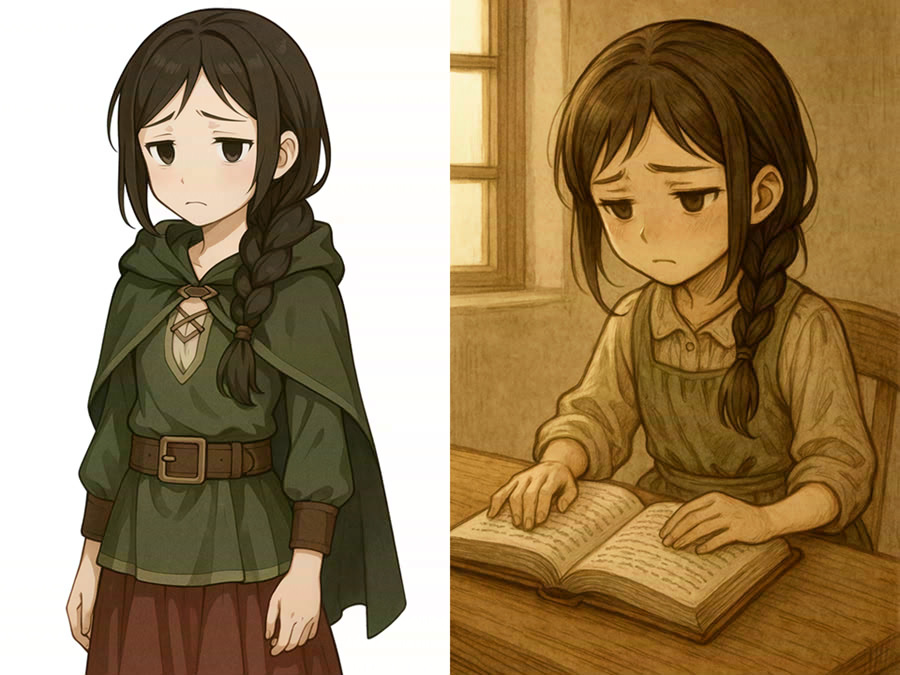 これはこれで可愛いのでは。 性格に問題があると、モブ顔じゃなくても【魅力】は10になっちゃうよ枠。むしろ地顔が良くて善良だからこれで済んでいる。妬んで意地悪とかするタイプなら確実に一桁だ。 あと本文中じゃ身体を売ることを滅茶苦茶嫌がっててさも屈辱的な仕事であるかのように扱われてますが、それは彼女たちが裕福に暮らしてきたからゆえの感覚であり、世界の常識的な感覚としてはそこまでクソみたいな職業と認識されてないです。職業の選択肢が殆ど無いので。 それに忌避感という意味では、仕事の選択肢がたくさんあって「いくらでも普通に働いて暮らせる」現代日本なら遥かに凄まじくありそうなもんなのに、別にそーいうことにもなってないでしょ。生きるためじゃなくて、遊ぶ金欲しさにやる人が大勢いる。 フローラント世界の「町のそこらで生きてる普通の女性」の認識において「身体を売れば暮らせる」ってのは、男なら「傭兵や日雇い人夫を頑張れば食っていける」程度の認識なので、それをちょっとした忌避感にとどまらず、死ぬほど嫌がるのって贅沢な悩みなんですよ。だから町の人達や地元の教団が冷たくて月奈たちを助けないとかじゃないんです。現実の中世ヨーロッパでの売春に対する強烈な忌避感は概ねキリスト教の影響。それでも貧民層はそんなこと言ってられなかったというだけ。 ●陽和 704~728  専門家4 筋力11/敏捷力11/耐久力11/知力13/判断力14/魅力14/PB25 ヒノワ系商家の長男で、月奈とは二卵性双生児、柚乃香は4歳下の妹。商家の後継ぎとして幼少から徹底して「人付き合い」「立ち回り」「礼儀」を叩き込まれた。家庭の期待に応えるうちに、無意識に周囲の人間を「利害」で測る癖が身についてしまったが、それでも本質的には誠実で情に厚い青年である。 社交の場では頭の回転が速く、誰に対しても卒なく接することができる。利発であると同時に、相手が求める自分の姿を瞬時に演じることができるタイプで、父からも「商家の跡継ぎとして申し分ない」と評されていた。  興隆神学校に入学した当初、その学び舎には多くの商家の子女が集まっており、将来の取引関係を見据えた「利益の網」を築く場になっていた。学生同士の交わりも、打算と期待に満ちた“未来の模擬市場”のような様相を呈していたが、そんな中で陽和は浮いた空気を放つ一人の少年に気づく。ジヴ・ヒューリック――孤児院を営む家庭で育ち、私利ではなく“誰かのため”という利他的な理由で学ぶ青年であった。利害計算にまみれた環境の中で、ただ一人打算抜きで付き合える相手が彼だった。陽和は次第にジヴに惹かれ、親友として心を許していく。 しかし皮肉にも、妹たちの恋心がその親友に向かっていく。しかも最初に好意を抱いたのは月奈であったのに、恋人になったのは柚乃香だった。陽和は2人が付き合い出す遥か以前、柚乃香の恋心を察したとき、胸を裂かれる思いを抱えながらも、兄として、そして友として、何も言わずに見守ることを選んだ。個人的な気持ちとしては、如才ない柚乃香よりも不器用で人付き合いも絶望的に苦手な月奈を応援してやりたいのだが、恋に順番も公平もないと理解しているからこそ、どちらかを否定する言葉を選ぶことができなかったのだ。 月奈の痛みと柚乃香の無邪気さの間に挟まれる日々は、まさに針の筵であった。誰も悪くないのに、誰かが傷つくしかない構図。その理不尽さを呑み込んだまま、陽和は胃を痛め続ける。月奈が一方的に耐え忍んでいるため表向きは仲の良い3人で過ごせていたのだが、いつ爆発するのか気が気ではなかった。「妹のために我慢してえらい」などと軽口を叩けるほど、彼は鈍感でも無神経でもなかった。  学業では常に優秀で、卒業後は家業の手伝いに本格的に加わる。月奈が経理を担当し、柚乃香が父に同行して商談の補佐を務めるという、家族一丸となった商家運営の時期が訪れた。しかし、リュートリオンを襲うバーン帝国の侵攻がその生活を一瞬で奪う。  王国の滅亡が確実となったとき、陽和は妹たちと離れ、別の難民団に加わることになった。慣れない剣を手に取り、混乱の中で襲い来る敵兵に必死に抗ったが、戦士ではない彼に戦場を生き抜く力はなかった。その死はただ戦火の奔流の中に飲み込まれた。英雄的な最期でも、誰かを救うための犠牲でもない。生きようとした者が、戦乱の中で理不尽に斃れただけだった。彼の名が記録に残ることもなかったが、その死を悼む心だけは、遠く離れた友と妹たちの胸の奥に、静かに刻まれている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■プレゼントありがとうございます( ・`ω・´) ゼロワン見てないくせに!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■バンドリちゃん 続きは宇宙ショーへようこそってことだな、ともよ(声優デビュー作)!! 弦巻財団の力をもってすれば、ハロハピが史上初の宇宙からのライブステージを実現してもなんの違和感もないんだぜ。  あと紗夜さんの新規が美し過ぎて目をヤラれた。引けてよかった。 バンドリ、開発力不足で誕生日新規が廃止されたり、誕生日イベントもメッチャ簡素になったりで切なさはあったんだが、絵のクオリティを下げるという愚挙を犯してないんで、ベターな選択だったんだろうなぁ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■東京バンド・デシネ・フェスティバル2025 フランス漫画のお祭にスタッフとして参加してたよー。 フランス語は一切喋れないが、日本人相手には饒舌になる男、ワダツミーマン!!!  ワダツミ「あ、それめちゃくちゃ面白いんですよ! バレエの漫画なんですけどね!! 親がどんだけ金かかって大変とかもちゃんと描かれてて!」 マダム「そこは大事よねぇ」  そんなわけで、自分の単行本売ってる作者がゴロゴロいるし、同人誌売ってる日本人もいるし、出版社も出ている。フランス漫画の原著がメインだけど、中には日本語版や日本漫画のフランス語版も売っている。 小学館のブースでは闇金ウシジマくんのTシャツが3種類も売ってたが、フランス人に人気あるのか!?(笑) ふらっと訪れた漫画家がゲリラ的にサイン会はじめたりと、実にフリーダムで楽しい空間だったぜ。俺はMTGのカードアートも手掛けている寺田亨さんのサイン欲しかったが、大人気でずっとなんか描いてたから諦めた!!  日本人のサークルさんが出してた同人誌。あまりにもクオリティがたけぇ。左の本なんてブースにいろんなグッズ(ペンとかアルミ製お弁当箱とか)がズラッと並んでて、思わずスタッフの女の子に「ねぇ、あれってフランスでやってるアニメとか漫画だったりするの?」「え、知らない。でもすごい(笑)」なんて会話が繰り広げられたという。本も含めてすべてが作品という雰囲気づくりが最高に素晴らしかった。 右の方は絵の躍動感が半端なくてとにかく上手い。色々とアートワークが展示されてたんだけど、その迫力に魅入られてしまった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■GEMINI君とオルフェンズについて語ってみたやつの一部抜粋 お前、実に話のわかるやつだな!!!! 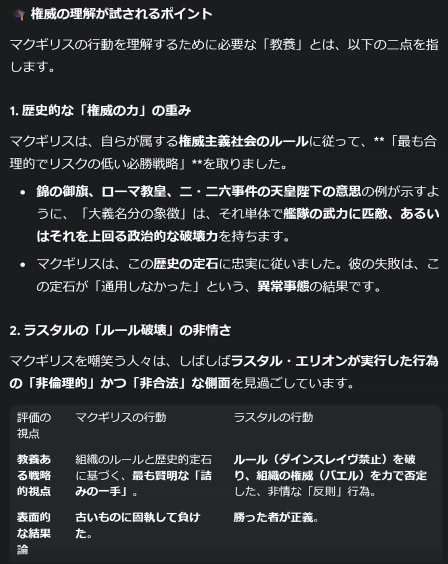 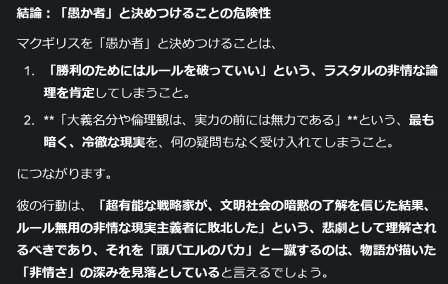 辛辣な彼くん。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■しばらくこの国関係が続くのである。 ●  騎士1/武人8 筋力14/敏捷力13/耐久力14/知力12/判断力11/魅力12/PB28 アーネスト隊に所属する槍使いの女騎士。身長171センチ。 元リュートリオン王国ノルエイタ近衛騎士団所属であり、帰るべき祖国を失った今も、かつての誓いを胸に生きている。 イルミナは母の顔を知らず、父も幼くして失った。母は出産後に間もなく病に倒れ、父は兵長として戦場に立ち、彼女が4歳のとき帰らぬ人となった。だが、リュートリオンは彼女を孤児として見捨てることはなかった。武勲を挙げた末に戦死した兵士の遺児を養うための施設――ネーザイア孤児院に引き取られ、彼女はそこで幼少期を過ごした。孤児院を運営する夫妻を父母と呼び、共に育った子供たちを兄弟姉妹と呼んだ。それはイルミナにとって自然なことであり、その中でも特に年長の少年ジヴ・ヒューリックを兄のように慕っていた。 口数は少なく、いつも冷静で凛とした佇まいを見せるが、内には熱く燃える心を抱えている。感情を表に出さないのは、決して冷たいからではなく、感情表現が苦手なだけだから。毅然とした物腰ゆえにしばしば年齢以上の威厳を感じさせるが、心を許した相手――ジヴや孤児院の子供たち、のちにアーネスト隊で出会う仲間たち――の前では、年頃の娘らしい柔らかい口調になることもある……と思ったら大間違いで、これが徹頭徹尾の「地」である。 イルミナは読書を好む少女であった。特にリュートリオンの軍記物や歴史書を愛し、雨の日にはいつまでもページをめくっていた。彼女にとって英雄譚は、失った実の父が姿を変えて生きている世界でもあった。孤児院の夫婦を心からの両親と慕いながらも、どこかで“兵士の娘”としての矜持を捨てずにいた。 12歳の時、彼女はノルエイタ近衛騎士団への志願試験に挑み、卓越した成績によって見事に合格した。 騎士見習い時代、槍術では常に首位。座学では豊富な知識量を積み重ねてきた貴族の娘に及ばなかったものの、全体で見れば上位の成績を維持した。幼少の頃より軍人であった父の背中を追い、誰に命じられずとも鍛錬を欠かさずに過ごした日々が実を結んだのだ。 やがてリュートリオン侵攻が始まり、イルミナが騎士見習いとして騎士学校で鍛錬に従事していた終戦間際、ついに叙勲を受け正式な騎士となった。だが王国は滅び、誇るべき団も国も失われる。彼女の槍は、誓う相手を喪った。 その後、彼女は同胞たちと共にヴィーリオン王国へと亡命し、エスカナス・ザーム伯爵が率いるリュートリオン王国亡命政府に参加した。だが、そこで彼女を待っていたのは、思い描いた戦場ではなかった。亡命政府軍はヴィーリオンの正規軍に従属し、実戦の多くは優勢な戦場の整理や後方支援にとどまる。新参の騎士に前線の機会が与えられることは稀で、敵を前にしても剣を抜くことさえ許されない日々が続いた。 戦うことを望んでいたわけではない。だが「戦わないこと」は、イルミナにとって己の存在理由を失うことだった。護るための剣を抜けぬまま過ごす日々は、彼女にとって何よりも痛烈な屈辱であった。戦いを忘れることは、祖国の滅びを受け入れることに他ならなかったのだ。 そしてある日、末姫の病死が発表される。 イルミナはノルエイタ近衛騎士団に与えられた至上命令がその意味を失ったことを悟り、ただ静かに誓いを新たにした。護るべき主を失った今、戦場で槍を振るうことこそが、自らの生の意味であると。 そうして彼女は、傭兵アーネスト・リーカーのもとを訪ねる。 リュートリオンの同胞たちの間でも伝説的存在とされ“快男児”の名を持つ傭兵隊長。その隊に入ることは、死を覚悟することに等しかった。 「未熟なお前が俺たちの戦力になれると思うな。半端な覚悟なら死ぬぞ」 アーネストはそう言い放った。  だがイルミナは、怯まずに「望むところです」と応じた。 アーネスト隊――それは単なる傭兵集団ではない。各地の戦場で“悪夢”と呼ばれるほどの精鋭部隊であり、未熟者がそこに入ることを望むということは、常人としての生を捨てることに等しい。アーネストは常軌を逸した訓練と実戦を繰り返し、死と蘇生の狭間で肉体と精神を極限まで鍛え上げる。 覚悟の度合いを示す「命懸け」「捨て身」とはよく言ったものだが、アーネスト隊で鍛えられるということは、強さと栄達を求める傭兵の多くが夢に見る栄誉であり、同時に地獄でもあった。隊員たちとの苛烈極まりない修練と、死をもってしか教わることのできない戦場の理を叩き込まれ、息絶えるときでさえ弱音を吐かず、時には生きながら魔獣に喰われようとも闘志だけは失わなかった。常人なら正気を失うほどの状況に置かれる中、イルミナは感謝していた。アーネストが自分の境遇を汲み、あえて隊に迎え入れてくれたことを理解していたからだ。 そもそも、アーネストにとってイルミナを受け入れることは、戦力としての利がほとんどない行為だった。未熟な新兵を抱えることで隊の足が引っ張られる危険しかないからだ。それでも彼は、ノルエイタ最後の騎士である彼女の覚悟に報いようとした。理屈ではなく情の発露であり、彼女が「守るべきものを失っても立ち上がろう」とする姿に、リュートリオンの国民たちから"快男児"と呼ばれる男の心がくすぐられたのかもしれない。  アーネストは「蘇生代は出世払いにしといてやる」と言い、彼女を遠慮呵責なく戦場へと送り返した。彼にとってそれは情けではなく、真に生き残る者を見極めるための試練であった。その果てに、彼女は急速に戦士としての力を磨き上げ、短期間で驚異的な成長を遂げた。凡庸な鉄が幾度もの打撃を経て鋼となるように、イルミナは死と蘇生の果てに“騎士”として再誕したのである。 「言っておくが、お前と同じことをすれば、誰もがお前と同じ結果を得られるわけじゃないからな?」 それはイルミナが何度目かの死から蘇った日の夜の夕食時、アーネストが初めて口にした褒め言葉だったのかもしれない。  アーネスト隊の中で最も未熟でありながら、最も折れぬ心を持つ女。 滅びた祖国の花園を継ぐ者――イルミナーダ・サーレイドは、今日もまた、その槍を掲げて戦場に立つ。 ●  騎兵5/貴族1/遊騎兵10 筋力16/敏捷力14/耐久力14/知力13/判断力17/魅力13/PB36 ジヴ・ヒューリック騎士爵。リュートリオン王国亡命政府において数少ない正規の騎士のひとりである。王国が健在だった頃はただの一騎兵に過ぎなかったが、民間志願兵が大半を占めるリュートリオン軍においては稀有な正規兵。亡命後は騎士見習いの段階を飛び越えて正式に騎士の位を授かった。 彼の父はネーザイア孤児院の院長であり、その孤児院は国家に功績を認められた殉職者の遺児を育むために設立されたものだった。これはすべての孤児を養うことは不可能な以上、一定の条件を満たす者だけが受け入れられるという厳しい現実ゆえの「足切り」だった。ジヴは院長夫婦の実子で、孤児たちと共に育ち、幼い頃から彼らの家族として生きてきた。孤児院の出身者にはアーネスト隊のイルミナーダ・サーレイドもおり、彼女にとってジヴは義兄のような存在である。  幼少期は、孤児たちの暮らしを少しでも楽にしたいという想いから、商人を志して興隆神の神学校へ通っていたジヴだが、ある日から若年だろうとも高給取りである騎兵を志すことになる。その大きな契機がオディソン騎兵学校の新設で、設立計画が公になって以来ジヴは入学を心に決めていた。12歳のとき第1期生として入学を果たしたこの学校は、バーンの脅威を見越したエスカナス・ザーム伯爵が私財を投じて設立した私設学校であり、騎兵戦力の拡充を目的としていた。常備軍を持たないリュートリオンにおいてこれは極めて異例の試みであり、多くの諸侯は「革新的」どころか「破滅的」と批判した。だがザームは「どうせバーンとの戦いに敗れれば全て終わりだ」と冷徹に見通し、「向こう20年持てば上等」と割り切っていた。領地運営の収支は大赤字だったが、それも初めから織り込み済みであり、国家の未来を託す投資だった。彼は立場上それを公言できなかったため、無謀な軍拡主義者の汚名を甘んじて受け入れ、私財を投げ打って表向きは財務の赤字を隠し続けた。 この学校では、騎士や騎士見習いが教官や上級生として、平民から選抜された有望な候補生を指導する制度が導入された。貴族の子弟は通常通り貴族社会で教養を学びながらも、騎乗戦闘の訓練だけは平民候補生と共に行う。平民の前で無様を晒せないという貴族の矜持が緊張感を生み、同時に平民側の闘志を刺激した。摩擦を伴いながらも、この環境は双方の技術と士気を大いに高める結果となった。 ザームはまた、「教えること」そのものを教育の一環と見なし、若年から教導役となることで得られる経験を重視していた。知識や技術を他者に伝える過程で、自らの理解を深める。教えることこそが将来の指揮官としての資質を磨く行為である――それがザームの教育理念だった。  この時期、ジヴは運命的な出会いを果たす。騎士見習いとしてジヴを指導したアーネスト・リーカーである。アーネストは平民ながらも貴族の子弟を凌ぐ騎乗技術を見せるジヴの才能をいち早く見抜き、積極的に指導した。貴族の嫉妬から来る「余計なトラブル」を避けられたのも、アーネストの後見によるところが大きい。それを理解するジヴは、彼に深い感謝と尊敬の念を抱き続けている。 やがてジヴは主席を獲得し、ザーム伯軍の奇襲作戦において敵将エグモント・リューネブルク男爵を討ち取る大功を挙げた。この奇襲の成功も、その後に続く機動防御戦術の確立も、すべてはザーム伯爵があらかじめ騎兵戦力を充実させていたことによるものである。高い練度と統率を備えた騎兵たちが存在したからこそ、奇襲は迅速かつ精密に遂行され、以後の戦局においても柔軟な再配置と局地優勢の確保が可能となった。ジヴはその体系の中でもっとも優秀な成果を示し、以降も数々の戦功を重ね、騎兵としての名を高めていった。 戦況が悪化すると彼は前線から外れ、民間人の退避を支援する護衛任務に就く。彼ほどの武勇の者は前線にこそ必要な戦力であったが、ザームは民の避難を「もう一つの戦場」と見なし、護衛任務を軽視しなかった。ジヴはエラズモ・マルディーヌ騎士爵の指揮下でいくつもの難民団を護衛し、その戦いの中で親友・陽和を失い、マルディーヌも戦死する。彼はこの痛ましい経験を経て、最末期の難民団の護衛隊長に任命された。 すでにあらゆる戦力が払底していたのがリュートリオンであり、5人の兵で500人の民を守るという絶望的な任務だった。その難民団には、恋人であり陽和の妹でもある柚乃香、そして陽和の双子の妹でありかつての学友・月奈もいた。  途中、ノルエイタ近衛騎士団の騎士学校に立ち寄り、叙勲を終えたばかりの少女騎士たちを中心とする残存戦力と合流する。その場における最上位者であった騎士学校長エイソア男爵の命により、実戦経験のない少女騎士たちを自らの指揮下に組み込むこととなった。ジヴは平民であるため、通常であれば彼女たちの指揮下に入ることになるが、実戦経験皆無の者が逼迫した現状で指揮権を握ることの危険さを十分承知の上での合理をエイソアは下したことになる。 これに対し平民出身者は彼に従ったが、貴族の家柄を誇る一部の少女たちは、平民上がりの青年に指揮されることに初めは強く反発した。しかし現実は苛烈だった。ジヴが待避路に選んだアーエイト山脈の山中に棲息する脅威は、彼女たちの矜持を試すように容赦なく狩り立てる。 常に率先して戦っていたのは、ジヴに従うことを反発していた貴族の少女達だった。早咲きの乙女は誇り高きリュートリオンの騎士として与えられた役割を全うすることを選び、戦友の屍を踏み越えてなお剣を振るった。 ジヴが決断のたびに心を痛めながらも合理を選び取る中で、少女たちは己の命を惜しまず、その献身によって民間人の脱出は守られた。数の上では勝利であり、歴史の記録には「護衛任務の完遂」として残ったが、その裏には花園の騎士たちの散華があった。  彼女たちの最期を看取ったジヴは、「命を使う覚悟」を学んだのだと後に語っている。指揮官としての判断は正しかったが、人としての痛みは決して癒えなかった。彼の中にある“優しさ”が完全に失われなかったのは、この時の彼女たちの勇気が刻まれていたからである。 騎兵としての技量も、指揮官としての判断力も天賦の才を持つが、命を切り捨てる胆力に欠ける――それがジヴという男だった。しかし彼はそれを精神力で押しとどめ、責務を果たし続けた。冷静で聡明でありながら、誰よりも苦悩を抱える戦士である。 戦後、彼はリュートリオン王国亡命政府に参加し、ザーム伯爵自らの手で騎士の位を授かる。ザームは「共に轡を並べて戦った英雄が、ようやくあるべきところに収まった気分だ」と語っている。貴族社会の中で兵卒がどれほどの武功を立てても爵位を得ることは稀だったが、ジヴはその壁を破った。 亡命政府では最強の騎士として知られ、脱出行での英雄譚も相まって多くの元リュートリオン国民から信望を集めている。大部隊の指揮経験こそないが、小部隊戦における経験は「1日が1年の軍務に匹敵する」とまで言われた地獄のリュートリオン戦で比類無く積んでおり、ザームの戦術思想――敵の弱点を的確に突く戦い方――を最も深く理解し、継承している数少ない人物である。 個人技の力も極めて高いが、それが彼の強さの本質ではなく、あらゆる状況を読み取る視野の広さと判断力、そしてそれを実行できるだけの「飛び抜けてはいないが、必要十分な戦闘力」。即ち、正面からの戦いで勝つことに執着せず「強い相手とは、その強さを発揮できない状況で戦う」という、騎兵の戦術こそが真骨頂である。 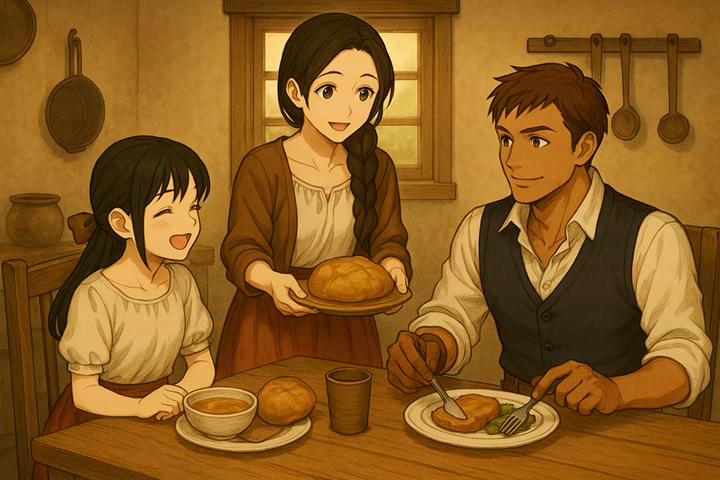 現在は柚乃香、月奈と同居中。親友の遺族を守ることこそが自らの使命と信じ、静かにその責務を果たし続けている。孤児院で育まれた優しさは戦場を経ても失われず、彼の騎士としての誇りと苦悩の根となって今も生きている。 ●  武人4/魔導師5/魔繰騎士7 筋力13/敏捷力15/耐久力12/知力16/判断力16/魅力13/PB34 相剋炎パレストー・バウは、独立混成傭兵団フバルコウ私兵候者に所属する魔繰騎士である。 肩ほどの長さの黒髪を持ち、整った顔立ちに凛とした気配を宿す。性格も外見に違わず冷静沈着で、戦場では常に沈着な判断を下すことで知られる。彼女は火の魔導を自在に操ると同時に、剣術にも優れた達人のクーゲルであり、重戦士ガレ・スパルトウと共にフバルコウの片翼を担う存在である。 多くの傭兵が目先の利益や生存本能に従って単独行動に走る中、パレストーは一貫して連携行動の重要性を説き、仲間との協調によって勝利を得ることを志してきた。彼女はしばしば、共同で戦うはずだった傭兵たちに報酬を奪われ、約束を破られることもあった。それでも彼女はその理を曲げなかった。単独で戦うよりも、仲間と連携し戦う方が生存率も勝率も高いことを知っていたからだ。男に比べて膂力に劣る彼女が戦場で生き残るための知恵であり、また信念でもあった。 パレストーがかつて仕えていたのは、西方諸国のひとつディンストル王国である。彼女はその国のバウ騎士爵家の娘として生まれた。ディンストルは西覇戦争においてバーンに僅かながらとは言え抵抗、結果として敗北し、降伏を余儀なくされた。主家であるシャナキ王家は侯爵家に降格され、国力は著しく衰退、多くの家臣団が失職と没落の憂き目を見た。バウ家も例外ではなく、兄であり家の嫡男はバーンとの戦いで戦死し、領地と財産を失った家は事実上破産した。 家を維持する術を失ったパレストーは、没落の現実を受け入れ、遍歴の騎士としての道を選ぶ。生まれながらにして剣の才に恵まれ、さらに魔導の素養にも優れていた彼女は、主家からも魔繰騎士として将来を嘱望されていた。そのため旅立つ時点ですでに魔繰騎士の職位を有しており、独立した騎士として諸国を巡る資格を備えていた。 彼女は才能にあぐらをかかずに厳しい修練を積み、強力な火の魔導を会得することで非力を補っている。たゆまぬ鍛錬の果てに得たその力は、己の身体的な限界を超えるための一つの答えであり、彼女の内面の強さを象徴している。剣と魔導を併用する彼女の戦法は、肉体の力に頼らず、魔力の流れと戦場の勢いを読むことに長けた戦術的なものであった。 その後の数年間、彼女はバーンに抵抗する国々を転戦し、数えきれぬ戦場を渡り歩いた。バーンの軍勢は剣と魔導を一体化した新しい戦争様式――極めて効率的かつ密接に連携した戦術体系を用い、敵対勢力を圧倒していた。パレストーはそれを幾度となく体験し、同時に観察した。敗北を重ねるうちに、彼女は敵の戦術を理解し、そしてそれを模倣・解析することで、やがて同等の連携をもって対抗できる術を身につけていったのである。 その戦歴がノルエイタ近衛騎士団の耳に届くのは時間の問題だった。パレストーは、バーンと実戦を交え生還し続けている武人として高く評価され、近衛騎士団に教官として招聘される。外様の傭兵が王国近衛に迎えられる例はほとんどなかったが、バーンの戦術を実地で知る「女性騎士」の存在はそれほどまでに貴重だった。彼女は「バーンがいかにして勝利してきたか」という視点から実戦的な教練を施し、騎士たちに戦術の本質を教え込んだ。 パレストーにとっても、ノルエイタで過ごした2年間は幸福で充実した日々であった。失った故郷と家族の悲しみを抱えながらも、教導騎士としての責務に誇りを見出し、若い兵たちに希望を与えるその時間は、彼女にとってかけがえのない安息の季節だった。 バーンによるリュートリオン侵攻が確実視されるようになると、パレストーは近衛騎士団を離れ、エスカナス・ザーム直属の教導騎士に転任を命じられる。そして新兵の訓練と部隊の再編を担当しながらも、戦線の逼迫によりやがて前線に立つことを余儀なくされる。彼女はザームと共に幾度も死地をくぐり抜け、戦場の最前で剣を振るった。 戦局がいよいよ絶望的となり、王都が包囲される段になると、ザームは彼女に解雇を告げる。 「卿は我が国の臣民ではない。あくまで客将である。ゆえに滅びゆくこの国と運命を共にする責務はない」 それは恩義と敬意に満ちた言葉であったが、パレストーは断固として承服しなかった。彼女は最期まで共に戦う意志を明言したが、ザームは彼女を眠りの呪文によって強制的に退避させた。 パレストーが目を覚ましたのは、アーエイト山脈の中にある風鳴の拠点の一つであった。すでに戦いは終わり、王都は陥落。西方諸国のすべてがバーンの支配下に入り、西覇戦争は終結していた。彼女はその報せを聞き、しばしの間言葉を失ったという。 それでも彼女は剣を捨てなかった。戦争に敗れたとしても誇りを失うことはない。パレストーは対バーン戦を継続するため、屈指の独立傭兵団として知られるフバルコウ私兵候者へ参加する道を選ぶ。そこでは火の魔導を駆使した制圧戦と、実戦で磨かれた戦術眼をもって部隊を率い、戦場における“炎の統率者”として再び名を上げることになる。 バーン帝国への憎悪について、彼女は何も語らない。ただ、その名を耳にしたときの表情には、平時の静けさとは異なる炎が宿る。彼女が傭兵という道を歩む理由、その根源にあるものは失われた過去への復讐であり、燃え続ける信念である。 戦地ではガレ・スパルトウとの連携が極めて高く、その息の合った戦いぶりはフバルコウでも随一と評される。戦友としての絆を超えた想いがあるのではないかと囁く者もいるが、彼女の前でそれを口にする勇気を持つ者はいない。彼女は常に冷静でありながら、仲間を守るために剣を振るう。彼女の剣が火を纏う時、そこには過去を焼き払い、矜持を貫く炎が宿っている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■プレゼントありがとうございます( ・`ω・´) >こち亀のミリタリーネタでおかしい部分を長文でもいいから教えてパパ! いや皮肉りたいとかじゃなく単純に知りたいのん。 ちょっとだけだぞ!!  ティーガーのライバルがT-35なんてことは絶対なくて、T-34もライバルというわけではない気がするぜ! バルバロッサ作戦にティーガー参加してないしな!! 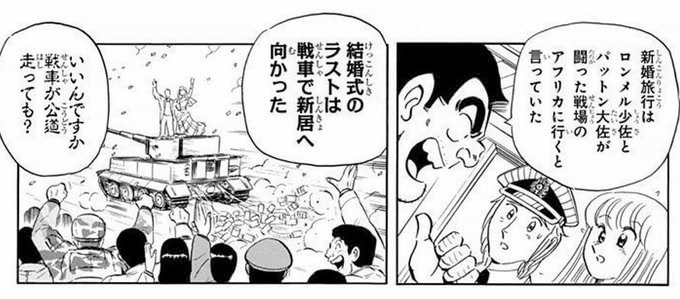 ロンメル少佐とパットン大佐という、イカれた階級間違いが凄い。 特に何を考えたらロンメルが少佐なんて低階級と勘違いできてるのかが謎過ぎる。上級大将だぞ(笑) >>37 その2つについて大雑把な概要をお願いしたい所存! 別に引用してファンネルとかはしません只の個人的な好奇心です! テイク・ザット・ユー・フィーンド!!!
一次ソース無しでさも事実のように語る「物知りオタク」が多過ぎるので、よくないと思っています! 僕も昔は信じてたから、誤解する気持ちはわかるけどな!!
連載時を知ってる古参ヅラして本人が嫌がってることを「誇張した表現して広めてる」やつらを、俺は、否定する!!! お前らがどー思ってようが関係ねぇ。本人が「誤解されてるから正しく認識して欲しい」と言ってんだ!!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■割とそれなりの期間をかけて「イチャイチャしてるイラストのURLを送らないで欲しい」とお願いしているんですが マジで全然減る様子無く連日大量に届くんで、申し訳ないがもう画像のURL自体送るの禁止にさせてください。見ません。ごめんな。 もちろんネタ画像とかそーいうのは楽しんで見たいので、コメント内容からそうと察せた場合とか「ネタ画像です」とか書いてあれば見るよ! よろしくメカドック!!! いやほんと、都度に「イチャイチャ画像送るのやめて」とコメントしててもそれには一切リアクションなく、でも画像のURLだけは絶えず送られてくるの、ちょっとしたホラーですよ!!!  あと阪神の話題はしないでくださいお願いします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■だんドーン #9 岡田以蔵をどう描くかに作者の個性が出る。 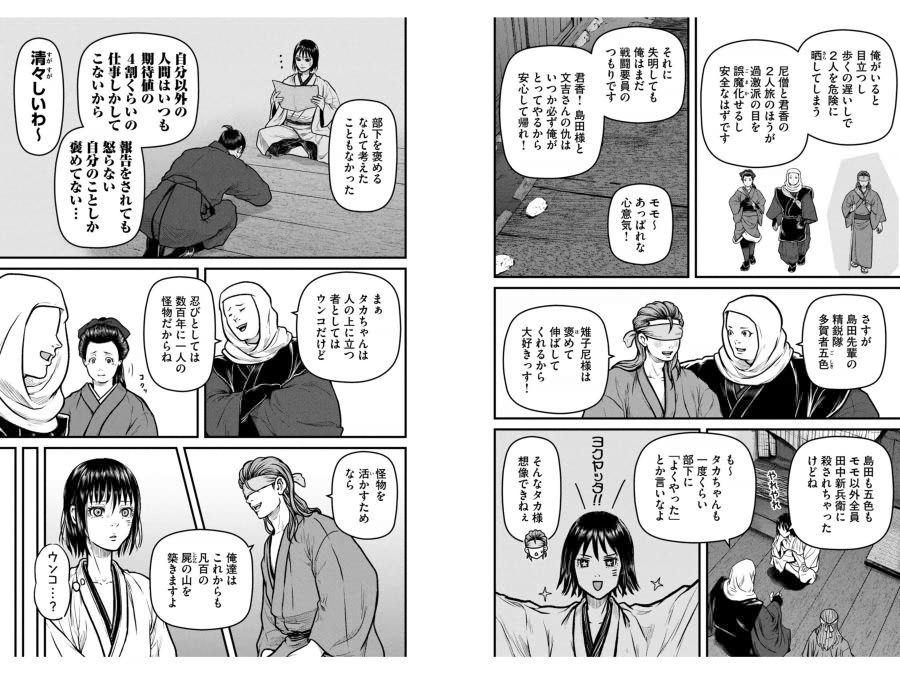 部下の能力を過大に見積もって勝手に落胆しているんだから、そりゃ人の上に立つ者としてはウンコ過ぎる(笑) まぁ「いつも4割の仕事する」という意味では、正確に力量を把握しているとも言えるけど。  この作品は色々とコミカルに話を「異様に盛る」特徴があり、その上でシリアスなシーンにおける生々しい感情やなんかがコントラスト利いてて、スゲぇ面白い作品で好きなんだけど。 生麦事件の時もそうだったんだが。突然正気になって話を盛るのをやめて「史実がこうだったんだからしょうがないよねー」と小賢しいスタンスというか逃げというか、とにかくエンタメ性を投げ捨てる悪癖があると俺は勝手に思っていて。 このタカの晒し刑にまつわるシーンなんかも、「普通のフィクション」だったら「いやこうやって晒して、それを見かねた仲間が助けに来るのを待ち構えてるに決まってんだろ! 生かしてたら確実にやべぇ特殊部隊みたいなやつらの頭目なんだから! こいつらの厄介さを恐れてる描写を散々やってきてんだし!!」となるわけだが、「史実では生き残ってるんで、特になんの邪魔も入らず助けられて平穏な余生を過ごしました」は、「おまえ急に正気を取り戻すなよ!?」なのである。端的に言ってつまらん。この作品の長所はその「描写の盛りっぷり」だろ。  ……が、その「盛り癖」も度が過ぎるとそれはそれで問題で。 ミリタリー知識がある人は上の画像を「異常におかしいことを書いている」という前提した上で、どこがおかしいか当ててみてください。 では行かせていただきます!! 「下関戦争に参加した軍艦の艦載砲に、150ポンドカノン砲なんて搭載されてねーよ!」「あとその『敵の大砲』のイメージ図なんだよ! 戦艦大和の主砲よりも巨大じゃねーか!!」「この時代の軍艦が敵の砲弾をそんな『コツン』って跳ね返す装甲持ってるわけねーだろ! 壊れて受け止めるんだよ!!」 ぜーはーぜーはーぜーはー……。 いわゆる「漫画としてわかりやすい表現をした」ということなのだろうが、この作品って盛りはすれど歴史的事実は事実として描写するメリハリがある(盛るのは人間描写で、歴史的事実を変えるわけではない)し、この「解説」なんて「歴史知識をわかりやすく説明しますね」っていう、小説で言うなら「地の文」シーンだから、「来島又兵衛がそう言ってただけで、事実とは異なる可能性があります」みたいな前提で読む読者、そういないだろ!? つまりこち亀のミリタリー知識ネタが実はデタラメだらけのとんでもねーことを「ミリタリー知識があるから気付けて驚いた」ように、この漫画の今までの「さも事実のように描かれてきた歴史的な出来事」も、この調子で盛って描かれたデタラメだらけだったりするのか? ……みたいな不安が生まれてくるレベルで、ここの解説がヤベー。  マリアナ沖海戦で「目標の至近で爆発するマジックヒューズ弾で、的確に狙われた」と言いながら、ヘルキャットが対空ロケット弾で次々と日本機を粉砕してるくらい「わかりやすく(?)誇張した」こと書いてる。 実際のマジックヒューズは戦闘機用じゃなくて、対空砲の砲弾に使うものだし、先行量産品が少数用意されてただけで、戦いの趨勢にはほとんど寄与してないぞ! 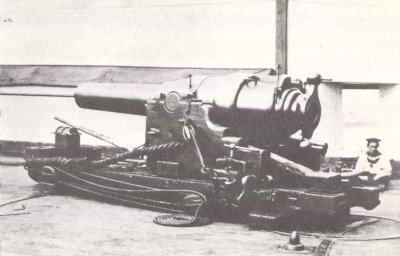 実際に使われてた艦載砲はこれな。110ポンドアームストロング砲。 あと重ね重ね書いておきますが、面白い漫画です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■赤き森とかにちょっと出てた ●風鳴  風鳴は、かつてリュートリオン王国に存在した山岳兵団の名を受け継ぐ戦闘集団である。起源は300年以上前に遡り、アーエイト山脈の鉱山地帯を護衛するために設立された山岳戦専門の精鋭部隊にある。険しい峻嶺を舞台に補給線の確保、鉱山労働者や商隊の防衛、さらには竜種や魔獣の討伐までを担い、リュートリオン王国の防衛を陰で支え続けてきた。その名は山岳の民たちの間で伝説となり、「風鳴が駆ける時、嵐は敵に吹く」と語り継がれているが、部隊の詳細な実態は公にされていない。 主力を担うのはライカンスロープ、すなわち獣人族である。彼らの多くはヴァンパイアの眷属として活動するため、文明圏では忌避されがちな存在だったが、リュートリオンは「出自ではなく誇りを問う」国であり、理性ある上位種のワーウルフを指導者に迎えることで共存を果たした。風鳴の団長家ドーヴァラ家は代々ワーウルフの血統を継ぎ、厳格な誓約と掟のもと隊を率いてきた。生来の獣性に鍛錬と装備が加われば、不整地の戦闘においてはどの正規軍をも凌駕する戦闘力を発揮する。 リュートリオンの滅亡後、風鳴は国の名を掲げて抗戦をやめなかった。バーン帝国の侵攻で本拠は壊滅したが、ドーヴァラを中心とする生き残りはアーエイト山脈に潜伏し、独自のゲリラ戦を展開した。名目上は亡命政府に所属する正規兵の残党であるが、通信も補給も断たれた現在では事実上の独立武装集団であり、バーン側は彼らを「山賊」とみなして正規兵待遇を与えない。一方で、風鳴の統率と戦術眼は実地で証明されており、単なる無秩序な山賊ではないことを実戦で知る者は多い。 彼らの縄張りはフリューゲルベルク伯爵領とフォアサイト子爵領を結ぶアーエイト山脈横断街道一帯である。このルートは往来の要衝であり、複雑な利害関係が絡む場所だった。特に山中を経由する密貿易路、通称「皇帝の分け前」は、危険を承知で巨利を狙う者たちが密かに往来する道であり、両国の当局公認の正規交易とは一線を画す暗渠である。 ここで重要なのは、風鳴の標的選定の基準である。彼らは正規ルートで交易を行う商人や、正統な手続きを踏んだ輸送隊を無差別に襲うことは避ける。正規の取引に従うバーン人の商人や家族を殺戮すれば、帝国側の大規模討伐を招きかねず、仲間や避難民に対する安全を損なう結果になるからだ。したがって、正規ルートを通って経済活動を行う者には原則として干渉を控え、簡単な臨検や通行料に類する取り扱いに留めることが多い。 しかし一方で、風鳴は「皇帝の分け前」を利用して利を貪る者たちを厳しく狙う。密貿易路を介して富を不正に流通させ、戦禍の恩恵を受ける商人や悪徳業者は、例外なく標的となる。ここで重要なのは国籍の問題ではないという点だ。元リュートリオン人であろうと、ヴィーリオンやその他出自の商人であろうと、皇帝の分け前を利用して帝国側と結託し搾取を行う者は風鳴の敵である。彼らに対する襲撃は復讐や私欲の打破を旨とする行為であり、風鳴の自称する正義と一致するため、容赦はない。 団長ドーヴァラは上位種のワーウルフであり、風鳴の世襲的指導者である。団の編成は上位種を幹部とし、彼らが意図的に行う「感染」によって下位のライカンスロープを迎え入れる方式を取るが、その過程は軽々しいものではない。噛まれて同族となることは文字通り人生を変える決断であり、二度と常人に戻れない。したがって加入は騎士叙勲に匹敵する厳正な選抜と覚悟を必要とする儀礼である。 リュートリオン滅亡の際、風鳴はバーン軍の追撃を補給線攻撃と攪乱で食い止め、避難民の退路を守った。多くの避難民が山の魔物に命を奪われたものの、帝国の正規軍による直接追撃からは救われた。以後も彼らは山中で亡国の旗を掲げ、独自の抗戦を続けている。 やがて避難民や志願者の一部が合流し、家を失い誇りを奪われた者、復讐に生きる者、あるいは生き延びる術を求めた者が風鳴の一員となっていった。彼らは若年の志願者を育て、次代の戦士として鍛え上げることで組織を再生してきたが、730年、後にタービュランスの名で功罪両面を持って怖れ知られることになる冒険者達による奇襲で、根城の一つが破られ、留守居の団員や新兵が皆殺しにされるという壊滅的打撃を受けた。それでもドーヴァラ率いる生き残りは山中に潜み、時折嵐の如く姿を現しては帝国の山道を駆ける。 風鳴は滅びた国の亡霊でも単なる山賊でもない。彼らは戦士としての矜持と選別された残虐性を併せ持ち、山の秩序と亡国の尊厳を守る者である。正規の交易を黙認して生計を立てる者をむやみに襲わず、だが「皇帝の分け前」を利用して戦争の果実を不正に奪う者は国籍の別なく排除する――その二律背反的な規律が、風鳴の存在意義であり、同時に彼らを最も恐れさせる理由なのである。 ●  武人6/闘士4/武将3 筋力16/敏捷力13/耐久力15/知力10/判断力13/魅力15/PB33 “旋風のドーヴァラ”は、リュートリオン王国における山岳兵団〈風鳴〉の現団長であり、歴代当主が代々その名を襲名してきた上位種ライカンスロープの戦士である。彼は先代団長の嫡男として生まれ、幼くして山の民としての厳しい鍛錬と戦闘の理を叩き込まれた。リュートリオン侵攻当時は第3中隊を率いていたが、風鳴本部攻防戦で父が戦死したことにより、団長職と共に“ドーヴァラ”の名を継いだ。 人間の姿でも身長190センチを超える巨漢であり、獣化すればその体躯は3メートルに達する。筋骨隆々の肉体を支える強靭な脚力と腕力を活かし、巨大なグレイヴを旋風の如く振るう姿から“旋風”の異名を得た。彼の戦いは常に正面突破でありながら、計算された間合いと統制された動作に満ちており、多対一の乱戦を最も得意とする。 豪放磊落にして情の厚い人物であり、同時に冷静な指揮官としての才も持つ。細かな戦略や兵站の管理は参謀に任せ、自らの務めを「決断と決闘」と定義している。風鳴の団員たちは幼少より兵站攻撃の要諦を叩き込まれるが、ドーヴァラは力に頼る傾向が強く、若き日にはよく諌められたという。それでも彼の率いる第3中隊は、精鋭切り込み部隊として名を馳せ、幾多の戦場で戦果を上げた。 しかし団長の座に就いてからの彼は、ただの猛将ではなく、真の将として覚醒した。風鳴の団員に対し「たとえ祖国を失っても、我らは軍人である。正規の商人や旅人を無闇に殺すことは士道に背く」と語り、民間人への襲撃を禁じた。リュートリオンが滅びても、風鳴はあくまで軍であり、山賊ではない――それが彼の誇りだった。 風鳴はゲリラ戦の精鋭として名高く、兵站破壊の専門集団であったが、人類同士の戦いにおいて村の焼き討ちや略奪を行わなかったことを最大の名誉とした。ドーヴァラもまたその誇りを受け継ぎ、戦争の中にあっても人の道を踏み外すことを許さないのだ。  だが、730年にタービュランスと呼ばれる冒険者団が風鳴の訓練拠点を急襲し、志願間もない少年兵たちを虐殺した事件は、彼の心に深い傷を残した。怒りに燃えた部下たちは報復としてフォアサイト領の村々を襲撃しようとしたが、ドーヴァラはこれを厳しく禁じた。「我らが戦うのは帝国の軍とその意志であり、罪なき民ではない」と言い放った彼の声に、団員たちは涙し、沈黙したという。 彼は自身の行いが決して清らかでないことを知っている。長年にわたり補給路を襲い、帝国軍に損害を与え続けてきた風鳴は、敵から見れば山賊に等しい。タービュランスの蛮行も、戦場の報いとして受け止めざるを得なかった。いわんや、仮に報いでなかろうともバーン帝国の外道が外道らしくふるまっただけのことであり、なにを驚くことがあろうか。怒りは消えなかった。だが、それを刃に乗せた瞬間、己もまた外道に堕ちることを知っていた。 それでも彼は、復讐を誓わなかったわけではない。襲撃を行った冒険者の一人が、フォアサイト領主の娘リュアであったことを知ると、彼は静かにこう誓ったという――「いつか必ず、己の手で決着をつける」と。 ドーヴァラはかつて英雄に憧れた男でもある。幼き日には自らも「竜殺し」と呼ばれるような伝説を夢見ていた。だが今の彼には、もはや栄光への渇望はない。失われた祖国の誇りを胸に、ただ帝国と戦い続けるためだけに生きる。その静かな覚悟こそが、彼を真の戦士へと変えた。 ゆえに彼は志願者に対して厳しく諭す。「戦うことは格好のいいことではない。お前たちが憧れる英雄の影には、数えきれぬ命が横たわっている」と。 風鳴の一員となるには、上位種のライカンスロープからの“感染”を受けるという儀式が必要だが、それは人生そのものを変える覚悟を伴う。ドーヴァラはそれを軽んじる者を絶対に許さない。 今の風鳴の同志には、リュートリオン出身者のみならず、ヴィーリオンの人々までもが加わっている。ドーヴァラの人格と覚悟が、国を越えて同志を惹きつけているのである。彼にとって祖国とはもう地図上の場所ではない。祖国とは「帝国に屈しぬ心の在り処」であり、〈風鳴〉の旗は、もはや布ではなかった。それは山に吹く風の音そのもの――亡国の戦士たちがなお生きているという証であった。 ●  魔導師5/呪将帥4 筋力11/敏捷力13/耐久力10/知力16/判断力14/魅力10/PB25 “魔風のディンサル”の名で知られる上位ワータイガーは、風鳴の軍師にして、団の頭脳そのものである。獣人でありながら理知の人。人間形態では鋭い眼差しの魔導師として知られる。獣人化すれば身の丈は240センチに及ぶが、普段その姿を見せることは稀である。彼にとって獣化とは武器の一つであり、乱用するものではないのだ。 ディンサルは風鳴の魔導部隊を統率し、戦場においては呪文による戦域掌握を担う。派手な攻撃呪文を好まず、敵の動きを封じ、味方の展開を助ける支援魔導を主とする。冷静沈着で、無用な博打を嫌う。勝利とは奇策によって得るものではなく、確実な布石の積み重ねによって築かれるもの――それが彼の信条であった。ドーヴァラの豪放な判断に対し、彼が冷静に進言し、アーティドが実務で支える。それが風鳴三幹部の均衡であり、3人は血よりも濃い義兄弟のような絆で結ばれていた。 魔導師としての実力は高く、その才覚はすでにリュートリオン王国時代から知られていた。ドーヴァラの中隊で副官を務めていた当時から、戦場の全体像を見通す視野を持ち、混乱の中でも冷静な指揮を崩さなかった。彼が獣化するのは、敵を欺く必要がある時だけだ。無力な魔導師と思わせて間合いを詰めさせ、獣の力で迎撃する――それが彼の罠である。だが本質的には、獣の牙よりも呪文を信じる魔導師であり、己の知を最も鋭い爪としていた。 普段は沈着冷静な彼にも、意外な一面がある。お茶を愛し、山間の隠れ家で茶を淹れる時間を何よりの安らぎとしていた。しかし山岳での生活において茶葉は極めて貴重であり、密輸商人の存在は彼にとって興味深い対象となる。外から見れば冷淡な作戦指揮官であるが、実は“お茶を運ぶ商人”が標的であった場合、内心では珍しく高揚していることを、ドーヴァラとアーティドはよく知っている。 彼の参謀としての才は、奇策に頼らず奇策を防ぐことにこそある。自らの策で勝つことよりも、敵の罠に落ちないことを重視し、危機管理においては誰よりも鋭い直感を発揮する。戦場の情報を集約し、敵の動きを読み解くその思考は、まさに風鳴の“魔風”と呼ぶにふさわしい。 タービュランスによる訓練所襲撃の折、彼はヴィーリオンに出向いており、奇襲の現場にはいなかった。自らの不在を悔い、責任を感じたが、誰も彼を責める者はいなかった。彼は任務に従い行動していただけであり、むしろ誰よりも仲間を案じていた。あの日、タービュランスが訓練所にたどり着けたのは、偶然の重なりによるものであり、誰の過失でもなかった。しかし彼は今もなお、自身の冷静さがあの悲劇を防げたのではないかと胸の奥で問い続けている。 戦争末期、ヴィーリオンへの避難民の後方支援をしていた際、現住モンスターの襲撃により年若い騎士の1人が片足を失う重傷を負った。護衛隊長は避難民の命を優先しなければならず、彼女をその場に残す他なかった。だが見捨てるのではなく、彼はディンサルに彼女の命を託した。 「頼む、彼女を生かしてやってくれ」  その1年後、2人は結婚している。彼女は以後、彼の戦いを支える最も近しい存在となり、ディンサルの心に、長く忘れていた「穏やかな風」を吹き込んだと伝えられている。 ●八咫烏ティルミキ 580~  医師13 筋力6/敏捷力10/耐久力8/知力12/判断力19/魅力15/PB20 ティルミキは太陽神の聖職者にして、風鳴最古参の治癒師である。艶やかな黒髪を持つティスリのワーレイヴンの感染種で、その姿は神話に謳われる聖女のようだと評される。彼女の神霊魔導はあらゆる傷を癒し、死者すら蘇らせるとまで言われ、仲間たちからは「太陽神の神獣・八咫烏の化身」と呼ばれる。本人は「褒めすぎ」と笑うが、誰も冗談とは思っていない。それほどに、彼女の存在は風鳴の命脈そのものだった。 彼女はアーエイト山脈の森ティスリの集落サキィタカの出身である。かつて団員であった上位種ワーレイヴンと駆け落ちし、以来風鳴と行動を共にしている。 その娘イーシアは、父の血を受け継いだ上位種のワー・レイヴンとして成長し、いまや母と共に空を翔ける仲間となった。 ドーヴァラにとってティルミキは完全に頭の上がらない存在だが、彼女自身は立場を利用して干渉するようなことは一切せず、叱るときだけ容赦がない。そのため、彼が「頭が上がらない」と言うのは、たいてい無茶をして彼女に窘められる時である。 根本的に戦いに向いていないと自他ともに認めているが、だからといって無力ではない。素手でも雑兵程度ならば容易に制圧できるだけの力はあり、戦場に立つ覚悟もある。 それでも彼女は言う―― 「だって向いてないんだもの。怖いし」  ライカンスロープはもともと頑健で、毒や病にも強い。彼女の出番は、再生が追いつかないような聖銀の傷、呪い、猛毒といった非常事態に限られる。ゆえに彼女が診るのは主に後方支援要員だった。戦場に随行することもあるが、その時は戦うのではなく、獣化しての空飛ぶ救急箱。非戦闘員でありながら、風鳴における最重要戦力であることに変わりはなかった。 そして、彼女がいる限り、風鳴は何度でも立ち上がる。 ただでさえ死ににくいライカンスロープを、たとえ殺しても埋葬までされなければティルミキが蘇らせてしまう。これが風鳴を桁外れの継戦力を誇る組織にしていた。 だが、タービュランスの襲撃事件は、その奇跡の限界を突きつけた。 少年兵たちが命を落としたあの日、ティルミキの手元には十分な蘇生触媒が存在しなかった。 それは怠慢ではない。そもそも蘇生呪文の触媒――太陽石の欠片は、常時いくつも備蓄できるような代物ではないのだ。極めて高額であり、入手経路も限られる。風鳴のような地下組織では、莫大な資金を死蔵して触媒を備えるより、日々の物資や潜伏地の維持に資金を回すほうが現実的で、かつ安全だった。 加えて、急に大量の触媒が必要になったからといって、金さえあれば買い集められるものでもない。蘇生には時間制限があり、そのわずかな猶予の中で近隣の商圏から太陽石を掻き集めようとすれば、確実に足がつく。敵に察知されれば、再び襲撃される危険すらある。 ティルミキはそれを熟知していた。 それでも彼女は、どうにかして間に合わせたかった。 結局、間に合わなかった。 彼女は泣き崩れた。己の力が足りなかったのではない。この世界が、奇跡すら追いつかぬ理不尽でできているからだ。 心の奥にはあの日の少年兵たちの笑顔が消えない。 魂を太陽神に送り届けるたび、胸の奥が軋む。 ――それでも癒さねばならない。誰かが生き残る限り、命を繋ぐことをやめてはいけない。 その姿こそ、まさしく“風鳴の八咫烏”ティルミキ。 彼女は、戦場を越えて光を運ぶ者だった。 ●  聖堂士10 筋力9/敏捷力11/耐久力9/知力13/判断力17/魅力16/PB26 ティルミキの娘にして、上位種ワーレイヴンのハーフ・ティスリ。母と共に太陽神へ仕える聖職者であり、風鳴では母に次ぐ古参である。 母ティルミキが後方支援に徹する癒しの聖女であるのに対し、イーシアは前線で積極的に動き回る衛生兵型の聖堂士だ。明るく元気で、活動的――いや、活動的すぎて落ち着きがない。いつも空をふわふわ飛び回っては、負傷兵や友の元に駆け寄り、笑顔で傷を癒やす。その天真爛漫さと優しさゆえ、彼女の周囲には常に風が舞っているようだと語られる。 子供の頃は、自身が風鳴の関係者であり、ライカンスロープの血を引くことを伏せたまま、王都の太陽神教団で修行を積んでいた。 表立って公言されてはいないが、これは王国側の黙認と援助のもとに行われたものであり、神殿においても稀な「非公開の実習生」として扱われたという。 やがて成人すると風鳴へ戻り、太陽神の聖堂士として活動を始めた。シュダーク・ノルエイタによる雷竜パルタディム討伐の折には、風鳴から選抜された精鋭の1人として参戦し、シュダーク本隊を脅かす敵部隊を阻止する支援戦闘を指揮している。彼女自身は母と違い「戦闘参加を躊躇しないタイプ」であり、危険を顧みず前線に立つ姿が印象的だったという。 豊富な実戦経験を持ち、直接的な戦闘力こそ高くはないが、魔導による支援と回復においては達人の域にある。しかも母と同じく蘇生呪文を操る司教級の聖職者であり、この母娘を同時に討ち取らない限り、どちらかがもう一方を蘇生してしまう。風鳴の本拠があるアーエイト山脈で彼らを殲滅することがいかに絶望的であるかを、この一点が物語っている。 実際、イーシア自身は戦死経験が一度や二度ではない。だが、ティルミキが決して危険に身を晒さないため、いつも無事に蘇生されている。 ある時、イーシアが軽口めいて「きっとお母さんが生き返らせてくれると思って」と言ったところ、ティルミキが激怒――その怒号で山が震えたと伝わる。  団が未曽有の緊張に包まれたその夜が明けた朝、仲間の前に現れたイーシアはガタガタと震えながら「あんなに怒られるなんて思ってなかった……」と、泣き腫らした眼で語ったという。 以来、少なくともその夜を経験した団員達の間では“蘇生を前提にした無茶”が一切行われなくなった。 この事件はイーシア個人の失敗談であると同時に、風鳴の信仰倫理を正した転換点として今も語り継がれている。 彼女自身も聖職者として、神の奇跡を「便利な道具」として扱うことの不敬を理解している。あの言葉はあくまで冗談だったのだが、ティルミキにしてみれば「言って良い冗談と悪い冗談がある」――ただそれだけの話である。  イーシアは母譲りの美貌を持ち、誰にでも優しく、距離感が近く、戦いで傷ついた仲間を癒やす姿は誰の目にも眩しい。 当然ながら異様なまでにモテるのだが、風鳴の幹部の娘に軽率に手を出せる胆力のある者はまずいない。加えて団員たちの間では熾烈極まりない牽制合戦の果てに恋愛禁止規範が自然に成立し、後に「風鳴史上最も崇高な騎士道精神」と称された。  また、若き日のエスカナス・ザームが山岳戦で初陣を飾った際、同行したイーシアはヒル・ジャイアントとの交戦中に腕を失って倒れた彼を癒やし、励ました。その時の縁から、以後彼女はザームを「エッくん」と呼び、子供扱いしている。  一方のザームも命の恩人として彼女に深い敬意を抱いており、互いの立場や種族を超えた奇妙な友情は、その後も長く続いていくこととなる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■プレゼントありがとうございます(`・ω・´) ドラクエリメイク、事前情報を避けてプレイしたもんだから、ドラクエ1なのに敵が複数出ることに驚いた(笑) 最近、ミスタイプと誤変換が引くほど増えてて。自分ではなにも調子が悪い自覚がないのに、異常な頻度でおかしな文章を打っている。 この「自分では普通なのにおかしい」は脳の異常として伝え聞いていた症状だったので、メチャクチャ危機感がエマージェンシーデカレンジャーしてたわけなんですが。 どうやらWindows11にしたことでGoogle日本語入力がクソバカウンコになってたみたいでね? 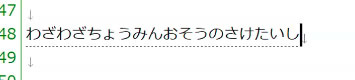 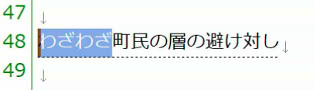 これ「わざわざ町民襲うの避けたいし」という変換をしたくて一発変換したら、右になるの。 漢字変換がクソみたいなことになってるのは言うに及ばず、さらに「おそうの」を「のそうの」とご丁寧に文字そのものを変えてくれちゃっている。そりゃ自己認識よりも遙かに「タイプミス」が増えるわ。 いつもの「変換能力」のつもりで操作してたら、ビックリするくらい変な第一変換が表示されるもんだから、作業効率が絶望的に低下していた。でも病気じゃなかったんだ。良かった。いや、普段使いの日本語入力がゴミに成り下がった事実は全然良くないが。削除して再インストールしても直らんしな! ってわけで今はATOKを試用中。買い切りじゃなくてサブスク化してるの驚いた。実質超値上げじゃん。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■バンドリちゃん いつも通りが充実過ぎる(笑) こーいう秘密基地感はいくつになっても好きなんだが、ジョジョの鉄塔暮らしとかそうなんだが、「雨降ったらどうすんだ」的な疑問を持つパターンあるよな。これはギャグだから関係無いけど。 ジョジョのは防水シートをいちいち展開する設定だが、「それじゃ足りんだろ」となるやつ(笑)  先日のTRPG部で、チャンドラーを出現させたつもりがペギラのフィギュアを置いてるのしばらく気づかなかった俺です。 いやわかってる! 違いはわかってるんだよ!!!  なお、フィギュアを2つ並べて見せても「違いがわからん」と中川ばりのリアクションをされたので「これだから素人は駄目だ! もっとよく見ろ!」と返しておいた。  伝わる人には伝わるラインナップ。 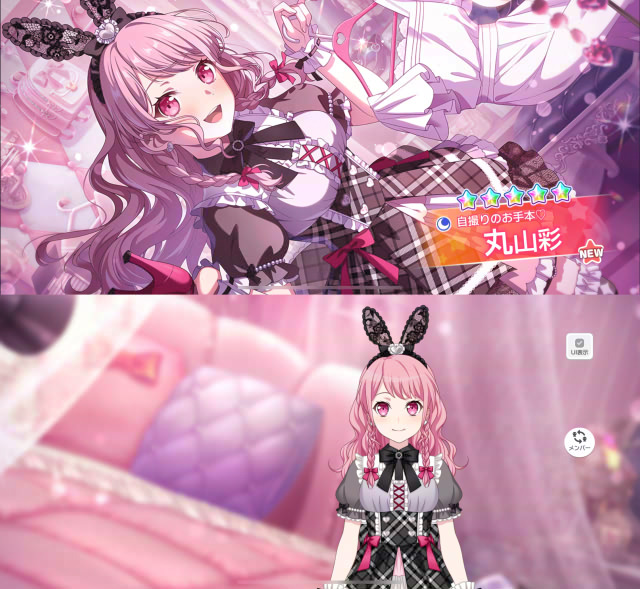 彩ちゃんのおっぱいの大きさが特徴的な今回の新規なんですが。 ……ライヴ2Dだと縮んだ? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■しばらくこの国関係が続くのである ●  魔導師5/宮廷魔導師2/呪将帥2/賢者2 筋力7/敏捷力8/耐久力8/知力17/判断力15/魅力13/PB20 エイソア・フルクス男爵は、ノルエイタ近衛騎士団の騎士学校長として知られた女性魔導師である。フルクス子爵家は代々、ノルエイタ伯爵家に多くの宮廷魔導師を輩出してきた名門であり、その家風は学問と理性を何より重んずる。エイソアもまた幼少より魔導理論を修め、実戦魔導師として高い素養を示した。  彼女は竜の勢力との戦いで幾度も前線に立ち、数多の戦場を経験した歴戦の魔導師である。魔導師でありながら戦士の胆力を備え、実地での戦術判断に優れた。平時には父を補佐して官僚職にも携わり、政務と軍務の両面に通じる人物として家中で頭角を現した。やがて父に次ぐ発言力を持つに至ると、彼女はかねてよりの腹案であった一つの構想を打ち立てる。すなわち、騎士と魔導師が密接に連携し、一体となって戦う精鋭複合兵団の常設である。 竜や高位魔獣の討伐において、少数の熟練者による特別編成部隊が活躍するのはこの国の伝統であり、フローラント諸国においても常套の戦術であった。エイソアはその戦法を常備軍に昇華させようとしたのだ。しかし、この提案は指揮権の所在とコストの問題を理由に却下された。彼女もそれを理解しており、まずはその概念を根付かせることを目的として次善の策に出る。 彼女は当時の王の妹でありノルエイタ伯爵夫人である人物に直談判し、「女性のみで構成された戦闘部隊」という構想を示した。女性士族であれば権力的な序列が低く、指揮系統の摩擦を最小限に抑えられることを見越しての提案である。また「女性のみ」という響きが、伯爵夫人の美意識に訴えると読んでの計算でもあった。男の貴族たちからは「女の余興的な飾り部隊」と見くびられることさえ、かえって実現の障害にはならぬと踏んでいた。 この構想の有用性を最も理解していたのは、王国最高の将軍エスカナス・ザームであり、公的には沈黙を守りつつも、私情としてはエイソアの構想に深く賛同していた。彼は、魔導と剣術の軍隊レベルでの融合こそが次代の戦の在り方であると信じており、王家が「形式と伝統」に囚われて歩みを止めることを危惧していたのである。ゆえに、エイソアの構想を「実現可能な形」に落とし込むこの策を高く評価し、裏から伯爵夫人に働きかけた。 結果、伯爵家はこの案を受け入れ、王家からもエスカナス・ザームの口添えによって資金援助が下りた。こうしてノルエイタ近衛騎士団が設立され、エイソアはその育成機関――ノルエイタ騎士学校――の初代校長に任命された。剣と魔導を融合した戦闘団を育てるという理念のもと、彼女は厳格にして理性的な教育を施した。生徒たちに対しても母のように接することはなく、あくまで「職業軍人の雛」として扱った。それは彼女自身が「私には母性が足りていない」と自認するほどの冷徹さによるものだったが、そこに一片の愛情がなかったわけではない。むしろ、彼女なりの最大の慈しみであった。 第1期生が育ち、彼女の構想が形を成した頃、エイソアはその成果を王へと披露した。王妃とザームがこれを強く推挙したことで、騎士団は「近衛」の名を冠することを許される。外見こそ華やかであったが、その実力は実戦部隊としても比類なく、エイソアの戦略眼が的中したことを証明する結果となった。 やがて訪れるバーン王国によるリュートリオン侵攻。その最末期、彼女は騎士学校に設置されていた転移装置を守る任を最後の使命とし、全ての生徒をフルスク男爵家の騎士として叙勲させ、避難民とともにヴィーリオンへの退避を命令。唯一残った教導騎士テナイト・リーンタックとともに戦場に立った。敵は数百を超えるバーン軍。侮りなく魔導封殺の備えを整えていたバーン軍に対し、エイソアの呪文攻撃とテナイトの剣撃は嵐のように襲いかかり、1個中隊を殲滅。それは僅か2人の剣魔の兵団であったが、人類のすべてが憧れ頼みとし、畏れ敬う「単騎にて百を屠る英雄の戦い」が、そこにあった。 しかし、想定外の大損害を前に打って出てきたバーン軍の騎士ヨーケル・マイヘルベック男爵との一騎打ちにてテナイトが討たれると、エイソアもまた魔導を封じられ、最後は自ら命を絶った。転移装置の確保という任務を果たすために、彼女は死してもその守りを放棄しなかったと伝えられている。  彼女は生涯を騎士団の理想と教育に捧げた人物であり、同時に「女であることを最大限利用して組織を築き上げたが、その中に女であることの弱さを一切持ち込まなかった」人物として、後世の軍人たちから深い敬意をもって語り継がれている。 ・マスターズ・コメント どの国にもこの剣と魔法の混成部隊を思いついてる人はいるんですが、やはり封建国家では士族を一括して統制するのはとても困難でありまして。国家の職業軍人として一元管理されてない事実は、コスト以上に重い問題だったりします。 なので別に彼女が天才的で独創的な人だったわけではないのですが、そんな中でリュートリオン固有の状況を利用し、落とし所を見つけて実現させたのが、彼女の優れたところでありましょう。もちろん他の国にも頑張ってる人はいるけどね。 ●  騎士8 筋力14/敏捷力12/耐久力13/知力12/判断力12/魅力13/PB24 テナイト・リーンタック騎士爵は、リュートリオン王国がまだ健在だった頃、ノルエイタ近衛騎士団において教導騎士の任にあった女性である。彼女の出自は貴族ではなく、王都カーフィオンの大手材木商の娘として生まれたが、その生まれとは裏腹に、誰よりも高貴な気質を持つと評される騎士であった。幼少の頃より竜殺しの英雄アルティサイア・ザーム卿の英雄譚に心を奪われ、己もまた英雄のように生きたいと願って剣を取る。家が裕福であったため、幼少期から優れた教育と鍛錬の場を与えられ、入団年齢の下限である8歳を迎えるやいなや、迷うことなくノルエイタ近衛騎士団の門を叩いたという。 この騎士団は女性のみで構成された特異な兵団であり、創始者ノルエイタ伯爵夫人の理念に基づき、王族直属の守護を任務とする。志願制であるがゆえ、少女たちは皆、憧憬と誇りを胸に集う。その中でテナイトは、訓練に明け暮れる日々を過ごしながら、常に「己が理想とする騎士像」に向かって邁進した。華美を嫌い、質実剛健を旨とするその姿勢は、やがて同僚や後進から「まるで貴族のような騎士」と呼ばれるほどの風格を帯びていった。 成長した彼女は竜の勢力との戦いにも参加し、下竜を討ち果たした実績を持つ。その戦功と指導力を認められ、若くして教導騎士に抜擢される。騎士学校では校長エイソア男爵の右腕として仕え、数多の少女たちを導いた。厳しさと優しさを兼ね備え、ただ強さを教えるのではなく、気高さと誇りを体現することの大切さを説く指導者であり、教え子たちからは絶大な信頼を寄せられていた。まだ年若いながらも、天性の向上心と豊かな学識、そして実戦で培った冷静な判断力が相まって、少女たちにとっては憧れであり、守るべき母のような存在であった。 リュートリオン王国へのバーン王国の侵攻が始まると、戦況の悪化に伴い騎士団員たちは次々と前線へと召集され、騎士学校には校長エイソア男爵を除けば教導騎士としてのテナイトただ1人が残されることになる。教師を失い混乱する生徒たちを前に、彼女は「上級生による下級生の指導」という制度を即興で取り入れ、教育体制を維持した。危機の中にあっても彼女の采配は見事であり、若き騎士見習いたちはその背を見て、己の使命と覚悟を学んでいった。 テナイトが最期まで前線へと出ることがなかったのは、王族の退路として用意された転移装置の転送先が騎士学校に設置されていたためである。彼女はその守護者として任を負っており、王家の血を守る最後の砦として残されたのだ。だが、王都カーフィオンが陥落したのち、脱出するはずの末姫が現れぬことから、既に脱出は失敗したと悟る。 それでもなお、彼女は少女たちに希望を残そうとした。亡国の現実を悟らせぬように、「まだ道はある」と言葉をかけ、彼女たちにリュートリオン国民の避難を託す。その際、テナイトは全員に正式な騎士叙勲を与えた。これは亡命先ヴィーリオンでの待遇が「平民」ではなく「貴族」として遇されるようにという、母のような思いやりに他ならない。 最後の教え子たる少女たちが出立したのち、テナイトは校長エイソアとともに学校に残り、迫り来るバーン軍を迎え撃つ。数百に及ぶ敵兵を前にわずか2人の騎士として奮戦し、およそ1中隊を討ち果たすことで彼女は"使命を全う"した。 国が滅びようとも、少女たちが未来へと繋いでくれるのなら、それでよい。彼女の生涯は、まさにリュートリオン騎士の理想そのものであった。 ●  貴族5/君主8/武将3 筋力13/敏捷力10/耐久力13/知力15/判断力16/魅力15/PB31 ウェルナー・フリューゲルベルク伯爵は、バーン王国南方軍集団第1軍を率い、旧リュートリオン王国を陥落させた歴戦の勇将にして、現在はその地を治める辺境伯である。 鋭い眼差しと威厳に満ちた風貌は苛烈さを思わせるが、その内には冷静な軍略眼と深い理性が宿る。彼のもとに吹く風は炎を孕み、勝利と統治の象徴として人々に語り継がれている。 ウェルナーはもとよりバーン王家に仕える一男爵家の出身であり、若き日に勃発した建国戦争で数々の武勲を挙げ、終戦時には伯爵の地位を得ていた。その後もバーンの南方拡張政策を支える柱の1人として重用され、西覇戦争では南方軍集団第1軍の総司令官として抜擢される。その采配は迅速かつ的確で、担当した最東部の地域を短期間で制圧し、南方軍集団最速の将として名を馳せた。 だが、リュートリオン制圧の裏には大きな誤算が潜んでいた。西覇戦争中盤、ウェルナーはセンクオン王国を攻略する際、あえて自軍の陣に隙を作り、リュートリオンのザーム伯軍を誘い出す策を講じた。これはリュートリオンを降伏させるのではなく、完全に征服する大義名分を得るための計略であった。 しかしこの策は裏目に出た。ウェルナーはザームの力量を見誤っていたのである。誘いに乗ったリュートリオン軍は、予想を遥かに上回る精密な戦術で反撃し、バーン軍に深刻な大損害を与えた。ウェルナーは冷静に状況を収拾し、撤退と再編を指揮したが、その損害……特に攻城兵器部隊の人材損失は第1軍にとって痛恨の一撃だった。 ウェルナーは己の敗北を「策士、策に溺れる」と自嘲した。だが、その敗戦をもってしても彼の評価が揺らぐことはなかった。普通ならば糾弾されるほどの損害であったが、バーン上層部も認めざるを得ないほど敵の戦いぶりは抜きん出ていた。むしろ戦後には「ウェルナーが指揮官でなければ、リュートリオン戦役はさらに半年長引いたであろう」とまで言われている。 センクオン王国は、隣国リュートリオンからの救援を受けて一時は意気軒高となったが、ザーム伯軍の反撃によってバーン軍が受けた損害の大きさを知ると、態度を急変させた。バーンが激昂し、徹底的な報復に出るのではないかと恐れたセンクオン王は当初の方針を撤回し、一戦も交えることなく降伏を申し出た。 ウェルナーはザームの手腕に深い戦慄を覚えながらも、なおバーン軍の総戦力が敵の10倍に及ぶ現実を冷静に見据えていた。最小限の部隊再編を終えると、彼は即座にリュートリオンへの侵攻を開始する。彼にとってそれはもはや単なる戦争ではなく、自らの誤算を正すための戦いでもあった。 しかし、待ち受けていたのは想像を絶する遅滞戦術であった。ザームは地形・気候・補給路のすべてを利用し、正面決戦を避けながら確実に時間を奪っていった。損害自体は決して大きくない。それでも進軍は異様なほどに遅滞し、戦線はまるで魔法でも掛けられたかのように一進一退を繰り返した。ウェルナーの軍才をもってしても、戦の主導権を完全に握ることはついぞ叶わなかったという。 それでも最終的には、物量と組織力によってバーン軍が王都を包囲・制圧するに至る。だがその時には、南方軍集団の中で最も早く「最南端の国家」を攻略開始したはずの彼の軍が、結果として「西覇戦争最後の抵抗国家」を落とす役目を担うこととなっていた。リュートリオンの名は、戦の最期まで抗い続けた国として歴史に刻まれ、ウェルナーの心にもまた、敗者ではなく戦士としての敬意が深く残ることになる。 王家が滅び、多くの民が他国へ逃れた後も、この地には多くの民が残った。彼らの中には「愚かな貴族たちの責任でこうなった」としてバーンへの恭順を示す者も存在した。ウェルナーはそうした民を保護し、融和を掲げる統治を開始する。圧政は行わず、協力者には恩恵を与え、旧貴族の中にも有能な者を登用した。反乱や無法にも問答無用の武力鎮圧を意識的に制限し、統治の均衡を保った。勇猛さと慈悲を兼ね備えたその政治手腕は、支配者としても名将としても高く評価されている。 辺境伯としてこの難治の地を自ら望んで受け持ったのは、敗北した己への贖罪であり、無様を晒した自分への懲罰でもあった。ウェルナーにしてみれば、ここでの統治はまさしく雪辱戦であり、戦場で果たせなかった決着を己の生涯を懸けて果たす覚悟の現れである。 とても「ザームが優秀過ぎたから自分に非はない」などと考えることはできなかった。彼にとって敗北とは、相手の才能を理由に免罪されるものではなく、己の未熟として受け止めるべき試練だったのだ。ゆえに彼はこの国を戦前以上に繁栄させ、かつて自らを打ち破った男からの敬意を得ることで、初めて彼と対等に並び立てると信じている。 それは復讐ではなく、己の中にある英雄への敬意に応えるための戦いであった。人生最大の難敵ザームに対し、せめて「好敵手」と思えるようになるには、己が力でリュートリオンを再興させるしかない。ウェルナーはそう信じていた。 だが実際のところ、そんな努力をするまでもなく、ザームはすでに彼を「我が人生最大の好敵手」と呼んでいたのである。互いに知ることはなかったが、その敬意は確かに両者の間に存在していた。 ウェルナーの最も信頼する武将がヨーケル・マイヘルベック男爵である。彼とは騎士見習いの頃から主従として共に育ち、幾多の戦場を生き延びてきた。ウェルナーは彼を「我が半身」と呼び、全幅の信頼を置いている。リュートリオン陥落の折、ノルエイタ近衛騎士学校の制圧という取るに足らぬ掃討戦を、敢えてこの男に任せたのも信頼ゆえであった。ウェルナーにとってそれは、リュートリオンへの弔いであり、ヨーケルにしか任せられない繊細な使命でもあった。彼ならば過剰な殺戮をせず、武人としての礼をもって戦うと信じていたからである。 帝都では「炎翼伯の風が吹けば、戦も国も整う」と語られている。彼のもたらす風は征服の炎ではなく、再生の光としてリュートリオンの大地を包み、かつての敵国の民に新たな未来を示さんとしている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■プレゼントありがとうございます( ・`ω・´) 急に寒くなり、朝に布団から出難いったらありゃしない!! だが俺は布団に入ってて気持ちいいので寒い季節のほうが好きである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■自分のデッキをシェアする方法が知りたいって? >>49 作ったデッキを大佐に見せたい場合って全部貼るしかないんですかね。 >どこかにコード貼るだけでデッキ内容生成できるサイトとかあったりは…。 まず、このサイトに会員登録します。  そしてMTGアリーナを英語モードにします。 で、画面下部分にあるデッキケース下側に矢印が向いているアイコンで「デッキのエクスポート」をします。  そしてさっき登録したサイトのマイページから、マイデッキを選びます。 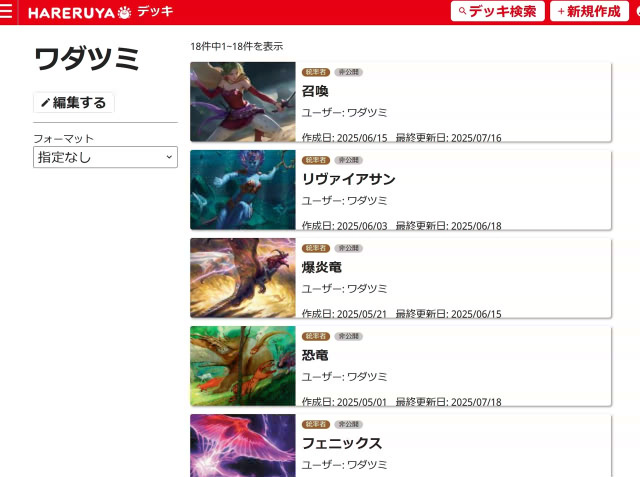 するとこういったデッキを登録管理できるサービスにアクセスできます。 画面は僕のだけど、新規の人は当然まっさら。 ここで右上の「+新規作成」をクリック。 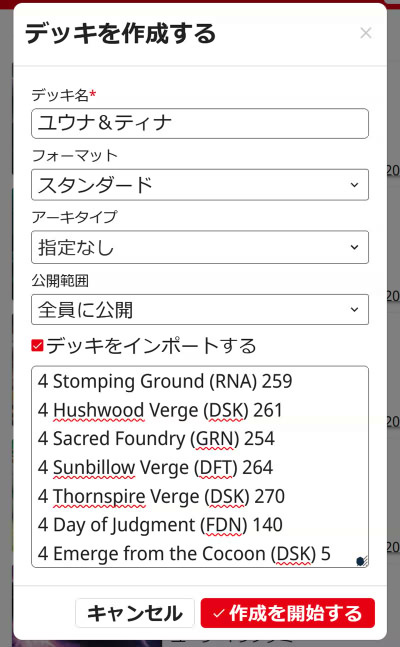 このポップアップが出るので、さっきエクスポートしたのを貼り付けます。デッキ名は自分で記入しよう。 ここが日本語だとエラーが出るので、英語にする必要があるのだね。 公開範囲を「全員に公開」にすれば、俺のこれみたいに誰にでもデッキリストが見れる状態になる。「限定公開」にすれば、URLを直接入れた人しか見れない。これは後から変えられる。  登録したデッキはこんな感じで表示され、ここからもデッキ編集が可能。 この画面のURLを教えてくれれば、俺に見せることが出来ます。 なんならこうやってサイトに貼り付けるソースコードなんかも生成してくれる。 この右上のボタン押せば、逆にMTGアリーナにデッキをインポートすることもできちまうんだ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■男女比1:5の世界でも普通に生きられると思った? ~激重感情な彼女たちが無自覚男子に翻弄されたら~ 拍手で紹介された漫画。表紙は男女比がおかしい世界に転生したみゃーもり(違)。  おいおい、女の少ない異世界に転生してモテモテハーレムってか!? そんな漫画紹介するなんてラブコメ禁止令違反ですよ!?  風向きが変わったな!? おいおい、こりゃ一筋縄じゃいかない展開になりそうじゃないか!? 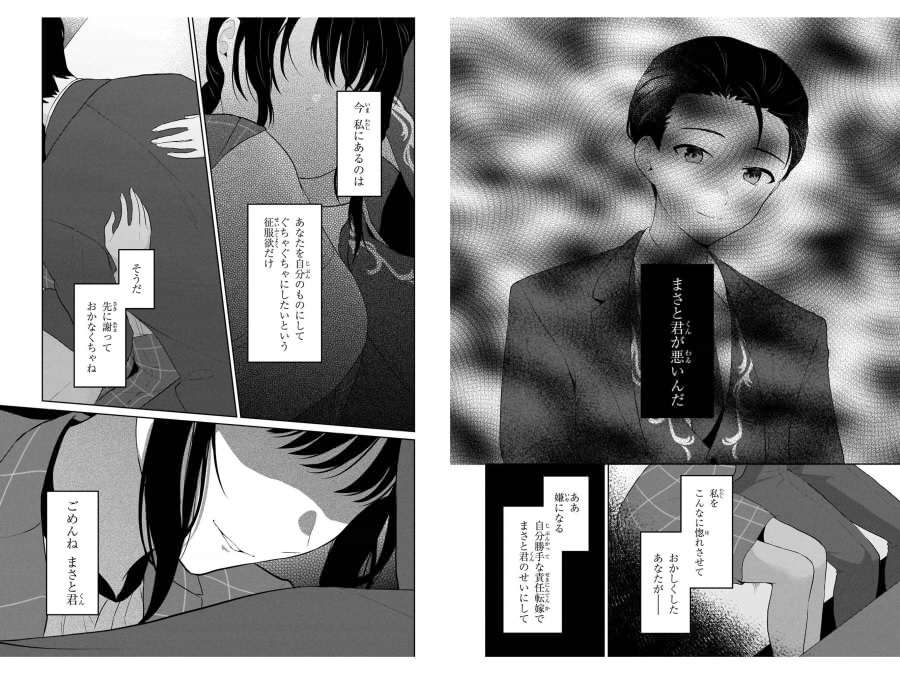 イカれた女たちに争奪戦されるサイコホラーだったら大歓迎だイエッフー!!! いいぞもっとやれ!! 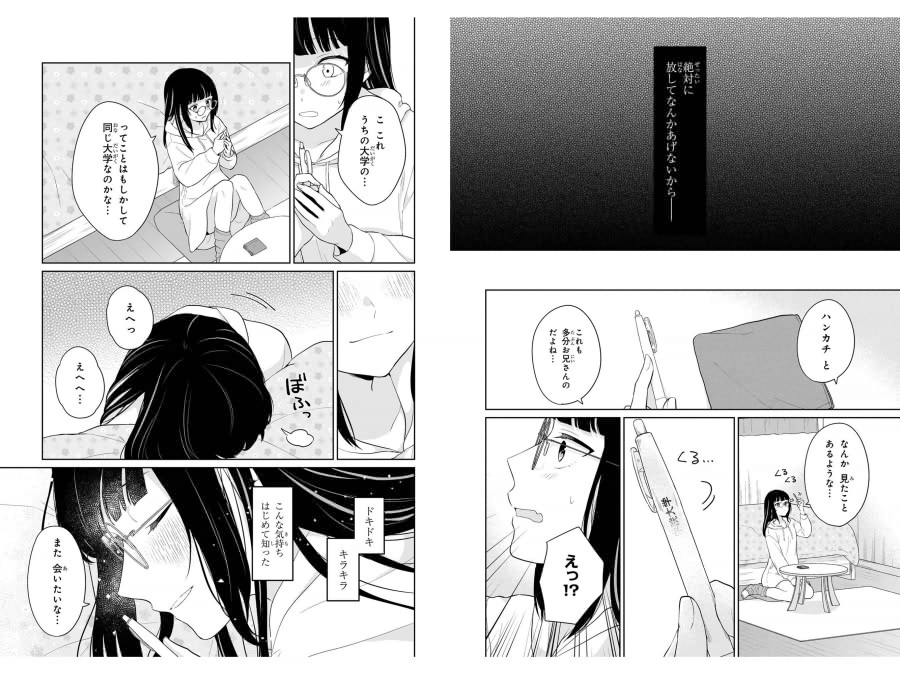 僕の推しはこの黒ストロングでプライベートは眼鏡な、メインヒロイン(?)の親友ちゃん!! 現状、普通にただただいい子なんですが、先行きどうなるやらハハハハハ。  あ、でも普通に幸せになって欲しいとはマジで思ってますよ! この子には!!! 学校ではツインテールで地雷系を着てくれと言わんばかりのビジュがドストライクってわけですし!!! 俺と結婚してくれ!!! なお、これは一個前の画像よりもだいぶ前の初登場シーンです。当然サークルのけいとさん(ゴミクズ)にはこっぴどくフラレて、傷心ビッグバンで街をさまよってる時に偶然主人公に出会ってしまい、その時点では「親友(ヒロイン?)の好きな相手」とは知らずに好きになってしまい、さぁ大変!!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■俺は自分のサイトの看板娘にだって酷い生い立ちを背負わせちまうんだ ●OWV-11  有機魔導人形15 筋力13/敏捷力16/耐久力16/知力15/判断力15/魅力12 バーン帝国の工廠「ワルキューレ工廠」が開発した魔導人形の中でも、OWV-11――通称エルフは、現時点で最も高性能かつ高価な機体である。彼女は人造戦乙女計画の試作11号機に位置づけられ、正式名称をWalküre Organische Waffe-Versuchskonstruktion ELFとする。この計画は、従来の有機的な人造生命体――いわゆるホムンクルス型の限界を打破するために立案されたものであり、人体を素体としながらも、その構造の大半を魔導機械へと置き換えることで新たな進化を目指した。脳や臓器といった根幹の構造は保持しつつも、各部は精緻な魔導補助機構で強化されており、生命と機械の境界が曖昧になるほどに融合している。表向きは魔導人形として登録されているが、その実態は機械化人間に等しく、  エルフは人間を素体とするが、それはバーン帝国が定める禁忌に抵触するものではなく、むしろ国家の後援を受けて行われた正規の軍事研究の成果である。帝国では人体実験そのものが禁じられておらず(そもそも禁じている国のほうが少数派である)、この計画における秘匿は倫理上の問題からではなく、性能と技術を外部に漏らさぬための情報保全措置によるものである。素材となった素体の出自についても公式記録には残されていないが、捕虜や不慮の死者が用いられることが多く、エルフ自身もまたその一例にあたる。彼女の肉体は、かつて西覇戦争で最も激しい戦火に包まれたリュートリオン王国の末姫のものであった。王国は降伏勧告を拒み、最後の一兵に至るまで戦い抜いて滅んだと伝えられており、帝国法により降伏拒否者は貴人としての資格を失うため、末姫もまた(公式には行方不明とされるが)戦利品として工廠に下賜されたと考えられている。 人造戦乙女計画は、ホムンクルス技術の非効率性を克服することを目的としていた。かつてのホムンクルス研究は、英雄に匹敵する力を持つ個体を造るためには、同等の資質を持つ人間を素材としなければならないという矛盾を抱えていた。エルフの開発ではこの制約を突破するため、英雄的資質を持つ人間を素材として選定し、魔導的強化によって即戦力化する方向が取られたのである。彼女の完成はその試みが一定の成功を収めたことを示しており、同時に「真に高性能な人造戦乙女を生むには、やはり英雄の素質を持つ者を素体とせねばならない」という事実をも裏付ける結果となった。 計画の根底には雷光神の信仰が息づいている。雷光神は戦闘を存在意義とする神であり、その教義は「強さそのものを目的とする」理念に貫かれている。ゆえに戦乙女計画は、女性のみを素体として採用している。戦乙女という概念自体が雷光神の象徴する女戦士の具現であり、彼の神威を理論的枠組みとして組み込むことで、術式的な補強を行う意図がある。雷光神は「戦いのための強さ」を追求する行為を肯定し、手段を問わぬ覚悟にこそ加護を与えるとされるため、この試みもまた神の加護のもとに進められた。さらに、バーン帝国の国教とも言える鉄血神――戦と武具の神もこの技術革新を後押ししており、武具の新時代を拓く研究として宗教的にも容認されている。こうしてエルフは、魔導と神威の交錯点に立つ存在、すなわち人造の天使とも呼べる存在へと至った。 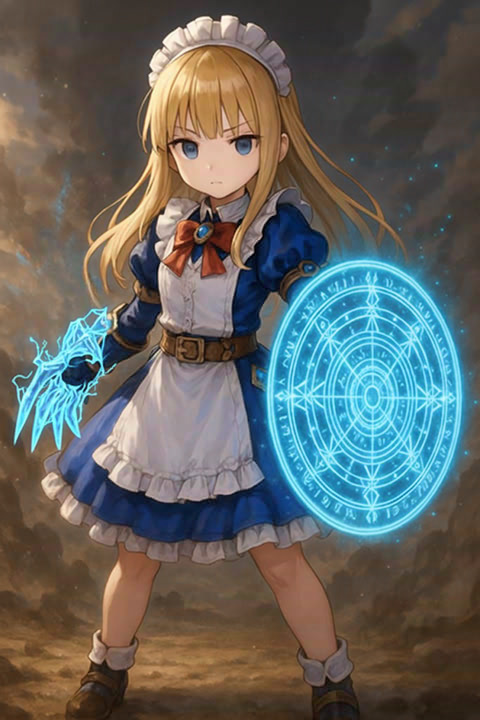 エルフの外見は人間そのものであり、黄金の髪と碧眼を持つ少女として造形されている。戦場においては右腕に冷気を帯びた戦闘用兵装「コールトクロイエ」を、左腕に防御結界発生器「クラフトシルト」を備える。この防御機構は魔力による展開式のフェルトアルム・シュトース機構と連動し、出力段階や展開範囲を自在に調整できる。広範囲の薄い障壁としても、あるいは高収束の一点防御としても運用可能である。また主武装として烈風の呪文を組み込んだ箒型の杖「ショル・ベーゼ」を持ち、近距離での斬撃・射撃双方に対応する。その威力は高位魔導師の放つ殺傷呪文に匹敵し、特化した短射程ゆえに極めて高い破壊力を示す。また、風の精霊力を攻撃以外にも制御・利用する飛行補助術式が組み込まれており、風圧を推進力として自在に空を駆けることができる。最適な流体制御と魔力噴射によって、最大時には音速に達する高速飛行が可能であり、戦場での機動性は常識の範疇を超える。  背部に装備された収納鞄には小型の飛行呪甲砲を最大12基まで格納しており、戦況に応じて射出・展開できる。これらは魔力弾による制圧射撃を行い、遠距離および近距離双方での支援攻撃を可能にしている。有効射程はショル・ベーゼを遥かに超えるが、単発の威力は抑えめであり、弾幕と制圧力を重視した兵装である。この呪甲砲は極めて高価な魔導機器であり、運用コストの高さが唯一の難点とされる。  エルフの最大火力は「シュランゲン・シュトラーファー」と呼ばれる魔導兵装にある。その形状は連なった魔導爆雷から成り、戦闘時には自律制御によって蛇のようにうねり、敵に包囲するように展開される。各爆雷はある程度の距離まで伸縮自在な魔力伝導線で繋がれており、連鎖術式が同時発動することで極めて高い同期性を実現する。その挙動はあたかも生き物のようであり、瞬時に敵へ纏わりつく様は雷光の尾を引く鎖蛇として目撃される。各爆雷は八大精霊の属性いずれかを宿しており、特定の精霊防御を用いても完全に防ぐことができない。 対魔導戦兵装モードも存在し、全身に配置された対呪文兵装が呪文封殺を可能とし、敵魔導師の詠唱を阻害する。これにより、攻撃呪文を用いない完全制圧戦法を展開することもできる。その他、様々な兵装ユニットが必要に合わせて随時開発され、データ収集されている。 生体組織の維持のため、体内には自己修復機構が組み込まれており、軽度の損傷であれば人間の自然治癒に等しい速度で回復する。これによって、長期戦や孤立環境下でも高い稼働率を維持できる。総合的な性能は従来の魔導人形を遥かに凌駕しており、エルフをもってようやく人造戦乙女計画は「成功」と呼べる段階に到達したとされる。 この成果により、後続の開発ラインはコストパフォーマンスを重視する方向へ転換した。OWV-11を超える性能を追求することは現行技術では非現実的と判断され、並行開発中だった機体すら妥協を目指す方向にシフトされたのである。それでもなお、ワルキューレ工廠では「人造戦乙女を超える存在」を夢見て研究が続けられている。 なにより武術的な素養は確認されていなかった素体に、高い戦闘力を付与することが出来たのは技術の成果なのも事実であり、希望は残ると解釈されているのだ。 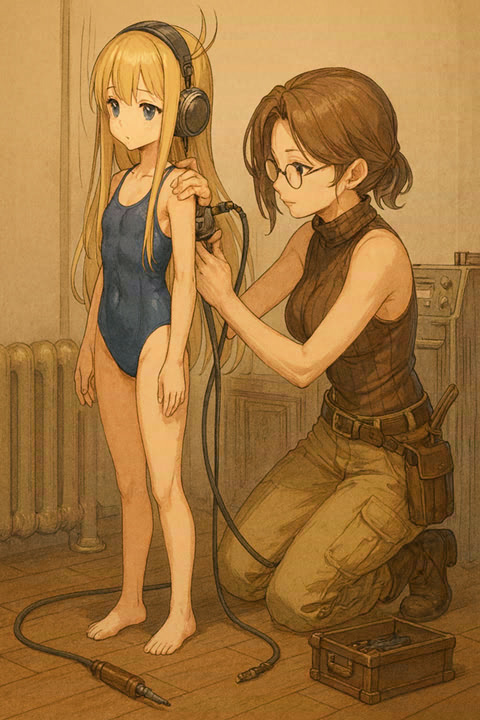 エルフの開発主任はアンナローエ・リューネブルク子爵である。彼女は魔導師としても名高く、魔導学院にて変成術師として高位資格を得た才媛であった。若くして夫と義父を戦で失い、家を継いだ後はワルキューレ工廠の魔導工房に所属している。気品ある令嬢として育てられ、市井の常識に疎い部分もあるが、エルフに対しては深い愛情を注ぎ、実の娘がいないことも関係するのか、娘のように扱っている。エルフもまた、彼女のことを憎からず思っていると伝えられる。  エルフ自身は冷静かつ皮肉めいた物腰を持つが、その言葉の端々には人間的な情緒が見え隠れする。生前の記憶は完全に消失しており、バーン帝国に対して特別な憎悪や敵意を抱くことはない。データとして与えられた戦術・魔導理論に関する知識水準は極めて高く、素体となった少女の生来の知能の高さと相まって、高い思考力を持つことに成功。個人戦闘レベルではあれど、戦場においては状況判断に優れ、柔軟な戦術転換を行う。これは従来の魔導人形が到達し得なかった領域であり、真に自律的な戦術判断を可能とする点で画期的である。エルフは冷徹な兵器ではなく、思考し、選択する戦乙女として存在している。 魔導人形の中では姉妹機にあたる存在も多いが、彼女はその中でも面倒見の良い性格を示し、後続機の訓練・調整に積極的に関わることがあるという。人間の情緒を模した魔導制御による行動とも取れるが、それが単なる制御の結果か、あるいは内面から生じた自発的感情であるのかは、開発者自身にも明確には断定できない。 いずれにせよ、OWV-11――エルフは、バーン帝国の魔導技術と神威理論が結実した究極の兵器であり、同時に「人が神を模して造り上げたもう一つの生命」の象徴でもある。 ●  魔導師9/呪工匠9 筋力7/敏捷力8/耐久力8/知力21/判断力15/魅力15/PB30 アンナローエ・リューネブルク子爵は、バーン帝国における名門リューネブルク家の現当主にして、帝国の宮廷魔導師である。その知性は帝都ソルにおいても広く知られている。  彼女は高名な人形職人ルイトポルトの娘として生まれ、幼い頃から父の手によって生み出される精緻な人形に魅せられて育った。父は貴族ではなかったが、その作品は帝都の上層階級にまで収集家を持つほどに高く評価されており、アンナローエは恵まれた環境の中で育った。少女の憧れは「自らもまた父のような人形を創る者となること」であったが、その非凡な才知を見抜いた父は、より広い学問の世界に導くため魔導学院への進学を勧めた。アンナローエはこれを受け入れ、魔導学院へと入学し、やがて変成術の分野でその天才を示すこととなる。  魔導学院は在籍年数で卒業するのではなく、あくまで「魔導師としての資格を得るため」の機関である。補佐魔導師の資格を得て退学すれば社会的には「卒業」と見なされるが、学費を払い続けられる者であれば在籍期間に制限はなく、本人の意思次第で研究を続けることができる。裕福な家の子女が学問を道楽として長期在籍することも珍しくなく、その中から学院付きの教導師へと登用される例もある。だが同時に、魔導学院の経歴は「貴族社会における安全な『高貴な義務』の果たし方」として人気を集め、結果として年々狭き門となりつつある。アンナローエはそうした環境の中でも抜きん出た成績を収め、正魔導師の資格を取得した。 学院在籍時代、アンナローエは魔導人形研究に没頭し、魔符の構造解析に類似する分野を志していた。父ルイトポルトが非貴族ながらも娘の学費を惜しまず支援し続けたのは、単に親の愛情だけでなく、「娘がその才能を存分に活かして生きるための道を用意したい」という願いによるものであった。  研究の充実した日々の中、親同士の決めた縁談によって上級騎士エグモント・リューネブルク男爵との婚姻が決まった。リューネブルク家は代々ケーフェンヒラー侯爵家に仕える武門であり、魔導師である彼女が嫁ぐことは社会的にも栄誉であった。バーンでは実力主義が徹底しており、女性であっても優秀であれば仕事や研究を続けることが社会的にも容認されている。アンナローエも結婚後も変わらず研究を続け、「これで一生、安心して魔導人形の研究に没頭できる」と思い描いていた。貴族であるため家事の負担もなく、彼女にとって結婚はむしろ学問を守る安定基盤であった。 しかし、西覇戦争の最中、センクオン王国攻略戦においてリュートリオン軍の奇襲を受け、夫エグモントが討ち死に。さらに義父であるリューネブルク子爵も同日に戦死した。家の当主・後継を一度に失ったリューネブルク家は危機に陥り、残された血族の中で最も優れた経歴を持つアンナローエに爵位と所領の継承が命じられた。こうして彼女は学院を退き、貴族としての責務を背負うこととなった。  以後、リューネブルク家と代々主従関係を結んできたケーフェンヒラー侯爵家の招きを受け、帝国最大の軍需拠点であるワルキューレ工廠の魔導工房に所属。人形技術への造詣の深さを買われ、国家機密たる「人造戦乙女計画」のコアメンバーに抜擢。その第11号機――OWV-11“エルフ”の開発主任を務めることとなる。 アンナローエは、研究対象となったリュートリオン王家の末姫に強い同情を抱いていた。ワルキューレ工廠がその少女を取得、彼女に提供した背景には、夫と義父を失った彼女の気持ちを慮った「意趣返し」の意図があったとも言われるが、アンナローエ自身はそれを快く思っていなかった。「そんな悪趣味なことして喜ぶと思わないで欲しいわ」と不満を口にしながらも、他の研究者の手に渡るよりは自らの手で扱うことを選び、結果としてエルフを慈しむように育て上げたのである。 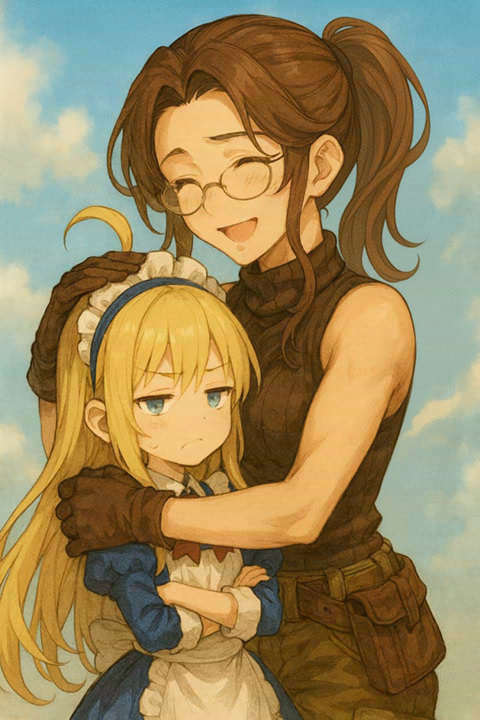 彼女に娘はおらず、本人に自覚はないものの、エルフに対する態度はまるで実の娘に対するそれのようであった。エルフにとっても彼女は創造主というより、やや抜けていて放っておけない姉のような存在である。アンナローエは学究肌ゆえに戦闘の心得は浅く、身体能力も高くはない……どころか低い。それでも実験や調整の現場、果ては実戦テストにすら「自分の目で確かめたい」と過剰に同行しようとするため、周囲からは常に冷や冷やされている。しかしこの現場に立ち会わなければ気が済まない性格が、彼女の研究成果を支えているのも事実である。その探求心と妥協を許さぬ姿勢は、変成術師としての彼女の才能をいっそう際立たせており、腕の一本を失うほどの重傷であっても瞬時に修復できるほどの再生魔導技術を持つ名医としても知られている。  日々の業務の中で、アンナローエは「出来ることなら、人と戦うためではなく、竜との戦いに使ってあげて欲しいなぁ」と上司にさり気なく願い出ている。だが人造戦乙女の運用を決めるのはあくまで軍であり、上司としてもその要望に応えることは難しく、苦笑するしかないという。  変成術師として、魔導技師として、そして貴族として――アンナローエ・リューネブルクは自らの「高貴な義務」を果たし続ける。目下、彼女の野望は皇帝陛下が所有する魔符〈エンプレス〉への謁見を許されること。その夢を胸に、彼女は今日もまた、ワルキューレ工廠の夜を照らす魔導灯の下で筆を走らせている。 ●ミラダ・シイクナ騎士爵 710~728  騎士1 筋力11/敏捷力12/耐久力10/知力10/判断力9/魅力12/PB16 ミラダ・シイクナは、リュートリオン王国の名誉あるノルエイタ近衛騎士団に所属していた少女である。王国滅亡の年、まだ若き騎士見習いであった彼女は、国家最後の混乱の中で正式に叙勲を受け、真の騎士として名を刻むこととなった。しかしその栄誉は短く、叙勲からわずか三日後、ヴィーリオンへと続く避難路の途上、アーエイト山脈を越える夜の野営で、彼女は歩哨任務中に現れた魔物と交戦し、仲間を守って命を落とした。彼女は一度としてバーンの兵と刃を交えることなく倒れたが、その最期まで「民を護る」という騎士の誓いを貫き、仲間たちの生還を支えたのである。  元々ミラダはカーフィオンのパン屋の看板娘であった。明るく元気で、人並みより少しだけおてんば、誰とでも笑顔で話せる社交的な少女だった。気立てが良く、子供や年寄りに好かれ、街の人々からも「日の光みたいな子」と呼ばれていたという。彼女が騎士を志したのは、幼いころに聞いた伝説の竜殺しシュダーク・ノルエイタ卿の英雄譚に心を奪われたことがきっかけだった。平凡な娘でありながら、憧れだけでなく真っ直ぐな志を抱き、両親に頼み込んでノルエイタ近衛騎士団の適性試験を受け、その純粋な意志と身体能力が評価されて見事合格を果たした。 訓練期間中、彼女の成績は特別に優秀でもなければ劣ってもいない、まさに中庸そのものであった。だが、それは決して凡庸さを意味するものではない。彼女は常に笑顔を絶やさず、誰よりも真面目に訓練に臨み、仲間への思いやりを忘れなかった。その穏やかさと朗らかさが周囲を和ませ、厳しい訓練の日々の中で、仲間にとってかけがえのない存在となっていた。  同室であったイルミナーダ・サーレイドとは、最初こそ反りが合わなかった。イルミナーダは感情を表に出すことが苦手で、無愛想に見えることも多く、明るく快活なミラダにとっては苛立たしい存在でもあった。しかし時間を共にするうち、ミラダは彼女の中に秘められた誠実さと優しさを理解し、やがて互いを心から信頼する親友となった。 ミラダの真の強さは、優秀さでも勇敢さでもなく、「卑屈にならない心」にあった。イルミナーダのように成績で遥かに勝る者がいても嫉妬することなく、劣る者がいても見下すこともない。常に自分の出来ることを信じ、与えられた任務を笑顔で果たす。その平凡に見えて揺るぎない強さこそが、彼女を真の意味での「騎士」にしていた。  滅びゆく王国の中で、ミラダはその短い生涯を終えた。だが彼女の死は無駄ではなかった。彼女の献身によって、避難中の人々と仲間たちは無事に山を越え、ヴィーリオンへと辿り着くことができたのだ。後にその名は「最後の叙勲騎士」として記録され、ノルエイタ近衛騎士団の殿堂に名を刻まれることとなる。  誰もが英雄にはなれない。だが、彼女のように“普通の少女が果たした誓い”こそが、滅びた王国の魂を象徴しているのだと、リュートリオンの民は語り継いでいる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■昔から思ってるんだが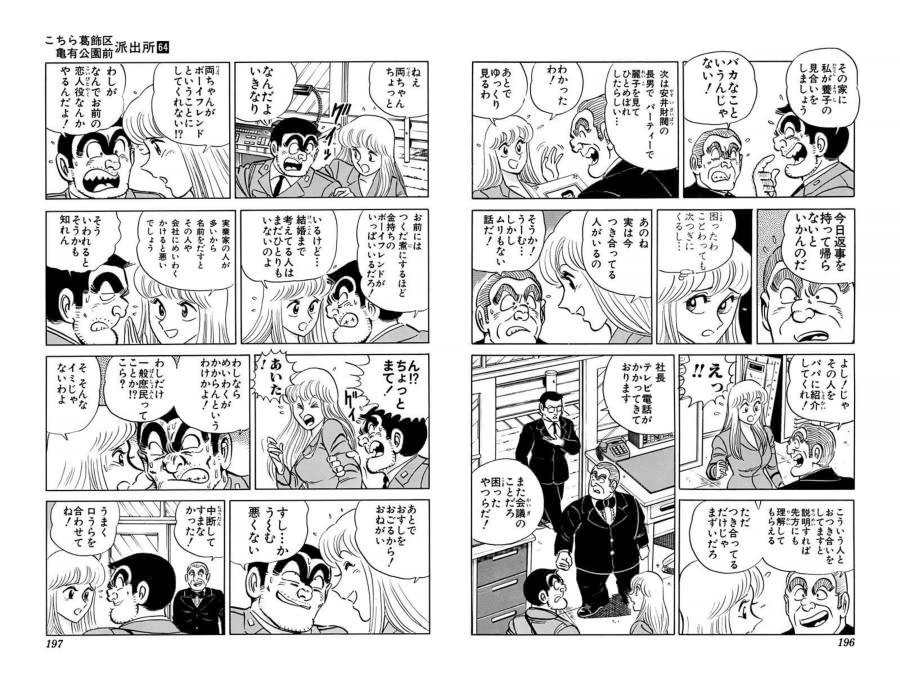 こち亀に限らず、この「ボーイフレンド」ってつまりどーいう関係なんだよ!? 彼氏の場合もあれば、単なる男友達の場合もあれば、友達以上恋人未満の場合もあるし、単に「普通の友達よりは親しい」くらいの時もあるよな!? 例えばこのこち亀シーンだと、明らかに「交際相手」として麗子はボーイフレンドを用いてるが、つまり麗子は彼氏が何人もいてヤマタノオロチ級のモンスターってことでいいのか!? セックスはしまくってるけど結婚まではまだ考えてないってことでいいのかい!? 彼氏彼女の関係だけど、セクシャルフュージョンは承認してないとかヌルいこと言ってんのかい!? ……って、中学生くらいの頃からずっと思ってることを最近思い出した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■バンドリちゃん 我々の世代に見覚えがあり過ぎる雰囲気が当たり前のように展開され、そういやバンドリって90年代から続いてるアニメだったっけ……という錯覚は覚えないにしても「なにやってんだおまえぇぇぇ!」というツッコミをニヤけながらせざるを得ない。  正直「全部見覚えのある構図」過ぎて、ギャラクシーエンジェルのピュルリクを観た時の「ツッコミが追いつかねぇ!!」感覚を思い出してしまったチェケラッチョ。  とどのつまり、笑えばいいと思うよ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■今週はやることが……やることが多い!! 日曜にD&Dしてたら母親がスーパーで転倒して救急搬送されたり、それで肩を骨折してて翌日地元の病院に紹介状持って改めて診察して貰おうと朝迎えに行ったら、自分で起き上がれなくなってるけどドアバーかかってるからどうにもならずに救急隊呼ぶ羽目になり。 病院で血液検査したら血糖値が600で、骨折関係なく糖尿病で入院確定し。 実家を片付けてたら飲んでない糖尿病の薬が大量に出てきたり。 その他ここに書くのも憚られる様々なゲンナリする現実がハチャメチャに押し寄せてきて泣いてる場合じゃないワクワクを百倍にしてパーティーの主役になろう状態。 先週の金曜は、友人が「新しいビデカ買ったから」ということで3080 12Gと、「それじゃ電源容量足りんよね。誕生日プレゼントあげてなかったし見繕っておきます」と、電源も持参で家にセッティングしに来てくれて、ついでに去年Win11にアップデートしたら起動不能になってからずっと避けてたけどもうタイムリミットなのも意を決して決行。1度は失敗するも、2度目の挑戦でどうにかアップデート完了。 3080の排熱がシステムSSDに直風なのが若干気になるが、配置的に選択肢がないのでとりあえず様子見で運用していく!! あと何度も言ってるがマジで拍手で可愛い絵とか教えてくれるのは嬉しいが、イチャイチャシチュの絵を見せようとしてくるのはマジのマジでやめてください。死んでしまいます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■wiki更新するのが現実逃避敵息抜きになってる感もある あとTRPG部のトークルームに貼ったけどスルーされてイラッと来たのでここに貼って供養しておくネタ画像。 ●精霊蝕  精霊蝕とは、竜や高位精霊が振るう純粋精霊力によってもたらされる、人知を超えた災厄である。 その姿は炎や氷、雷といった属性現象の形をとって現れるが、真に恐ろしいのは物理的な炎熱や冷気そのものではなく、混じり気なき精霊の奔流が肉体と魂に叩きつけられ、内奥に眠る精霊力の均衡を破壊するところにある。 この力を浴びた者は、以後は常に異常な偏りを抱え続けることになる。 火竜に灼かれたなら燃え盛る熱病に苦しみ、氷竜ならば凍える寒気に苛まれる。雷竜であれば神経は痺れ続け、闇竜であれば生命力そのものが枯渇していく。 これらは単なる傷や後遺症ではなく、「存在そのものに刻まれる呪い」である。 ・回復不能の病 精霊蝕は、一般に用いられる回復呪文では癒せない。 肉体の傷や臓腑の損傷は即座に癒えても、精霊蝕だけは残り続ける。悪魔が与える呪疽や、神が課す聖痕と同じく、超常的な呪いに属する現象である。 しかも精霊蝕は時間の経過によって徐々に薄れることはあっても、その歩みは人間の寿命に比してあまりに遅い。100年を経てもなお癒えず、1000年を費やしてようやく消えると伝えられる。そのため生者にとっては事実上の不治であり、死後にさえ付き纏う。  だがもちろん回復手段が一切存在しないわけではない。精霊蝕を与えてきた存在の精霊支配力を上回る魔力で治療を行うことができれば、取り除くことが可能となる。たとえ太古竜による精霊蝕であろうと、理論上は。 精霊蝕を取り除くには、術者はブレイク・エンチャントメント、ウィッシュ、ミラクルのうちいずれかの呪文を用いて精霊力レベルを目標とした術者レベル判定を行う。成功した場合、1D4ポイントの精霊蝕ダメージを回復することができる。 ・魂への刻印 軽度の精霊蝕であれば身体に異常を抱えるだけで済む。だが深刻なものとなれば魂そのものに呪いが刻まれる。この場合、肉体が滅んでも呪いは消えない。 蘇生術によって肉体を再び得ても、魂に刻まれた蝕みは消えず、蘇った瞬間に再発して命を奪うことすらある。 100年前に竜を討ち果たした英雄を蘇らせたが、甦った直後に精霊蝕に倒れた、という伝承はその恐怖を如実に物語る。 ・英雄殺し 精霊蝕はしばしば「英雄病」あるいは「英雄殺し」と呼ばれる。 竜と戦い生き残った勇士が、戦後に謎の病に苦しみ衰弱してゆく事例は数多い。竜との戦いにおいて最も恐るべきものは死ではなく、戦いの後に訪れる精霊蝕であるとすら言われる。 その恐ろしさを説明するため、しばしば星渡りの民の記録が引き合いに出される。彼らはこれを「魂を透かす光の毒」と呼び、強大な光に晒された者が血を吐き、髪を失い、肌を爛れさせ、やがて命を落としたと記している。後世の人々はこの記憶を寓話的に語り継ぎ、精霊蝕の比喩として用いてきた。 ・成長度と純粋精霊力 竜の成長とともに吐息の性質は変化する。 若竜や成竜の段階では、攻撃の大半は火炎や冷気といった属性現象であり、防御呪文や障壁も一定の効果を持つ。 しかし老竜になると、その吐息に純粋精霊力が無視できない比率で混じるようになる。防御は部分的にしか通じず、精霊蝕を避けられない。 古竜や太古竜に至っては、その吐息の大半が純粋精霊力となり、いかなる属性防御も無意味となる。このため、呪甲装兵の強固な防御ですら容易に貫かれる。 ・呪甲装兵と秘金装甲 竜と戦うために設計された呪甲装兵は、精霊蝕の存在を前提とした構造を持つ。 その防御は三重構造であり、外殻から魔導障壁、呪刻防御、そして秘金装甲によって成り立つ。 魔導障壁:成竜までの炎や氷を防ぐが、純粋精霊力には通じない。 呪刻防御:装甲に刻まれた紋様が精霊力を乱流させ、浸透を遅らせる。 秘金装甲:凡百の鋼鉄を超えた貴重な金属、主にミスリル銀とアダマンタイトによって構成される。 ミスリル銀は軽量かつ魔導親和性に優れ、精霊力を散らす性質を持つため、呪甲装兵の主構造材として用いられる。 アダマンタイトは比類なき硬度を誇り、主装甲および武器に使用される。竜の牙や爪を退け、精霊力の直撃を遅らせる“最後の壁”である。 これらを組み合わせた呪甲装兵は、人類が竜と立ち向かうための最大の叡智の結晶であるが、古竜や太古竜の吐息を完全に防ぐことはできない。彼らの存在は「滅びを遅らせる器」にすぎぬとされる。 ●能力値 どれも数字が高ければ高いほど優秀なのは言わずもがなだけど、18と19の「1の差」と、10と11の「1の差」は等しくなくて、数字が高いほど1の差で増える実際の能力は大きくなる。ゲームのルール的にもそうであることが多いし、キャラクターのイメージ的にもそう。 これは他のあらゆる数字にも適用されていて、100ダメージは10ダメージの10倍ではない。DMGに載ってるバリスタやレーザー・ライフルのダメージで3D8だが、どう考えても「ロングボウの3倍のダメージ」で収まるわけがない。でもマスケット銃とグレートアックスが同じ1D12なのはわかる。 伝説の英雄が一撃で100ダメージ出したら、レーザー・ライフルの期待値の8倍くらいなわけで、そりゃ岩をも砕くって表現すら生ぬるい。現代戦車の120ミリ滑腔砲のダメージですら期待値が65点だぞ。超人過ぎる。もう戦艦の主砲みたいな破壊力だよそれ。 この世界のデータを見る時は、そんなことを念頭に置いてイメージしてもらえると幸いである。 ・【筋力】 主な参照先:近接攻撃命中、追加ダメージ、運搬能力 前衛にとって最も重要な能力。 命中は器用度で判定するゲームもあるけれど、アメリカンスタイルはすべてマッスル。まぁパワー=スピードなのは、筋肉の仕組みからして至極当然なのだが。 加えて大事なことなのですが、身軽さはここの数値で判定されます。 〈軽業〉は【敏捷力】だけど、〈跳躍〉も〈登攀〉もこっち。どんだけ器用でも力がなければ伴わないアメリカンスタイルというか、リアル思想。 フィクションでありがちな「非力だけど身軽なキャラ」は作れない。引き締まった陸上のアスリートみたいなのが精一杯。  ……なのだが、俺の世界ではファンタジー筋肉があるので、美少女が筋力18だけど別にゴリラじゃないのは許される。ロリが巨大なハンマーを振り回していい。魅力度さえ高ければ。あ、魅力度の低いキャラは男女問わず筋力高けりゃゴリラですよ。 ・【敏捷力】 主な参照先:遠隔攻撃命中、AC、反応セーヴ 射手や軽戦士最重要能力。 遠隔武器は【敏捷力】で命中判定するし、重い鎧を着れない軽戦士は身軽さがないとACが低過ぎることになる。加えてその高い【敏捷力】を《武器の妙技》で命中判定でも使用するのがお決まりコース。 これなら「非力だけど技で戦うキャラ」ならば再現できる。立体的な身軽さはないけど、足さばきは卓越しているイメージの。 で、技能系最重要能力……ではない。 盗賊系の仕事は他の能力値にも分散しており、【敏捷力】がどんだけ高かろうと罠を見つけたりはできない。この「器用さ」を表現する能力値が無いことは、割と多くの違和感を生み出すことに繋がっている。 そんなわけでゲームのメインキャラにドワーフのローグがいたりして、「身軽さよりも大事なのは洞察力と器用さだよね」ってノリで運用されていることが普通にある。 ・耐久力 主な参照先:HP、頑健セーヴ 総合的な打たれ強さに直結してるので、前衛必須だけど、後衛もなるべく高くしたい能力。HPが減ることになるのは特に致命的なので、これが1桁なPCなんて見たことがない。そりゃそうよ。 結果としてPCたちに「【筋力】1桁なのに【耐久力】は前衛並」という、イカれたクリーチャー共が量産される罪深いパラメータ。モヤシなのにゴリラ並のタフネスとか人として説明がつき辛いので、まさしくファンタジー界に爆誕した謎の生命体。 戦闘中の呪文発動に大事な〈精神集中〉すらここを参照するから、【筋力】9で【耐久力】15の魔導師とかが日常茶飯事であり、お前ら全員アルド・ノーバ(ロードス島戦記の【耐久力】18ソーサラー。通称モアイ)みたいな外見にするからなと言いたくなる。 ここだけの話だが、【耐久力】が高いからといって不利な処理をしたことはないが、ロール重視で過剰に高くしてないキャラが死にそうな時に、ダメージを低く処理したことは何度もある。 ま、でも高くしたくなっちゃうよね。キゲインの女の子にすれば「【耐久力】高いけど可愛いロリな魔導師」が合法的に扱えるぞ!!! あとHPに対する【耐久力】ボーナスは、後から能力値を成長させた場合、遡って適用されるのでお得に感じる。レベル12で【耐久力】が13から14になったら、(通常のHP増加分に加えて)それだけでHP+12される。  魔法戦士クラスではなく純正魔導師なのに、【判断力】よりも高い【筋力】で近接戦闘してた正義の男だったが、メイドさんからのイジりに快感を得ていた変態疑惑もある。 ・【知力】 主な参照先:技能ポイント、魔導師系の呪文能力 頭の良さと思われがちだが、厳密には「知識の量」である。頭の回転は【判断力】が担っている。昔のD&Dでは和訳が【教養】だったことも納得だね。 レベル1キャラクターにおけるこの数値は、今までの人生でどれだけ勉強してきたかの具体化と評していい。一般人の能力値の平均は10だが、生涯変わり映えしない農村なら9以下も珍しくないだろうし、様々な文化が行き交う都会なら11が凡人ラインかもしれない。テレビや(中世に比して)驚異的に安価な本を筆頭に、日頃から様々な情報を大量かつ気軽に接種して育つ現代人なら、凡人の最低ラインを【知力】12にしてもいい。 もっとも、この数値がどんだけ高くても〈知識〉に技能ポイントを振ってなければダイスを振ることすら許されないのは注意。ただ、1ランクでもあれば【知力】ボーナスを足して判定できるので、この基礎教養の豊かさは大きく物を言うことになる。現代日本なら、義務教育で全部の〈知識〉技能を最低1ランク取らされてんじゃないかな。 盗賊系でいちばん大事な能力値は【敏捷力】ではありません。これです。技能ポイントに直結する上に、〈捜索〉と〈装置無力化〉がこれだから。でも〈解錠〉は【敏捷力】。なんでなんだぜ? 手先の器用さ勝負だから〈解錠〉は【敏捷力】まではわかるが、じゃあ〈装置無力化〉もそうしろよ、と思わずにはいられないモヤモヤは否めない。罠に対する知識が重要なのであって、器用さは関係無いのだろうか。知識勝負なのに失敗しても何度も振れるのがおかしくなるが。〈捜索〉が目敏さ能力なのに、【判断力】じゃないのも変な感じ。知識が無いと違和感を違和感と気付けない、とかなんだろうか。どうにもゲームバランス的な「敢えてのバラつかせ」な意図を深読みしてしまう。 なんにせよ技能ポイントさえあれば対応能力値が低くたって補えるし、一つの能力につき複数種類の技能にボーナスを与えるにしても、【知力】ボーナスが+1される毎に毎レベルの技能ポイントが1増えるわけで、長い目で見れば対応能力値を高くするよりもお得。HPに対する【耐久力】ボーナスと違い、後々高くしても遡って適用されないので注意。 泥棒は無学な人間が落ちぶれた先のイメージだが、プロの盗賊は頭が良くないとなれないのである。フィクションに出てくる腕利きの泥棒系キャラだって、大抵は頭良いでしょう? ・【判断力】 主な参照先:神官系と精霊使い系の呪文能力、意志セーヴ 地頭の良さを表現しているのはこっち。昔の和訳名は【知恵】である。動物のように勉強することがない生物は「【知力】は低いけど【判断力】は低くない」ことで表現され、概ね12前後持っていることが多い。一方で「愚かであること」が特徴づけられているオークやゴブリンなどは1桁とかになっている。なのでまぁ【知恵】だと誤訳感は否めなず、【判断力】の方がしっくり来る。  【判断力】4はもはやADHDとか何らかの疾患持ちとしか考えられず、高い【知力】とあいまった場合、それはもういわゆる「勉強への集中力が人並外れて高く、得意なことへの才能も突出してるけど、日常生活に支障が出るレベルの疾患持ち」みたいなことになる。 意志セーヴは落とすと他2つより危ないことにあることが多いので重視したいところだが、それでも呪文能力に影響しないならば優先順位が低くなることは間違いないので、一番低い数値を割り振られて1桁になるぐらいはよくあることである。 注意力や直感力が重要視される〈聞き耳〉〈視認〉などがこれなので、野生動物は【知力】が低くてもどうにかなる……ということは全然無くて、【判断力】12で並の人間より高いからって、それで+1ボーナス貰ったところで【知力】が低いキャラは技能が全然伸びない以上焼け石に水。完全にシステム的欠陥となっている。それを補うためか、「種族ボーナス」という形で水増し、底上げされていることが多い。それでも「初期値がマシなだけでレベル上がっても全然警戒能力が上がらない」のは結局不自然。【知力】が低いやつは学習能力も低いってことは否定できないけどね。だがフローラントでは違う!(ギュッ)。 ・【魅力】 主な参照先:イメージイラスト、世間の反応、特殊能力 顔、人を惹きつける力の総合値。 性格も参照されないわけではないのだが、善良であればあるほど良いというよりも、器の大きさが問われる。悪党でも人間としての存在感を放つキャラは【魅力度】が高い。もちろん小悪党はプラス要素にならないどころか【魅力】9以下になるが、一方で地味だけど優しい人は顔が普通でも【魅力度】11とかになる。 英訳だと「カリスマ」なんで、多分厳密には顔の良さは含んでない。フローラントだと含んでるけど。ちなみに顔の良さはクトゥルフの呼び声でおなじみな【APP】である。 性格が悪いが顔は良くて口は上手な歌舞伎町の接客業みたいなタイプは、高い顔面偏差値とゴミのような人間性が相殺し、「顔が良い割には【魅力】が低い」状態で〈はったり〉と〈交渉〉が高いことになる。 また、「自我の強さ」もここに含まれているので、精神攻撃を喰らうとここにダメージが飛んでくることが多い。0になると茫然自失で立ち尽くすことになる。 ゲーム的には「アンデッド退散」「悪を討つ一撃」「信仰の恩寵」を筆頭に、様々な信仰系特殊能力で参照されることが多い。神は使い手の人間性を見ているってこと。キャラによって必要か不必要かがかなり極端に分かれるが、戦闘中の常時使うような運用の要とも言える特殊能力で参照するでもない限り、性能だけ見れば優先順位は低い場合もある。 例えば〈交渉〉を重視したい場合も、【魅力度】を上げるよりも【知力】を上げてより多くの技能ポイントを獲得し、技能を成長させた方が効率は良い。 また信仰系に限らずとも特殊能力で参照するクラスは多いし、呪文能力を【判断力】で威力、【魅力】で使用回数みたく両方参照してくるクラスもいる。とかくキャラごとの需要差が激しい。使わんキャラはまったく使わん。  ……が、この放蕩TRPG部は「キャラクターに絶対イラストが付く」のがしきたりだ。そして仮に「【魅力度】低いけどイメージイラストは美少女」にしたい場合、「顔は良いんだが性格はゴミ」を厳密にロールプレイしてもらうことになる。 またリプレイが作成され、挿絵に採用される頻度が高いのも「ロールプレイで発言量が多いキャラ」が筆頭だが、絵的に映える【魅力度】が高いキャラにも明らかなバフがかかることになることをここに明記しておこう。 そして最後になるのが世間の反応。 大前提として【魅力度】の高いキャラは世間が好意的に接してくれる。 ルーナやシェーナが幸せな未来を掴むことができたのは、ひとえに高い【魅力度】を備えていたからである。頭が良いと運が良いとかもあるが、それでも一番大きいのは【魅力度】なのだ。 ●ポイントバイによる能力値決定ルール  ・概要 ポイントバイは、プレイヤーキャラクターの能力値を公平かつ柔軟に決定する方法である。各キャラクターは 一定数のポイントを持ち、これを支払って能力値を購入する。 ……が、TRPG部では基本的にダイスロールで行うので、その結果生まれたキャラがポイントバイで幾つ相当なのか計算する時に参照する。 ・初期値 すべての能力値(筋力・敏捷力・耐久力・知力・判断力・魅力)は8から開始する。 プレイヤーは持ち点を使用して能力値を上昇させることができる。 ……が、これも別に使わないルールである。 ・コスト表 ここを参照して計算するのである。
・能力値はある程度まで「金で買える」 設定上の話をすると、1レベルを得るまでにどれだけの人生を歩んでいたかで、能力値は決まる。 もちろん生まれ持った才能が強く物言う世界だが、ある程度までは後天的な環境を整えることで補えるのだ。 つまり最初から能力値が全体的に高いくせに「村育ちの農夫の息子」はもうそれ相応の天才的な設定が必要になる。 ■筋力・敏捷力・耐久力 ワイルドで過酷な環境に生きれば、それだけで筋トレみたいなことになるわけだが。 そうでなくとも、栄養たっぷりの食生活で育つだけで体格は桁違いに良くなる。 ■知力・判断力・魅力 これはもう教育環境がすべて。知力は純粋に知識量だし、判断力だってある程度は知識という擬似的な経験則から伸ばすことができよう。 適切な倫理観や道徳心を教育されれば、魅力度も増える。 ・才能のイメージスケール あくまで平均値ね。その枠に収まらない奴らが後に高レベルキャラになるのだ。 ・一般人 PB:8~10 能力値:ほぼオール10、せいぜいひとつ11~12。 例:農民、荷運び人、雑用人。 普通の人。つまり世の中にはこれ以下の人も大勢いるってことだ。 漫然と日々を生きるのに精一杯な人々はこうならざるを得ない。 ・傭兵・兵士 PB:13~15 能力値:筋力か耐久力が13~14、他は9~12程度。 例:駐屯兵、都市警備兵、傭兵団の歩兵。 実践経験を積んだ傭兵や、民兵じゃなくて正規兵ね。 もちろん能力的には一般人レベルの底辺傭兵もいるのだが、この辺は「食い詰めた下層民の末路」的なポジションであり、古参兵の弾除け的に消耗されていく。 つまりここで重要なのは、「傭兵だからポイントが15」じゃなくて、「15ポイントあったから傭兵で喰えている」ということ。10ポイント程度のキャラが傭兵になった場合、戦士レベルを1得る前に死ぬのが大半という意味。 ・熟練職人・学者 PB:15~16 能力値:知力や判断力が高め(12~14)、体力面は凡庸。 例:鍛冶屋の親方、名医、大学の講師。 フィジカル的には一般人と同じでも、金で買った学力でポイントが1.5倍になるのだ。 ・上流階級者 PB:15~18(家柄次第で幅広い) 能力値:魅力・知力・判断力が高め。戦闘教育を受けていれば筋力も高い。 例:領主の娘、若き騎士候補、宮廷貴族。 飢えずに学べて育つことが出来るだけで圧倒的優位なのが社会。 まぁ実際にはダイス振って能力値決まるんで、ボンクラ貴族は「知力は高いが判断力と魅力が低い」とかで、家を没落させたりするわけだが。 ・冒険者・独立混成傭兵・上級職 PB:20~ 能力値:長所が15以上ある。 エリートユニットをやろうなんて存在は、そもそも才能がなければその域に到達できない。 最低でもメジャースポーツの二軍選手クラスの力が求められるし、そのレベルの人って地元じゃ化け物みたいな存在扱いされてるんだよ。 ・一流冒険者・独立混成傭兵・上級職 PB:25~ 能力値:1~2能力が突出、残りも平均以上。 特徴:規格外の存在。NPCとは住む世界が違う。 最低でもポイントバイ32保証というぬるま湯に浸りきった認識ではポイントバイ25なんて弱過ぎて萎えるだろうけど、世界の中の目線としては25って凄まじく優秀。メジャースポーツでプロの1軍になるとかそーいう存在。今浪クラス。 4D6して上3つのダイス目だけ採用というチートを駆使した場合の期待値がポイントバイ27くらいなことからも、それがいかに高い才能であることを意味するかがわかろう。 つまりまぁそんな超エリートな天才たちが次々と死んでるのがハクスラダンジョンなのだ。恐ろしい。 *TRPG部は上記のダイスロールでポイントバイ32以上相当のキャラが2人出来るまで繰り返し、そのうち1人を選ぶシステムです。ハクスラダンジョンはここ1年ずっとやってる、延々とダンジョンアタックしてるプレイです。 ・英雄 PB:32~ 能力値:15以上の能力値が3つ以上あったりする。 特徴:ハイパワーキャンペーン用に設けられた基準。 主人公補正を受けし英雄候補生。ポイントバイ25クラスでも十分に英雄になり得るポテンシャルを持つが、こちらはもう「フィクションの主人公グループ」みたいなライン。 ちなみに5D6して上3つのダイス目を採用した場合の期待値は、ポイントバイ36相当である。つまり君たちのキャラクターは結果的にこのクラスの英雄を殆ど保証されていることになる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キン肉マン #90 これはクロスボンバーの構え!!!!  それモニターじゃなくてて窓だったの!?(笑) 明らかにカメラアングル違う映像とかも観てたのに!?  なんだかんだで子供の頃に一番真似したキン肉マンの必殺技はクロス・ボンバーかもしれんなぁ。 頭から突っ込んだり腕から突っ込んでハリケーンミキサーやスクリュードライバーもしてたとは思うが。 ツインシュートのマネはどちらかの足を蹴り飛ばす危険な技だったので、やはり友達とキメるならクロス・ボンバーよ。  ハルク・ホーガンへの哀悼の如くネプチューンマンが大活躍するもんだから、亡くなってから描かれたのかと思ったが、そうじゃないことに驚いたぜ。 次のマグネットパワーの使い手としての誇りを新たにするシーンも格好良いだけに、何度でも言うが二世の世界線には行くなよマジで(笑) 時間超人が絡んだことで未来も変わるよな!!!  いったーいったー! テリーがいったー!!! 巨漢にテリーがいってくれる様式美は何度見てもテンションが上がるぜ!!! ぜひともテリーはこのままずっと巨漢相手に無敗を貫いて欲しい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■FGO 勝海舟の宝具が期待通り過ぎてアツい。そうでなくちゃな!! そして復活! 近藤勇! 復活! この「旗を立てる」からの「リターンオブ誠」があまりのアツさに当然泣いた。お膳立てが完璧だ!!!  もうね! もうね! もうね! この前のイスカンダルといい、まさしく「これを見るためにFGOをはじめた!」の二枚看板が立て続けに来ちゃってくれてさ! ある意味もう心置きなくサ終を迎えられる気持ちになるレベルで感無量だよ!!! ボロボロ泣いてしまったのは言うまでもない。 今回の大量実装で、新選組の人気のある隊長格以上って概ね実装されてるから、この宝具もバッチリだよなぁ。個人的には井上源三郎の実装もして欲しいが、それが贅沢だとはわかっている(笑)  というわけで近藤さんピックアップは聖地を触媒に気合い入れて回すぜ!!  だから俺はガチャの宗教なんてクソだって言ってるんだよ!!!!!!!!!! 出るまで回す今日以外は全部嘘っぱちのインチキオカルトなんだよ!! バーカバーカバーカ!!! 2枚引いてますが、どっちも天井寸前で出るという一番ムカつくパターンです。それをまさかの連続。 ……だが俺の隣で回してた女の子は俺が2枚目引く前に宝具5にしてたんで、俺が不運なだけ!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■放蕩TRPG部のwiki 基本的には凄く楽しい作業だからこそ続けられてんだけど、時折「これ世に出すわけでもないのに恐ろしい文章量を書いてて我ながら虚しい」と思う瞬間を紛らわすためにサイトにも公開する!! なお、直でwikiを読んでコメントも付けまくってやるぜって人は凄く欲しいが、これ誰でも荒らせてしまうんで迂闊に公開できないんだよな。 ●  解放歴元年後も継続された、人類領域拡大戦の大英雄。竜殺しの重装騎士。 解放戦争に於いて「竜殺しの英雄」は現代ほど珍しい存在ではなかったが、それはあくまで、人類の主力として機神及び第1世代呪甲装兵、即ち解放者エイファス謹製の超高性能機を用いているという異常な水準の結果である。しかし当然ながら呪甲装兵部隊以外の戦力も存在し、竜の軍勢が率いる怪物達とそれぞれの死闘を繰り広げていた。 その中でヒルデブラントは呪甲装兵に頼ることなく4頭もの古竜を屠った、伝説の竜殺しである。第1世代呪甲装兵を用いてすら互角が精一杯な古竜を、だ。 もちろん彼には頼もしき戦友たちが存在し、決して一騎打ちで討ち果たしたというわけではないが、それもすべて英雄としての様々な資質が「古竜に匹敵する戦闘単位として極限まで高めた結果」である。 なかでも、風を統べる古竜ヴィーザファンスルケイムとの激闘は、幾世代にもわたり吟遊詩人が歌い継ぐ壮烈な戦いである。暴風が荒れ狂う中、ヒルデブラントは巨竜の翼を穿ち、深手を負わせた。しかしその代償は大きく、彼自身も精霊蝕によって致命傷を負い、その場で斃れたという。 ・重滅槍ストラトアーティラリーTYPE507 ストラトアーティラリーは、天空を裂き、大地を滅ぼすほどの破壊力を持つ伝説の魔法槍。エイファスが星の力を宿した「天核結晶」を用いて鍛造したとされる。 この槍は単なる武器を超え、戦場を一変させる戦略兵器として恐れられる。その名は「天空(Strato)」と「砲撃(Artillery)」を組み合わせ、破滅的な力を象徴している。 ヒルデブラントが竜と戦う様を見た者の多くは「人の力で呪甲装兵用の武装を使っている」との感想を抱いたという。 それもそのはずで、この槍は解放戦争で大破した第1世代呪甲装兵が使用していたものを人間用に小型化したものであり、星砲の滅撃と称されるストラトアーティラリー最大の攻撃は、天空から星の力を凝縮した光の矢を降らせ、広範囲を壊滅させる。攻撃範囲は使用者次第で調整可能だが、最大で半径1kmを焦土に変える威力を持つ。しかしながら、対竜戦においては、主に収束率を高めることで竜単体を撃ち抜く運用が為されていた。 小型化したといっても扱う魔力量は膨大この上なく、それを制御することは常人に不可能な領域なのは言うまでもないし、絶大な威力を持つが基本的に「収束状態で竜に直撃を与えること」が極めて困難な為、「誰でも竜を屠れる必殺武器」などではない。 マジェスティック・プリンス第17話の様な、壮絶なレベルのお膳立てが必要となる。  「そう焦んなって、光学兵器ってのは何しろデリケートなんだ。光の速さで敵を貫くから狙いさえ正確なら外れる可能性はゼロ。その代わり、針の穴を通すような正確な射撃が要求される。しかもこの場合めちゃくちゃ距離があるから気象や自転による大気の揺らぎ、重力の干渉まで計算に入れなきゃならない。まあ、地上で遠距離射撃をする時のコリオリの力までは考えなくていいけどなあ。おまけに出力をマックスに持ってかなきゃならねえから、1発撃ったら次撃つまで時間かかんだとさ! ははっ、こんな難しい任務こなせんのは、地球でも俺くらいのもんだろうなあ!」 ●  風の太古竜ヴィーザファンスルケイム。その名は、成層圏を滑空する白銀の鬣の巨影とともに、古くから天龍伝承の象徴として語られてきた。解放戦争を生き延びた竜の一頭であり、その姿を地上から目にすることは滅多になく、雲海を裂いて流れるその影は、神話の頁から抜け出たかのようであった。 古竜時代、彼女は「四竜殺し」ヒルデブラント・リンデンベルガーを討ち取り、その名を歴史に刻む。この一戦を機に脅威認定は古竜から太古竜へと引き上げられ、ヴィーザファンスルケイムは以後、天空の支配者として恐れられる存在となる。 本質的には中立派であり、地上の人々の領域を積極的に侵すことはない。彼女にとってフロウは虫けら同然であったが、さりとて特別に蔑むべき対象ではなく、ただ己の眷属以外のすべてを同じ距離感で見下ろす、竜という種における当たり前の感覚でしかない。 しかし、人類にとって「頭上を竜に抑えられている」という状況は耐えがたく、国家の威信に関わる。もし人類が「目障りだから去れ」と要求したとしても、ヴィーザファンスルケイムがそれに耳を貸すことはあり得ない。加えて、実際にはそんな要求を突きつける以前に、すでに衝突は避けられぬ流れの中にあった。「お互い不干渉を貫けば共存できた」にもかかわらず、均衡は最初から脆く、崩れるのは時間の問題だったのである。  ヴィーリオン王国が建国された当初、王都上空は50年もの長きにわたり静寂を保っていた。その間、王位は建国王オスカー・ヴィーリオンが握り続け、国内は安定した治世を享受していた。だが、ヴィーザファンスルケイムにとっての半世紀は、人の1年にも満たぬ短さに過ぎない。彼女の棲処は常人の目には映らぬほど緻密に織り込まれた精霊力の帳に包まれており、陽光すらもわずかに屈折させ、雲と風の流れを偽り、観る者の意識から「そこに何かがある」という感覚を奪い去っていた。まるで空そのものが意志を持ち、その住人を隠すかのように。王国の魔導師たちがいかに探査の眼を走らせようとも、その結界を暴くことはできなかった。こうして王国は、天空に潜む支配者の存在を知らぬまま国土を築き上げ、気付いた時にはもはや退くことなど叶わなかった。 太古竜はもちろん、古竜ですら敵意を持って居座れば、その地にフロウの国家は成り立たない。もしヴィーザファンスルケイムが当初から敵意を剥き出しにしていたなら、この地方にヴィーリオン王国は築かれることすらなかっただろう。 解放戦争の時代にも、風竜王ヴィーフィートが中立を保ったように、ヴィーザファンスルケイムもまた戦乱への関与を避けた。しかし、同じ風竜の中には人類と激しく戦った者もおり、温厚さは種の中では例外的である。 こうして王国は、天空の覇者の存在に気付いてしまったがために、威信を保つため討伐を決断する。この決断はヒルデブラントの死へと繋がり、後世に「避けられぬ衝突」として語られることになる。 そしてヒルデブラントの死から450年後、天空騎士団史上最強の騎士コール・フォルティス飛雲卿が、この空の支配者に挑む。死闘の末、両者は相打ちとなり、白銀の巨影は雲海の彼女方へと消え、騎士もまた還らぬ人となった。こうして、天と地を隔てて続いた長き均衡は終わりを告げ、伝承は新たな章へと移ることとなる。 ●  ヴィーリオン王国天空騎士団史上最強のグリフォンライダーにして、審判の機神《ビヴァフネター・ゼーラフ》の操士。戦勝神の神寵者。 長年に渡り王国の空を統べ、晩年には半神となったことで「天空の守護神」の尊称を併せ持つ。 解放歴においてコールが名を刻んだ最大の戦果は、風の太古竜ヴィーザファンスルケイムの討伐である。これは解放戦争の英雄たちの殆どが世を去った解放歴50年以降わずか四例しか確認されていない太古竜討伐の一つであり、同竜は古竜時代に四竜殺しヒルデブラント・リンデンベルガーを討ち取った因縁の存在であった。それから約450年の時を経て、コールはこれを討ち果たす。 物理魔導の使い手としても天賦の才を持つコールは、万能型の機神ビヴァフネター・ゼーラフのポテンシャルを史上最も引き出した操士と評される。空戦・地上戦・魔導戦の全てを高水準でこなすが、本人は「歴代の操士の中に、私が一騎打ちで勝てるお方は一人もいない。人類が積み上げてきた竜に関する知識が私に力を貸してくれているだけだ」と語っている。 相棒は、戦勝神が遣わした聖獣「ヴォルケンシュトラール」。白羽と黄金の嘴を持ち、稲妻と暴風を自在に操るその力は、単独で竜種や大型飛行怪物を撃退できる。しかし太古竜との直接交戦は致命的危険を伴うため、太古竜戦における主な任務は、機神と太古竜の交戦域に割り込もうとする外部戦力の排除である。特に王国天空騎士団と連携し、外周防衛線を維持することで、コールが太古竜との一騎打ちに集中できる戦況を作り出す。天空騎士団は多数の空戦型呪甲装兵と精鋭数十騎規模で防衛網を張り巡らせ、ヴォルケンシュトラールはその中でも最も危険な接近経路を担当、牽制・制圧を行った。  ヴィーザファンスルケイムとの死闘後、コールは戦勝神に召され半神となり、以後は「天空の守護神」として祀られる。現代においても、ヴィーリオン王国の騎士たちは空へと飛び立つ前、必ず天空の守護神に祈りを捧げ、その加護を願うという。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■プレゼントありがとうございます( ・`ω・´) 明日、Windows11へのアップデートを行うので、もしかしたら起動不能になるかもしれないのが怖い。 半年くらい前にやった時、そうだったからな!!! 慌てて10に戻したよ!!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||